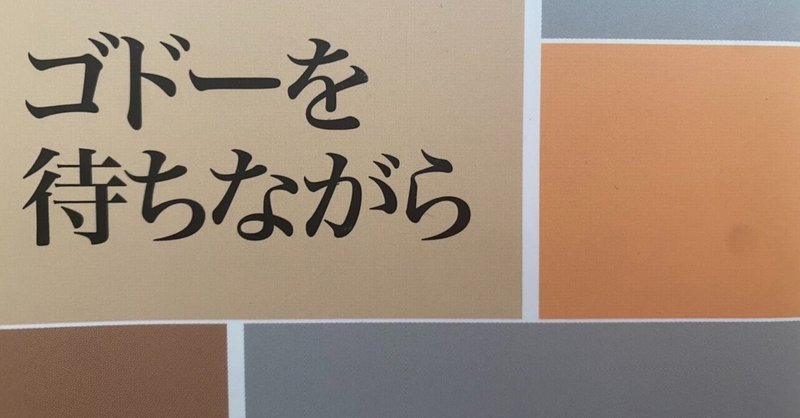
ゴドーを待ちながら/サミュエル・ベケット
もう30年くらい前からいつかは読もうと思ってたサミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』。アイルランド出身の劇作家で小説家の1952年の作。初演は53年だそうだ。ノーベル文学者ベケットによる、不条理演劇の最高傑作と呼ばれる作品だ。
ありとあらゆる人に語られてきたこの作品、僕からあらためて語ることなど、そうない。なので、この本を読みながら考えたことをすこし書いてみよう。

僕らにとっては不条理ではない
ゴドーというゴッドの抜け殻を思わせる響きの名をもつ誰かをひたすら待つエストラゴン(ゴゴ)とヴラジミール(ディディ)という2人の浮浪者が主人公の物語だ。物語といって特に筋はなく、ほかにラッキーという召使いを連れたポッツォという金持ちの男と、ゴドーの使者だという男の子が登場するだけだ。舞台も木が一本立ってるだけの田舎道である。
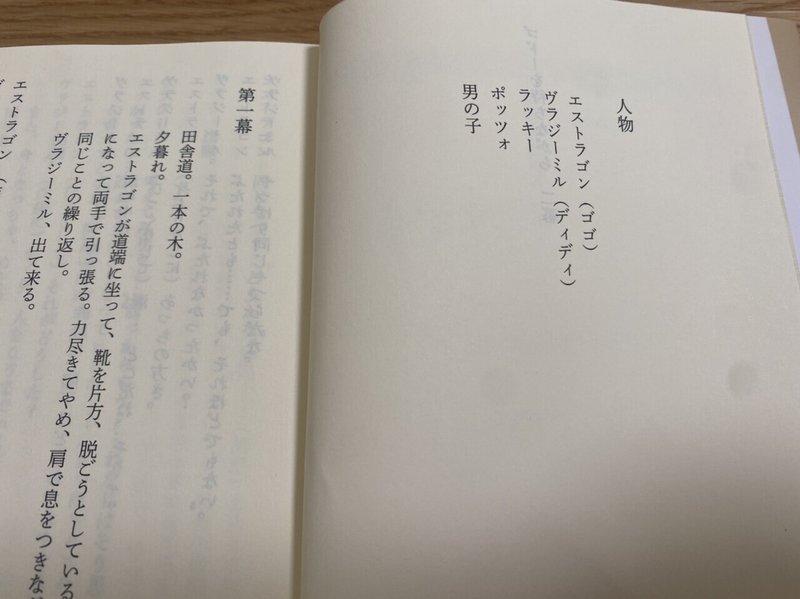
この何も起こらなさ。
この作品は常にそう言われるが、読後感はすこし違う。
といのも、もはや何が起こっても驚きにくくなってしまうほど、これまでの常識が維持できなくなっている現代の僕らにとっては、登場人物が繰り広げる意味のわからない出来事も不条理と呼ぶほど、不条理ではなく、たしかに筋の通った物語的なことは何一つ起こらないのだけど、何か意味のあることは起こらなくても、僕らをざわざわさせる状態がつねにゆるやかに起こり続ける状況はむしろ僕らに何かが起こっていることを実感させてくれるからだ。
僕らの日常に起こっていることはこの作品が不条理で何も起こらないと評されてきたこととあまり変わらない。来るかも分からないゴドーを待ちながら、目の前で起こる意味不明なことに、決定的な危機が自分たちに起こらない微妙な距離で関わろうとするのも、僕らにとってはむしろ馴染みのあることのように思う。
それがこの2021年と、この作品が書かれた1952年のあいだのおよそ70年の時代の違いではなかろうか。
1952年
1952年といえば、大戦終結から7年目にあたる年で、2月にエリザベス2世女王が即位、4月にはアメリカによる琉球臨時中央政府が発足、同月日本は西ドイツと国交樹立し、アメリカとのあいだで安保条約と呼ばれる日米安全保障条約が発効されたのもこの年だ。
5月にはロンドンとヨハネスブルク間に世界初の旅客用ジェット機が就航、現在のEUの前身である欧州共同体(EC)と融合していくことになる欧州石炭鉄鋼共同体が生まれたのもこの年の7月、日本と西ドイツが国際通貨基金(IMF)に加入するのは8月のこと。
10月にはイギリスがはじめての原爆実験を行い米ソに続く第3の核保有国になれば、11月にはアメリカが初の水爆実験を行った。そして、12月には1万人以上の死者を出した公害事件、ロンドンスモッグ事件が発生したのが、ベケットがこの作品を発表した1952年という年なのだ。
第2次世界大戦後の世界が新しい世界体制に向けての準備が整いはじめ、それがいまのさまざまな環境・社会問題をつくる原因となるようなさまざまな仕掛けが用意された年のように見える。
この舞台のような木一本のみとまでは言わないまでも、戦争で荒れ果てた荒地の状況から新たな意味の判然としないものが立ち上がってきている状況がこの1952年の空気感だったのではないだろうか。それはもちろん明るい新時代を告げる部分もあったのだろうけど、社会のはずれで時代の趨勢とは無関係に生きるゴゴやディディのような立場の人びとにとっては、すくなくとも意味のわからないコードとプロトコルに支配された、不可解な出来事に見えたのかもしれない。
非連続な時間
この作品を読んで感じるのは、非連続な時間の流れである。この時間の流れの非連続性――あまりに流れが早くて今日が昨日の続きとは思えない間隔――もまた、僕らにとっては不条理ではなく、日常になってしまっているものではないだろうか。
ゴゴは忘れっぽくて、すぐさっきまでやっていたこと、話していたことを覚えていなくて、ディディを訝しがらせるが、そんな忘れっぽさも僕らにとっては日常的だ。どんな炎上案件も時間が立てば、そんなことあったかくらいに記憶の外に追いやられるのが、僕らの日常ではないか。あたかもなによりも重要なことであるかのように騒ぎ立てたくせに、ある日まったく意識の外に追いやってしまう。
自分たちがゴドーを待っていることも忘れるゴゴの姿に、そんな僕らのいい加減で都合の良い忘れっぽい熱情が重なる。ゴゴはこの作品中、何度もゴドーを待つというミッションを忘れてその場を離れようとし、ディディに「ゴドーを待っているだろ」と諭されて、「あ、そうだった」となるのを繰り返す。
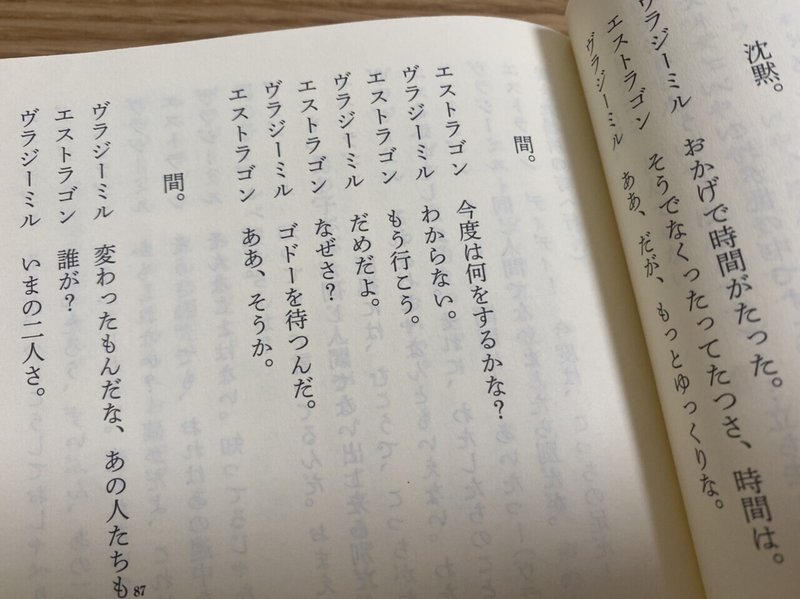
今日は昨日の続きなのか
特に、時間の流れが連続しているのだろうかと思えるのが、2部構成となるこの作品の1部と2部の関係だ。
1部の最後に、ゴドーの使者だと自称する男の子が、2人の浮浪者の前にやってきて、彼は今日は来れないが明日は来ると言っていると伝える。
そんな終わり方の1部のあとの2部の幕開けだから、当然2部は昨日の続きの今日だと思って読むと、いきなりゴゴは昨日はここに来なかった、来たことを覚えていないという始末。自分で足が痛いといって脱いで置いてあった靴(だと思われるもの)が舞台にそのまま残されていても、そんなことした覚えはないという。で、実際に履いてみると、昨日とは履き心地が違って、痛くないから、これは自分が脱いでいったものではないだろうとなる。ディディもさすがに不思議に思いはじめる。
昨日も同じ場所で会ったポッツォに再び会うが、様子が明らかに違って、盲になっていて、2人のことがわからない。見えないからだけでなく、昨日会ったか?と言い出す始末。もちろん、忘れっぽいゴゴもポッツォとラッキーに会ったことを覚えてなくて、会ってないという。ずっとそのまま会っていないと言い通せば、ディディのほうの思い違いかともなるが、ポッツォもゴゴも中途半端に一部を覚えている風だったりするので、真相はよくわからなくなる。
だが、この場合の真相ってなんだろうということでもある。ここでの真偽は、今日が昨日の続きで、昨日の価値や情報が直線的な時間に沿って蓄積されていくものだという暗黙の前提のうえに成り立っている。しかし、それ自体、近代的な科学と資本主義の蜜月から生まれたひとつのプロトコルでしかない。ここで今日が昨日の続きであることが揺らぐことは、真相が知識の蓄積によって保証される価値であるということも同時に揺らぐということでもあるだろう。
そして、何より知識の蓄積が価値となるという仕組みで隠されているのは、未知あるいは無知からも実は価値が言説や意識の外側で収奪されているということだろう。商品生産=資本主義的な価値生産において、女性や自然資源のはたらきが無償で奪われるのと同じことだ。最近ではSNSのユーザーの無償での日々の情報投稿がビッグデータとしてプラットフォームが利用しているのも同じことだ。
こうした無償での搾取や収奪が明るみに出るのも、ゴゴとディディという2人の浮浪者が主人公のこの劇のひとつの特徴かもしれない。そして、それが明るみに出るのは一直線の時間軸に沿って価値は無限に蓄積可能――つまり無償の収奪が永遠に可能――という幻想があってこそなのだ。
この劇がみせる非連続な時間とは、そうした価値の蓄積=無限の収奪が幻想だと教えてくれる避け目のようなものではないか。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
