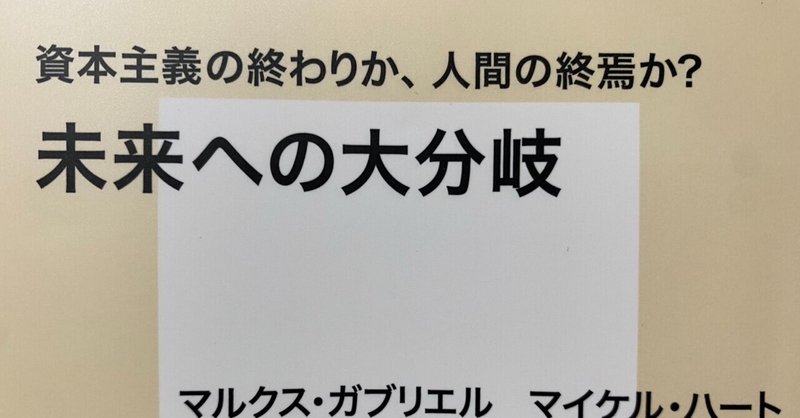
資本主義の終わりか、人間の終焉か? 未来への大分岐/マルクス・ガブリエル、マイケル・ハート、ポール・メイソン 、斉藤幸平
シンプルで、わかりやすく、とてもためになる本だ。
この本の先になら、未来が見える。
『資本主義の終わりか、人間の終焉か? 未来への大分岐』は、以前に絶賛した『人新世の「資本論』を書いた斎藤幸平さんが、マルクス・ガブリエル、マイケル・ハート、ポール・メイソンという、それぞれ『なぜ世界は存在しないのか』、『〈帝国〉』、そして『ポストキャピタリズム』という世界的名著を世に出した気鋭の3人の新実在論の哲学者、政治哲学者、経済ジャーナリストと対談した内容を1冊にまとめたものだ。
どんな内容かといえば、資本主義を乗り越えるための民主主義の可能性について議論が交わされている本だ。
前からこの本の存在は知っていたけど、この表紙のデザインがどうも表面的な軽い印象を受けてたので買わなかった(笑)。
でも、今回、まあ読んでみるかと思って読んでみたら、とても興味深い内容で、読み始めたその日中にあっという間に読み終えてしまった。

マイケル・ハート
三者三様でどの対談も面白い。
たとえば、アントニオ・ネグリとの共著『〈帝国〉』で知られるマイケル・ハートが、こんなことを言っているのが、まず印象に残った。
本来、特定の経済システムが果たすべき責任とは、生産力を増やして人々にまともな生活を提供することにとどまらず、人々の才能や能力を十分に活用することなのです。
つまり、社会を成り立たせる生産様式や生産力について問うべきなのは、こういうことなんです。「資本は、人々の能力や才能を十全に活用できているのか?」、「人々の才能や能力は、現在の経済システムのもとで無駄遣いされているのではないか?」。
才能や能力を十分に活用することが経済システムの責任だというのは、ものすごく共感する。
そして、それはグレーバー指摘するところの「ブルシット・ジョブ」ばかりが生まれる経済のしくみとは正反対のものだ。
そして、才能や能力を活かすことのできるかの有無こそが本当の意味での経済システムの生産性だとしたら、利益ばかりを追う思考は根本的にズレていることになる。
しかし、グレーバーも書いていたが、そのためには、仕事にあたるものがただ上から降ってくる仕事をこなすのではなく、下からのボトムアップで自分の才能や能力を活かせる仕事を行えるような民主主義的なしくみがいる。そして、そのための財への平等なアクセスが前提となる。
だから、やはりここでも〈コモン〉の話になる。
〈コモン〉とは、民主的に共有されて管理される社会的な富のことです。〈コモン〉を具体的にイメージするには、ベルリンの電力システムを〈コモン〉にするかどうかを争点にした2013年の住民登録が良い例となるでしょう。公共事業体だった電力システムの運営権は1989年以降、私企業である電力会社にゆだねられ、ベルリンの団システムは民営化されていきました。
この投票は再公営化を目指したものですが、その際、電力システムを国家がコントロールする国有財産でも、私有財産でもない、〈コモン〉にすることが争点となりました。
仕事というものが単にお金を得るためのものでなく、日常的な家事労働や、なんなら趣味的な創作や研究なども含めて仕事なのだとしたら、それを行うための財へのアクセスを容易にできるよう、財を国有でも私有でもない形の〈コモン〉として民主的に管理しておく必要がある。
そして、この財の共有という考え方は、法的権利としての所有を超える形で、人間社会のなかだけの話ではなく、地球環境とのあいだの共有にまで発展する。
ハートと斎藤さんはアメリカ・ダコタ州での石油パイプライン計画に反対した先住民スー族の運動に、さまざまなほかの先住民や白人の環境保護活動家まで連携したことについて、こんな風に話している。
ハート スー族が土地という財産も所有権を主張してパイプライン建設に反対し、抵抗運動を組織することも可能でした。「この土地は我々の財産なのだ」「パイプラインも建設によって、私たちの財産が破壊される。少なくとも、その危険性が十分にあるはずだ」といった具合にです。でも、そういう主張の仕方はしなかった。
斉藤 もしスー族による所有権の主張だけだったら、この運動は、基本的に資本主義的な私的所有の論理をいくばくか拡張したものにしかならなかった、ということですね。
ハート ええ。「所有」の論理に基づく主張の代わりに、運動のリーダーたちはこう言ったのです。我々が発展させていかなくてはならないのは、地球との新たな関係だ。
ハートは、こうした民主主義的な活動を成功させるためには、カリスマ的なリーダーを求めてはならないと繰り返している。
そうではなく、先に、水平的にたがいに議論しあえる市民運動があって、それらに耳を傾け続けるリーダーがいてこそ、民主主義的な政治は機能するのだ、と。
もちろん、政治だけでなく、先の仕事の環境でも同じだ。カリスマリーダーに頼るのではなく、ボトムアップの活動があってはじめて、そこに民主的なガバナンス機能が動きはじめる。
それがネグリとハートが提唱するネットワーク型の権力としての「マルチチュード」という考え方にもつながっている。
どうすれば多くの人が一緒になって統治を行うことができるのか、ということについて、先天的に知っていたり、自然にわかっていたりする人はどこにもいない。ネグリと私にとって、ここが分析を始めるべき出発点です。「社会のなかにどういう場所があれば、みんなで共に民主的な決定を行うための能力を発展させていくことができるのか」を問わなくてはなりません。
それゆえ、「マルチチュードははじめから存在しない。マルチチュードはつくり出される必要がある」と私たちは言うのです。
マルクス・ガブリエル
次のマルクス・ガブリエルの話は、どちらかというとポストモダン的な思想のマイケル・ハートとは違って、啓蒙主義的な思想になるので、僕としてはちょっと苦手な面もある。
この社会の危機的な状況を打破するためにも、哲学がもっとも必要なものだという指摘も最初は「?」と思ったりもした。
でも、土地で「自然科学」偏重の傾向を指摘するあたりで、「そうそう」と僕も共感できるところにたどり着く。
ガブリエルは、多様な「意味の場」がある。ゆえにそれらを統合するような、ひとつの「世界は存在しない」という観点から、自然科学偏重についてこんな指摘をする。
粒子加速器や脳のMRIでは、道徳、宗教、共和国、数字、精神史のいずれも見ることはできません。しかし、これらの世界史的なものが存在しないということにはなりません。ただ、それらが自然科学によっては原則的に研究できないだけなのです。
自然科学の扱う宇宙は、存在論的な地域のひとつに過ぎません。数多くある他の「意味の場」と並んで存在しているもののひとつなのです。
そう。自然科学はほかにもある意味の場において、ひとつの説明を可能にする場でしかない。ゆえに、自然科学的な思考だけですべてを説明しようとする姿勢には不備がある。
そして、ここにおいてガブリエルの民主主義に対する姿勢も明らかになる。
自然科学を絶対視する「自然主義」を放っておけば、政治的な決定を「自然科学の専門家」にゆだねてしまう危険なテクノクラシーの傾向を生み出します。専門家集団は、一見、完璧に見えますが、しかし、専門家集団による支配は、民主主義の理念と相入れません。なぜなら、近代民主主義の理念は、人間の自由と平等という考えに依拠しているからです。
このガブリエルの姿勢は前に紹介した『リヴァイアサンと空気ポンプ』における、ボイルら科学者の実験主義に対抗しようとしたホッブズの姿勢に似ていると思う。
ホッブズの考えでは「信念と意見は個々の人びとに属しており、その人の信念や関心の影響を受けるので、それらは社会的秩序の枠組みを構築する基礎としてはあまりにも変化しすぎて役に立たない」ものと見做されていた。だから、ホッブズは「信念をふるまいや理性とは対照的なものとみなし」、「公的な領域に属していた」「ふるまいと理性の両者」こそ社会的な秩序の構築に役立たせるべきだとしている。
このホッブズの姿勢に、ガブリエルの新実在論の思考姿勢は似ている。
個々人の信念ではなく、実際のふるまいや理性的な真理を重視し、そして、それがさまざまなパースペクティブにおいて異なることを認めるがゆえに、彼は政治的な場面においては、熟議型民主主義を志向し、議論を通じて、態度を調整していくことが必要だとする。
ガブリエル 法の支配は、倫理的な考慮に基づいていない場合、機能しません。それゆえ、倫理的領域と法的領域のあいだでの態度調整が必要となります。それはパースペクティブの管理をするために必要な実践的な知恵の一形態なのです。
斎藤 だから、あなたは民主主義をさまざまなパースペクティブのあいだを取り持つ絶え間ない管理や調整の過程として描いているのですね。すべてを包摂する「世界」が存在しないからこそ、人々はパースペクティブの調停に政治的にかかわることを必然的に要請されるわけですが、その基礎にあるのが倫理です。
この「倫理」をもった人々による民主主義を実行できるようにするためにも、哲学教育が必要だというのがガブリエルの意見である。
そして、それがもはや不可欠なほど、致命傷になりかねないくらいの危機が迫った、切迫した状況であることを認識する必要性を説く。
人類は、今、胸元に拳銃をつきつけられているような状態だ。「撃たないでくれ」と叫び、最悪の事態を避けるために、行動する選択肢もある。それなのに、「どうぞ撃ってください」と言っている。未来ではなく、終末を選ぼうとしているのは、私たち自身なんだ―― 。
実際、私たちがいる状況は、生死の選択という分岐点にいるわけです。気候変動やテロなどの脅威に直面しているのですから。
とりわけ、今、哲学教育をやらなければ、私たちは敗北します。私たちは民主主義を破壊することになり、世界を覆う気候変動などの諸問題を解決できず、サイバー独裁が民主主義に取って代わるでしょう。
サイバー独裁。この話が次のポール・メイソンの話にもつながっていく。
ポール・メイソン
ポール・メイソンは『ポストキャピタリズム』の著者として知られるジャーナリストである。
まさに、資本主義のあとを考える本であり、その考察は、成長率の鈍化したままの経済への疑問に端を発している。
その資本主義に代わる社会を可能にするのは、デジタル技術による分散型の社会であるというのだが、特にそれ自体は新しい話してではない。
ただし、メイソンはちゃんとGAFAなどによる情報の独占、情報所有の非対称性によって自由市場が機能不全に陥っていることも指摘していて、決して楽観主義的に情報技術が「潤沢な社会」をつくると思っているわけではない。
さらには、AIのもたらす危機も理解しているが、かといって、ハラリのように悲観的なストーリーを描くわけでもない。
ハラリの考え方が世界中で人気を博しているのは、非常に危険な現象です。ハラリは西洋のポスト啓蒙主義的な先進国社会における知識と主体性をめぐる哲学的問題を再検討しています。そして、彼は技術のなかに答えを探します。
けれども、答えはそこにはありません。答えは技術ではなく、人間の理論であるヒューマニズムのなかにこそあるはずです。
ここで、ヒューマニズムをもってくるのは、ガブリエルが「哲学教育」の必要性を説いたのに近い。自然科学や情報テクノロジーはもちろん大事だが、哲学や人文学の重要性が、民主主義のために説かれるのだ。
そうした哲学や人文学の知恵を手にした人たちが、AIの時代に新たな「人間とは何か?」の答えを導き出し、aのコントロールについても考えられるようになるのでしょう。
21世紀にもっとも問題とすべき、哲学的な問いは、「AIをコントロールする権利をどのように根拠づけられるのか?」というものなのです。
(中略)
AIが私たちを出し抜き、優位に立つのです。人間があらゆる存在に対して優越しているという、多くの宗教が今まで主張してきた前提が融解してしまう。だからこそ、人間とは何か、という人間の固有性についての答えは、人間の優越性ではない、何か別のものに根ざしたものでなければなりません。
そんな風に、主体的な人々がネットワークのなかで、AIとも、国家とも、そして、資本主義とも共存していく、そんな民主主義のあり方を考えているのが、メイソンです。
ポストキャピタリズムへの道は、古臭いレーニン主義者が主張する国家社会主義への道であってはなりません。資本主義経済と並行しながら、非資本主義経済を小さいスケールからつくっていくことが、ポストキャピタリズムへの移行プロセスなのです。自由への道を模索している主体的な個人の行為がネットワーク化していくことで、ポストキャピタリズムへの道が開かれていくのです。
最後に、斎藤幸平さん自身も書いているとおりで、三者三様の思考が語られていますが、資本主義を乗り越え、新たな「自由、平等、連帯、そして民主主義」を語っている点では共通している。
いずれも残念ながら、いまの日本の社会に足りないものだ。
この本に触れる人が増え、日本にももっと社会運動や市民運動が起こってくる土壌がつくっていけるとよいと思った。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
