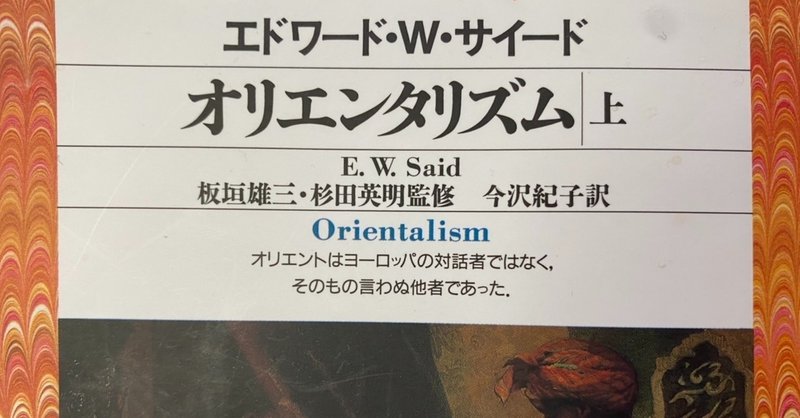
オリエンタリズム(上)/エドワード・W・サイード
知は搾取する。
いや、正確には知と無知の混合によって、知る側による知られる側からの搾取が行われる。
知ることによって奪い、知らずに奪う。
もちろん知ることで奪うことを避けることもできる。
こうした知の功罪を、認識しなおすことがいまの時代、つよく求められている。
オリエント(東洋)をみるオクシデント(西洋)の広範にわたる思考様式としてのオリエンタリズムを西洋による帝国主義の問題と関連づけて論じた、もはや古典である、1978年にエドワード・W・サイードが発表した『オリエンタリズム』を、いま読もうと思ったのはそういう理由だ。

受け入れられない差異
ドラクロワによる「アルジェの女たち」が図版として採用された表紙に「オリエントはヨーロッパの対話者ではなく、そのもの言わぬ他者であった」とある。

本書で問題視されるオリエンタリズムは、男女、大人と子供など多くの二項対立同様、西洋と東洋の二項も同列関係にあるというより、一方の側(西洋)が他者と自分を比較することで、自己を肯定的かつ優勢な立場に置くために、もう一方の側(東洋)を不等価な関係に置こうとする思考の形式である。
実は、この本、20代前半の頃、一度読もうとして途中で断念している。当時の僕には問題を自分ごととして捉えられず、むずかしかった。
その本をあらためて読もうと思った直接のきっかけは、緊急事態宣言下で読んだアメリカの黒人作家テジュ・コールの小説『オープン・シティ』のなかで言及されていたからだ。
小説のなか、休暇でベルギーのブリュッセルを訪れた主人公のジュリアスが出会ったモロッコ出身の青年ファルークに、こんな風に言われるシーンがある。
だから僕にとってサイードは重要なのさ、とファルークは言った。ほら、若かりし頃のサイードは、ゴルダ・メイヤ首相の「パレスチナ人など存在しない」という発言を聞いたのがきっかけで、パレスチナの問題に引き込まれたよね。そして人間は差異というものを決して受け入れないことを悟った。
言うまでもなく、この数年、自分とは異なる他者を決して受け入れることなく、誹謗中傷や、身体的・物理的な攻撃の対象とすることが、SNS上でもオフラインの日常のフィールドでも頻繁に見られるようになっている。特に、このパンデミックによる社会的な分断によって、その傾向はいっそう顕著になった。
認識の限界
サイードは本書でこう書いている。
我々はヴィーコの「人間は自分自身の歴史をつくる」、そして「認識が認識しうるのはみずからのつくったものだけである」という達見を真剣に取りあげて、それを地理にまで敷衍して当てはめてみるべきであろう。
と。
僕らが認識しうるものは、自分たちがつくったものだけで、他者がつくりあげたものを僕らは認めえない。
何が起こるかと言えば、自分たちが知っているものだけを認め、それ以外を認めず排除しようと攻撃対象にする。
さらに悪いのは、相手に対する敬意をはらっているふりをするために、相手の一部のみを理解したことにし、それ以外を無理矢理捨て去り、相手の像を歪めて、結果、相手を不利にしてしまう。
僕らはその思考形式そのもの、知のありようそのものによって、他者を差別化し、攻撃し、搾取の対象にしてしまうのだ。
何が東洋的で、何が西洋的だなどということが単純に決まるはずがない。
しかし、僕らは「わかりやすさ」などといったつまらないことを理由に、簡単に(かつ暴力的に)自分とは異なる者たちのことをあまりに単純すぎる形で類型的に言語化、イメージ化してしまう。
そして、いつのまにか、それがただの観念であることを忘れて、現実の相手を見ようともせず、自分たちの勝手な観念で相手をコントロールしようとしてしまうのだ。
歴史的実体たることは言うに及ばず、地理的実体でもあり、かつまた文化的実体でもある「東洋」と「西洋」といった局所、地域、または地理的区分は、人間によってつくられたものである。したがって、ほかならぬ西洋がそうであるように、東洋もまた、思想・形象・語彙の歴史と伝統を備えた一個の観念なのである。
サイードが問題視したのは、そうした非対称かつ一方による支配的であるような知のあり方としてのオリエンタリズムである。
外から剥ぎとる
オリエンタリズムとは何かということを、あらためてサイード自身の言葉を通じて紹介するなら、こうだろう。
詩人であれ学者であれオリエンタリストとは、オリエントに語らせ、オリエントについて記述し、オリエントの秘めたるものを西洋のために西洋に対してあばく人間だという事実、すなわち外在性こそがオリエンタリズムの前提条件なのである。
オリエントを言及する学者も、オリエントを描こうとする詩人も、ともに、彼らがオリエントに目を向けるのは、それが自分たちとは異質なものだからである。
つまり、彼ら西洋のオリエント研究者、詩人は、自分たちと異なり相容れないものだから、東洋に魅了され、決して、東洋と一体化しようとなどとは考えることなく、あくまで外部の存在として、そこから知を摂取しようとする。
ようするに、それは彼ら自身のため、彼らの読者である西洋の人びとのためであって、観察される側の東洋の人たちのためではない。
「オリエンタリズムの限界とは、すでに述べたように、他の文化、民族、または地理的区域の人間存在を無視し、エキスをしぼり出し、剥ぎとる結果として生じる限界なのである」とサイードは言っている。
東洋とひとつになろうなどという考えは、まるでなく、異なるからこそ、そこから自分たちが持っていないものを得ようとして臨むところに、オリエンタリズムの知の限界があるというのだ。
こうした現代のオリエンタリズム的姿勢は、報道や大衆の心のなかに氾濫している。例えばアラブは、駱駝にまたがり、テロを好み、鉤鼻をもち、万事金銭次第の好色漢であり、彼らの分不相応な富は、真実の文明に対する公然たる侮辱であると考えられている。このような見方に絶えずつきまとっているのは、西洋人消費者が、数のうえでは少数派であるにもかかわらず、世界の資源の大半を所有するか、または消費する(またはその両方の)権利を持っているという前提である。その理由は何か。東洋人とは異なって、西洋人は真の人間だからである。アヌワル・アブデル=マレクが、「持てる少数者の覇権主義」およびヨーロッパ中心主義と結びついた人間中心主義と呼ぶものの実例として、今日これ以上に適切なものはないであろう。白人中産階級に属する西洋人の信念に従えば、非白人世界を管理するだけでなく、それを所有することもまた、人間としての彼らの特権なのである。
ここにあるのは、現代における移民の問題や米中の対立の問題にも通じる。
自分たちのいまの不幸は、移民たちや中国人が自分たちの仕事を奪っているからだという欧米の考えは、サイードがこの本で指摘していた頃のオリエンタリズム的思考となんら変わりない。
自分たちで他者を、必要以上に他者として認識するために他者としての数々のレッテルを他者に付与した上で、彼らは自分たちと違うということを声高にいうというある種トートロジー的な振る舞いに、本人たちは気づくことはない。
もちろん、それは欧米の人たちの問題というだけでなく、このコロナ禍でいっそう明らかになったように僕らの外――自分たちとは違うと認識する対象――への態度も同じように問題だ。
観察される
あいつらは自分たちとは違うといって、敵視したり、逆に好奇な目でみて見世物にしたり、認識的な外在化によって、その対象からこっそり彼らのものを搾取する。
それは物理的な搾取のみならず、彼らを敵視し悪者扱いすることで自分たちの正当性を主張するというような意味での地位の搾取もある。
オリエントは観察される。ほとんど(決して十分にではないが)攻撃的で人に不快感を催させるオリエントの行動が、特異性の無尽蔵に詰まった貯蔵庫からとり出されてくるためである。ヨーロッパ人――オリエントを旅するのはその感性なのだ――は、みずから一箇の観察者であることを忘れず、決して巻き込まれず、つねに超然としていて、『エジプト誌』が言うところの「奇妙な享楽」の新しい事例を発見しようと鵜の目鷹の目なのである。東洋は奇妙さを表現する活人画となるのである。
サイードがオリエンタリズムの問題として指摘するここのところが、最近の僕の問題意識と重なるところだ。
利用可能な資源に対する非対称なアクセス、本来共有資産であるところのものが何らかの形である人たちのみにアクセス可能な私有財産になってしまう。
先のテジュ・コール『オープン・シティ』をはじめ、最近紹介している以下の本を通じて考えていることは、非対称な知的所有や物質的所有に基づく格差に端を発するさまざな問題は根本的になぜ生じてしまうのか?ということだ。
『人新世の「資本論」』斎藤幸平(書評)
『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』デヴィッド・グレーバー(書評)
『植物園の世紀 イギリス帝国の植物政策』川島昭夫(書評)
『暴君 シェイクスピアの政治学』スティーブン・グリーンブラット(書評)
『絶望を希望に変える経済学』アビジット・V・バナジー & エステル・デュフロ(書評)
斎藤幸平さんは「生産や分配をどのように組織し、社会的リソースをどのように配置するかで、社会の繁栄は大きく変わる。いくら経済成長しても、その成果を一部の人々が独占し、再分配を行わないなら、大勢の人々は潜在能力を実現できず、不幸になっていく」と書いている。
オクシデントに外から観察される対象としてのオリエントは、観察を起点に搾取に晒され、搾取されたものは自分たちに再配分されることなく、自分たちとは無関係な西洋(のこれまたごく一部)の人を潤すことになる。
1つ前の「暴君 シェイクスピアの政治学/スティーブン・グリーンブラット」のなかでも紹介したように、リチウム電池の原料であるコバルトの約60%はコンゴで採取されるが、その恩恵に預かるのは、電気自動車やモバイル端末を多く利用する富裕国の人びとであって、コンゴの人は少ない賃金で本来なら農作物をつくるために使えた土地を、自分たちの暮らす環境を破壊しながらコバルトを掘る。
西洋の資本はそんな彼らの生活とは関係をもたないまま、一方的な搾取を続ける。
サイードが「オリエンタリストとは、オリエントに語らせ、オリエントについて記述し、オリエントの秘めたるものを西洋のために西洋に対してあばく人間だという事実、すなわち外在性」といった、オリエンタリズムと同じ構造がいまも続いているわけだ。
理解できないものに対して距離をとる
この外在性――自分たちの理解できないものに対して距離をとる姿勢――が、あらゆるものからの搾取を可能にし、その非対称な資源の利用によって世界のなかで比較的富裕な側に位置づけられる僕らの暮らしは成り立っている。
持続可能性が問われるなか、いちはやく見直しが求められているのは、この無知をなんとも思わないまま、他者から平気で搾取し続ける姿勢だろう。
そういう意味で、このサイードのオリエンタリズム研究はいま注目しなおす必要があると感じた。
「わからない」ものを遠ざけ、都合よくわかる部分だけを編集的に意味を置き換えて利用するという例として、サイードは、18-19世紀のフランスの東洋学者アントワーヌ=イザーク・シルヴェストル・ド・サシの考えについて、こんな風に紹介してくれる。
オリエントの文学作品は、ヨーロッパ人にとって本質的にあいいれないものだというばかりではない。それは読者の興味を持続させるに足るだけのものを含んでもいなければ、十分な「趣味と批判精神と」をもって書かれてもいないので、抜粋として以外には刊行するにも値しない、というのであった。こうしてオリエンタリストは、一連の表象的断章によって、すなわち翻刻され、説明を加えられ、注を付され、さらに多くの断章群を周囲に配した断章によって、オリエントを提示することが要求される。
サシは、オリエントの文献を研究し、その結果を西洋の人びとに知らせる際、オリエントの西洋から見て理解できない部分、意味があるとは考えられない部分を削ぎ落とした。そして、残した部分にも西洋的観点で解釈を施し、注を加えて、西洋的な視点でオリエント像を編集した。
他者を理解しようとする際に、自分たちが理解できない部分は削ぎ落とし、自分たちが理解できる部分の抜粋からなる編集的な他者像をでっち上げて、他者を理解したことにする。
ここで指摘されていることは、そういうことだ。
自分たちに都合の良い他者像を、他者自身とは無関係につくり上げたうえで、自分たちの同胞たちに広める。
それが後の西洋におけるオリエント像をつくった。
18世紀後半に起こったのはそういうことだ、とサイードはいう。
一方通行の理解
また別の例では、エジプトに暮らし『エジプト風俗誌』を著したエドワード・ウィリアム・ レインについてサイードは言及している。
エジプトに暮らし、エジプトの人たちの暮らしについて観察し話を聞き、その内容をまとめつつ、彼らと完全には交わろうとせず、その成果を、たんに西洋人にエジプトの風俗を伝えるだけに使ったレインについて、サイードはこう語る。
オリエンタリストはオリエントを模倣することができるが、その逆は真ではありえない。したがって、オリエンタリストがオリエントについて語ることは、一方通行の取り引きのなかで得られた叙述として理解されなくてはならない。すなわち、彼らが語り、行動することを、彼は観察し、書き記すのである。レインの力は、現地語をいわば母国語のようにあやつりながら、隠れたる作家として彼らのただなかに存在していたという点にあった。しかもレインの作品は、彼らにとってではなく、ヨーロッパとそのさまざまな普及機関にとって有用な知識となることを念頭において書かれていたのである。
知的搾取というしかない。
しかも、この理解の前提には、先のサシによって固定化された西洋のバイアスのかかったオリエント像がある。
エジプトに暮らしながら、レインは、西洋の見方で彼らの暮らしをみて評価する。それはエジプトの人びとの暮らしそのものの記述というより、西洋人がそれをどう見たかの記録となる。
エジプト人の習慣、儀礼、祝祭、幼年期、成年期、そして葬式を順次経験する一人称代名詞としての自我は、実のところ、普通の手段では手に入れることのできない、価値ある情報をとらえ、伝達するために考察された東洋人の顔をした仮面であり、オリエンタリズム的な仕掛けなのである。語り手としてのレインは、展示物であるとともに展示者でもあって、経験に対する2種類の欲求、すなわち人づきあいのよさ(あるいはそう見えるもの)に対する東洋人の欲求と、権威ある有益な知識に対する西洋人の欲求とをかきたてながら、この両者から同時に信頼をかちえるのである。
だが、それを読む者はそこに書かれたものがエジプト人の真の暮らしだと理解してしまう。
エジプト人の側もレインの表向きの人づきあいの良さに気を許して、搾取されているとも気づかず、どんどんと情報を提供してしまう。
ようは搾取であるだけでなく、イメージの捏造でもあるといえるのだが、それを西洋人の側も、エジプト人の側も気づかないのだ。
事実というつくりもの
前に「リヴァイアサンと空気ポンプ/スティーヴン・シェイピン+サイモン・シャッファー」でも言及したように、17世紀中頃以降、科学の名で人工的なつくりものである「事実=fact」があたかも真実であるかのような言説が可能になる。
同じことがオリエンタリズムの形成においても起こったのだ。
1848年に執筆され、1890年に初めて出版された『科学の未来』におけるエルネスト・ルナンの示した姿勢がまさにそうだ。
生命体および準生物(インド=ヨーロッパ語、ヨーロッパ文化)と、これに並行する半ば奇形的で非有機的な現象(セム語、オリエント文化)とを統合し括りあわせてしまうのようなヴィジョンの維持を可能ならしめたのは、まさにヨーロッパの科学者が実験室でなした達成にほかならなかった。
オリエンタリストたちが描いたオリエントは、実験室で「事実」が生み出されたのと同様、実験室的なオリエンタリスト的な頭のなかで創造されたのであって、実験室のなかの事実が自然を映し出す鏡では必ずしもないのと同様に、東洋人の暮らしや思考を反映してはいない。
科学者とは構築する者であり、構築という行為そのものが、反抗的現象に対する帝国的権力のしるしであると同時に、支配的文化の力を確認し、これを「自然化」することなのである。実際、ルナンの文献学的実験室は、ヨーロッパ民族中心主義の実践の場であったといっても過言ではない。だが、ここで強調しておく必要があるのは、文献学の実験室が、つねに実験室がそのものを生み出し、また実験の機会を与えてくれるような言説や著作物の外側では、まったく存在しえないのだという点である。かくてルナンが生きた有機体と呼ぶヨーロッパの文化もまた、実験室のなかで、文献学者によって、創造された被造物なのである。
それはありのままを描いた言説ではなく、つくられた言説なのだ。
なのに、僕らはありのままとつくられた言説を混同してしまっている。
それがいまも続く知の問題なのだ。
とりあえず、上巻を読み終え、引き続き、下巻を読み始めた。
いよいよ20世紀のオリエンタリズムに言及が及ぶ。果たして、その変遷は僕らの時代にどうつながっているのだろうか。
P.S.
下巻も読み終えました。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
