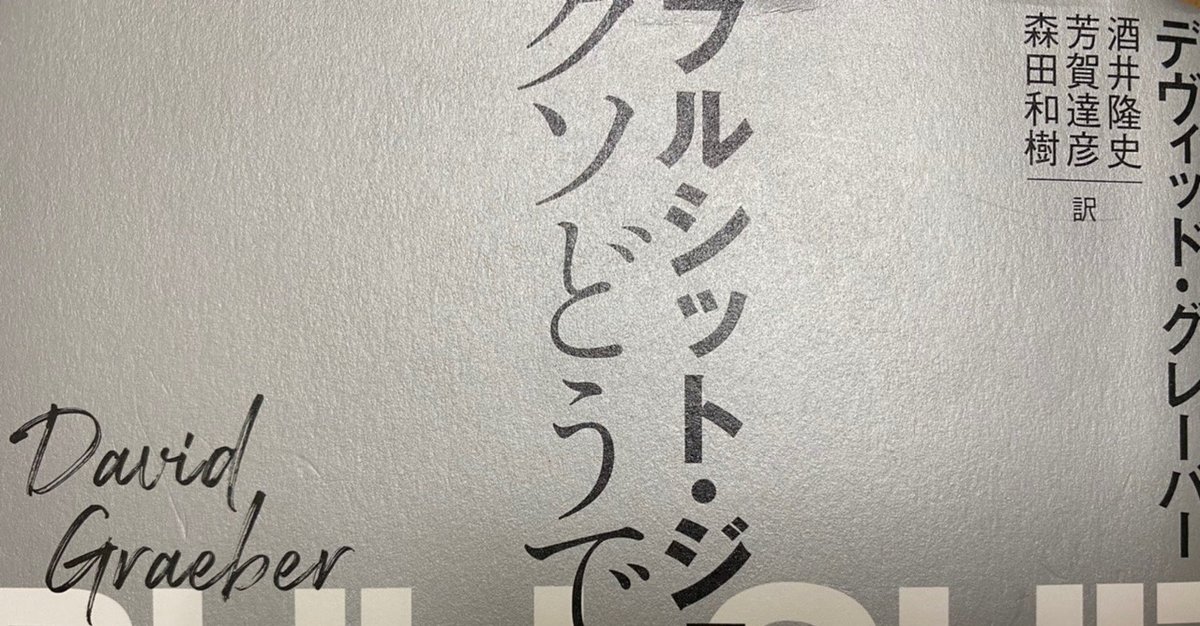
ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論/デヴィッド・グレーバー
最初に書いておこう。
この本はとにかくみんな読んだほうがいい!
その理由はあとで説明するが、この本を読んで、まあ、世の中は、こんなにも「クソどうでもいい仕事」であふれているのか!とまず唖然とした。
この作業、本当にやる必要があるのだろうか?と思うことは、僕の日常にだってある。
でも、自分の仕事全体的でそれが「クソどうでもいい仕事」だとは思わない。幸運なことに。
そう。それは幸運なことかもしれない。
デヴィッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ』。
この本に掲載された、ブルシット・ジョブに自分がたずさわっていると自覚している多くの人からの「訴えの声」を読むと、「自分たちの仕事はなんの影響も及ぼしていない」と考える人がそんなにもいるのかと驚く。
すくなくとも、ここで紹介されているイギリスとオランダでの調査にもとづけば、一国の労働人口のうちの37%から40%が自分たちの仕事がブルシットだと感じているのだという。

不条理きわまりないブルシットな仕事
たとえば、1章の冒頭で紹介されている、ドイツ軍から下請けの、下請けの、下請けとして雇われているクルトの例などはすさまじくブルシットだ。
ある兵士が2つ隣の部屋に引っ越す際、PCを移動するのに自分で運ぶことはできず、書類に記載し移動を依頼する必要がある。
一次請のIT企業がその書類をうけとり、二次請の物流会社がそれを受託。
それで物流会社が移動するのかというと、そうではない。ここからが強烈にブルシットだ。
物流会社はさらに三次請の人材管理会社(クルトの会社だ)に連絡をし、パソコンの取り外し、梱包、移動に際しての必要書類の記入、そして、物流会社が梱包した荷物を移動(たった2つ隣の部屋に!)したら、また別の書類に移動完了の記載をし、パソコンの梱包をといて設置し、完了の電話をして作業報告をするという仕事を依頼する。
しかも、クルトはこの「その仕事いる?」と思える仕事をしに、レンタカーを借りて自宅から100キロから500キロ離れた兵舎に移動するのだという。
まるでフランツ・カフカの『城』の世界だ。
不条理きわまりない。
『城』の主人公である自称測量士であるKは、自分を雇ってくれるはずの城に住む伯爵が領主である村に辿り着くが、さまざまな人のメッセージにたらい回しにされ、無意味な行動をひたすらさせられる。城にも、伯爵のもとにも、そして、測量士の仕事にもありつけないまま、無駄骨のような行動を延々させられる。
そんなKのように、何のためにそれをやらされているのかわからない、無意味で理不尽な仕事が、このクルトの仕事も含めて、実はこの世界にはありふれていることを教えてくれるのが、先日、9月2日に亡くなったばかりの人類学者にしてアナーキストであるデヴィッド・グレーバーのこの本なのだ。
ブルシットな仕事とは
クソどうでもいい仕事とは、どういうものか。
最終的な実用的定義=ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償な雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうでないと取り繕わなければならないように感じている。
グレーバーはこんな風に定義している。
そんなブルシット・ジョブがどれだけ世界に溢れていて、それがどんな問題――とくにブルシット・ジョブにたずさわる人びとのメンタルの問題――を引き起こし、どうしてそんな仕事がどんどん増えてしまっているのか?が問うているのが、本書である。
ブルシットで、必要なさすぎて、その仕事をしてる人が実際に仕事をせずに何年もすごしても気づかれなかった例も紹介される。
たとえば、スペインの水道局で働いていたホアキンの例がそうだ。
少なくとも6年にわたって、仕事をせずに給料を受け取っていたスペインの公務員が、その時間を使って、ユダヤ人哲学者、バルフ・スピノザの著作の専門家となっていたことが、スペインのメディアによって報道された。
ユーロニュース・ドットコムが先週報じたところによれば、先月、南スペインにあるカディス裁判所は、水道局勤務のホアキン・ガルシア(69歳)に対して勤務先のカディス水道局を欠勤しつづけたことから、罰金30,000ドルを科した。ガルシアは、技師として1996年から同局に雇われていた。
技師が6年間欠勤しつづけても問題にならないどころか、気づかれもしないというのは、いかにその役割がそもそもなくても大丈夫だということを物語っている。
しかも、このホアキンの欠勤が発覚した理由が笑える。
同氏の不在が最初に発覚したのは2010年で、ガルシアが永年勤続表彰を受賞したさいにだった。副市長のホルヘ・ブラス・フェルナンデスが調査を実施したところ、ガルシアが6年にわたって職場に不在であった事実が発覚した。
しかし、このホアキンのように、自分に与えられている役割が不必要なものであることを自覚しつつも、クルトの例のように具体的な不必要な仕事は渡されることはない場合はまだ幸運かもしれない。
その空いた時間を好きにスピノザの研究をする時間にあてられるのだから(度を越して、あとで罰金を課せられたけど)。
問題は、多くのブルシット・ジョブが本来やらなくてもいいような不必要きわまりない仕事を無理やりやらされる点にある。
取り巻きの仕事とは、だれかを偉そうにみせたり、だれかに偉そうな気分を味わわせるという、ただそれだけのために(あるいはそれを主な理由として)存在している仕事のことである。
尻ぬぐいの最もはっきりした例は、目上の人間の不注意や無能さが惹き起こした損害を原状復帰させることが仕事であるような部下である。
「取り巻き」と「尻ぬぐい」は、グレーバーが示したブルシット・ジョブの類型のうちの2つだ。
見てのとおり、管理職の業務のまわりにブルシット・ジョブが生みだされているのがわかる。
ブルシット・ジョブが心を壊す
まったく必要のない仕事でも、我慢してやっていれば、給料をもらえるのならいいのではないかと考える人もいるかもしれない。
たしかに、そういう人もいなくはないだろう。
なにもすることがなくてもこっそりPCでゲームやネットサーフィンして過ごしたり、意味のない仕事だと思いながらも時々まわりとおしゃべりしながら言われたことをやったりしながら、それなりの給料をもらえているなら、まあ、なくはないかと考える人もいるだろう。
しかし、ブルシット・ジョブの無意味さに、その無意味なものに自分の人生の時間を無駄にさせられていることから、心が壊れてしまう人も少なくない。
エリックをおかしくしたのは、自身の仕事がなんらかの目的に奉仕しているようには、どうしても解釈できないという事実であった。エリックには、家族を養うためだと自分を納得させることもできなかった。当時、家族をもっていなかったのだから。かれの出自は、人びとの大多数が、事物の製造や、保守や、修理に誇りをもっている、あるいはともかく、そのようなことに対してひとは誇りをもつべきだと考えている、そのような世界であった。だから、かれのなかでは、大学への進学も専門職の世界に入ることも、同様のことをもっと意味があってもっと大きなスケールでやるのとイコールだった。ところが、現実には、かれはまさに自分のできないことでもって職を得てしまった。辞職しようとした。すると上司らは、給与を上乗せしてきた。クビになろうとしてみた。上司はクビにしなかった。
このエリックのように、自分でその仕事の無意味さを自覚して、クビになろうとしてもなお、給与を上乗せされて、ブルシット・ジョブから身を剥がすことができないという例はたくさんある。
また、無意味だと感じても、その仕事の給与が高くて、ほかの仕事(ブルシットではない、意味のある仕事)に移れないことにストレスを感じる人の例もたくさん紹介される。
問題は、先にもあげたように管理職まわりにブルシット・ジョブが集まるように、高給取りのホワイトカラーの仕事のほうがブルシットだということだ。
もしある朝起きて看護師やゴミ収集に従事している人びと、整備工、さらにはバスの運転手やスーパーの店員や消防士、ショートオーダー・シェフ〔手早くできる料理を担当する料理人〕たちが異次元に連れ去られてしまったとすれば、その結果はやはり壊滅的なはずだ。小学校の先生たちが消え去れば、学校に通う子どもたちのほとんどが1日や2日は大喜びするだろうが、その長期的な影響は甚大であろう。(中略)ところが、ヘッジファンド・マネージャーや政策コンサルタント、マーケティングの教祖、ロビイスト、企業の顧問弁護士、あるいは大工が来なかったことを謝罪するのが仕事であるような人びとに、同じことをいうことはできない。
このパンデミックであらためて明らかになったように、看護師、ゴミ収集人、飲食店従業員、スーパーの店員、バスの運転手などは、どれほど世の中に不可欠な仕事だろうか。
それらの仕事は、リモートワークで済ませてしまえる仕事よりもあきらかに誰かの役に立ち、それらの人が数日働かなくなっただけで、社会がパニックになる。
しかし、残念ながら、そういう人の仕事のほうが薄給だったりするのだ。
だから、どんなにいまの仕事がブルシットでも、家庭があったりするとなかなか仕事を変わらなかったりする。
そして、仕事がブルシットなものであればあるほど、人は心を病んでしまうという、どちらを選んでも地獄のような状況がある。
なくなっても社会に支障がない仕事
残念ながら、なくなっても社会に支障がない仕事が多いようである。
この2つの例なんか、見事なまでにそのことを示しているのではないだろうか。
近年、ベルギーは、政府が成立しないままの状態、すなわち首相もいなければ、保険や交通、教育を担当する人間もいないままの状態が一時的に続くという体制危機を経験してきた。ところが、かなりの期間――記録的には541日――にわたるこうした危機のあいだ、保健、交通、そして教育に目立った悪影響がなかったことはよく知られている。
世界で最も勢いのある会社の1つとみなされているウーバー社で、創立者のトラヴィス・カラニックだけではなく多数のトップの役員たちが辞任することになったが、それ以降も、会社は「目下のところ、CEO、最高執行責任者、最高金融責任者、最高マーケティング責任者の不在のまま維持されている」。要するに、日々の業務にはなんらの支障もないのである。
多くのブルシットな仕事が、官僚的な仕事、管理業務やそれにまつわる書類書きや整理の仕事だったりするわけで、それこそ政府や企業の管理部門の多くが実はなくなっても困らないものなのだろう。
このパンデミックにおいても、日本の政府がほとんど何も行わなくても、この国ではさほど感染被害は広がっていない。
その一方で、余計な対策によって感染被害が広がったり経済的な打撃を受けていたりする人がいるはずだ。
おそらく、企業のなかでもなくてよい指示や管理が山ほどあって、そうしたものがなければ、もっと社会は豊かになり、うまく問題も解決されているのではないかと思えてくる。
しかし、そういうブルシットな仕事をしてる人たちが、なぜか社会にとって有益で欠かせないはずの仕事をしている人たちを苦しめる。
イギリスにおいては「緊縮政策」の8年間に、看護師、バスの運転手、消防士、鉄道案内員、救急医療スタッフなど、社会に対し直接にはっきりと便益をもたらしているほとんどすべての公務員の賃金が、実質的に削減された。その結果、チャリティーの食料配給サービスで生計を立てるフルタイムの看護師があらわれるにまでいたったのである。ところが、政権与党はこの状況をつくりだしたことを誇りに感じるようになっていた。看護師や警察官の昇給を盛り込んだ法案が否決されたとき、歓声をあげた議員たちがいたくらいである。この政党はまた、その数年前には、世界経済をほとんど壊滅に追い込んだシティの銀行家たちへの補償金を大幅に増額すべきという大甘の見解をふりまわしたことで悪名高い。にもかかわらず、その政府の人気は依然として衰えを知らなかったのである。
どこの国の政府も同じようなものなのだろう。
そして、どこの国も似たように、ブルシットな仕事を増やし続けている。
この不可思議な現象がなぜ起きているかについてのグレーバーの考察が素晴らしすぎる。
この本を読むべき理由はまさにそこにある。
この本を読むべき理由
グレーバーは、近年、あたらしいサービス業(昔ながらの飲食業や美理容業、接客業ではない、コンサルティングや会計士、金融保険、その他情報産業)の経済全体に占める割合が増え、多くのブルシット・ジョブがその領域で増えていることを指摘しつつ、何故、そんなクソどうでもいい仕事が増加しているのかを問うために、そもそも歴史的に「仕事」とはどんなものと見做されてきたのか?を振り返っている。
近代経済学の中核をなす諸前提のほとんどが、そのルーツをたどれば神学的な議論に帰着するのである。たとえば、わたしたちは有限の世界のなかで無限の欲望に呪われているため、おのずと〔自然状態において〕競合の関係におちいるほかないという聖アウグスティヌスの議論である(17世紀に世俗的なかたちでトマス・ホップズにおいて再登場する)。この議論は、人間行動の合理性とは「節約」の問題であり、競合関係のただなかで合理的アクターにより稀少な資源をいかに最適に配分するかの問題であるという考えの基礎となった。
グレーバーは、仕事を評価する際に用いられることの多い「生産性」あるいは「生産」という概念は、「本質的に神学的である」と主張する。
「ユダヤ教とキリスト教の神は、無から宇宙を創造した」。そう考えた人びとは、「無から宇宙を創造するという点で、神を模倣すべく呪われている」。
その結果、「生産」以外の人間労働が見えなくなった。
見えなくなったのは、人が人の世話をしたり、植物や動物の面倒をみるような人以外のものの世話をしたりする、グレーバーが「ケアリング」と呼ぶ類の仕事である。
それは主に家庭内の仕事として無報酬で行われているが、先のなくては困る仕事をしている人たちの仕事も基本的にそれである。
ところが、そういう仕事は無報酬もしくは低報酬の仕事とみなされ、「生産性」が高いとみなされたり、生産性の高さを問う管理的な仕事が、仕事とみなされる。
グレーバーが示す、この「価値(value)」と「諸価値(values)」の区別にもそれが現れている。
現在使われている英語では、しばしば単数形の「価値(value)」と複数形の「諸価値(values)」とが区別される傾向にある。金の価値、豚バラの価値、骨董品の価値、金融派生商品の価値などというときは、単数形の「価値(value)」が使われるのに対し、家族、宗教道徳、政治理念、美、真実、尊厳などにかかわるばあい、複数形の「諸価値(values)」が使用される。
単数形の「価値(value)」は、生産的であるのに対し、「諸価値(values)」のほうは非生産的なものだとみなされる。
付け加えるなら、単数形の「価値(value)」には値がつけられるが、複数形の「諸価値(values)」のほうはほとんどプライスレスなのだ。
「諸価値(values)」に分類される、このプライスレスな価値あるものが、生産的な仕事から除外される時点で、仕事がブルシットなものにするものの影が覆い被さろうとしているのが感じられるだろう。
無報酬な仕事、サービス
無報酬な仕事。サービス。
このサービスという考えにまつわる、中世の封建制における「ライフサイクル奉公(サービス)」という概念をブルシット・ジョブにつなげるという発見がグレーバーのすごいところである。
理論的には、封建社会は広大なサービスのシステムだった。農奴のみならず下級の封建領主も、上位の封建領主に「奉公(サーブ)していた」。さらにその上位の領主は王に封建的奉公(サービス)を供与していた。しかしながら、ほとんどの人びとの生活にとって強い影響をもたらしていた最も重要なサービスの形態は、歴史社会学者たちが「ライフサイクル」奉公(サービス)と呼ぶものである。基本的に、ほとんどすべての人間が、みずからの仕事人生の大まかにいって最初の7年から15年を、よその世帯の奉公人(サーバント)として仕えるものとされていた。
貧しかろうと、裕福だろうと、封建制の社会においては、若者は他所の家に奉公(サービス)をしに出た。7年から15年という決して短くはない期間ではあるが、親方のもとで弟子として働き、その後は独立して自分が親方となって弟子をとることができた。
中世においては、マナーという語は、いまのエチケットという言葉よりはるかに広い意味をもっていたのだとグレーバーは指摘する。
「支払い労働も教育も、ともに「あさましい欲望の統御法を獲得」するべく自己規律を学ぶ過程であり、しっかりと自立した大人のようにふるまう術を学ぶ過程とみなされていた」というのが、徒弟制を行う意味であり、人はそうして生き方としてのマナーを身につけていたのだ。
この時代はまだ、仕事には、生産すること以外の価値がちゃんと認められていたのだとわかる。
人としてどう生きるかも含めて仕事だと見做されていたことが。
マナーはどこへ?
しかし、近代になって、そのマナー習得のあり方が大きく変化してしまう。
「資本主義の出現とともにすべてが変わることになる」のだ。
資本を所有している人間と資本を所有しておらずそれゆえ仕事を強いられる人間とのあいだの関係への変化である。人にとってこれが意味しているのは、なによりもまず、無数の若者が反永続的に社会的青年期に囚われているということである。ギルドの組織が解体していくにつれて、依然として徒弟は1人前の職人になることができたが、1人前の職人はもはや親方になることができなくなった。このことが意味しているのは、伝統的な観点からすれば、かれらは結婚して自分の家族をもつ立場にいないということである。かれらに求められたのは、未熟な人間のまま人生をまっとうすることだったのだ。
この変化で何が起こったか。
フィリップ・スタッブズというピューリタンによる16世紀のマニフェスト『悪弊の解剖』からの引用がすべてを物語る。
おまけに、10歳、14歳、16歳、あるいは20歳の生意気な少年が、神への畏れもなく、女性をつかまえ、結婚している……それどころではない。己の職業や身分をわきまえず、いかようにふたりでやっていくのか、とんと考えなしなのだ。(中略)こうして連中は、ほとんどありとあらゆる小路に古い柱のあばら屋を建てて、それ以降の人生を乞食として暮らすのである。この国はそれで物乞いであふれているのであり……まもなく連中は増えていって貧困と物資不足をもたらすであろう。
仕事にありつけない貧困層が急増したのだ。
プロレタリアートの誕生である。
プロレタリアートという語は「子どもを産む人びと」という意味のラテン語に由来する。
グレーバーは、スタッブズの『悪弊の解剖』を、ピューリタンによる「マナー改革」宣言とみなしうると指摘する。
中世までのマナーをつくる仕組みとしてのライフサイクル奉公が失われたからこそ、あらたなマナーを育てる仕組みとしてのピューリタニズムを生みだそうとしたわけである。
グレーバーは、中世までのライフサイクル奉公が解体されたことで、プロレタリアートが形成されたのだという大きな文脈を理解することなく、プロテスタントの労働倫理の起源を理解することは不可能だと指摘する。
イングランドのカルヴィニスト(「ピューリタン」は、かれらを嫌悪する人びとによってあてがわれた名称である)は、親方層やあたらしく形成されつつあるプロレタリアートを雇用する「開明的な」農民層から支持される傾向にあり、かれらの称える「マナー改革」は、民衆の祝祭や賭け事、飲酒、そして「若者たちが一時的に社会的身分関係を逆転させるような無礼講をともなう年中行事のすべて」をとくに標的としていた。ピューリタンの理想は、そのような「主人なき男たち」をかき集め、敬虔な世界の厳格な規律のもとにおいて、家父長の指導によって仕事と祈りを叩き込むことであった。しかし、これは、諸下層階級のマナーを改革する試みにかんする長期の歴史のはじまりにすぎなかった。貧民に正しい時間の規律を教え込んだヴィクトリア朝の救貧院から、今日のワークフェアやそのたぐいの政府プログラムにいたるまで、脈々とその歴史はつづいている。
そうしたピューリタンたちの努力も虚しく、結局は、マナーを身につけるしくみは失われてしまった。
ただ、残されたのは、仕事から楽しみを抜き去ったあとの、苦行のような仕事だけだった。
仕事の大多数はケアリングである
そして、いまAIによる自動化の波によって多くの職が危機に晒されていると言われる。
しかし、果たしてそれは本当だろうか。
グレーバーはそのことに疑問を投げかけることで、ブルシット・ジョブの正体をより明らかなものとする。
自動化によって、地下鉄職員の仕事が失われるという話となったとき、地下鉄職員たちは、実際の彼らの仕事のほとんどが地下鉄にのる人たち――障害のある人、小さな子ども、お年寄りも含まれる――の手助けであることを主張した。
つまり、彼らの仕事は、ぼくらがそう思っているような機械的なものとはまるで違っていて、とても自動化に見合ったものではないということだ。
地下鉄労働者が実際におこなっていることは、フェミニストが「ケアリング労働」と呼ぶものにかなり近いものである。それはレンガ職人よりも看護師の仕事のほうに共通点を多くもっているのだ。女性の不払いケアリング労働が「経済」についての説明から抜け落ちているのと同じように、労働者階級の仕事におけるケアリングの側面はみえなくなっている。
ブルシット・ジョブが増えてしまっているのは、ピューリタニズムの形骸化した部分だけを受け継いで、仕事とはあたかも苦行であり、目に見えて生産的なものだけを指すというふうに間違って定義してしまっているところにある。
そのことによって、人が人を幸せにしてくれるケアリング労働は無償のサービスであるかのようにみなすようになり、それらを無報酬、低報酬でとるにたらないものであるかのようにみせてしまう。
このまま、仕事とは、生産性を高めることであるという、経済的な価値――単数形で、値がつけられる「価値(value)」――ばかりを重視したまま、自動化を進めれば、この持続可能性が問われる社会の要請とはまるで逆行した事態が起こるだろう。
人間的観点からすれば、食べ切れないほど大量の食料を消費するために何百万ものロボットを組み立てたり、国民が死滅してしまっては経済に悪影響を与えるからという理由でHIVに対応せよとアフリカの国々に対して勧告することを(周知のように世界銀行はしばしばこれをおこなっている)は、まったくもってイカれている。
まさに、このパンデミックの状況下において、異常なまでに経済の再稼働を重視する姿勢がこの発想から生まれている。
そうではなく、プライスレスな価値をもった複数形の「諸価値(values)」を生むケアリングのような仕事の意味をもう一度見直さなくてはならないはずだ。
カール・マルクスは、かつてつぎのように指摘した。産業革命以前には、最大の富はどのような条件においてつくりだされるのかという問題について本を書こうなどという発想は、だれの頭にも浮かぶことはなかった。しかし、最良の人間がどのような条件においてつくられるのか――すなわち、友人や恋人、仲間や市民として共にありたいという気持ちを抱かせるような人間をつくりだすために社会はどのようにあるべきなのか、については多数の書物が著されてきた。アリストテレスや孔子、イブン・ハルドゥーンが関心をよせた問題はまさにこれであり、つまるところいまだ真に重要なただひとつの問題がこれなのである。人間の生活とは、人間としてのわたしたちがたがいに形成し合うプロセスである。極端な個人主義者でさえ、ただ同胞たちからのケアとサポートを通してのみ、個人となる。そしてつきつめていえば、「経済」とは、まさに人間の相互形成のために必要な物質的供給を組織する方法なのである。
この引用の最後の一文に尽きるだろう。
「経済」とは、まさに人間の相互形成のために必要な物質的供給を組織する方法なのである。
もちろん、なにより「必要な物質的供給」とは、たがいをケアするためのものであろう。
そういう供給がたがいにできるように、仕事のあり方、経済のあり方、そして、これからのマナー=生き方を変えていくためにはどうしたらいいだろうか?
そんなことをみんなでいっしょに考え、行動していくことができるように、ぜひ、この本を読んでみてほしい。
こんなに素敵な一冊はそうそうないと思うから。
この記事が参加している募集
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
