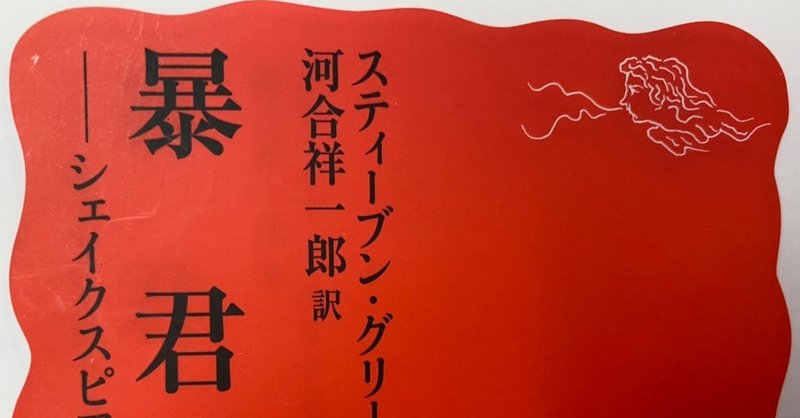
暴君 シェイクスピアの政治学/スティーブン・グリーンブラット
この世の中に一番足りないもの、それはフェアなことではないだろうか。
とにかく公正さが欠けている。
みんながみんな、自分のこと優先で、意図するかしないかにかかわらず、他人のことを顧みずに、他人から奪う。奪っている意識さえないのだから、たちが悪い。気づきもしなければ、奪われる不幸な側は永遠に奪われ続けてしまうかもしれないのだから。
その意味では、いまや誰もがこの本に描かれた暴君と変わらない。

スティーブン・グリーンブラットの『暴君 シェイクスピアの政治学』。
『ヘンリー六世』、『リチャード三世』のような最初期の作品から『マクベス』や『リア王』などの4大悲劇に数えられる中期の作品にいたるまで、シェイクスピアの作品には数多くの暴君が登場する。
なぜ国全体が暴君の手に落ちてしまうなどということがありえるのか?
暴君がなぜ可能になってしまうのか?を考察したのが、本書であり、著者のグリーンブラットは、こうした暴君が支配する世の中の持続性について、こんな風に言っている。
専制政治は、今いる者のみならず、これから生まれる世代をも永遠につぶさなければ続かない。マクベスがリチャードのように子供殺しとなるのは偶然ではない。暴君とは、未来の敵なのだ。
自分のいまある状態を続けようとするだけで、今存在する者たちだけでなく、これから生まれてくる者たちも含めて、つぶし続けなくてはならない。まさに究極の搾取だ。
暴君がこんな風に「未来の敵」なのだとしたら、社会の持続可能性に致命的な欠陥をもったいまの状況をもたらしてしまっている僕らはまさに暴君みたいなものだ。
そんなことを思いながら、この本を読んでいたので、とても参考になった。
誰かの不幸を踏み台に
この本で紹介されるシェイクスピア劇の暴君たちは、自らが王の座に上り詰めるため、あるいは、上り詰めた王の座を維持し続けるためだけに、多くの者を殺したり殺させたりする。
その残虐な行為の対象となるのは、敵対する者だけでなく、味方や忠信を誓った部下、さらには自分の親や兄弟、妻や子供に至るまで際限をしらない。
狡猾な悪知恵をはたらかせ、他人を罠に陥れて死に至らせることを繰り返すうちに、誰のことも信じられなくなり、他人のちょっとした行為が自身に対する裏切りや敵対であるかのように思えて、残虐な暴挙を繰り返してしまう。まさに底なしだ。
僕が思い出していたのは、斎藤幸平『人新世の「資本論」』で紹介されていた、リチウムイオン電池をつくるために必要なコバルトの採掘の話だ。コバルトの約6割は、「アフリカでも最も貧しく、政治的・社会的にも不安定な国」と言われるコンゴ民主共和国で採掘されている。
コバルトの採掘は、地層に埋まっているそれを重機や人力で掘り起こす単純なものだという。しかし、いかに単純とはいえ、携帯電話やパソコン、そしてガソリンエンジン者からのシフトで今後増え続ける一方の電気自動車など、世界中のリチウムイオン電池の需要をまかなうためには採掘は大規模になるし、どんどん拡大が求められる。その結果、コンゴでは水質汚染や農作物汚染といった環境破壊、そして景観破壊が引き起こされているというのだ。
それだけではない。劣悪な労働条件の問題もある。
コンゴ南部では、クルザー(仏語で「採掘者」の意味)と呼ばれるインフォーマルな形での奴隷労働や児童労働が蔓延している。ノミや木槌のような原始的な道具を用いて、手作業で、コバルトの採掘に従事しているのだ。そのなかには、6-7歳程度の子どももおり、賃金は1日あたりわずか1ドルほどだという。
こうした子どもたちの1日1ドルほどにしかならない過酷な労働なしでは、僕らは毎日スマホを使い続けることも、ガソリンエンジン車から電気自動車に乗り変えてエコだなんて思いこむこともできないのだ。
こうした搾取のうえに僕らの暮らしは築かれ、この犠牲なくしては維持できないのだとしたら、シェイクスピア演劇で描かれる暴君たちと何が違うのだろう。
まったくもって、アンフェアだ。
読みながら、そう思わずにはいられなかった。
暴君を可能にするもの
僕らはなぜこうしたアンフェアな搾取をやめられないのか?
それを考えるうえでも、この本で問われるなぜ暴君が可能になってしまうのか?という問いは参考になる。
自由社会は、ブカナンの表現を借りれば、「国民の利益を考えずに私利私欲に走り、国のためでなく自分のために」政治を行おうとする者を排除する仕組みになっているはずなのだ! 一見堅固で難攻不落に思える国の重要な仕組みが、どのような状況下で不意に脆くなってしまうのかと、シェイクスピアは考えた。なぜ大勢の人々が、嘘とわかっていながら騙されるのか? なぜリチャード3世やマクベスのような人物が王座にのぼるのか?
暴君が王座にのぼるのは、暴君のみの力によるものでもない。暴君が暴君たりえるのはもちろん暴君そのものがもつ性格や運命にもよるが、彼一人が彼を暴君たらしめるのでもない。
暴君を暴君として可能にするためには、まわりの力もいる。『ヘンリー6世』のヨーク公には、ジャック・ケイドがいた。『リチャード3世』のリチャードには、バッキンガム公やケイツビーが、『マクベス』のマクベスには妻がいた。
いや、そうした暴君のまわりで、暴君の悪事を助けたり、そそのかしたりする者だけではない。
暴君が悪いと知りながら恐れのあまり意に従うもの、問題はあるかもしれないと思いつつ、とりあえず現状の問題を解決してくれるかもしれないと期待して暴君の嘘に騙される市民たち。
暴君そのものまでの暴虐さはもたないまでも、他人を犠牲にすることですこしでも自分に利を得ようと、暴君に協力したり従ったり持ち上げたりしてしまう、自身のためなら他人の不幸には目を瞑るやからが多くいるからこそ、暴君は王座につくことが可能になってしまう。
暴君の命令に理由はない
そして、そういう人たちがたくさんいるからこそ、暴君はそういう人たちに忠誠を尽くさせようとし、そうでない人がそれを拒めば殺したり追放したりする。
その行為を正当化するものは暴君の意思以外の何の理由もない。彼がそれを望むかどうか、それだけだ。
暴君には、事実や証拠などどうでもよい。自分が非難しているだけで十分なのだ。誰かが裏切り、嘲り、こちらをスパイしていると王が言えば、そうに違いないのだ。反対する者は嘘つきか愚か者だ。かりに誰かの意見を求めるようなふりをしても、意見などほしいわけではない。暴君が本当に求めているのは忠誠であるが、誠実、名誉、責任を伴う忠誠ではない。暴君が求める忠誠とは、暴君の意見を臆面もなく直ちに承認し、暴君の命令を躊躇なく実行することだ。ワンマンの被害妄想の自己愛的な支配者が、公務員と席をともにして忠誠を求めるとき、国家は危険なことになる。
暴君が何の理屈もなく、ただひたすら自分の意思を全員に押しつけようとすることが可能なのは、それを認めてしまう人がいるからだ。
委ねてしまう人たち
自分の意思を自分自身で行使する労力を割くことなく、他人へとその実行を委ねてしまう人。
自分で何も考えて決められないがゆえに、誰かの指示待ちの人。
そうした人たちが他人へと力を委ねていく蓄積が、あとで誰もコントロールできないような、勝ち組と負け組、富者と貧者、強者と弱者のような格差を生み、一方がとことん得て、他方がひたすら搾取され続けるようなフェアなところがどこにもない状況を用意してしまうのだ。
そして、多くの人々が自分で考えることなく、自分の外へと判断責任を委任してしまうことで、無意味な派閥と無意味な派閥争いの構図もできてしまう。
『ヘンリー6世』で派遣争いを繰り広げることになる、ヨーク公とサマセット公の場合もそうだ。
歴史上のヨーク公とサマセット公は、個人的な軍隊をゆうする強力な封建領主であり、ブリテン島の特定の領域を巧みに統治していた。この劇は現代のアフガニスタンの将軍らを思わせるような書き方をすることだってできたが、そうなってはおらず、政党が生まれて、対立する貴族が政敵へと変わっていく様子がわかるような書き方をしている。(中略)シェイクスピアが見せてくれるものは、奇妙にも我々に見覚えがあるものだ。薔薇は政党のバッジのように機能し、2つの対立する政党を表す。法的議論(それが何であったにせよ)は、白か赤かをただ選ぶことに変わってしまう。奇妙にも現代の政治そのままではないか。
まったくもって、現在の政治でもみられる本質を外した対立、諍いだ。
王であるヘンリー6世がまだ若すぎて、王の役割を担うことができないがゆえに、実質空席ともいえる権力をめぐって諸侯たちが争う。
その争いは本質を失って、自分たちが赤か白か、そして、互いに色が異なるというだけで、永遠と対立し続ける。
本質を欠いた対立だから争いは止まらない
しかしながら、本質を失った対立だから、ほっといても大丈夫なのではない。むしろ、逆だ。
本質的な意味ある対立項を欠くからこそ、論点は合うはずもなく、結局、暴君的なものの典型としての、自分の考えと同じかどうか、違ったら漏れなく攻撃の対象となるような状況に陥ってしまうのだ。
まるで王という支配的存在がいないがゆえに、赤薔薇と白薔薇という純粋に因習的で意味のない象徴が、突然の派閥の結束と派閥間の憎悪を生んだかのようだ。
この憎悪こそ、やがては社会崩壊そして専制政治へとつながる重要な要素となる。憎悪のせいで、敵対する相手の声が絶えがたく思え、敵のことを考えるだけで我慢ならなくなる。敵か味方か、そのどちらかでしかありえず、味方でないなら憎み、敵は全員ぶっつぶすまでだ。どちらの派閥も当然ながら権力を求めるが、権力を得ようとする行為それ自体が怒りの表現となる。
権力を求める気持ちは、自らに逆らうあらゆるものを敵とみなすよう働く。そして、「敵は全員ぶっつぶす」のだ。
面倒
こんな敵対関係を可能にするのも、自ら考えることを面倒がり、それを他人へと委ねてばかりの人たちが自身の意思なく過ごそうとするからゆえのことでもあるのだ。
そして、それは暴君自身も同じなのだ。
面倒だと思うがゆえに、ひたすら自分に逆らおうとするもの、疑わしいものを排除することをやめられなくなる。
「ここまで血の川に浸りきったら、もはや先に進みたくなくとも、/今更引き返せぬ、渡り切るのみだ」。
原文では「引き返すのは、渡り切るのと同じくらい面倒だ(tedious)」と、「面倒」という語が用いられているが、この語はマクベスが今いる悪魔のような状態を表すのにふさわしい。道徳を考えたり、戦略を練ったり、基本的な情報活動などどうでもよくなって、ただ何とかしようとあがくのみだ。立ち止まって考えたりせず、衝動的にやってしまったほうがいいのだ。
後戻りすることなく、ひたすら衝動のまま突き進むしかなくなる。悪いと思ったところでもはやブレーキはない。
温暖化ガスがでるのがわかっていようと、マイクロプラスティックが海に流出し続けようとも、遠く離れた国の生活がどんどん悪化しようとも、このままの生活を変えることができないのと同じことではないだろうか。
そして、そんな生活を惰性的に続けていくことは、そんなに長くはできない。だって、それは未来を犠牲にして、つぶし続ける行為なのだから、いつまでもこの先に「未来」があり続けるはずはない。
だから、こんな風に指摘されるのだ。
暴君は長続きするものではないと、シェイクスピアは考えていた。どんなに狡猾に頭角を現そうと、一旦権力の座に就くと、暴君は驚くほど無能なのだ。統治する国の展望もなく、持続的な支持も得られず、残酷で乱暴であっても抵抗勢力をすっかりつぶすこともできない。その孤立、疑い、怒りは、傲慢な過信と相俟って、その没落に拍車をかける。暴君を描く劇では、少なくとも共同体の再生と正当な秩序の回復を示唆して終わるのが常となっている。
そう。その未来をつぶす流れを食い止めようとするなら「少なくとも共同体の再生と正当な秩序の回復」が必要なのだと思う。
それは自らの判断や自らの責任ある行動を他人に委ねることなく、面倒な活動も自分たちのコモンズ(共有財産)として取り戻したコミュニティの再生が必要なんだと思う。
その方向に舵をとらない限り、僕らは誰かの不幸のうえに、自らの安泰を願う暴君のままだ。それは結局、自分たちの未来をも食い潰してしまう刹那的すぎる態度だ。
僕らは意思をもって、「未来の敵」=暴君であること。やめなくてはならない。
そんな思いを新たにさせられた一冊で、とても面白く読むことができた。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
