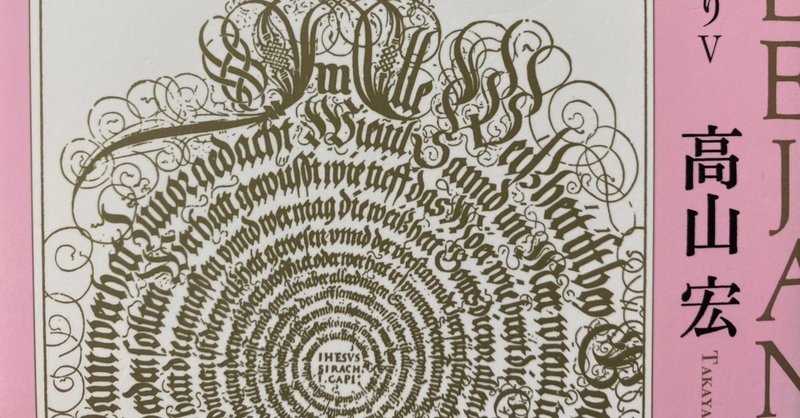
アレハンドリア/高山宏
僕の心のなかの悪魔は 凛と呟いた
あいつのなかの悪魔は お前を食いつぶすと
くるりの「心のなかの悪魔」の歌詞の一部だ。
何年か前に読んだ高山宏さんの『アレハンドリア』所収の「悲劇か、喜劇か 悪魔のいる英文学誌」を読み返しているとき、このくるりの曲がちょうどSpotifyから流れた。
17世紀のシェイクスピアやベン・ジョンソンの時代を中心に英文学に現れた「悪魔」について考察する小編のなかで高山さんは、こんなことを書いている。
1620年代に入り、清教徒の力が強まっていくにつれて、実存主義に向けての一種のすりかえ、近代化がおこなわれていくんですね。ハンス・ゼードルマイヤーのいわゆる「地獄の世俗化」だね。きみが行く所に即ち地獄があるのだ、と。
ピューリタニズムというのは、人間の内面的なものを価値の中心に置くわけで、外在的な神は案外無視していく傾向にある。それと同じように、悪魔もまた人間の心の中にある、フロイトのいうイドですね、それが投影されたものが悪魔なのだというような説明の仕方へとすりかえがおこなわれていく。
ここで指摘されているのは、17世紀の初頭の頃からピューリタニズムが力をつけていくにつれて、中世までの物語では具体的な形をもって人間の外部にあるものとして存在していた悪魔が、内面化され、形のないものとして、「心のなかの悪魔」へとすりかえられたという歴史的事象だ。
「地獄の世俗化」というのは、ある意味、印刷された聖書を各自が読むことが推奨されたピューリタニズムにおける神の個人所有という新しい宗教生活のあり方と連動しているのだといえる。
心のなかの悪魔が、凛と呟くようになったのは、その17世紀初頭以降のことに過ぎないのだ。
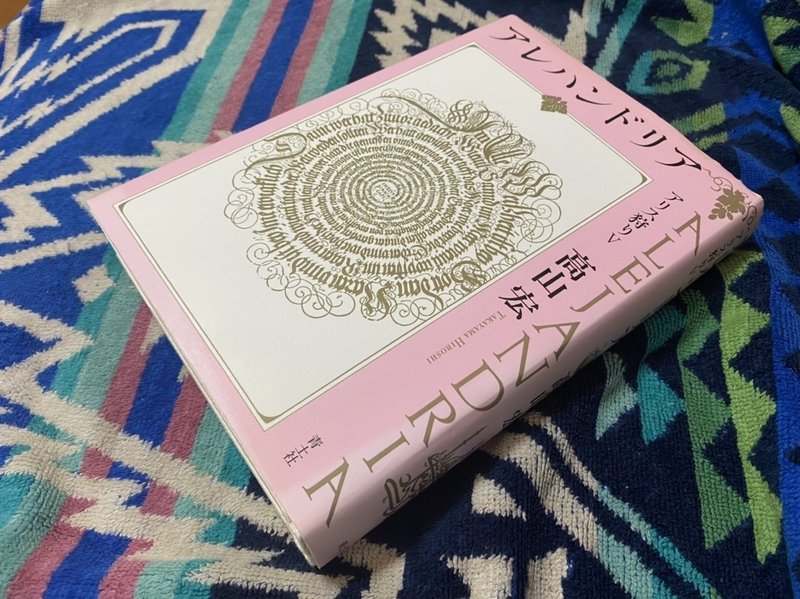
ヴァイスに誘惑されるエヴリマン
シェイクスピアが1606年に書いた『マクベス』に登場させた3人の魔女たちのように、「外にあって内面を誘惑するものなのか、あるいは本来、内面にある誘惑の声が外面化されたものなのか曖昧になってくるような、要するに心理現象としての悪魔が初めて描かれるようになる」のが、17世紀の初頭だが、そのシェイクスピアも、1591年初演の『リチャード3世』では「主人公自身が悪魔そのもののような、滅ぼされるべき王朝の最後の王として書かれ」た芝居をつくっている。
まさに悪魔の内面化という変換点にシェイクスピアはいたのであり、その変換を担ったひとりだったのだ。
シェイクスピアらによるその変換のすこし前に、「モラリティ・プライズ」という「悪魔の機能だけを取り出した不思議な演劇」が成立していたのだという。「ヴァイス VICE」という悪を擬人化したキャラクターが出てきて、「エヴリマン Everyman」と呼ばれた人間一般を意味するキャラクターを悪の道に誘惑する。芝居のほとんどが「ヴァイスの勝利という形で、エヴリマンがどんどん堕落していく過程を描く」のだが、「最後に、一種の機械仕掛けの神みたいなことが起こって、誘惑されていた男や女が、これじゃいけないと善の道に戻り、ヴァイスは去って行く」という筋の芝居だそうだ。
このモラリティ・プレイスはフランスやドイツにもあったが、イギリスでだけものすごく盛んになったという。それはチューダー王朝を正当化するプロセスにおいて、旧来の王朝はすべて悪=ヴァイスであり、それに対して善に導かれて誘惑に打ち勝ったのがチューダー王朝なのだという説明に芝居を用いたからだ、と高山さんは書いている。
そして、その典型例がシェイクスピアで、先の『リチャード3世』などは悪魔のような王をやっつけた王家として、当時のチューダー王朝の王エリザベス1世を盛り立てようとする意図があった芝居だとされる。
抑圧されたものの回帰
こうして誘惑する悪に対する、善の側の勝利として、悪魔の退散あるいは改心を描いたのがモラリティ・プレイスのような芝居であったのだが、とはいえ、そうした形式的な悪魔祓いによって消えるのは、せいぜいが中世的な外面化された悪魔の姿である。善との争いに敗れたかのようにみえる悪魔は、結局、人間の内面へと姿を隠す。このあたり、以前紹介した道化の話とも絡んでくるが、脱線してしまうので、興味のある人はこの辺りを読んでほしい。
こうした抑圧されたものが回帰してくるのは、それから300年ほど経った時期にフロイトが論じることへとつながっていく。
結局、人間の記憶を意図的に消すのはむずかしいということだろう。消したつもりで奥底に押しやってみても、時がくればそれはふたたび表へと這いだしてくるということなのだと思う。
そもそも抑圧されたものとしての悪魔のイメージそのものが、中世キリスト教社会が抑圧した古代ケルト文化のイメージを援用しているのだと指摘される。
ひとくちに抑圧されたものと言っても、その実態は差別された側のものがいろんな形で混淆されていますから一概にはいえないわけですが、基本的にはケルト文化だと考えていいと思う。それはいつ頃かということも難しいけれど、だいたい紀元前7世紀頃ではないかといわれています。ご存知のように、ケルトにはドルイドと呼ばれる古代祭儀の司祭集団がありまして、さっき言った死と再生の農耕儀礼を司っていた。そのドルイドたちのもっていた雰囲気や文化の中に、英文学における悪魔の起源を求めることができるだろうと思うんです。
この抑圧されたものの回帰としての悪魔的なものは、この引用中にもあるように、農耕社会における再生の儀礼としても用いられてきた。悪魔的なものの回帰を通じて、豊穣をもたらす再生が可能だとする具体的な儀礼の形がカーニヴァルだろう。
高山宏さんも言及しているように、ヤン・コットの『シェイクスピア・カーニヴァル』で展開される、カーニヴァル的なものとシェイクスピアやマーロウら16世紀末から17世紀初頭にかけてのイギリス演劇の関係に、この悪魔的なものを読み解く鍵がある。
コットからすこし引こう。
農人祭から中世、ルネサンスのカーニヴァルや祝祭まで通して、人間精神の高尚英邁な性質は片はしから――バフチーンが説得力豊かに示してくれたように――(特に排泄、放尿、性交、出山といった「下層原理」に力点が置かれた)肉体的諸機能に取って代わられる。カーニヴァル的知においてはそれらこそが生命力の精髄である。生命の持続を保証してくれるものだからだ。
悪魔は両義的なものとして、あらわれる。
既存の価値を破壊する存在であるのと同時に、腐敗したものをすっきりと洗い流して再生可能にする存在として。
バラバラな断片をつなぐ知識生産の方法
しかし、こうした両義的なものがもつ曖昧さへの嫌悪が表面化してきたのも16世紀末という時代であった。
高山さんは「シャーロック・ホームズのマニエリスム」という別の小論で、こんな風に書いている。
16世紀マニエリスムは曖昧や過剰に苦しみ、その逃げ場として無理矢理の単純さ、力まかせの整理術をうんだ。僕自身はこれをマニエリスム〈対〉近代という形ではとらえず、マニエリスムが内包する2段階とみて少し大掛かりなマニエリスム近代論を構想してきた。たとえばコンピュータ言語(0/1バイナリー、1667発明)はマニエリスムの綺想か、「近代」への突破口か。ルルス主義(最後はジョン・ケージ、一柳慧や松本潔にまで至る)を認めるなら、コンピュータ言語以上の組合せ術的マニエリスムはほかにない、ということになる。
16世紀という時代は、宗教改革とそれに伴う世俗の権力争いがヨーロッパ中を混乱させていた時代である。
イギリスにおいても1534年にヘンリー8世によりプロテスタントのイギリス国教会が設立され、多くのカトリック教会が廃止されたが、1553年にメアリー1世が即位すると、カトリック教会を復活させ、プロテスタントを取り締まって約300人を処刑した。ブラッディ・マリーと呼ばれる所以である。
そうした混乱のなか、1558年にエリザベス1世が即位する。女王はふたたびイギリス国教会を国教とするが、それもまた不十分なものとされ、清教徒たちがのち(1642-1648年)に革命を起こす流れとなる。
こうした混乱のなか、信じるべきものがなにかが曖昧になり、バラバラの事象をどう整理して有効な知へと編成しなおすかが課題であったわけである。
フランシス・ベーコンが1605年の『学問の進歩』や、1620年に『ノヴム・オルガヌム』で、従来の演繹的な知の生産方法に代わる、帰納的な知識生産の方法を打ち出したのも、15世紀半ばからの大航海時代によって広がった世界からもたらされるヨーロッパにとっては未知の事物や、コペルニクスやガリレオによって塗り替えられつつあった宇宙観、解剖学の発展によってこれまで不可視だった人体の内部が明らかになるなどの要因で、とにかく過剰にもたらされた未知の事物を「無理矢理の単純さ、力まかせの整理術」ででもまとめあげなくてはならない状況にあったわけだ。
間違いないのは、超越を欠く事物横溢の熱死状態の密室と化してしまった16世紀末以来の「近代」という展望であり、終りないディテールの累積という形で、部分ばかり見えて「全体」が見えなくなった世界で、部分を按配して仮想の全体に繋げる祭司の奇跡のような肉体行動と、そのことを紡ぐテキストの誕生である。主知的思弁の極とも言うべきマニエリスムの出発点が「マヌス manus」即ち「手」である時、頭と化す手こそこれからのアートだと言い放ったミケランジェロの言葉を思いだす。
この状況こそが、ひとつ前に紹介した『リヴァイアサンと空気ポンプ』が考察の対象とした1660年代のロバート・ボイルやロバート・フックら英国王立協会フェローらによる実験科学という知識生産方法が成立させた背景である。
実験という実験室という閉ざされた空間で繰り広げられる手と目による操作から生みだされる事実(=つくられたもの)を、公的な学問的な知識とすりかえる、きわめて近代的な知識生産プロセスが生まれるようになったのは、高山宏さんが指摘する「マニエリスムが内包する2段階」のあとの方の段階だと捉えると、この時代に何が起こったのかをあらためて理解しやすい。
清教徒と個室文化とペストと
そもそも何年も前に読んだ『アレハンドリア』を読み返したのは、『リヴァイアサンと空気ポンプ』の議論で展開される17世紀半ばに起きた出来事をもうすこし理解したかったからである。
学問領域間に隔たりを設けず、すべてを「公共の平和」のために統一的な学問のあり方にこだわったホッブズが、実験科学をほかの学問領域と明確に区切ることで専門知というあり方を提示することにより新たな知識生産の方法を確立を狙ったボイルら王立協会の面々との対立の図式に賭けられていたものは何だったのだろうか?と思ったからだ。
すると、最初に紹介した「悲劇か、喜劇か 悪魔のいる英文学誌」という小論のなかに、こんな一文を発見した。
もうひとつは、清教徒というのは人間が集まって何かをやる空間をとても嫌う。もちろんそれは当時ペストが流行ったせいもありまして、劇場封殺というような事件が起こるんだけど、そのため悪魔の存在を許す共同幻想の成立する場がどんどん潰されていった。それに替わって生まれたのが個室文化ですね。個々の人間はそれぞれの個室にいてお祈りをあげる、その一対一の結びつきが大事なのだという考え方。同時にそれは小説の発生にも繋がるんです。広場が潰されることによって芸能が衰え、その一方で、個室で読まれる小説というジャンルが生み出されていくわけです。
ロンドンをペストが襲ったのが1665-1666年にかけてである。
もともと先に書いたように、ピューリタニズムとはカトリックにおける教会におけるミサなどを重視する代わりに、聖書に立ち戻って、ひとりひとりが聖書を通じて神に向きあう宗教生活をよしとしており、それがヨーロッパの家庭に、個室というものを生む要因ともなったし、ミサで多くの人が集まるよりもその個室でひとりで神と向きあう引きこもり生活に人びとを向かわせる傾向にあった。
つまり、印刷された聖書という新たなメディアが疫病が蔓延する社会でリモートワークを可能にする下地をつくっていたし、人びとをテクスト中心のコミュニケーションに向かわせる変化を促していたのである。
なにしろ、それがあって小説というジャンルが可能になったのだから、知的生活におけるこの変化は大きい。
抑圧されたものの暴力的な回帰
そして、こうした内に閉じる傾向があっての、実験室への引きこもり、専門知という内外の区切りの明確化という傾向が、新たな知の生産方法にも採用されたのだとしたら、わかりやすい。
さらには、その分断を特徴とするありようが、テクスト中心のコミュニケーションとともに生じているのだとしたら、現在のように、人同士がたがいに会うことがむずかしい分断された環境における生活様式について考える際にも注意が必要だとわかる。
ホッブズが繰り返し指摘したように、「知識人のどんな独立した集団も、世俗社会への脅威を構築してしまうことは避けられない」ものであり、「内戦の勃発と特権的な技能の領域をみとめることのあいだには関連がある」のだから、僕らは、知の専門性や独立性には十分に注意をする必要があるし、何よりそうした専門領域で独立し整理されているようにみえる知のあり方そのものが自明なものではないことを認識しておかないといけない。
それは何かの暴力的な抑圧のうえに成り立っているのであり、その暴力的な抑圧こそが抑圧されたものの暴力的な回帰を生みだすのだということを。
そうした例の文学的事例が19世紀におけるメルヴィルの『白鯨』なのだろう。
人が抑圧しきれない存在としての白鯨、そして大いなるうみそのものを描いた、それ自体化け物じみた作品である『白鯨』は、実は、脱専門領域的な百科全書的博識によって成立する作品でもある。それはボイルやフックらのマニエリスム第2段階の知の生産方法によるものというより、第1段階におけるもっと魔術的な組み合わせ術(=アルス・コンビナトリア)による生産方法を彷彿とさせる。
「語源(Etymology)」で始まる小説はそう多いと思えないが、ともかく"Whale"の語源は北欧語系の'hval"にたどれるが、これは"roundness or rolling"の意味と、二種類の大辞典にある、と作者は述べる。鯨とは即ち丸ないし円、円運動そのものなのだ。「白」と「鯨」とはお互いに相関し合う。パラドックスそのものなのだと理解すると同時に、こうして開巻1ページを"roll"で初め、本体掉尾を"...the great shroud of the sea rolled on as it rolled five thousand years ago."で締めるこの巨大作自体が、丸く、そして循環する、早く来た『フィネガンズ・ウェイク』なのだ。
魔術的な姿勢が必要だ。
魔術的な姿勢による、脱領域的かつ包括的な姿勢での取り組みがこの分断された危機の時代には必要だ。
高山さん自身、「フクシマ」という別の危機に対してこんな風に書いてもいる。
「脱領域」への切迫した必要があったのが、空念仏と化して数十年経るうちにすっかり色褪せたというのが実感だ。理系が人文・社会系との接点や干渉を言うには余りにも専門化が過ぎてしまって、文理融合だの脱領域だの声高に言うこと自体、恥ずかしいという状況になっている。「サイエンス」と「テクノロジー」の間ももはや途切れてしまっていて、その黙示録的危険が「フクシマ」で露呈した。諸学融合を謳った「観念の歴史」派、観念史家たちの発想と営みを牧歌的なものと感じさせるとすれば、そうさせたものは何か、いつ頃そうなったか、よく考えてみる必要がある。哲学が「魔術」をも排さなかった時代があったことが『存在の大いなる連鎖』(1936)一冊見てもわかる。今、魔術的哲学を「オカルト・フィロソフィー」としてカリキュラム化している大学が一体どれ位あるだろう。
まったく、心のなかの悪魔の呟きなどに惑わされている場合ではない。
そんな閉ざされた目ではなく、開かれた目で世界とともに立ち向かわなくてはならないはずなのだから。
悪魔はどこから生まれているのか。
その認識こそがこの危機的な状況では大事である。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
