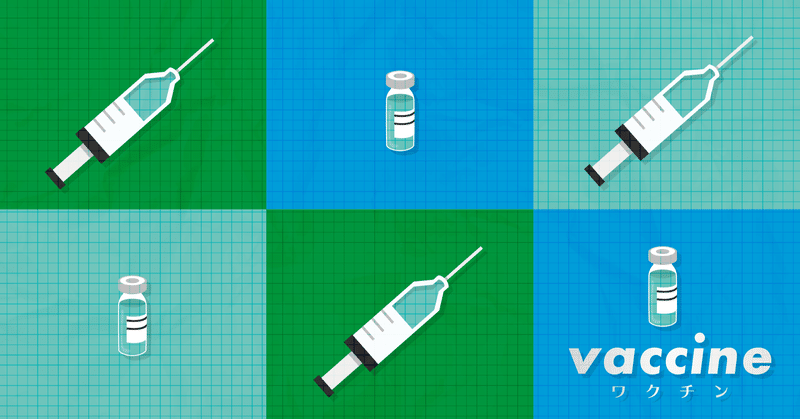
子宮頸がん(HPV)ワクチンのその後
おさらいとニュース
まずは今、日本で認可されているHPVワクチンについておさらい。
シルガード9(旧ガーダシル)MSD株式会社(米メルク社)
9種類のHPVタンパク質ウィルス様粒子(6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
ウィルスのプラスミドを用いて遺伝子組み換え酵母でつくったもの
アジュバントとしてアルミニウムヒドロキシホスフェイト硫酸塩
製造工程で混入する物質としてウシの乳由来成分(カザミノ酸)を含む
添付文書:https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341CG1023_1_03/
サーバリックス 英GSK社
2種類のHPVタンパク質ウィルス様粒子(16, 18)
バキュロウィルス(チョウ目の幼虫に感染するDNAウィルス)とイラクサギンウワバの幼虫の細胞を用いて製造
アジュバントとして水酸化アルミニウム
製造工程で混入する物質としてウシの乳由来成分(カザミノ酸)を含む
添付文書(PDF):
https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/ja_JP/products-info/cervarix/cervarix.pdf
産経新聞が報じたのがこちら
子宮頸がんワクチン接種、積極的勧奨再開へ 厚労省部会が容認
2021/10/1 21:22産経新聞
国が積極的な接種呼びかけを中止している子宮頸(けい)がんワクチンについて、副反応を議論する厚生労働省の専門部会は1日、積極的勧奨の再開を認める方向で合意した。今後、再開時の具体策を協議して最終決定する。部会は厚労省に対し、接種者の増加を見据えて接種後の症状を診療する協力医療機関への支援強化を検討するよう求めた。
この日の部会では、海外の大規模調査で近年、子宮頸がんの予防効果が示されたことが報告された。ワクチンと接種後に生じる症状の関連性について、国内外の調査で科学的根拠が認められていないとした。一方で、症状に苦しむ人への相談窓口が設置され、医療的な支援や救済が行われているとした。
ワクチンは子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐ。国は平成25年4月に小学6年から高校1年の女子を対象に計3回の定期接種とした。ただ、接種後に体の痛みやしびれなどの症状を訴える人が相次ぎ、2カ月後に個別の案内を送る積極的な勧奨を中止した。
積極的勧奨の中止後は接種数が低迷していたが、実施主体の市町村がリーフレットなどを個別送付して情報提供を推進。接種は増加傾向にあるという。
これに対し、HPVワクチン薬害訴訟全国原告団・弁護団は1日、東京都内で会見し、原告の20代女性がオンラインで「接種から9年経つが、治療法もない。新たな被害者が出てしまう」と訴えた。
これに関連して、どんな経緯で積極的勧奨を再開するのかを報じた記事も出ました。
厚労省のトラウマ、メディアの罪...... HPVワクチン問題を汚点ではなく、より良い予防接種の教訓に
https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/hpvv-moriuchi-3
<抜粋>
ワクチンの有害事象と言われているものの中にも、ワクチンの成分で起こるものもあるし、金属片やゴム片が混じるような作る時のエラーもあるし、筋肉注射が関節に入ってしまったというような手技上のエラーもあるし、ワクチンとは完全に無関係な紛れ込みもあります。
そしてもう一つ、予防接種に関わるストレス(WHO「予防接種ストレス関連反応Immunization Stress Related Responses (ISRR)」)がある。それも全部含めて、予防接種の時に起きるデメリット、と捉えていくべきです。成分だけが問題ではありません。
本人にとっては、血管迷走神経反射で倒れて奥歯が折れたとか、機能性身体症状としておかしな不随意運動(意思と関係ない体の動き)が出て苦しんでいるのも、広い意味での予防接種の副反応です。
それを減らそうと思えば、予防接種への不安感や恐怖感を和らげないといけません。事前にきちんとした説明をしないといけないし、あとで気になることが出た時も門前払いするのではなく、しっかりと受け止めて対応する。
そこまできちんとやることで予防接種の副反応は減らすことができると伝えるなど、以前はなかった接種者の教育に取り組むことが必要です。
私たちはこのトラブルを乗り越えて、より一層高いレベルで予防接種に関する医療をしていくことができるはずです。
有害事象をもっと報告するシステムを作ることで隠れた副反応を見つけられるかもしれないし、困った人たちをちゃんと受け止める仕組みも作る。
何よりそういうことが起きないように、同調圧力をかけて接種するとか、疑問点があっても「そんなの気にしなくていいんだよ」とごまかしてうつようなことはしない。相手が困っていることや不安をしっかり受け止め、解決した上でワクチンを接種する。
そんな、よりステップアップした予防接種医療に日本は向かってほしい。そのために、HPVワクチン騒動を汚点や負の歴史にせずに、より良い将来に向けた教訓にしたいと思います。
HPVワクチン 当時の副反応検討部会で積極的勧奨を差し控えた立場から振り返る
https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/hpvv-okabe
<抜粋>
ーー名古屋スタディなどで、ワクチンの副反応だとして訴えられている症状は、接種していない女子でも起きており、ワクチンとは関係なさそうだという結論が広がりました。一方で、WHOが出した「Immunization stress related responses(予防接種ストレス関連反応)」では、ワクチンへの不安などがいろいろな症状を引き起こすという意味で、予防接種と関係のある反応はあるのだと示しています。
「ワクチンと症状は全く無関係」という方向に極端に振れるのも、それはそれで問題があります。
ワクチンを接種するという行為そのものが人の不安感を増強します。それによって起きた症状は本来、消えるはずなのに、不安が不安を呼ぶような感じで次第に増強され、場合によっては慢性的、あるいは不可逆的な反応になるという考えです。
僕もこの議論にはWHOで委員会メンバーとして加わっていました。
ーーワクチンの成分そのものが影響したわけではないけれども、接種を受けることへの恐怖不安、社会的な影響、本人のストレスへの対処などが影響しているということですね。
ある病気を考えるときに、病理学的な変化だけでなく、本人の持ついろんな生物的・精神心理的な状況、社会やメデイアが与える影響があるという概念(Bio-Psycho-Social model 生物・心理・社会モデル)がありますが、その考えをワクチンでも応用しています。
はじめてこの考えをWHOの会議で聞いた時、僕としてはHPVワクチン接種後の症状の理解が、ストンと胸に落ちた印象でした。十分説明がつくし、納得がいきました。
ーーワクチンとは無関係な症状だ、と主張するのも間違いだということですね。
その主張を切り捨てるのは良くないです。また、これは本人の気持ちの問題とか気のせいではありません。その不安を強化するような周りの問題、社会的な問題も周辺にはあるということです。
ーーそういう見方からすると、あの症状は国の救済の対象になってもおかしくないわけですか。
そこから派生して「無過失補償」(加害責任の有無を問わずに救済する制度)を適用しようという考え方があります。日本の予防接種健康被害救済制度は、基本的にはこの無過失救済制度となっています。
徹底的に因果関係を科学的に徹底的に求めるのではなく、現象としてそういうことがあり、他に明らかな理由がないのであれば、予防接種を勧めた方が責任を持つべきだという考え方です。
国際的にもそのような考え方に動いています。医学的因果関係が明確になくても、それについて否定できなければ、救済はされています。
再開する理由
2つの記事を読むと、積極的勧奨を再開する根拠として以下の2点があるようです。
1・スウェーデンの研究で異形成だけではなく子宮頸がんそのものも防いでいることがわかった
2・WHOではISRR(Immunization Stress Related Responce=予防接種ストレス関連反応)という概念が取り上げられ、成分による作用だけではない反応も救済しようという動きになっている
1に関して、2004年6月から臨床試験が始まって、15年近くたってようやく「子宮頸がん」の予防効果があることがわかった、と。これは「ワクチンで病気を予防したい」人にとっては福音だと思います。反論もしません。よかったね、と素直に思います。
2について、WHOがISRRという概念を提唱し、医療関係者に周知を図り始めたのは2021年4月。COVID19ワクチンの副反応に関して成分への作用だけではなく「不安」によって生じるものも「ある」としました。ISRRという言葉が新たにつくられたことは、子宮頸がんワクチンの積極的勧奨再開のニュースで初めて知りました。あたらしく言葉がつくられ、概念を広めることで、これまで「そんなこと起きるわけない」と門前払いをくらっていた人がケアに繋がりやすくなるのはありがたいことだと思います。
一方で、これまでワクチンに関してこういった考え方が受け要られてこなかった不公平さを思わずにもいられません。治療薬の場合「プラセボ(安心感によって治療効果が増す)」も効果のうち…というのは暗黙の了解です。薬剤そのものや処方する医師や服用をサポートする看護者との信頼関係によって不信感や不安感で「ノセボ(不安や不信感によって治療効果が減るor悪影響が出る)」についても警戒感をもって認識されていましたが、どうしてワクチンの場合「気のせい」の一言で済まされてしまうのかと、不思議だったのです。ワクチンにだって「これでもう大丈夫!」というプラセボが期待できるのであれば、「本当に平気かな…」という不安感でノセボ効果が現れたとしても不思議ではありません。そしてプラセボもワクチンの作用のうちなら、ノセボだって同じくワクチンの作用だろう、と。今回それが認められて、救済の対象としていこうという世界的流れができつつあるのは、本当によかったと思います。
だれも見捨てられない社会
たとえ少数であっても被害を被害として認め、救済していこうではないか…という考え方は今やっと出てきたのかと思うと感慨深いものがあります。
「水俣病患者の百十一名と水俣市民四万五千とどちらが大事か」
石牟礼道子著の「苦海浄土」に書かれた一文です。昭和36年当時の水俣市の税収のうち約55%をチッソ関連から得ており、製造業従事人口のうち80%がチッソ関連に勤めている状況で、市民にひろまった考え、ということでした。多くの人のメリットのためには、少数の人の犠牲など取るに足らない、黙っておれ、知ったことか…という「空気」があり、まるで一揆のような暴動で被害者団体が工場へ突入したときには「とうちゃんのボーナスの減る!」と叫ぶ子どもを連れた女性もいたと書かれています。
ワクチンの場合、成分による副作用にしても、不安感によるISRRにしても、健康被害が起きる確率が「低い」と言えるのは、提供する側と接種によるメリットを感じる人です。実際に健康被害を被る人は何万回も接種するわけではなく、たった1回かもしれないし2回か3回目のことかもしれません。よくある副作用や回復できたのであればまだしも、後遺症が残ったり回復できずにいる人にとっては、「低い確率に当たった当事者」と喜べるわけもなく、たった数回の接種で被った被害はその人と家族の人生にとって大きな禍根となるのです。
公害も薬害もワクチンの健康被害も、多くの人にメリットをもたらす一方、少数が犠牲になります。犠牲になるのが少数だから目をつぶれ、だまっておれ、というのが納得できないのです。犠牲になった少数が公式に「犠牲」と認められ、何らかの形で「救済」されるのであればいいのですが、認めるシステムも救済するシステムも、被害者にとってはあまりにも高いハードルが幾重にも連なっているのが問題だと思っています(こちらの「まとめ」を参照ください)。ワクチンは1993年の予防接種法改正により「義務」のものはなくなりました。「必要かどうか」を考慮して選ぶ際には認定と救済を受けるハードルが高いことまで知っておいたほうがいい、と考えます。
先に紹介した記事中にもあるように、日本のお役所では数年に1度の人事異動があり、その在任期間に言い出しっぺになることや前例をつくることを嫌う傾向があります。一旦作られたシステムを変えにくい「雰囲気」が脈々と受け継がれているといってもいいでしょう。なので、いくらWHOがISRRもワクチンの副作用として救済しましょうね、と言ったところですぐに変わるとは思えないのです。
「善悪」、「正誤」ではなく「必要かどうか」で選ぶ
そして、ワクチンを接種している子どもとそうでない子どもの健康状態全般を比較した研究
https://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_vacunas95.htm
では、接種していない子どもの母数が少ないのと、おそらく食生活など暮らし全般も一般的な接種している子どもとは異なるようなので(ファストフードは食べないetc.)、あまり引用したくはないですが、アレルギー、喘息、ヘルペス、中耳炎など、ワクチン接種していない子どものほうがどう見ても元氣そうなのです。そしてこれらはSIRRではなくて、ワクチンの成分がたとえ少量ではあっても長期間健康状態に影響しているという「現象」が数値化されたものと見てもいいでしょう。

ワクチンを接種するかどうかを選択するときに考慮するポイントとして考えられるのは
・そのワクチンでどんな病気がどんな確率で予防できるのか
・その病気は接種する人にとってどれほどの脅威なのか(年齢や持病の有無etc.)
・どんなタイプのワクチンでどう免疫システムに作用するのか
・どんな成分が含まれるのか
・治療法の有無
・他の予防法の有無(定期的な検査も含め)
・元氣に暮らすために実践していることがあるかどうか
・不調があるときに実践できる養生の方法(民間療法etc.)があるか
・一般的な医療へのアクセスが容易な環境かどうか(活動内容や地域)
などです。必要かどうか、信頼に足るかどうかをこれらのポイントで決めてもらいたいのです。ホメオパシーのユーザーがワクチンを必要と考えない傾向が強いのは、あらゆる感染症に対応するレメデイがあるからです。
ちなみに、わたしは犬をかまいたくなる性分があるので狂犬病の発生地域で野犬が多いところ(インドやフィリピン)に行く必要が生じたときには狂犬病ワクチンは接種してから行こうと思います。
実習に参加できる、就業の際に有利、自由に人と会える、人からとやかく言われない、渡航に必要…などの社会的メリットで選んだとしても、知らないことによるじんわりとした不安を抱えたままではISRRは防ぎようがないため、ワクチンそのものと、それで防げるとされる病気の現状についても「知った」うえで腹を据えて選んでもらいたいのです。
ちなみにわたしは、どうしてもイエローカード(黄熱病ワクチンの接種証明書)が無ければ入国できない国(ケニアとか)に渡航しなくてはならなくなったら、「ワクチンで黄熱病を発症したら適切な治療を施すこととNIIDに届け出ることに同意します」という同意書にサインをもらった上で接種しようと考えています(生ワクチンなので発症する可能性があります)。
まとめ
自然農の畑や雑木林の微生物たちにまみれて暮らしていると、病原性の微生物やウィルスが付け入るスキなどどこにあるのか…という感じで、この日常が続く限り、わたしはワクチンの「必要性」を感じません。でも、どこ行っても消毒薬を振りかけられ、日々忙しくて運動不足で、ストレス解消にジャンクなものを食べがちで、ゆっくりお風呂に浸かる余裕もなく、人間関係のストレスも半端ない…という暮らしをしていたら、話は別です。それらをどう解消してゆくか、どうおりあいをつけるか、どうリソースを確保するか、いかに自律神経と免疫システムのケアをするか…という根本解決に取り組めるかどうかもその人がおかれた状況やタイミングにもよります。「ワクチン」とひとくくりにして善悪や正誤を論じるのは科学的ではありません。ある意味「思考停止」と同じだと思います。「その人にとって今必要かどうか」をいろんな側面から考慮して個別に答えを出すのがいいと思うのです。
単純に、わかりやすく、何かについて述べられたとき、それはその物事の「一部」だということを忘れてはならないと思います。あらゆる物事にはいろんな側面があり、それと出会うわたしにもいろんな側面があり、複数のレイヤーがあり、何が何とどう響き合うのか、反発し合うのか、全てを予測することはできません。だからこそ、納得して腹を据えて選んだことを受け入れるために、マスメディアには「情報」を広く公平に出してもらいたいし、利用する人たちには落ち着いてなるべく多角的に集めてもらいたいのです。
他のいろんなワクチンについてのマガジン、お話会の内容プラスαをまとめてあります。
自分自身のカラダを整えることをサポートします。
遠方の方はお泊りセッションも可能です。お気軽にお問い合わせください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
