
男性が育休を取りやすくする取組は、地球にやさしい買い物も増やすかもしれない。
SUMMARY

(さしあたりの)結論
育休を(特に男性が)長期的に取得してよいと思えるようにする会社の取り組みは、その会社の働きやすさを高めるだけでなく、その会社の社員のサステナブル購買の"障壁"(同性への競争意識)を下げることで、サステナブル購買の浸透にも寄与する可能性がある。
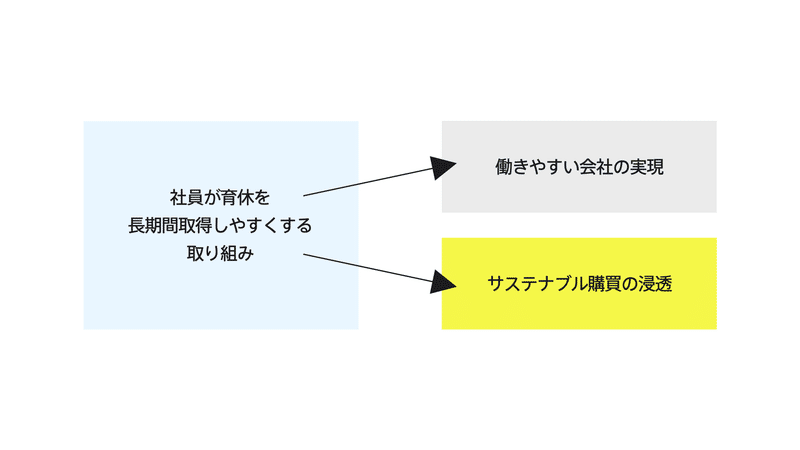
本記事では、サステナブル購買を「地球環境にやさしい商品を優先的に買うこと」と定義します。なお「サステナブル購買」の定義に関するより詳細な検討については、Phippsら(2013)を参照ください。
DETAIL
仮説立案のために検討したこと
男性は、女性に比べて、サステナブル購買に積極的ではないということはさまざまな研究で指摘され、検証されています(Phillips et al., 2022)。
この性別によるサステナブル購買への意向の"差"について、これまでは「ジェンダーアイデンティティ」(Gender Identity)に基づく検証がなされてきましたが(Brough et al., 2016)、最近の研究(Otterbring et al., 2023)では「同性への競争意識」(Intrasexual Competition)による説明が試みられています。
つまり、男性は女性よりも「同性への競争意識」が強く、かつその競争意識が強いほどサステナブル購買の”障壁”として働くと言うのです。なぜなら、男性にとって「サステナブル商品」は、現在のところ、(それらが”女々しさ”を連想させる点で)同性に対する競争力を減じる可能性を示すものだと認識されているからである、と。なおOtterbringら(2023)は、約1400名を対象としたアンケート調査による分析で、この仮説を検証しています。
Otterbringら(2023)の研究を日本に当てはめてみたときに、日本企業においては”同性社員との競争”のメタファーとして「育休」が思い浮かびます。例えば、男性育休に関する先行研究(中里, 2023、齋藤, 2020)は、男性社員が育休の取得を躊躇させる要因の一つとして「社内評価が低下することへの怖れ」を挙げており、同様のことがパーソル総合研究所の2023年9月の調査でも言及されています。このことは、先行研究では直接的に言及されていないものの、「同性社員に対する競争力低下への怖れ」を含み持つものとして捉えて差し支えないでしょう。
つまり「育休取得の適切な期間」の認識は、その人の「同性への競争意識」の隠喩として機能している可能性があるのではないか。筆者はこの推論をもとに以下の仮説を立て、その検証のための調査と分析を実施することにしました。

調べて分かったこと
調査仕様
調査方法 :QiQUMOを利用して調査
調査地域 :全国
調査対象者:20~59歳の会社員の男女500名
調査期間 :2023年11月7日(金)
本調査にあたっては、以下の3つの設問を聴取しました(各設問の具体的な内容は、APPENDIXを参照ください)。
男性および女性の適切な育休期間
サステナブル商品の購買傾向
同性への競争意識
男性および女性の適切な育休期間については、株式会社パソナグループが2023年9月に発表した調査をもとに、期間については中里(2023)を参考に、(「取得しなくてよい」を含む)1ヶ月未満から2年以上までの期間を8段階に分け聴取しました。次にサステナブル商品の購買傾向については、Otterbringら(2023)では「私が使用する製品が環境に害を与えないことは、私にとって重要だ」(Haws et al., 2014、筆者訳)といった"価値観"で聴取していますが、本調査では"実質的な購買傾向"の違いを明らかにするために「ラベルレス飲料」と「植物性ミルク」について認知、購買意向、購買経験、継続購買といった購買傾向の差を5段階に分けて聴取しました。また比較商品として「完全栄養ドリンク」と「微アルコール飲料」も同様の設問で合わせて聴取しています。そして同性への競争意識は、Otterbringら(2023)の研究でも使用された 同性間競争尺度(Buunk and Fisher, 2009)を筆者翻訳の上、聴取しました。
なお本調査では、育休取得経験者に限定せず、広く会社員を対象としています。なぜなら、男性の育休取得において当事者の認識や意向だけでなく、その周囲の人の「適切な育休期間の認識」が、当事者の「実際の育休取得期間」に大きな影響を与えると考えられるからです。
分析仕様
有効回答者:418名(男性213名/女性205名)
/調査対象者500名の内、複数設問で同位置の回答が連続(例:4・4・4・4・4・4・4・4と連続)した回答者を分析前に除外
調査データの基礎情報は、APPENDIXにゆずり、本節では仮説検証のために行った分析結果を示します。
検証にあたって、男女別に、サステナブル商品(ラベルレス飲料と植物性ミルク)の購買傾向(5段階)を従属変数として、(調査対象者にとっての)「同性の適切な育休期間」(8段階)を独立変数とした回帰分析を行いました。なお「年齢」、「役職」(一般社員or管理職)、(調査対象者にとっての)「異性の適切な育休期間」を統制変数として分析を実施しています。すなわち、これらの変数の条件が同じでも「同性の適切な育休期間」が長くなると「サステナブル商品の購買傾向」が高まるかを検証しました。分析結果は、以下の表の通りです。


上記表の通り、仮説を肯定する結果が得られました。まとめると、
男性会社員は「男性の適切な育休期間」を長く認識しているほど、サステナブル商品の購買傾向が高くなることが予測される(なお女性会社員では予測しない)。
男女問わず、「同性の適切な育休期間」の長さの認識は、非サステナブル新カテゴリー(完全栄養ドリンク、微アルコール飲料)の購買傾向を予測しない。
男女問わず、「異性の適切な育休期間」の長さの認識は、対象商品の購買傾向を概ね予測しない(女性会社員のみ「植物性ミルク」で予測される)。
なお、より直感的な分析結果として、男性会社員(215名)の「男性の適切な育休期間」を「1年未満」と回答した群(1-4で回答:132名)と「1年以上」と回答した群(5-8で回答:83名)に分け、ラベルレス飲料と植物性ミルクの購買傾向を比較したグラフを以下に示します。


分析結果から考えたこと
1と2の結果から、「適切な育休期間」の認識とサステナブル商品への購買傾向の連動は、たんなる新しい価値観や商品への受容性とは別の因子(本記事の仮説では「同性への競争意識」)が働いていることが示唆されます。
さらに、仮説にはなかった分析結果として3に関連して、女性会社員の「男性の適切な育休期間」の長さの認識が、「植物性ミルク」の購買傾向の高まりを予測することが明らかになりました(他方で、ラベルレス飲料の購買傾向は予測しません)。本調査では、調査対象者のパートナーの有無や世帯形態について聴取していないため仮説となりますが、ラベルレス飲料に比べて植物性ミルクは、それをシェアする同居人の価値観の認識によって購買傾向が左右される可能性があります。そのため、「異性の適切な育休期間」の認識(すなわち、近しい男性が「同性との競争意識」を強く持っていそうかの連想)が、女性会社員の植物性ミルクの購入傾向に影響を与えている可能性が推察されます。
さらに調べるべきこと
分析結果では明示しませんでしたが、「同性への競争意識」は、「適切な育休期間の認識」と「サステナブル商品の購買傾向」の間に関連性を持ちませんでした。このことは、直ちに「同性への競争意識」がこれらの変数と関係を持たないことを指すと解釈されるのではなく、もうひとつの可能性について考慮する必要を示していると、筆者は考えています。
Buunk and Fisher(2009)らの同性間競争尺度は、「私は、いつでも他の同性に勝ちたいという意識が強い」といった当該個人を主体とする競争意識を聴取しています。しかし、こと日本においてはむしろ「自分は積極的に競争したいと思っていないが、場の雰囲気が競争を要請している」というふうに捉えている可能性があるかもしれません。したがって、さらなる調査としては、「私が働いている会社は、同性の同僚との競争を促していると思う」といった"会社を主体とした競争の雰囲気"を変数として再検証してみる必要があると思います。
また本調査では、育休取得の経験/未経験は問わず分析しましたが、その経験の有無が「適切な育休期間の認識」と「サステナブル商品の購買傾向」の両者に対して交絡因子として働いていた可能性があります。したがって、さらなる調査としては、育休取得の経験/未経験の影響を考慮した分析が望まれるでしょう。
さらに本調査では「サステナブル商品の購買傾向」について、認知や意向、購買経験などの複数視点を組み合わせた設問を5段階の連続変数に変換して分析を行ったため、エビデンスとしての水準は高くありません。したがって、さらなる調査としては、例えば当該商品カテゴリーの購買データを従属変数としたよりロバストな検証等が求められると思います。
さいごに
男性育休について長らく研究してきた中里(2023)は、
(・・・)制度の変化を待つまでもなく、子どもを持った個人、身近な人たち、職場の人たち、子育て支援に関わる人たちが、「男性育休」の社会的な意味を理解して、自らの意識と実践を変えていくことは可能であり、また必要であろう。
確かに、男性育休というのは、子どものいる男性が、子どもがごく小さいときにだけ経験する可能性のあることがらに過ぎないかもしれない。しかし、私自身は本書全体で見たような検討を経て、改めてこのテーマはジェンダー構造の、さらには社会全体の価値観の転換に関わるテーマだと感じている。
と述べています。同氏の言う「男性育休の社会的な意味」を理解し自らの意識と実践を変えていくためのナラティブの一片として、"育休制度について考えることを、ある特定の社員のための特殊な課題について考えることだけではなく、よりマクロな課題について考えることでもあること"を具体的に示すことを、本調査では目指しました。
なぜなら、「サステナビリティ」に(内実はともあれ)取り組んでいない企業を探すことの方が難しい今、その企業が社員の長期的な育休取得支援に前向きでないとすれば、(そして本調査が示した事実が正しいとすれば)それはある種の矛盾を示していると言ってよいのですから。例えば、ユーグレナのような企業が男性社員の育休取得に積極的であるのは、企業の理念と行動とが整合的な模範例だと言えると思います。
最後に、"男性会社員は「男性の適切な育休期間」を長く認識しているほど、サステナブル商品の購買傾向が高くなることが予測される"という分析結果は、裏を返すと冒頭に述べた通り、現代の日本社会において「育休」が"同性間競争"のメタファーとなっていることを示してもいます。ですから、最終的に目指すところとしては、そのようなメタファーとしての意味が消えてなくなる、すなわち本調査の結果が再現できなくなる社会を目指すことになると思います。
APPENDIX
サンプルの基礎情報(有効回答)

適切な育休期間への回答結果

サステナブル商品設問への回答結果

同性間競争意識設問への回答結果

REFERENCE
サステナブルタイムズ(2023-09-14)『男性育休取得率100%にむけて。仲間の声から見えてきた、取得推進のためのヒントと次の課題とは。』(アクセス日:2023-11-10)、URL:https://www.euglena.jp/times/archives/22263
株式会社パソナグループ(2023-09-26)『仕事と育児・家事・介護に関する意識調査』(アクセス日:2023-11-10)、URL:https://www.pasonagroup.co.jp/news/index112.html?itemid=4845&dispmid=798
パーソル総合研究所(2023-06-29)『男性育休に関する定量調査』(アクセス日:2023-11-10)、URL:https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/paternity-leave.html
齋藤早苗(2020)『男性育休の困難:取得を阻む「職場の雰囲気」』青弓社
中里英樹(2023)『男性育休の社会学』さいはて社
Brough, A.R., Wilkie, J.E., Ma, J., Isaac, M.S. and Gal, D. (2016), “Is eco-friendly unmanly? The green-feminine stereotype and its effect on sustainable consumption”, Journal of Consumer Research, Vol. 43 No. 4, pp. 567-582.
Buunk, A. P., and M. Fisher. 2009. “Individual Differences in Intrasexual Competition.” Journal of Evolutionary Psychology 7 (1): 37–48.
Haws, Kelly L., Karen Page Winterich, and Rebecca Walker Naylor. 2014. “Seeing the World through GREEN-Tinted Glasses: Green Consumption Values and Responses to Environmentally Friendly Products.” Journal of Consumer Psychology: The Official Journal of the Society for Consumer Psychology 24 (3): 336–54.
Otterbring, Tobias. (2023). “Stereotypes, Same-Sex Struggles, and Sustainable Shopping: Intrasexual Competition Mediates Sex Differences in Green Consumption Values.” Baltic Journal of Management, Vol. 18 No. 4, pp. 450–73.
Phillips, D.M. and Englis, B.G. (2022), “Green consumption is both feminine and masculine—just ask the androgynous consumer”, Journal of Consumer Behaviour, Vol. 21, pp. 1028-1039.
Phipps, M., Ozanne, L.K., Luchs, M.G., Subrahmanyan, S., Kapitan, S., Catlin, J.R., Gau, R., Naylor, R.W., Rose, R.L., Simpson, B. and Weaver, T. (2013), “Understanding the inherent complexity of sustainable consumption: a social cognitive framework”, Journal of Business Research, Vol. 66 No. 8, pp. 1227-1234.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
