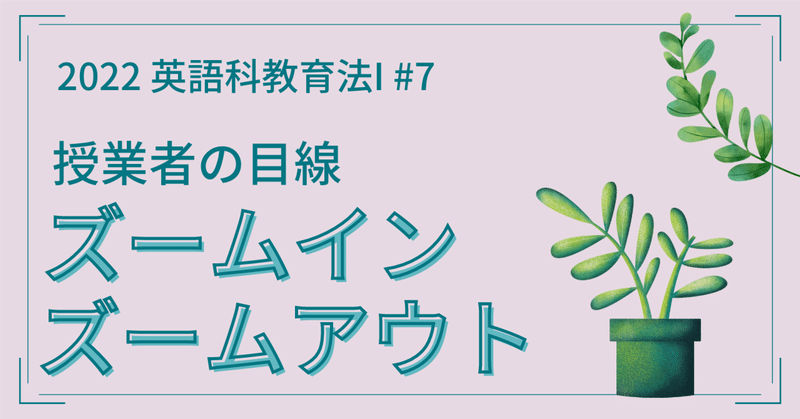
授業者の目線—ズームイン・アウト
英語科教育法Iの振り返り。
毎回行なっている模擬授業は早くも2巡目の2人目まで回ってきた。正式な履修者4人が毎週1人ずつ模擬授業をするという鬼スケジュールなので、模擬授業が「学期に一度の大イベント」みたいなテンションにならず、比較的自然に日常に組み込まれる(そして地味に忙しくなり、思ったより詰めが甘くなる)という感じになっている。人数が多い教員養成学部ではなかなか経験できない授業作りのリアルなところに足を踏み入れている感じがしてこれはこれで良いなと思い始めた。
模擬授業1回目—教室全体を見渡す目線
今回先生役を務めた学生(以下、Aさん)は、前回の模擬授業では高校1年生を対象にSVCとSVOの区別ができるようになることを目指した授業を行なった。
その際Aさんは隣の人と相談することを促したりして、生徒を巻き込みながら授業をすることを目指していた。
また、練習問題もその前の文法確認よりずっと難しいトリッキーな問題を使用しており、「簡単だと思わせない」「生徒に戸惑いを生みたい」という野心的な教師の信念(WANT)を垣間見せた。
しかし、彼女自身が課題だったと振り返ったように、その授業では一人一人の生徒に対してどの問題がどういう難しさを持つかというところにはあまりアプローチしていなかった。
もちろん、模擬授業の特性上、生徒の英語力などは事前に把握できないのだが、練習問題に取り組む間に机間指導を通して生徒の状態をより細やかに把握することも状況的には可能だった。
Aさんとしては、その後の答え合わせの際に「これ、分かんないよね?」という流れに持っていきたかったのだろう。つまり、「SVCとSVOを見分けよう」と言いながら、45分の実際の授業の尺で考えると本当のゴールはそこではなくて、「副詞」という概念の理解を目指す授業だったと考えられる。
そのためには問題演習中にはあまり口出しし過ぎずに、分からないモヤモヤのあるまま次に進む必要があり、そのためにも彼女はあまり生徒一人一人にきめ細かい指導をあえて入れなかったのだろうと今振り返ると思う。
一方で模擬授業検討会では生徒役の一人から「全問正解したかったけど分からん問題があって焦った」という、問題の難しさをややネガティブに捉えるコメントがあった。仮に分からないままでも先生に一言「難しいよね」と声をかけてもらったり、「どこまで分かった?」と確認してもらえるだけでも、「あ、これはこの後ちゃんと説明してもらえそう」という安心感につながるかもしれない。
やや単純にまとめると、Aさんは事前に構想した授業全体の流れを大切にして教室全体にぼんやりと「難しい」「分かんない」という空気を漂わせることを目指していたと言える。そしてそれ自体は見事に成功した。4人という少人数の生徒役だったが、クラス全体の空気を授業者としての狙いを持って生み出した。
しかし、その授業者としての狙いの裏返しとは言え、やはり個々の生徒ととの関わりにどうしても物足りなさの残る授業だった。
模擬授業2回目—一人一人の高さに合わせる目線
Aさんの今回の模擬授業の省察レポートにも生徒との関わりの少なさが1回目の課題であったという旨が書かれていた。そしてその課題を乗り越えるべく、二つのアプローチを試みた。
一つは生徒との会話や発問を介したやり取りを増やすこと。そしてもう一つは、中1の自己紹介の活動の中に自分の「推し」の紹介を埋め込むことだった。
ちなみに、たまたま良いタイミングで「面白そう」と思って研究室にこちらの本を入荷したことも彼女の背中を押したようだった。
自分の好きなものや好きな人について授業中に語ったり書いたりできるのは、基本的にみんな嬉しいものだろう。(まぁ、それに共感してくれる友達がいるかどうかも結構重要にはなってくると思うが)
Aさんの狙い通り教室は時間を追うごとに盛り上がりを増していく。
いろいろなところで「何書いた?」「好きな芸能人とかいる?」「ガチの好きな人書けば良いやん。告れよ」など中1(を演じる大学生と26歳の私)がザワザワしながら笑っている。(ここ最近毎回複数人のゲスト生徒役が来てくれて助かってます)
Aさんも教壇から降りて色々な生徒に近づきながら様子を見たり、ヒントを出したりしていて、少なくとも私の演じた子どもにとっては先生が自分達の書くことに興味を持ってくれていると感じられる居心地の良い空間だった。
一通り「推し」の紹介を組み込んだ自己紹介の文が書けたところで、一人ずつ声に出して読んで発表していく。
しかしこの場面、他の人が紙を読み上げている時に、何人かの生徒がそれを聞いていないという状況が生まれていた。自分の番が回ってくる前に原稿を完成させるのに必死な生徒、それを笑いながら見ている生徒、おしゃべりしている生徒。「聞いていない」の中身は様々だったが、あまりクラス全体に他の人の発表を聞こうという空気がなかった。
もちろんこの場面だけを改善しようと思ったら、生徒が読み上げる前に先生が全員に声をかけて「はい!Listen to 〇〇さん」とか言うのもありだし、他の人の「推し」を聞いて書いておくようなワークシートを配ると言うのも一つの方法だ。
しかし、それは単なる「行為の選択肢の拡大」(ALACTモデルの第4段階)でしかない。この英語科教育法ではその前の第3段階「本質的な諸相への気づき」をとにかく大事にしたいと考えている。そして今回はすでにAさんからの省察レポートも受け取った後なので、このnoteであえて私なりに第3段階に踏み込みたい。(彼女の省察も彼女なりの本質的諸相へのタップがあった)
模擬授業1回目と2回目の目線の違い
端的に言えば、Aさんが1回目の模擬授業で気にしていたような「教室全体の空気感」をこの授業でももう少し意識できていれば、何かしらの手を打つことができたのではないだろうか。
1回目の模擬授業では一人一人の問題への取り組み状況よりも、「分からない」「難しい」という空気がクラス全体に流れるように意識して授業をデザインしていた。その狙い自体はすごく綺麗にはまっていた。
今回は、そんな前回の模擬授業で見えた「生徒との関わりが少ない」という課題を意識し過ぎたが故に、クラス全体にどういう空気感を作り出すかということが意識できていなかったように思われる。
「鳥の目と虫の目」とか「木を見て森を見ず(じゃダメだよ)」とか言い方は何でもいいが、一人一人の生徒を見て個々との関わりを大切にすることと、教室全体の空気を見る・作ることの両方が授業者には求められる。
そのバランスとかの話になると、これはもう経験を積んでいってもらうしかないだろうし、彼女の課題に対して明確な答えはある意味何も出してあげられないのだが、自分の授業者としての意識の向き方に自覚的になることは、単に「あの場面でこういう声かけをしていれば」という行動レベルの提案を積み重ねるよりずっと、今後の授業作りを豊かにしてくれるはずだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
