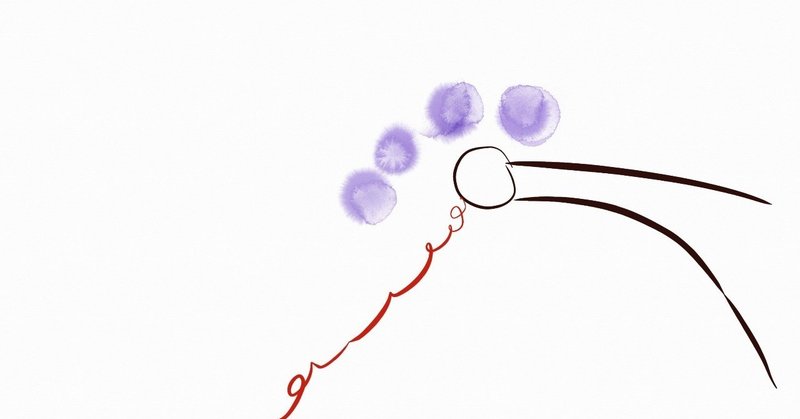
ストリートで出会った人の話
大阪に住んでいた頃、毎日のように高架下で歌っていた。
僕が住んでいたのは「十三」と書いて「ジュウソウ」と読む、おかしな街だった。
ふつうに暮らしていたら会えないようなひとたちと出会った。
よかった思い出もある。
でもそのほとんどが飲んで、モメて、争って、借りて、奪って、奪われて、壊して、壊されての記憶だ。
僕も態度が良くなかったし、今よりも苦しかった。だから、むかしに戻りたいわけじゃない。
だけど、ひとにはそんな黒い歴史のなかでしか触れられないものがある。
あの日の記憶を漁っていると、名前を付けられないような感情が蘇る。
「愛だった」とか「恋だった」とかありふれた名前を付けるには、あまりに軽薄に思えてしまう感情だ。
忘れられないことの、そのほとんどは「酔い」に浸かっているから、鮮明には覚えていないけど、それでも消えないものっていうのはあるみたいだ。
あの日も僕は歌っていた。
東口と西口をつなぐ高架下の通路で、僕の声と通行人の笑い声が混じり合っていた。
日付けをまたぐ時刻から、2時間近く声を張りあげていたが、誰も聴いてくれなかった。
もう今日はやめようと思った矢先に、ふらふら歩いてくる女がいた。後ろからオレンジのライトが差していて、顔はよく見えない。
ひどく酔っ払らっているようだった。明るい色の髪に、崩れた化粧は、なんていうか「街っぽかった」
女は倒れこむように僕の前に座った。
通路を挟んだ反対側の壁にもたれて、トロンとした目でこちらを見てくる。
「絡まれたらいやだな」と思っていたら、彼女はろれつの回らない舌先で「ねぇ、尾崎のI lovd youうたって」と言った。
酒の臭いが酷かった。
絡み酒だとは思ったが、誰かに聴いてもらえるのは嬉しかった。たまたま僕も知っている曲だったので歌うことにした。
原曲のプレイキーは分からないけど、左手が疲れていて、バレーコードを使いたくなかった。カポタストをはめて、簡単なコードで歌った。
彼女はvodafoneの携帯電話をいじくりながら、僕の歌を聴いていた。
袖から覗く手首には無数のためらい傷があった。
僕がそれに気が付いたときには曲が終わっていた。
「けっこういいやん」と言い、彼女はパチパチと手を叩いた。
乾いた反響音が少し遅れて重なった。泡のような拍手だった。なんだか、とても嬉しかった。
「ありがとう」
「大阪のひと?」
「いいや、神戸。大阪には来たばっか」
「いいなぁ、神戸。おしゃれで」
僕たちは狭いダクトのような高架下の通路を挟んで、しばらく話していた。
それは人生に無かったとしても、絶対に困らないような不必要な会話だった。なのに損をしている気にはならなかった。
遠くの方から、叫び声や笑い声が鳴り響き続けている。もう深夜だというのに何人もの人間が街にいる。
僕たちは綺麗とは言えない地面に座り込んだままだった。
通路の端と端に座っていた僕たちのあいだを、次々と人が通り過ぎていく。
通過する人々の腰のあたりの目線で会話をしていると、自分たちが街の中で特別な存在になった気分だった。
「いろんなひとのこと見あげながら喋るのたのしいね」と彼女は言った。
「惨めにならへん?」と僕は聞き返した。
「ぜんぜん」
「そっか」
「ねぇ、なんでこんな時間にうたってんの?」
「早すぎると目立つやん」
「誰かに聴いてほしいんじゃないん?」
「聴いてほしいけど、多すぎてもいややねん」
「なに? ビビってんの?」
「たぶん」

それから少しずつ間をおいて、口を開いた。
「でも、そういうことってない? 欲しいけど、多すぎると怖い、みたいな」
「あ、それならわかるかも」
子どものときは暗闇を恐れていたのに、大人になると光を恐れてしまうのだから、おかしな話だ。
僕は必要か不必要か分からないアルペジオを弾きながら、彼女と話し続けた。
本当に人生には無かったとしても困らないようなものが多い。このアルペジオが無かったとしても、僕たちの人生は絶対に変わらない。
とりとめのない話が続いた。
腰が痛くなったのか、彼女が少し姿勢を変えて口を開いた。
「あんな、わたしの友達が彼氏にサンドバッグにされてんねん」
僕は直感でなんとなく、このひと本人の話なのかもなと思った。
「その娘な、ずっと殴られてんのに、その男から離れられへんねんて。アホじゃない?」
「そうかな」
「自分やったら離れるやろ?」
「分からんけど、まぁたぶん」
「じゃあなんで『そうかな』なん?」
そこまで話すと、彼女は手に持っていたペットボトルの水を一口飲んだ。
僕は彼女がそれを飲み干すのを見てから、アルペジオを鳴らしたまま口を開いた。
「殴られたくはないけど、離れたくないんちゃう?」
「あぁ、それはそうかも」
「殴られるだけで離れなくて済むなら、離れへんってひともいるんちゃうかなと思って」
「たぶん……そうやわ」
そこまで話して、彼女はうつむいていた。
僕はなんとなく、アルペジオの曲調を変えた。しばらくして、彼女が眠そうな目をこちらに向けた。
「ねぇ、もういっぺんなんかうたって。できればお兄さんが作ったやつ」
「あんまりかもしらんで」
「いいねん。自分で作ったやつ聴かせてよ」
「そんじゃ新しく作ったの」
ledという作ったばかりの曲を歌った。
音量も控え目で、聴き味も重たくならないように書いた歌だった。誰が聴くわけでもないのに、やけに細部までこだわって作った記憶がある。
アルペジオのまま歌った。声が出づらかった。喋りすぎたからだろうか。
でも、今度は携帯をいじらずに彼女は僕の歌を聴いていた。猫のような目で大人しくしていたのが印象的だった。
演奏が終わって、彼女はまたパチパチと手を叩いた。泡が高架下の天井に跳ねて消える。
「けっこういいやん。尾崎ぐらい」
彼女は少し笑いながらそう言った。
「みんなそう言ってくれたらええねんけどな」と僕は返した。
「そっか、一生けんめい作ってんなぁ……」
聞こえるか聞こえないかぐらいの声だったが、高架下のトンネルの反響のせいで聞こえてしまった。独り言にもとれる言葉に僕は返答した。
「せやな。一生懸命作ったな」
「そっか……」
それから彼女はもう一曲、あと一曲と繰り返した。僕も悪い気はしなくて、歌い続けた。
このひとは自分が曲に込めたディティールを理解してくれるのだと思った。
気が付いたら、あたりはもう明るくなりそうだった。
僕はなんとなく、太陽の下でこの時間を続けると、苦しくなってしまうような気がした。
人生に無かったとしても、困らないようなものを堂々と振りかざせる時間は限られているのかもしれない。
ギターをケースにしまって、終わりにした。
「また別のやつできたら聴かせてな」
彼女はそう言って、僕と反対の方向に歩いていった。
バッグをクルクル回して、来たときよりもスッと背すじを伸ばして。
気付いたら彼女の姿は見えなくなっていた。
なんだか、僕たちふたりの座標軸だけじゃなくて、他のものまで離れていくように感じた。
あの日以降、僕は彼女に一度も会っていない。
いつか会えると思って、毎日高架下で歌い続けたが、彼女はついに現れなかった。街のひとに聞いても、手がかりは何も得られなかった。
だけど、僕はあれからずっと「別のやつ」を作り続けている。
分からないけど、僕にとって、それはとても意味があるようなことなのだと思う。きっと彼女との座標軸を近づけるよりも、大事な意味を持っている。
僕はたまに、まだあの狭い高架下に座っている錯覚に陥るときがある。
ダクトみたいな通路で、誰も聴いてくれない歌を歌い続けているような気がする。
そしてまた人生に無かったとしても困らないようなものに挟まって、「別のやつ」を作っている。あのダクトにだって朝が来た。誰の夜にだってきっと朝が来る。
朝が来たら、バッグをクルクル回して、来たときよりもスッと背すじを伸ばして歩いていくんだ。
音楽を作って歌っています!文章も毎日書きます! サポートしてくれたら嬉しいです! がんばって生きます!
