
航空戦力だけでは戦略的効果を見込めない『勝利のための爆撃』の紹介
第一次世界大戦が終結した後に、イタリアの戦略思想家ジュリオ・ドゥーエは、将来戦の結果を決めるのは航空機、特に爆撃機だと考え、開戦と同時に敵国の政経中枢に戦略爆撃(strategic bombing)を加えれば、短期間で敵国の民衆は戦意を失い、政府を降伏へ追いつめることができると主張していました。
シカゴ大学のロバート・ペイプ教授は、『勝利のための爆撃(Bombing to Win: Airpower and Coercion in Warfare)』(1996)で、このような戦略思想は実用的なものではないと批判しており、より現実的な航空戦略のあり方を模索すべきであると提案しています。これは現代の航空作戦を考察するための基本文献となっている一冊です。
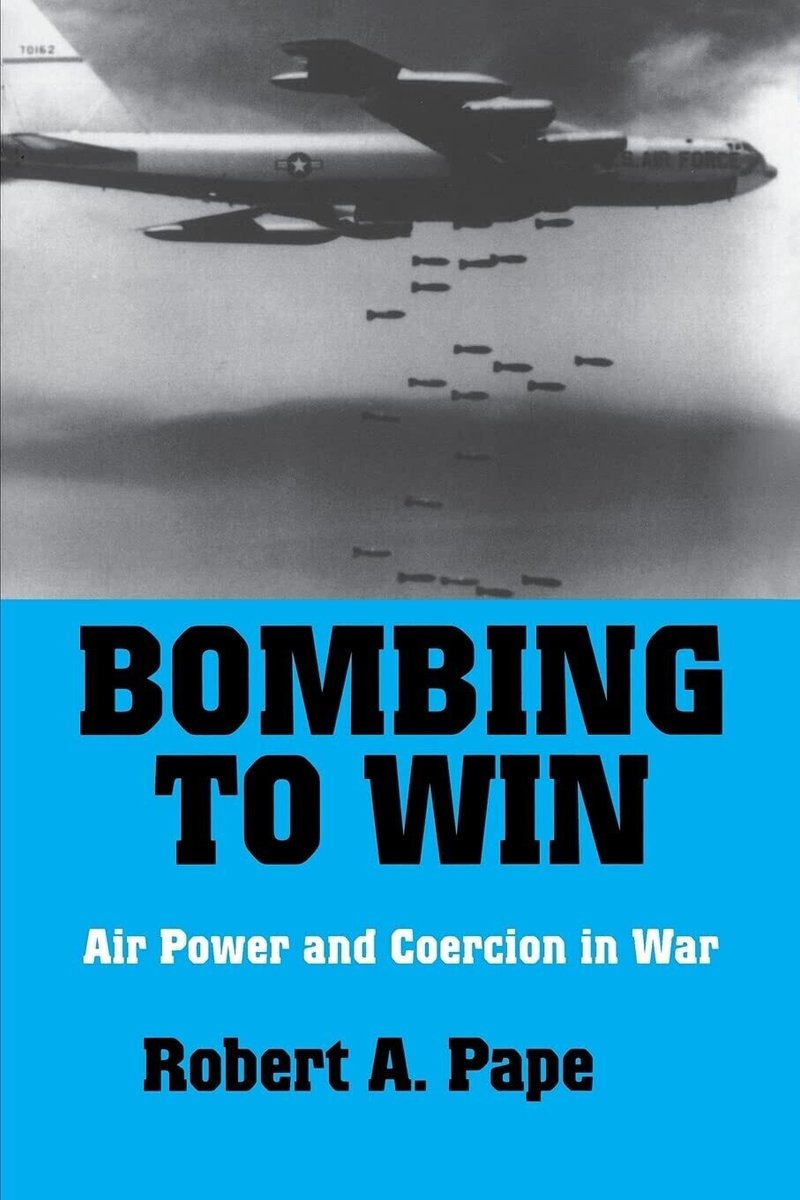
航空戦略の理論は、先ほど言及したドゥーエの研究を起点としているものが多く、さまざまな系統に枝分かれしています。このため、一見すると同じように見える戦略爆撃の構想であったとしても、攻撃目標の選定の仕方、ターゲティングの方法では異なった思想があり、戦略爆撃とは異なる爆撃の効果も包括的に考察する必要もありました。そこで著者は、相手に対する強制を政治的目的とした航空戦略を4種類に区分することを提案しています。
一つ目は懲罰(punishment)であり、意図的に民間人を攻撃目標とする戦略です。二つ目は拒否(denial)であり、敵の戦闘力を低下させるために軍事施設や軍事産業基盤を攻撃目標とするものです。三つめは威嚇(risk)であり、交渉における自国の決意の固さを示すために、段階的に爆撃をエスカレートさせていきます。四つ目は斬首(decapitation)であり、これでは敵国の政権中枢、指揮系統、特定の要人を攻撃目標とします。
このような類型を踏まえ、第二次世界大戦におけるドイツへの爆撃、日本に対する爆撃、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争の事例をそれぞれ分析し、航空戦力がどのような戦略的効果を及ぼしていたのかを調べました。
著者の分析結果によれば、航空戦力だけでは戦争を終結に向かわせる効果は限定的でした。敵国の政経中枢に対する爆撃は、生産活動を混乱させる上で効果がありましたが、それは政府が対処できる混乱であり、爆撃が加えられる中でも武器の生産が粘り強く継続された事例が見出されています。国民は爆撃を受けたとしても戦意を喪失するわけではなく、むしろ決死の覚悟で立ち向かおうとしてきます。
結論として、爆撃それだけでは和平を敵国に強いる上で決定的な要因になり得ないというのが著者の立場です。ただし、戦略爆撃の類型の中で拒否(denial)には限定的な有効性があることが確認されています。これは拒否が軍事目標に対する爆撃を加えることで遂行される戦略であるためだと説明されています。
著者の見解によれば、航空戦力には政経中枢を破壊する上で有効な手段ではありません。しかし、軍事目標を撃破するために使用すれば大きな戦果を上げることが期待できます。そのため、空軍の戦略思想で何よりも重要な位置を占めなければならないのは統合運用であり、味方の陸上作戦と歩調を合わせ、前線に展開する戦闘部隊の背後で活動する後方支援部隊を対象とした航空阻止、前線に展開する戦闘部隊を対象とする近接航空支援を遂行するべきです。
ペイプの議論に対して、アメリカ空軍軍人のジョン・ワーデンは徹底的な反論を出しているので、それについても簡単に触れておきます。ワーデンはぺイプが戦略爆撃の議論の多くの部分に反論を加えましたが、特に強く反対の立場を打ち出しているのは、現代の精密誘導兵器がさほど重要な技術革新ではないというペイプの立場です。ワーデンはこれは大きな間違いだとしており、精密誘導兵器が登場したことで、アメリカ空軍は湾岸戦争で正確な航空爆撃を加えることが可能になったと主張しています(Warden 1997)。ペイプもワーデンに再反論を加えていますが、それに関してはまた別稿で解説しようと思います。
参考文献
関連記事
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
