
権威主義国が武力を行使する条件を説明する『戦争と平和における独裁者』の紹介
ウィスコンシン大学の准教授ジェシカ・ウィークス(Jessica L. P. Weeks)は国内政治が対外政策に与える影響を分析してきた研究者です。2014年にコーネル大学出版会から出版した著作『戦争と平和における独裁者(Dictators at War and Peace)』は独裁的な政治システムを持つ権威主義国がどのように武力行使を決定するかを説明するモデルを提示し、計量的アプローチや事例分析で裏付けを行った研究です。
Jessica L. P. Weeks, Dictators at War and Peace. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014.
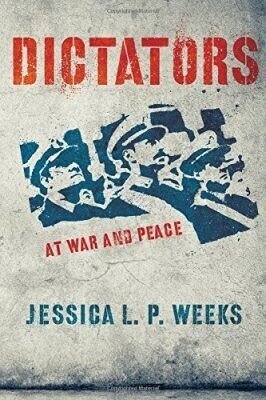
著者の理論によれば、権威主義国が武力行使を決意しやすいかどうかを判断するために注目すべきポイントは二つです。一つは政権を率いる指導者が行使できる権力の強さであり、もう一つは政権を構成するエリートの属性です。この二つの要因を踏まえ、著者は権威主義国の政治状況を4つのパターンに類型化しています。
(1)文民機構(civilian machines):集団指導・文民エリート
(2)軍事政権(military juntas):集団指導・軍人エリート
(3)民間的指導者(boss):個人指導:文民エリート
(4)絶対的指導者(strongman):個人指導:軍人エリート
著者の説明によれば、武力行使の公算が高い権威主義国は(2)、(3)、(4)のパターンです。特に個人指導と軍人エリートが組み合わさる(4)のパターンは最も武力行使に踏み切りやすいパターンであり、反対に集団指導と文民エリートが組み合わさる(1)の権威主義国は民主主義国以上に武力行使に対して非常に慎重であるという分析結果が示されています。(1)のパターンは武力行使を避ける傾向が強いだけでなく、武力行使に失敗する公算も低いことが示されており、非常に興味深いパターンです。
集団指導に比べて個人指導を採用する権威主義国は戦争に失敗する確率が高いと著者は論じています。これは戦争に敗れることが、政権を失う政治的リスクを引き起こすためであると考えられています。逆に個人指導の方式をとる指導者は軍事行動に際して説明責任を負う必要がないため、成算がなくても軍事行動をとる可能性があることも示されています。また、軍人エリートは軍事予算の膨張を通じて戦争から利益を得ることが期待できるので、戦争に対して前向きな態度をとることも説明されています。
本書の事例分析では、イラクのフセインとソ連のスターリンという典型的な独裁者が取り上げられています。彼らは個人指導を徹底した点で政治的に類似性があっただけでなく、軍事行動に関する意思決定で失敗のリスクを十分に検討していなかった点でもよく似ていました。
フセインは1990年の湾岸戦争でクウェートに侵攻しましたが、政策決定の過程でアメリカ軍が軍事的に介入するリスクを考慮した形跡はなく、当時の側近で作戦計画のリスクを指摘する者もいませんでした。スターリンも1939年にフィンランドに対する武力行使を行っていますが、やはり政権の内部で侵攻のコストが十分に評価された形跡はありません。結局、この戦争でソ連軍は大きな損害を出すことになりましたが、スターリンは政権を保持し、1941年に再びフィンランドに侵攻したのです。
本書は国内政治と国際政治の関係を考える上で意義があったと思います。権威主義国が民主主義国よりも武力行使のリスクが高いことは以前から指摘されていましたが、著者は権威主義国にもバリエーションがあり、特に指導者の権力とエリートの選好が対外政策を予測する上で重要な要因であることを実証しています。抑止論の観点から見れば、個人指導を徹底する指導者が作戦の失敗を恐れないことは深刻な問題です。
このような国の武力行使を抑止するためには、単に軍事作戦を失敗させるだけでは十分ではないのかもしれません。
関連記事
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
