
そうか、僕は父に愛してもらいたかったのか!(『僕は、死なない。』第20話)
全身末期がんから生還してわかった
人生に奇跡を起こすサレンダーの法則
20 悲しみよ、こんにちは
6月2日、友人のさおりちゃんに会った。さおりちゃんは、昨年寺山心一翁先生の「スマイル・ワークショップ」で出会ったがん仲間。彼女はがんに苦しみ、がんを治していく過程で梯谷幸司さんというメンタルコーチが編み出した独自のメソッドのカウンセリングを学んだ。なんと、これでがんが消えた人もいるとのこと。
「私、カウンセリングの練習をしたいの。本当のがん患者の人と話したいの。タケちゃん、モニターになってくれるかな?」
「いいよ」僕は二つ返事で答えた。僕もそのカウンセリングには興味があった。
そのメソッドの考え方では、感情と臓器には密接なつながりがあるとされる。漢方の考え方と同じだ。その特定の感情に気づかずに無視しているとストレスがたまっていく。そしてたまりにたまったネガティブな感情が臓器の細胞に不調を起こし、最終的に病気になるというものだ。がんはその最たるもの。
喫茶店で席に座ると、さおりちゃんは聞いた。
「がんになった原因は自分では何だと思う?」
「うん、怒りかな……」僕は銀座でサラ先生に言ったことを繰り返した。
「何の怒り?」
「社会とか、政治とか……なんかそんなものに、すごく腹を立ててたんだ。自分でも何やってたんだろうって思う」
「そうなんだ……でもね、怒りは肝臓に影響があるって言われているんだけど、がんになったの確か肺……だよね」
「肺ってなんの感情を表すの?」
「肺はね、悲しみ」
「悲しみ?」そういえば、サラ先生にも同じことを言われていた。
悲しみか……ピンと来ない。怒りならわかる。テレビや新聞で政治や国際情勢の記事を見るたびに怒りを感じて、ブツブツと独り言を言っていたから。
「おかしいなぁ、悲しみか」
「じゃあ、怒りを感じてた人、いる? 身近に」
「うん、父親だな」
「お父さんか、じゃあ、お父さんについて聞いていくね、いい?」さおりちゃんは、質問シートに目を落とした。
「いいよ」
父は、今では世界に名だたる自動車会社で、当時最年少の販売店支店長になった人物だ。その後その会社を辞め、今度は世界的な総合電機メーカーに転職し、転職組にもかかわらず支社長、役員にまで昇りつめた経歴を持つ。いわゆる社会的、組織的に成功した人物だ。
「お父さんに何を隠していましたか?」さおりちゃんが聞いた。
「そうだね、怒っていたことかな」
そう、僕には反抗期ってものがなかった。怒りを隠していた。
「なんで怒ってたの?」
「うーん、もっと無条件に認めてほしいって、思ってたのかもしれない。いつも条件がついてたんだ。これができたらとか、ここまで来たら、とか。とにかく無条件に褒めてもらったことはないね。僕にしてみると、いつもケチをつけられてたというか、ダメ出しをされていたというか」
今思うと、父はそうやって自分を追い込むことで成功したんだと思う。だからそれを、子どもの僕にも叩き込もうとしたんだろう。おかげで僕はキッチリ仕事をしたり努力をする人間になったし、その結果、仕事を評価されたことも多かったのかもしれない。
「厳しい人だったんだね」
「うん、そりゃもう。褒めてもらった記憶はないな」
「褒めてほしかったの?」
「そうかもしれない」
「じゃあ、次の質問。お父さんにどんな抵抗してた?」
「抵抗か……そうだね、なるべく距離を取る。近づかない。そんで本音を言わない」
「なんで距離を取って、本音を言わないの?」
「傷つくからだよ」
「そうなんだ」
「うん、まず僕が何を言っても、そのまま受け取ってもらえた記憶がない。いつも否定され、ケチをつけられ、足りないところを指摘されるから、傷ついていたんだね。傷つくくらいなら、近づかないほうがいいじゃない。いやな気分にならないから。とにかく親父は合格基準が高くって、ダメ出しの連続だったんだ」
「じゃあ、お父さんにやってあげようと思ってることで、何をやっていない?」
「んー、愛してるよって言ってないな」
「お父さんのこと、愛してるの?」
「たぶん、そうだと思うけど、よくわからない」
「じゃあ、お父さんにやってはいけないと思っていることで、何をやってしまっていた?」
「会話しない、距離を取る、かな」
「お父さんに、言わねばと思っていることで、言っていないことは何?」
「ありがとう、かな」
「その気持ちはあるんだ」
「うん、感謝はしてるんだけど、言う気にならない。というか、そういうシチュエーションにならない。まあやっぱり親父がいるから今の僕がいることは間違いないし、いろいろ言われたことで、役に立ってることもたくさんあるし。でも言えないし、言う気にもならない」
さおりちゃんは、シートに目を落とした。
「お父さんとのやり取りの中で、何を諦めてしまっていましたか?」
「近づくこと、かな」
「お父さんとのやり取りの中で、何を我慢してしまっていましたか?」
「親しいやり取り、かな」
「もっと親しいやり取りを、したかったんだ」
「そうだね、うん、そう。もっといろいろ話をしたいって思ったこともあるけど、無理だった」
「お父さんが決めたルールで、よく言われていたことはある?」
「我慢しなさい、努力しなさい、頑張りなさいっていつも言われてたし、周囲に合わせなさい、相手が期待する以上のことをやりなさいとか、集合時間の15分前には行きなさいとか、そうしないと社会では生き残れないとか、他にも男らしくしなさいとか、泣くなとか、そんなことも言われてた。それが僕にもしみ込んじゃったと思う」
他にもきちんとやりなさい、ちゃんとしなさい、コツコツやりなさい、間違わないようにしなさい、注意深くやりなさい、人に迷惑をかけてはいけません、約束は絶対に守りなさい、最善の努力をしなさい、とにかく勉強しなさい、周りの人から可愛がられなさい、など気がつかないうちに僕にしみ込んでいた山のような父のルールを思い出した。
「お父さんに言われた、こうあるべき、こうあってはならないという基準で、今も使っている基準はありますか?」
「完全、完璧でなければならない、かな」
「それ、どう感じる?」
「苦しいね、完璧であることなんて無理なのに、それを自分に課してる感じかな。だからいつも自分にダメ出ししてる気分」
そうだ、失敗してはいけない、間違ってはいけないし、負けてはいけない。もちろん泣いてはいけない、やるなら完璧にしなければならない。それが僕だった。
「そうなんだ……それは苦しいね」
「うん、まあね」
「それ、お父さんにちゃんと言ったことある?」
「それって?」
「苦しかったってこと。いやだったってこと」
「あるわけないじゃん」
「じゃあ、ちゃんと言葉に出して言って」
「え? ここで?」
「違うよ。お父さん本人に会って、ちゃんと伝えるの」
「……」
全身が固まった。想像するだけで緊張感で身体が熱くなる。
「そう、直接言ってほしいの。自分の中にある感情を相手に全部伝えることが大事なの。とにかく、自分の中の感情を全部外に出すのよ。そうすると、病気の元になったエネルギーが、身体から出ていくの」
父に直接これを話し、この感情を手放す必要がある……。
オー・マイ・ガッ!
なんてことだ。絶対に言いたくない、言えない。
「それから、これも必ず言ってね」
「何?」
「私は前に進むために、あなたを許しますって」
マジか。むむむ……どうしよう。絶対にできない、絶対にやりたくない……。
「これは宿題ね」さおりちゃんはニコッと笑った。
「うん、まあ」
僕はそう答えたが、それをやるつもりなど毛頭なかった。
帰りの電車の中、窓を走る景色を眺めながら、僕はさおりちゃんとの会話を振り返っていた。すると心の奥深いところから、いろいろな想いが湧きあがって来た。
なんであんなに父のことが出てきたんだろう?
なんで母じゃなくて、父なんだろう?
なんで僕はこんなに父にこだわっているんだろう?
それは雲間の輝きのようなひらめきだった。
そうか、僕は父に愛してもらいたかったのか!
僕は怒りの下にある悲しみに気づいた。怒りは悲しみを感じなくするためのカモフラージュだったのだ。
子どもの僕は、父に愛してもらおうと頑張った。一生懸命頑張った。僕は愛してほしかった。ただ単に、愛してほしかった。ひと言「愛してるよ」「大好きだよ」「そのままのお前でいいんだよ」、そう言ってほしかった。
だからこそ、愛されるために無理をして、背伸びをして、自分以外の何者かに必死でなろうとしていたんだ。でも、いつもダメ出しをされ、いつの日かそれを諦めた。
ダメな自分、弱く臆病な自分、足りない自分、不完全な自分、ビビりな自分、そういう自分を心の隅に追いやり、蓋をして『なかったこと』にしていた。感じないようにしていた。こんなの僕じゃない。僕はもっと強いんだ、僕はもっと大きいんだ。
僕は1人で生きていくんだ。もうあんなヤツの言うことなんて聞かないぞ。あんな父親になんて、なるもんか!
そうやって心の中から父親を排除し、弱い自分を感じないようにするために、怒りというエネルギーを使って、強くエネルギッシュで自信満々な自分を、作り上げていた。
行動、行動、Do,Do,Do! 格闘技で身体を鍛え、心理学の知識を蓄え、仕事でも様々な評価や成果や結果を手に入れた。僕はいつも勝者であり、優越者であり、上から見下ろす存在でいたかった。
さおりちゃんは言っていた。肺の臓器の感情は『悲しみ』だと。
そうなんだ、僕は、悲しかったんだ!
次回、「21 完敗……そして……」へ続く
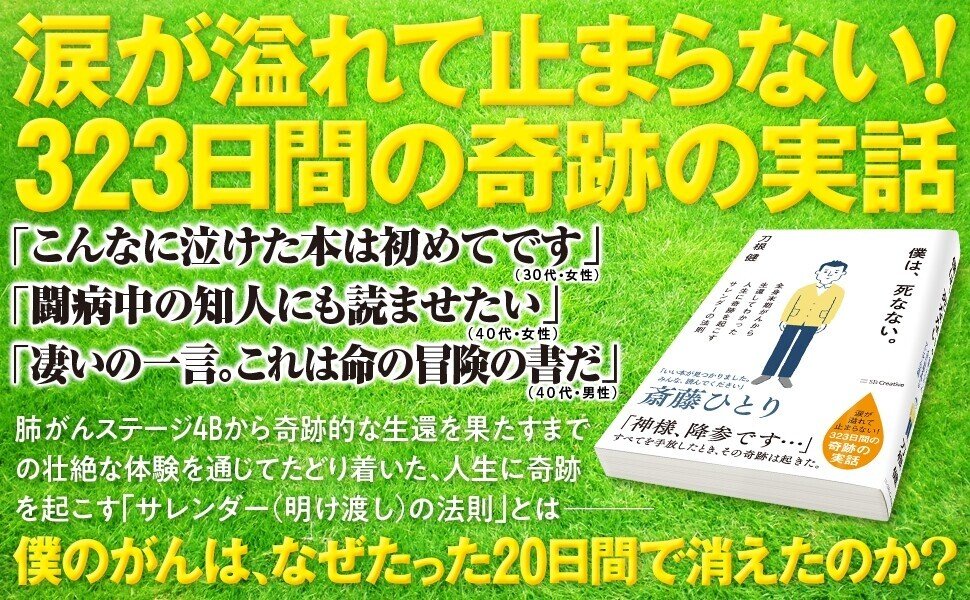
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
