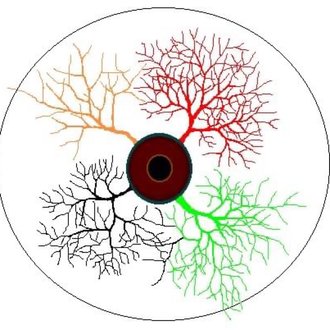★我楽多だらけの製哲書(9)★~北海道と向き合ってこなかった自分とヘッセ~
北海道出身ということが分かると、羨ましいと言われることが少なくない。
社会人になってから、幾度となくそのように言われるので、最近はそういうものなのかなと思えるようになってきた。
ただ自分は北海道愛に欠けていると思っている。ここ10年間を振り返ってみると、そのうち7年間は海外に住んでいたが、それにしても夏・冬・春の長期休みは日本に一時帰国していたので、いくらでも北海道に戻るチャンスがあったにも関わらず、10年間で北海道に戻ったのは、片手で収まる回数だと思う。
「北海道愛に欠けている」と表現してしまうと、北海道を嫌っているように聞こえるけれども、決してそんなことはなく、北海道は自分が生まれ育った大切な場所として好きではある。それなのに北海道愛に欠けていると思ってしまうのは、「北海道と正面から向き合えなかった」ということが大きく関係している。
普段からそのことについて頭を巡らせているわけではない。ただ昨日、改めて北海道と自分との関わりについて考える機会があった。
ネットニュースに「『北の国から』とは一体何だったのか? 放送開始40年、国民的ドラマが問いかけたもの」という記事があがっていた。『北の国から』は、北海道のイメージに大きく影響を与えたテレビ番組のシリーズの一つである。最近では、今年の4月に田中邦衛さんの追悼特別番組として「北の国から'87初恋」が放送されている。
実は私はこの『北の国から』を今年の4月までしっかりと見たことがなかった。「見たことがなかった」というのは語弊があるので、正しく表現するならば「しっかりと見続けることができなかった」ということになるだろう。あの作品で表現された北海道というものは、あくまでもドラマなので、ステレオタイプな北海道の農業の町というイメージがあることは否定できない。しかし、私が生まれ育った北見市や、私の親戚や祖父母が多く住んでいた周辺の町のイメージと結びつく部分が多かった。私はその親戚や祖父母などを中心とした人間模様や農地・町の中で、常に「居心地の悪さ(アウェイ感の方が適切かもしれない)」のようなものを感じていて、それに取り囲まれている状態に息苦しさを覚えていたように記憶している。
そのため『北の国から』を見ることは、そのような息苦しさを覚えることにつながるので、まともに見ることができなかったのである。だが『北の国から』が表現していた「透き通るような風景と音楽」は、とても心地の良いものだったので、純や蛍が雪原を走り回ったりするシーンや、動物たちとともに北海道の風景の雄大さが映されるシーンを見るのは好きであった。
「子どものとき暮したところは、何もかも美しく神聖なんだ。」
これはドイツ生まれで後にスイス国籍を取得した作家であるヘルマン・カール・ヘッセの言葉である。この言葉について、「暮したところ」を「場所」に限定するならば、ドラマの中で映し出される北海道の風景は眩いばかりの輝きを放つようなもので、ドラマが映し出していた風景は、特に冬については、自分の身近な場所でも同様の輝きを感じることができていて、それも相まって、私がそのシーンに魅入られていたわけである。しかし、人間模様なども含めてしまうと、それは私にとっては美しさや神聖さに結びつかないものになってしまうのであった。そのため、このドラマは連続ドラマのあとも、スペシャルドラマとして2002年の遺言まで断続的に作品が作られ、時折再放送によって見ることができる機会があったが、北海道を離れた後であっても、作品全体を見ようとすると胸が締め付けられる感じがして、風景に関わるシーン以外はまともに見られなかった。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?