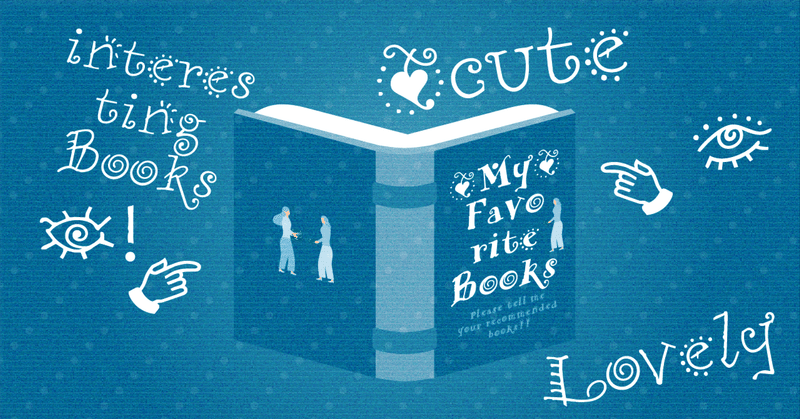
私が読了した書籍をアウトプットする理由
noteを使って読書のアウトプットを始めようと思います。以前は紙に書いてまとめたものをTwitterでシェアしていましたが、今回はnoteを使って、テキストデータ化したものを共有していきます。
「実力も運の内」マイケル・サンデル著
— ジョージ | 亀井丈嗣 (@takeshit2300) December 18, 2022
今回も最高でした。
これまでのキャリアは、本当に運に恵まれています。
これまで得た知識を、微力ながらも社会へ還元したいと思える書籍でした。#読書
#読了#読書ノート#読書記録#読書好きさんと繋がりたい pic.twitter.com/Uk7c6Eyj3E
読書アウトプットのきっかけ
読書アウトプットを始めたきっかけは、荒木博行さんの書籍「自分の頭で考える読書」を読んだことが影響しています。
その書籍の中では、読んだ本を「生き残る沈殿」として「刻み込む」ことについて書かれていました。
私は本を読むときに「問い」があって読むことが多いのですが、本を読んでもすぐに「答え」が出ない本や、フワッとした「答え」しか浮かばない本があります。
そのような本は、ふとした瞬間に「答え」がひらめくことがあります。
その際、「生き残る沈殿」をサッと取り出すことで、「答え」に近づき、解像度がクリアになる。
この「生き残る沈澱」をサッと取り出すために、テキストデータ化しようと思った次第です。
また、「刻み込む」ことの一番の効果は、刻み込んだ内容が別の本と結びつく時です。
荒木さんの書籍では「つなげる」と表現されていましたが、まさにそのように「つなげる」事を実践するため、読書のアウトプットをするようになりました。
自分の脳の中でつながった時、「あ!」というひらめきが起こり、快楽物質が脳から解き放たれた感覚になり、「本を読む事を趣味にして良かった」という気持ちになります。
とくに異なる分野の本がつながった時は、最高です!
「つなげる」はChatGPTの得意技?
ChatGPTに代表される大規模言語モデルは、言語同士のつながりを定量的に数値化したものと書かれていました。
この言語モデルは、数値が高い物を優先してつなげる仕組みのようです。
そのため、ChatGPTの答えはありきたりの内容になることが多いと思います。
私はあえて数字が低いものをつなげ、自分の中では意味が通じる。そのような事を期待しているのかもしれません。
私のアウトプット方法
私のアウトプット方法ですが、以下のフォーマットを使って書き出しています。
1、問い
2、きっかけ
3、問いに対する答え
4、学びのポイント3つ
5、自分だったらどう書くか?
6、感想
補足「自分だったらどう書くか?」
荒木さんの書籍にあった「懐疑3割」を実践しています。どういう事というと、 「本に読まれないようにする」ということです。
私は本の内容を100%信じてしまうことが多いのですが、この「懐疑3割」を入れることで本自体に読まれないようにしています。
ただ、この項目を入れることで、新たな「問い」が浮かび、沼にハマります(笑)
今後
手書きノートの内容をnoteへテキストデータ化した上でアウトプットしようと思います。
ペースは不定期。
継続できるように、皆様から反応を頂けると嬉しいです。
今後ともよろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
