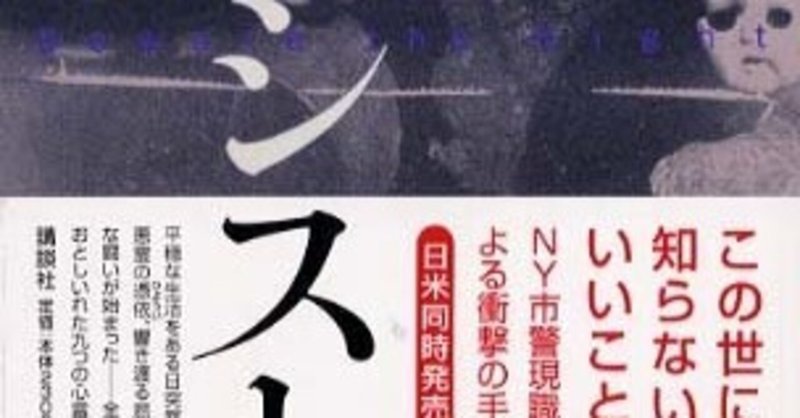
書評『エクソシスト・コップ NY心霊事件ファイル』
ホラー映画についての本を書くようにと言われたので、ともかく調べてまとめ始めている。その中で、映画『NY心霊捜査官』の原作本があることを知り、読んでいる。
映画が非常ーに興味深いのは、乱暴者で嫌な男である主人公ラルフ・サーキ(エリック・バナ。この人コメディアン出身ってびっくり。陰鬱なホラーの主人公が似合いすぎ)の人物像。警察の仕事がいかに厳しいかということの現れでもあるが、心にストレスがかかると妻や子供に対する態度が閉鎖的で冷たい人間になってしまう。にも拘らず劇中で二人目の子供の妊娠が発覚する。とてもじゃないが、父親には向いていなそう。そこに出現したメンドーサ神父(エドガー・ラミレス)に導かれ、悪魔祓いを体験する。その体験を通じ、彼は一つ成長して、いい父親・いい警官になるという物語になっている。
オカルトという出口を見いだすことで、彼の人生が安定するという、何かホラーファンのお手本のような人物像だが、原作『エクソシストコップ』のサーキは、元から根っからのホラーファンであったことが分かる。『エクソシスト』の本を見つけた興奮から本書が始まっているのは偶然ではなかろう。また、後に『死霊館』として映画で取り上げられる心霊研究家のウォレン夫妻との出会いによって彼は悪魔祓いの道に入る。
2001年に刊行された本書の描写を読んでいると、その後から今も尚続くオカルト映画ルネサンスとも言うべき、アメリカの悪魔祓いテーマの映画に利用されたであろう描写が次々に出て来る。
身の回りの物は、まるでごみのようにあちこちに放り出された。未来の花嫁が大事にしているピエロ人形のコレクションは、たびたび床にまき散らされた。彼女の本は絶え間なく本棚から飛び出し、ときに漆喰がへこむほどの勢いで、近くの壁にぶち当たった。(65ページ)
重い家具類がひとりでに動いて、自身のときのようにがたがた揺れたり、床から浮き上がったりした。(65ページ)
また、悪魔祓いの段階を六つの段階に分けており、「存在」「偽装」「転換」「声」「衝突」「追放」と名付けられていることも紹介している。まるで映画の脚本のようだ…。
また、アメリカ人にとっての悪魔とはどういうものなのか、ということを考える上でも大変示唆に富んでいる。
彼はまだ憑依されているのだ。そして、自分の中に悪霊が棲んでいることを、まだ認めていないのだ。彼は悪霊を、敵意に満ちた侵略者ではなく、自分の体の一部と考えている。(189ページ)
悪魔という存在は、自分ではない、外から来るものだという捉え方である。悪魔が人に悪いことをさせるのだという風に考えているのだとしたら、「悪いこと」から離れることの難しさを言っているとも言えるし、それが抜けた後、人を責めることをよしとしないということなのかもしれない。また、悔い改めることで許される余地も出て来る。日本の場合はそうはいかないのではないだろうか。
また、サタニスト(悪魔崇拝者)についての記述は非常に面白い。80年代に、アメリカではサタニストパニックと呼ばれる現象が起きた。
本書117ページ~118ページには、あるサタニストの父親のことが書かれている。彼は他の男と共に、幼い男の子に性的虐待を加えたとされており、最終的には子供から引き離されることになる。また、子供たちの証言では、赤ん坊を殺して生贄として悪魔に捧げたとされた。しかし遺体が入っていると子供が証言した箱の中は空で、赤ん坊が本当に殺害されたという証拠は出てきていない。そこで筆者は、組織的サタニストは組織ぐるみで死体を隠したのかもしれないと書く。この想像力こそ、後にトランプ支持者が愛する有名な陰謀論「ピザゲート」に繋がる。
ある推計によると、この国には八千を超えるオカルト教団が存在する。メンバーを小児性愛者の聖職者や、レズビアンの元修道女に限っている特殊化したオカルト教団も存在する一方で、ほとんどすべてのアメリカの都市では、毎週、各地で万人向けの黒ミサが開かれている。サタンを”現世の肉の欲望をかなえてくれる象徴的、個人的な救世主”とみなすように説くアントン・ラヴェイの『悪魔のバイブル』は、百万部を超えるベストセラーとなった。こういうメッセージは学校ですぐに追随者を生み出すらしく、大部分の学校では、白魔術であれ、黒魔術であれ、魔術を行なう自称魔女が、生徒の中に少なくとも二、三人はいる。不満を抱えた今日の若者の間では、悪魔の紋章を付けるのが流行している。憑依が増加傾向にあるのも、不思議はない!(235ページ)
ヴァチカンによる儀式書の改訂が、悪魔祓いに対する人々の興味の火つけ役となった。二〇〇〇年九月、シカゴ大司教管区は百六十年の歴史の中で初の公式エクソシストを任命したと発表した。…<中略>…ニューヨーク大司教管区に属する四名のエクソシストのひとり、ジェイムズ・ルバー師によると、一九九〇年には市内で皆無だった悪魔祓いの儀式が、十年後の二〇〇〇年には年間三百回以上に激増している。(248ページ)
憑依や悪魔祓いが増加傾向にあるとしている点は興味深い。そのような状況を背景として、現在、オカルト映画がルネサンス期を迎えているのだろう。また、悪魔への恐れは政治的な空間にさえもしばしば顔を出している。そして、オカルト映画は、善と悪の対立を描くが故に、多分に保守層とも相性がいいのではないだろうか。
上記で彼が言及している自称魔女の女子生徒とは、私見では、クラスの中で浮いている、どこにも居場所のない子供達だ。『ザ・クラフト』はその寂しさを描いていると思う。なぜ人々が悪魔信仰に走るのかは、彼には理解できないに違いない。最終的に悪に走って処罰された形のファルーザ・バーク(元々『リターン・トゥ・オズ』でドロシー役だったのに後にはゴス化w白目がいい)の役は気の毒に思えた。
筆者サーキは、ニューヨークの白人男性、厳格で短気な父親に育てられ警官になったというマッチョ主義の権化のような人だ。抑圧的な性格であろうし、正しく・善くありたいと心底願っている一方、自分の中にある怒りや暴力的な衝動を恐れているように思われる。本書では、悪魔祓いのストレスで妻と仲が険悪になり、8カ月別居、その間ほとんどの時間を母親の家で過ごしたということまで書いている。
彼自身は、男性の方が悪魔の攻撃に対し、精神的に弱いということを意識しているように思われる。
”制圧”が始まるころには、たいていの家庭は機能不全に陥っている。みんなが意気消沈し、各々の小さな世界に閉じこもるか、そうでなければ、いがみ合い、けんかが絶えなくなっている。しかしこの一家は、超自然的な逆境の中で、崩壊せず、団結を保てるだけの精神的強さを持ち合わせていた。女ばかりの一家なので、ひとりひとりが互いの気持ちや不安を共有することに慣れていたからかもしれない。(146ー147ページ)
サーキの周囲の人々もほぼ全てが男性で、何かしら従軍体験や武術の心得がある。しかも仕事の相棒と喧嘩して数カ月も口をきかず、活動の支部が解散することになってしまったりする。本書は荒くれ男の信仰告白なのかもしれない。未見だが、『マシンガン・プリーチャー』の話を思い出す。
また、『アメリカン・スナイパー』の主人公も連想させる。根はいいやつだが自我が弱く、シンプルに、善くあろうとしている。そういう彼らにはマッチョ主義が憑依しやすいのかもしれない。
私は、オカルト好きというは、マッチョ主義からは程遠い、性格が薄暗い人たちなのではないかと思っているのだが、そういう人達自身はあまり悪魔を信じていないように思われる。
彼の「悪」との向き合い方は何だか重たい。ある悪魔に取り憑かれた一家の娘たちが、ナイフで家族を傷つけようという衝動を感じて怯えるところがある。悪霊は人間の負の感情を増幅させるものだとして、
深い無意識のレベルで、彼女たちは自分たちが傷つけられ、引っ掻かれ、ベッドの上で威嚇されたのと同じように、誰かを傷つけたいと思っていたのだ。そう思わない人間がいるだろうか?わたしたちは誰しも、暗い面を持っている。(146ページ)
と書いている。
一方、ファンタジー・SF作家のル=グウィンは『夜の言葉』の中で、
影とはわたしたちが自我として意識するもののなかに入れたくないもの、入れられないものすべて、わたしたりの内にありながら、抑圧され、否定され、とりあげられることのなかった性質および傾向のすべてなのです。
別の言い方で言えば、人が自分の影を見ることが少なければ少ないほどその力は強くなり、ついには一種の脅威、耐えがたい重荷、魂のうちなる恐怖の種ともなりうるのです。
意識に受け入れられない影は外側に、他人に投影されます。わたしはなにも悪いところはない――あの人たちが悪いのだ。※太字箇所は傍点
おのれ自身が悪と深い関係をもっていることを否定する人は自分自身の現実性を否定する人です。(6 子どもと影と)
と述べている。自分の中の暗い部分に降りて行き、それと対峙することを自我の成熟と捉えるル=グウィンの考え方と、そのような感情を抑圧しようとするサーキのような考え方は、真っ向からぶつかるのではないかと思う。どちらも頷けるところがあるのだが、パヨク性という正しさの権化からのリハビリを試みてきた私は今、専ら、ル=グウィンの方の意見を支持する方に寄っている。
『エクソシストコップ』からは、アメリカ保守層の思考法が分かる。そして、保守層のホラーファンとは、極めて信じやすい、純粋な人々なのではないかという感じもする。アメリカ人は元々ピューリタン=宗教意識高い系として旧世界から逃げてきた人々の末裔だ。最後にアメリカの都市伝説を論じたベン・C・クロウの文で終わりたい。
慧眼の持ち主とは言いがたい著述家たちが、散文的と評したニューイングランド移植(317ページ)の清教徒たちですら、神話創造に一役買っている。しかしそれは想像力の奔放な運動から出たものではなく、宗教的熱意ゆえの信じやすさから出たものだった。たとえばコットン・マザーは悪魔の行う驚異や双頭の蛇のことなどを記録している。もちろん、それは躁病的精神の産物と形容しても、当たらずとも遠からずといった類のものであるが、そうした精神はセイラムの魔女たちの処刑といった騒動をもたらすことになる。…<中略>…
全体として、初期のニューイングランドにおける驚異への嗜好は敬虔さ(虚飾と表現する者もいるだろう)が核になっていたし、神意を説明する際に格好の手法を提供することにもなった――とりわけそれはインクリーズ・マザーとエドワード・ジョンスンの著作のなかに見ることができるだろう。(ベン・C・クロウ『アメリカの奇妙な話1 巨人ポール・バニヤン』(西崎憲監訳)、ちくま文庫、2000年、316ページ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
