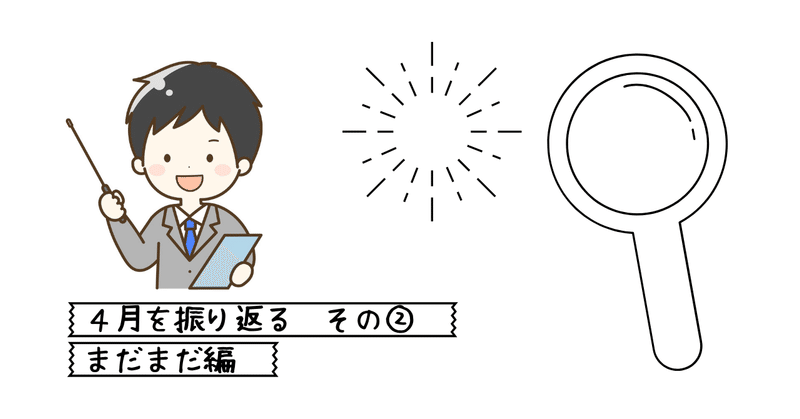
[note25]新学期開始から1か月を振り返ろうPART②(見直しましょう!)
読むこと+授業と社会を繋げること
1か月の振り返りPART②は高校3年生の政治経済の授業に関しての振り返りです。3月に迷いに迷って、結局、授業プリントは空欄付きではなく、全て文章化して、生徒に読むことを重視してもらうことにしました。授業構造は以下の形にしています。
予習(授業分のテキストを読み、不明点はマーカーなどを引く)
canvaで作成したスライドで全体解説
生徒の質問に対応+補足
実際のニュースや記事を素材に授業で扱った知識でまとめていく
プリント内容の振り返り(毎回8問程度を口頭で質問)
45分の授業内で最初は上手く機能していたけど、内容が難しくなってくると次第に時間コントロールが上手くいかなくなります。実際、テキストを読んで来たかどうかについては確認する術はなく、ある意味、こちらの意図を説明して、生徒を信頼していた面があります。ただ、理系の社会系科目はどうしても学習が後回しになりがち…仕方ないとは言え、その対応が難しい。

まだまだ編①
本来の目標はインプット3:アウトプット7とまではいかなくても、せめて5:5くらいのバランスを保ちたいと思っていました。しかし、どうしても教師の説明が多くなる➡結果としてアウトプット時間が詰まるという悪循環に陥っていました。もちろん毎年、政治経済は担当しているので、経験もあるし、大失敗という状況ではないけど、自分の中で描いていたイメージとは、どうにも一致しない。主体が教師側になっています。
そもそも、事前の予習として「テキストを読む」ことをお願いしている以上その内容確認で理解度をチェックすることが欠けているのが問題ですね。
学習の事前理解度(レディネス)を見る診断的評価というものがありますが、それがあってこそ、教師側も生徒側も「分かっているから、ある程度飛ばしてもいいところ」と「丁寧に補足が必要なところ」が分かる訳ですよね。何か根本的に授業デザインに問題があったように感じています。
まだまだ編②
授業内容と実社会を繋げる、言い換えると具体と抽象の往復を目標としていますが、問い方や素材の選び方に少し無理があったのかも…。ニュースに対して自分の意見や考え方を持つのは大切だし、それが目標ではあるけれど、テキスト内容とニュースを無理やり結びつけようとすると、歪な感じになります。ここのところは個人の拘りが強すぎたと思っています。45分という授業時間の中でテキスト内容を扱いながら、さらに時事に踏み込むのは結構、厳しい。もっとシンプルにニュースタイトルや概要だけでもいいので、そこから、一定のフォーマットに従って授業知識を使っていく形にしないと、取り組む側の生徒がやりにくいはず。そこは生徒視点が欠けていました。ともかく生徒にとっては来年1月の大学入学共通テストの政治経済や倫理政治経済で得点を取りたいわけだから、彼らの目標と教師の目標が乖離(教師側は両立を目指していたとしても)しているように感じれば不安が増します。
結果的に中間試験の成績は悪いものではなかったけど、修正は必要!!
とりあえず、いつもの「マイノート」に書きつけて、修正ポイントを可視化しつつ、次の授業に備えようと思っています。noteで書くことでもだいぶ、整理されますが、そこからもう少し掘り下げるのが最近の流れです。
全国の社会科の先生方、教える量と内容、時間、敢えて生徒の自学に任せること…授業は色々難題が多いけれど、どんな風に取り組まれているのかな?これからも学ばせてもらいたいなと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
