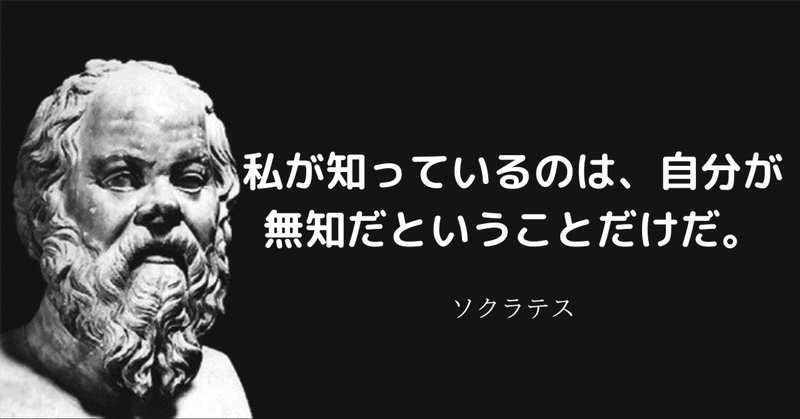
ギリシャ哲学〜「人間の内面」と「超越したもの」への考察
ギリシャ哲学の展開、ソクラテス、プラトン、アリストテレスについてお話しします。この3人はがっつり師弟関係にある哲学者です。
この3人が登場する以前の時代は、基本的に哲学というと「自然哲学」でした。その自然哲学から、この時期、「人間の内面」に関する哲学への移行が始まるわけです 。ペリクレス将軍によってアテネはギリシャ文化の中心となり、いわゆる民主政治の全盛時代を迎えていました。多くの悲劇、喜劇の演劇が演じられ、アテネ市民は都市文化、ギリシャ文化を満喫していました。そこで当時、「ソフィスト」と呼ばれる新しい形の知識人たちの多くがアテネを訪れ、この都市で有能な人物になるための「徳(アテレ)」を授けるための学校を設け、授業料を多くとっていました。その内容は雄弁術であり、相手を言い負かすための詭弁術まで含まれていたといいます。こういった状況に対する反対者としてソクラテスが登場するのです。
ソクラテスの「無知の知」と「対話」
ソクラテスは、人間とっての「徳」とは魂、精神の卓越性であることに他ならないと信じていました。なので、彼は、魂と精神の卓越性を求めて「知」の探求を求めました。ソフィストたちの掲げる「知」を偽りの「知」と断じ、自分は無知であることを知って、ソフィストたちの有能な「知」と対決しました。その対決方法が「対話」という方法でした。この方法は自分こそ有能な「知」の所有者であると自負するソフィストたちとの対話であり、その対話を重ねることによって双方とも「無知の知」であると自覚に至る方法なのでした。この対話はその後の西欧思想にとって、重要な方法となるのです。

ソクラテス試みた「対話」という方法はこの通り、その後の西欧思想の重要な方法論のスタートを成すことになります。ただし、ここで問題が起きてしまうのです。自分は有能な知識人と自負してるアテネの有名人と対話し、結局相互に何も知らなかったと自覚に至ることはソクラテスにはよいかもしれないけれど、アテネの有名人、有力者にとっては許しがたい屈辱だったのです。なので、アテネが民主政治から衆愚政治に移り代わろうする時、ソクラテスは、「アテネの有名人、有力者を侮辱した罪」に問われ、死刑を宣告されてしまうのです。
プラトンを含むソクラテスの弟子たちは、師匠であるソクラテスにアテネからの逃亡、亡命を進めましたが、ソクラテスは「悪法も法である」と言って毒杯を仰いで自殺してしまうのです。ちなみにソクラテスは一冊も著作を残しませんでした。すべては、プラトンなど弟子たちの描いたものによってソクラテスについて私たちは知ることができるのです。
プラトン初期「ソクラテスの弁明」
プラトンはペロポネソス戦争ーーアテネを中心とするデロス同盟とスパルタを中心とするペロポネソス同盟との間の戦争ーーの最中にアテネの名門に生まれ、青年期を送った哲学者です。その上、ソクラテスに認められて、彼の弟子になりました。彼は名門の出身であるため、アテネの国家的職務につこうと考えていましたが、アテネの衆愚政治のもとで、先生であるソクラテスが自殺するという悲劇に遭遇し、国家的職務に着くことの虚しさを自覚するになりました。そこで、彼はエジプトまでの旅行をしながら、自分と先生であるソクラテスとの関係を考えるようになり、初期の著作「ソクラテスの弁明」に代表されるような人間の生き方はどうあるべきかについての考察を行うようになるのです。それは我々の魂がより良いものになるため、自分を知ること、知ることを愛すること、「philo(愛すること)+ sophy(知)」=哲学の第一歩をしるすことになります。
プラトン中期「イデア論」
初期は「知」を愛することからスタートしたプラトン。次の段階は「知」を愛することと言うが、人間の真の「知」の対象となるものは何かと言う問いに移ります。それは個々の対象を超えたものであり、「イデア」と呼ばれるものでした。例えば「動物とは何か」と問われれば犬、猫、猿、トラ、ライオンと私たちは答えることができるでしょう。つまり、それらの生き物たちにとって「動物」とは抽象的イデアである。また、例えば「美」とは何かと尋ねられれば具体的には美しい風景、美しい着物、美人など様々あり得る。これらの一つ一つの個物を超えて「美」は抽象的イデアでとして存在します。それは代表作「パイドン」に記されています。
プラトン後期「神のイデア」と「アカデメイア」
結局、中期の哲学におけるイデア論は、個々の思考のあり方を問題にしたものでした。しかし、後期になると個々人のあり方よりも、イデア論はこの宇宙の創造者、つまり神のあり方にまで拡大されることになります。「神」が様々なものを想像するのは、「神のイデア」によってであると言うのです。それは代表作「テイマイオス」にしるされています。つまりプラトンの哲学は先生であるソクラテスにならって人間のあり方、愛知のあり方から始まって、宇宙創造主の愛知、つまり神の「イデア」によって全宇宙が創造されたのだとする説にまで拡大されたことになります。なお、プラトンは、郷里アテネの北に「アカデメイア」という学園を創立し、長く師弟を教育する場にしたことはこれまでこれまた有名な話です。
プラトン主義はキリスト教に影響与える
プラトンの「神による秩序ある宇宙の創造」「 霊魂の不滅と輪廻転生」等の思想は、古代のみならず、中世や近代に入っても大きな影響与えることになります。特にキリスト教へ大きな影響与えることになるのです。
アリストテレスは現実主義者
アリストテレスはアテネを始めとするギリシャ本土の都市国家群がマケドニアのアレクサンドロスに滅ぼされ、ギリシャ帝国の一部になった頃の哲学者です。彼はプラトンの創設したアカデメイアで研究生活を続けながら、アレクサンドロスの幼少時代に家庭教師まで務めたのです。
アリストテレスは、先生であるプラトンのイデア論を単なる観念論と言って退け、彼はこの現実世界を成り立たせているものは「何か」と言うところからスタートする。彼によると、我々の現実世界を成り立たせてさせているものには、4つの要素があると言う。
形はどんなものであるか。
どんな質によってなっているか。
どんな動きをしているのか。
どんな目的のために存在しているか。
一切の存在物を以上、4つの要素に分類されて考察されるべきと考えたのです。アリストテレスのこのような分類は、現に我々の目前に存在している全ての者に対する考察であり、特に3と4の要素の設定は、新しい考察の対象として登場してきていた動植物学を含めた生物学の考察の重要な手がかりとなったことは想像に難くない。
その上、このような4つの要素によって構成される「思惟」の背後に、「思惟の思惟」である「神」の想定を持ってくることになります。つまり、アリストテレスについては、こう言うことができると思います。あのソクラテス以前の「自然哲学」とプラトン以来の「超越神」の設定とをあわせ持つ総合哲学の樹立を主張する態度がアリストテレスにあったのだ、と。このようにしてソクラテス、プラトンに続く哲学として、アリストテレスは自分の立場を誇らかに示したものでありました。
その通り従来からの自然学、形而上学、倫理学、論理学、政治学は一見、アリストテレスによって統合、統一されたかに思われました。これはあたかも古代世界の完成を思わせるものであったと言えるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
