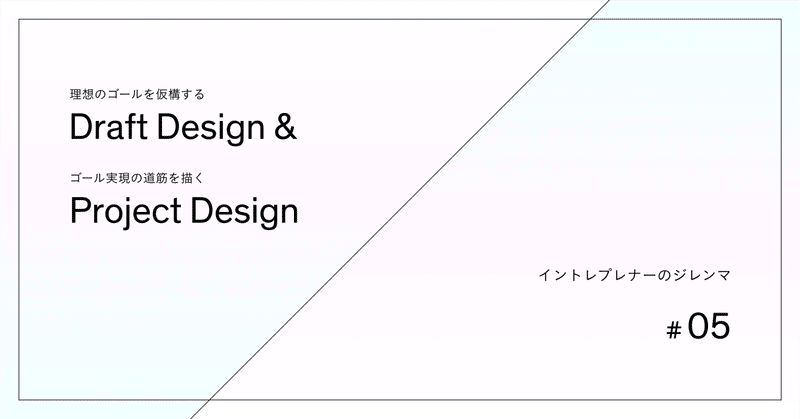
#05 イントレプレナーのジレンマ
ここまで、理想のゴール像を解像度高く描くことで、実現の道筋をプロジェクトとして描けるようになること、そしてプロジェクトをドライブさせるためのモメンタム(勢い、推進力)を保つには、管理ではなく自主性の最大化が重要であることについて触れてきた。
ではそもそも、最初の「理想のゴール像を解像度高く描く」にはどうすればいいだろうか?
ここでもまたキーワードになるのが「自主性」だ。
起点がなければゴールも描けない
理想のゴールを描き、その実現に向けて邁進する。そんなリーダー像の最たるものの一つは起業家だろう。実際に、これまでデザインファームのディレクターとしても数多くの新規事業創出支援に携わってきた。
しかし、残念ながらそのほとんどは失敗どころかスタートすら切れないまま終わってしまう。
もちろんそれは支援に携わったこちらの力不足によるところもあるだろうが、いくつもの事例を経験するうちに気付いたことがある。生存者バイアスと言われるように成功には再現性がないが、失敗にはパターンがある。その最大の要因の一つこそが「自主性の欠如」だ。
当たり前だが、ゼロから新たな事業を生み出すのは並大抵のことではない。
資金も時間も労力も信用も、必要なものは常に足りることはなく、それらが尽きるタイムリミットに追いつかれないうちに、何もないところから価値を生み出し、事業を軌道に乗せないといけない。冷静に考えてみると、さながら時限爆弾を抱えながら全力疾走するような芸当だ。
そんな勝負に挑んでいるというただ一点だけで、すべてのスタートアップと起業家は尊敬に値すると思う。
今「冷静に考えてみると」と言った通り、そんな勝負に身を投じて、その上勝とうとさえ望むなら、普通ではいられない。つまり、自分自身のパーソナルな部分から生まれる、心から共振するような課題や渇望、憤怒など、一種の「狂気」とも呼べる自主性がなければ勝負の土俵にすら立てないのだ。
そういう意味で、「大企業の新規事業部」や「イントレプレナー」は、それ自体が矛盾を孕んだ難しい存在とも言える。なぜならば、会社や上司から仕事としてやれと指示された時点で自主性やアントレプレナーシップから遠ざかってしまうからだ。それが誰かから与えられたものになってしまった時点で、新規事業創出をやり抜く強度も狂気も持ち得ない。
外部のパートナーとしても、リサーチやアイディエーション、ビジネスモデルの検討などを手助けすることはできても、心から本当に賭けたいと思えるミッションだけは残念ながら授けることはできない。
そして、自主性に基づいた強い意思がなければ、マーケットやユーザーをいくら調査しても、その中から答えを見出すのは難しい。
ただでさえ「千三つ(1,000個のうち成功するのは3つくらい)」と言われる起業だ。なんとなくそれっぽいアイデアやペルソナを作っても、うまくいかなそうな理由やリスクはその何倍も簡単に見付けられてしまう。
そんなやらない理由を乗り越えてなお「やるべきだ」と信念を燃やし続けられるだけの強度と狂気がやはり要るのだ。
自分自身の中に起点がなければ、理想のゴール像を解像度高く描くことはできないし、ゴールイメージが曖昧なままでは、実現させるためのモメンタムを保てない。これは新規事業創出という特に難易度の高いプロジェクトであればなおさらだ。
大企業という後ろ盾があり、資金・時間・労力・信用のサポートを受けられ、一見大きなアドバンテージがありそうに見えるイントレプレナーのほとんどが失敗する、いや勝負を始めることすらできない理由もそこにある。
心に種火さえあれば
ただし、これはすなわちイントレプレナー(社内起業家)は駄目だ、という話ではない。
資金・時間・労力のサポートを受けられ、もし失敗しても即一文無しになるわけではない状況は、ハングリーさを持ちづらい点だけを除けば、アドバンテージであることに間違いはない。
外から心に火は点けられないが、逆に心に種火さえあれば、外から風を送りその火を大きくすることはできるからだ。
例えば、借り物ではない課題意識や世の中に対する怒りさえ持って来てくれれば、単純に壁打ち相手として対話をするだけでも、外部性という光でよりその姿を鮮明に映し出せるかもしれない。
また、トレンドスクレイピング(先進事例調査)や競合調査によって、より効果的なポジショニング検討に役立てることもできる。
その事業を通じて助けたい相手に対してインタビューやデザインリサーチを行えば、思いもしなかった問題の構造が見えたり、当事者でさえも気付いていなかったインサイト(潜在的な心理や動機)を発見し、より本質的な解決策を考えられるかもしれない。
そして、こうして立てた課題仮説を検証するときこそ、MVP(Minimum Viable Product:最低限実用に足る製品)やプロトタイプなど、理想を精緻化・具体化した中間成果物としての「ドラフト」がその力を発揮するだろう。
担当者自身が心に主体性から生じる熱量を持ち、会社や上司を、そしてこうして時に僕らのようなデザインファームなどをもうまく利用しながら、それを実現させてやろうと狡猾に貪欲に邁進できさえすれば、イントレプレナーの成功の確率はむしろ少なくないはずだ。
誰もが「ドラフトデザイナー/プロジェクトデザイナー」であっていい
冒頭で「理想のゴールを描き、その実現に向けて邁進するリーダー像の最たるものの一つが起業家だ」と述べた通り、「ドラフトデザイナー」や「プロジェクトデザイナー」は、クライアントワークを行うデザインファームだけでなく、プロジェクトオーナーやクライアントサイドにいたっていい。
むしろ、様々な立場から「理想のゴール像」を描き、それを互いに叩き合い磨き合いながらフィードバックループを加速させていく方が、社会の閉塞感を打ち破るモメンタムを生み出せるのではないだろうか。
何より、そっちの社会の方が面白そうだ。もっと軽率に色んな理想を見たいし語り合いたい。
デザインが誰のものでもないように、ドラフトデザインもプロジェクトデザインも誰もが自由にしていいのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
