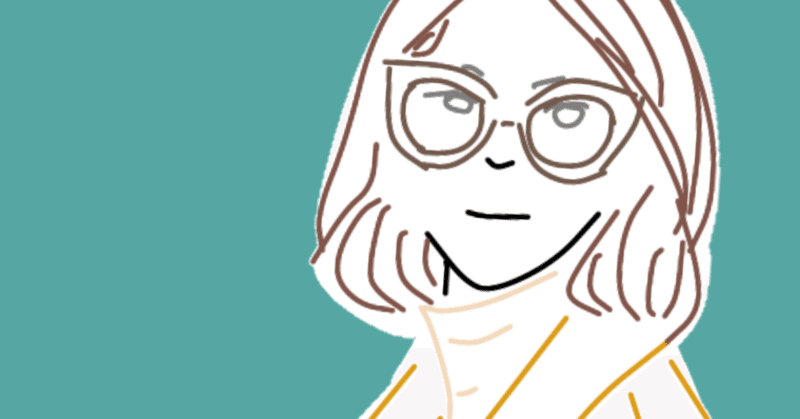
【ダイバーシティ】「異」と共に成長する②(山本、2022)未発の異と異対面
今回も、『異文化コミュニケーショントレーニング~「異」と共に成長する』を取り上げます。
属性も価値観もますます多様化する組織や社会において、排除(exclusion)や過度な分化(differentiation)を作らないために、何を意識する必要があるか。この本を読むと、「異」との向き合い方を考えさせられます。
ご紹介するのは、書籍の第8章『未発の異と異対面』というパートです。
どんな内容?
今回ご紹介する『未発の異と異対面』という章は、「異」と対面するときに私たちが何を「見る」のか、何を「見ていない」のか、なぜその違いが生まれるのか、そして、どう「見える」ようになるのか、という知覚に関する内容が紹介されています。
私たちは「見たいものを見て、聞きたいことを聞いている」ようです。
そして、前回の投稿で紹介した心理構成主義の立場に立つと、見たいもので自分の世界(または現実)を認識しています。
言い換えると、気付かずに見過ごしている「異」が自分の世界の外側にある、ということです。
こうした「異」に気付き、対面することで、新たな視点・まなざしを得ることが出来ます。すなわち、これまで見ていた世界が再構成され、より広い世界を認識できるようになります。さらに、「異」によって世界が広がることで、「自分」を相対化し、自分に対する気付きも得られます。
「異」と対面し、新たなまなざしを得て知覚が変化し、認識する世界が変わっていく。そのメカニズムを説明するのが、この章になります。
「見る」と「見ない」
まず、「見る」というテーマに関して、はじめに心理学において有名な、「ルビンの壺」が紹介されています。

超有名な図なので、紹介不要かもしれませんが、簡単に言えば、黒いところを見ると壺に見え、白いところを見ると向かい合った顔に見える、という多義性をもった図です。
不思議なことに、壺を見ているときは顔は見えない、顔を見ているときは壺は見えません。片方を図、もう片方を地と呼び、図と地は、瞬間的に切り替えられても、同時に見ることはできないと言われます。
著者らは、この図形が「ルビンの『壺』」と呼ばれるラベリングについて指摘しています。ルビンの顔ではなく、壺と呼ばれるので、壺を意識し、顔が見えにくくなるようです。つまり、私たちはラベリングすることで、もう一方が見えにくくなる、という性質を持つとのこと。
また、「選択的知覚」という、全体の中で自分にとって意味のある情報だけに注意を向けて知覚する考えが紹介されます。この知覚を働かせている時、過去の経験にもとづいた補正がなされます。例えば、私の大好きなサウナの記事で「ストロング」という説明があると、サウナ温度の説明がなくても「かなり熱いのだろう」と勝手に補正しながら情報を選択的に知覚します。
また、こうした補正(シミュレーションと言うそうです)は、私たちの経験によるコンテクストに左右されます。書籍では、以下の例示がなされます。
アメリカ社会で白人の警察官が無抵抗の黒人住民に対して暴力をふるい、発砲して死に至らしめる事件が繰り返し起こる背景にも、差別意識のあるほかに、偏った世界観によるシミュレーションがあることが考えられる。黒人は乱暴者という先入観と偏見にもとづきシミュレーションした世界には、やらなければやられるというストーリーが成立する。そうなると、背中を向けた相手でも反射的に構え、携帯電話の所持と銃を勘違いして発砲するような、過剰防衛が起こる確率も高まってしまう。
私たちが、「異」に直面した際に、「先入観と偏見にもとづいたシミュレーションで作られた世界」の生み出すストーリーに反応して、感情を抱く、という例です。
「異」と対面したときに私たちが作ってしまう世界観やストーリーのもつ怖さ・危うさが感じられます。
異を体験し、自分のこれまでのストーリーに気付いたり、そのストーリーが引き起こす感情のラベルだけで理解するのは危険。
異を体験して得られた新たな「まなざし」から、見える世界や現実を変えることも役に立つ、と筆者は述べています。
未発の異と可視化
筆者は、顕在化していないがゆえに見過ごしている異を、「未発の異」と呼びます。ルビンの壺も、一度見えるようになり、図と地の境界を理解できると、見えていなかったものを見るようになる「カテゴリー化」の視点、新たなまなざしが獲得できます。
書籍では、高いヒール=女性らしさというカテゴリー化によって、その裏にある苦痛が顕在化しなかった例が語られます。「ヒールのせいで足が痛いなんて、プロ意識の欠如だ」なんて言われるようです。(ヒドイ・・)
しかし、一度顕在化され、認識が広まると「女性らしさ」いう話は差別と結びつき、炎上します。こうした盛り上がりによって、ヒール=苦痛という未発の異がより顕在化されていくようです。(Black Lives Matterも一緒ですね。)
異と対面すると、「そうだったのか」とハッとさせられる気付き・知覚(アハ体験、と言います)を得て、「異」から現実を捉えなおすことが出来ると筆者は述べています。例えば、外国で生活をすると、「外国も住みやすいし、楽しい!」「日本人という人種を超えて仲間になれるんだ!」という気付きを得て、海外での仕事に興味を持ちだす(=これまでの仕事観という現実が書き換わる)ことが起こり得ます。
また、興味深いことに、「異」を体験すると、「自」への気付きもあるようです。確かに、自分が海外で生活したときに、「サウナが当たり前の日本の生活って豊かだった」とか、バスで財布をすられそうになって「やはり日本は安全だ」と感じたことが思い返されます。
越境学習にもつながる視点ですが、異を学ぶから自に気付ける、というのは、研修における他者との相互触発でも起こる事象です。他者という異との触発で、自分を相対化し気付きを得るのは、「異対面」の文脈からも重要だと感じました。
一方で、「異」との対面には、痛みを伴うこともあると紹介されます。例えば、良い会社に入れているのは自分の実力だ、と考えている人は、自分の恵まれた経済環境に無自覚であり、経済的困窮から、実力の発揮さえ叶わない人たちがいる、という「異」に気付けないことはよくある話です。以前紹介した、公正(Equity)に目を向ける重要性ともつながります。
こうした異対面によって、自分の持つ特権性に気付いてヒヤッとしたり、他者の辛さに無自覚であったという痛みを感じることもあるが、その痛みや無自覚といった負荷を避けてばかりいると、異対面やそれによって世界を拡げたり、自分を再構築するチャンスが失われる、と筆者は主張します。
感じたこと
「異化体験」は重要だし、学びになる、という感覚は持っていたものの、そのメカニズムに対する理解はすっ飛ばしていた、、、と感じ、とても参考になりました。
自分のまなざしが世界を構築し、その世界を「異」との対面が拡げてくれることに対して、個人的にはワクワクします。
一方で、自分の世界にとどまりたいという人もいるでしょうし、わざわざ痛みを伴ってまで「異」を体験したくない人も結構いる気がします。局面においては、自分にもそういった傾向が出る気もします。
そんな局面に直面した時に、
「新たなまなざしを得て、自分の世界を変えていこう」
「見えていない領域に気付くことで、もっと多様性を受け入れ、共感できる自分になろう」
と言った、自分自身にかけられる言葉が得られたのはとても有意義でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
