
音楽にとって感覚/意味とは何か?
1. 音楽には「単語」がない
文字には「単語」というものがある。それに対して、音楽は記号的に捉えることは可能でも、文字が持っている「単語」にあたる部分がないために、いわゆる「意味」というものが発生しないんじゃないか。そこが「音楽」と「言葉」との大きな違いではないか。レヴィ=ストロースは「音楽には辞書がない」といっている(「言葉と音楽」『みる きく よむ』みすず書房収録)。
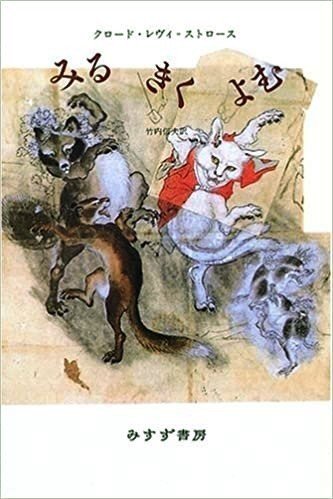
そもそも「単語」とは、外在する特定の事物と対応関係を持った記号だといえるから、たとえば、目の前を一匹の動物が歩いてきて、誰かがそれを指差して「これは猫だ」といったとすると、この場合、指し示すという動作が「これは」にあたり、その示された事物が「猫だ」という言葉で表わされることで、その事物と「猫」という単語は対応関係を持つことになる。つまり目の前のこの動物は「猫」という単語によって、人の意識のなかの言葉の脈絡のなかに入ることができ、世界と言葉との有機的なつながりが確保されるわけである。そして、もはやいちいち目の前の動物を指し示さなくても、辞書を開けばこんなふうに書いてある。
ねこ[猫]:猫科のほ乳類。家畜。皮は三味線の胴張り用。云々。
ここではすでに「単語」は、外在する事物との対応関係をやめて、言葉同士の対応関係のなかへと移っている。つまり「単語」は具体的な事物との関係から逃れ、言葉だけで出来た世界で「抽象的な」関係を取結ぶことになる。しかし、このような「抽象的な」関係が成り立つためには、多くの単語が「具体的に」必要とされる。たとえば、「猫」とか「犬」とか「馬」とか「蛙」とかいった単語がそれぞれの動物を指し示すために具体的に必要となるように、「概念」とか「解釈」とか「形容」とか「経験」とかいった抽象度の高い単語もまた、固有の単語として具体的に存在していなければ、言葉同士の対応関係が成り立たなくなってしまう。つまり、「単語」とは、外在する事物との対応関係を示しながら、言葉の世界のなかでは固有の事物のように他の言葉と関係しているものだといえるかもしれない。ここから「意味」が生まれる。そのために、外在する事物との対応関係を持たない「単語」というのは、意味不明になる。

いま、誰かがいきなり「がっぴぶっぱっぱぼう」といったとする。がっぴぶっぱっぱぼう? なんだそれ、聞いたこともない言葉だ。つまり意味不明ってことだ。仮に、その人が目の前の猫を指差して「がっぴぶっぱっぱぼう」と言っていたとしたら、そうか、「がっぴぶっぱっぱぼう」とは「猫」のことだったんだと気がつくかも知れない。この場合、「がっぴぶっぱっぱぼう」という言葉の意味は「猫」だというふうに納得できる。でも、その人が無闇に「がっぴぶっぱっぱぼう」と発音しているだけで、その「がっぴぶっぱっぱぼう」がどこにも結びつかなかったら、「がっぴぶっぱっぱぼう」とは無意味な言葉である。
ところで、音楽というのは、この「がっぴぶっぱっぱぼう」みたいなものなのではないか、というのがレヴィ=ストロースの発想なのだと思う。ただしこの考えは、あくまで音楽を、言語とのアナロジーとして記号的に捉えた場合のみに妥当するのではないかと思う。音楽を記号的に捉えると、言葉には存在するはずの「単語」にあたる部分が見当たらない。だから音楽には「意味」がないということになる。でも本当にそういいきれるのだろうか。もう少し考えてみたい。
2. アルファベットとひらがな

上はアルファベットの26文字である。たとえば、ここから「c」と「a」と「t」を取り出して並べれば「cat」という「単語」となり、これは「猫」というものを意味する。つまり、文字の特定の組み合わせ(cat)が、外在する事物(猫)と対応関係を結ぶから「cat」は「猫」をあらわす記号であるというふうにいえる。ここで、記号を形作っている道具は、「アルファベット」と呼ばれる文字で、この26文字の組み合わせ方によって非常に多くの単語が存在しているので、辞書というのはとても分厚いわけだ。ここから生まれる単語や文法その他によって言語というものが成り立っているのだが、言語活動を行うのは人の意識であるといえる。たとえば、理論とか、ものを考えるといったことは、(英語圏の人たちにとっては)上の26文字をもとにして出来上がっている言葉によって行われるわけだ。
でも、いったいどうしてアルファベットって、25文字でも37文字でも45文字でもなく、26文字なんだ、といった疑問に対して、アルファベットが26文字として決まっている理由を理論的に説明することができるだろうか。そして、どうしてアルファベットの最初の文字が「a」というような形をしていて、つぎが「b」というような形をしているのか、誰か理論的に説明できるだろうか。たぶんそれを演繹的には説明できない。アルファベットが26文字で、こういった形の文字として現在通用しているのは、おそらく歴史的産物としかいいようのないものだからだ。このことは、アルファベットだけでなく、すべての言語についていえることだと思う。たとえばひらがな。

ひらがなは、漢字から出てきた日本の文字で、「あ」は「安」に由来するといったふうに、その出自はわかっている。しかし、その結果として「あ」という形がほかならぬ「あ」となったのはなぜかを問われれば、それはもう、歴史的な出来事が絡まって、いろいろな経緯が重なった上に、偶然、こうなっているとしかいえないものではないか。この、「いろいろな経緯」をひとつひとつ解きほぐしていけば、それはおそらく必然の集積のように捉えられるかも知れない、しかし、結果的にそれが、それ以外ではなく、ほかならぬ「あ」という文字になったのはなぜかと問われた場合、つまりそれらの必然がなぜああならずにこうなったのかを問われれば、そのことを完全に理論的に証明することはおそらく無理だと思う。なぜなら、「あ」という文字の成り立ちには、意味論的な体系の外部にあるところの歴史的出来事が関わっているからだ。文字の成り立ちは、単語や文法といった、意味を形成している体系の外部にある、固有の出来事性が関与している。

この二種類の文字はまったく違っていることは見ただけでわかる。それは、日本語と英語の違いからくることは当然だけど、両者の違いを帰納的に説明することはある程度可能でも、演繹的に説明するのは無理なんじゃないかと思う。たしかに、「cat」は「ねこ」と翻訳することが可能なために、双方の言語には意味論的には多くの共通性があるはずだ。しかし、アルファベットとひらがなといった文字を同じ天秤に乗せたうえで比較類推することは、ほとんど不可能なんじゃないか。これと似たような思いを、ぼくは音楽でよく感じるのである。
3. 一見、形象には「意味」がないように思える
たとえばバッハの「G線上のアリア」とコルトレーンの「ブルー・トレイン」を比べた場合、一方はバロック、もう一方はジャズと分類できる。そして、両者の違いを様々な観点から分析することも可能だ。旋律、和声、リズム、曲形式、楽器の種類や編成等々。しかしそれだけで十分だろうか。

いま、「G線上のアリア」のどこか4小節と、「ブルー・トレイン」のどこか4小節を取ってきて、その二つを簡素にメロディーライン化したものを聴いてみたとする。すると両者には、そのメロディー(旋律)が作りだす形象の違いというものが抜き差しがたくあって、この違いは把握できないものではまったくなく、聴けばはっきりとした違いであることがわかる。にも拘らず、それがどんなふうに違うのかを言葉で言おうとしたときに、それを表現する手立てがないというか、もどかしさを感じることになるのだ。そしてこの点こそが、バロックとジャズを分ける歴史の違いなのだと思う。というのも、こういう形象の違いが生まれるのは、記号的な体系の外部にあるところの歴史的な出来事性が関わっているはずだからだ。
あるひとつのメロディーには、和声やリズムなど様々な要素が絡んでいるから、ひとつの旋律を取り出してきて、それを和声的に、あるいはリズムとの関係から分析していくことは可能だ。でも、それだけでは、なぜひらがなの「あ」がほかならぬ「あ」となったのかを説明できないように、「バロック」といわれる音楽がなぜこんな特徴の形象を有しているのかということを説明できない。あるいは「ジャズ」との違いを形象の違いとして説明できない。だから、一見、形象には「意味」がないように思える。でも、たとえ言葉で言いあらわせなくても、その特徴や違いは聴けばわかる。聴けばわかるということは、その形象を、把握し、理解できているということなのだから、ここには「何か」があることは間違いない。この「何か」は心理的なものではなく、記号的な体系の外部にある出来事性と関係している。だから、この「何か」は具体的にあるのだが、それが言葉の外部にあるために、なんらかの事象を伴った「意味のようなもの」が、言葉とは別の位相で感受されることになるのではないか。そして、そこに音楽の「意味(のようなもの)」があるのではないだろうか。
4. 音楽が「わかる」ということ
レヴィ=ストロースは、音楽には単語にあたるものがないため、それは完全に無意味であり、作曲家の数だけ、あるいは作品の数だけの言語を音楽は有しており、それらの言語は相互に翻訳不可能であるといっている。
ところが、いま、ギター一本を持って、自分で曲を作ってみればわかる。「作品の数だけの言語を有している」どころの話じゃない。作曲したことのある人ならわかるんじゃないかと思うけど、相手にも通じる曲というものを考えた場合、音楽は何らかの既存の傾向のなかへと強く限定されていくことになるだろう。それはたとえば、フォーク、ロック、パンク、ミクスチュアー、RnB、ヒップホップなど、なんでもいい。仮に、そういったジャンルやスタイルを意識しないで曲を作ってみてもいい、必ず何か既存の音楽に似てきてしまうことは避けられないだろうから。音楽は無意味だから何でもありどころの話じゃない。文字言語とは別の領域における感覚的な部分を、非常に強く何らかの形式性によって規制しているのが音楽なのである。そのため、いままで一度も存在したことのないような、あらゆる側面で新しい音楽を作ることなど至難のわざだし、仮にそういう音楽があった場合、それを聴く人にとっては「意味不明」なものになるはずだ。そのために、トータル・セリエルなどの現代音楽はなかなか多くの人に理解されないから、やたら注釈というか、解説が長くなっていくのだろう。

しかし、ぼくの考えでは、どんな音楽も、大勢の人にその意味するところが伝わるようになれば、これまで「意味不明」だったものが「わかる」ようになっていく可能性はあると思っている。ここで「わかる」というのは、解説を読んで「言葉」で理解できるだけではダメで、その音楽を聴いて、その音楽が持っている「形象」を把握することが、なんらかの固有の事象に関連しており、それが、自分たちにとっても意味あることだと納得でき、理解できた場合のことである。平たくいえば、「言葉」のみならず「感覚」でもわかるということである。
5. 「センス(sense)」=「感覚/意味」
通常、ある音楽を聴いてすばらしいと感じたり、いいと思ったりするのは、その音楽を「言葉」ではなく「感覚」で捉えているからだろうと思う。ここで、「感覚」という言葉に2種類あることに注意したい。「フィーリング」と「センス」だ。「フィーリング(feeling)」は主に気分や感情に関わり、漠然とした感じをあらわすのに対して、「センス(sense)」は、「判断」「道理」「意味」などといったものを含んだ言葉である。「ナンセンス」というとき、それは「無意味」として使われる。つまり「センス」は「感覚」をあらわすと同時に、その「感覚」のどこかに意味や判断が含まれているということを示している。音楽を「センス」で聴くというとき、それは感覚的な、好みの問題だとされるのが普通だけれども、実際には、知らず知らずのうちにその音楽の意味を感じ取って自己判断しているという行為が含まれているはずなのだ。「センス(sense)」=「感覚/意味」とは、言語化しないまま感覚だけで意味を感じ取り判断するということなのである。

言葉には意味があるというとき、たとえば「ねこ」という単語はある動物の種類を意味しているというように、そこに明確な指示作用を見ることができるけれど、音楽を聴いて感覚で判断するという行為には、それをどのような仕方で判断しているのかという部分が言葉で明確に指示できないために、一見、単に好みの問題とかいうふうに、心理的なもののように捉えられがちだ。けれども、究極的にはこれは違うと思っている。たしかに、言葉で何かを理解するときにも、あやふやな判断とか錯誤とかいうものが付きまとうように、音楽を聴く際にも似たようなことはつきまとう。あるいは、たとえばある小説を読んで、それをどのように感じるかとか、そこから何を汲み取るかとかいったことは読者の自由であって、限定された意味付けなり、その小説がたったひとつの解釈しか許さないといった考えが不毛であるのと同じことが、音楽にもいえる。しかしそのことと、音楽は言葉で意味付けできないために完全に無意味であると捉えることは全然違う話であって、その点を混同してはいけないと思う。
重要なのは、好きな音楽とか、よく聴く音楽というのは、それを聴いている人たちの判断が必ず関わっているのであり、彼らはその音楽が有している「何か」に感応されているのだろうけど、その「何か」は言葉で意味付けできないからといって決して神秘的なものではなく、それを探っていけば必ず固有の出来事性に突き当たるはずである。それは、「あ」という文字の形がなぜほかならぬ「あ」になったのかということを、三角形の定理みたいに本質論的に説明することは無理でも、歴史的に考察することが可能であることと似ている。音楽が有している形象というものは、完全に解明できるかどうかは別としても、固有の事象とのかかわりから生まれてきているはずだというのがぼくの考えである。固有の事象のなかには、大きな歴史的意味を有しているものばかりでなく、取るに足りないものとか、些細な理由なども多く含まれて入るだろうけど。
6. まだ記憶にない形象

ブッソッティ『デビッド・テュードアのための五つの小品』(1959)
そして、音楽が有している形象が無意味ではなく固有の事象に関わっているからこそ、新しい音楽というのはそう簡単にできないものだし、多くの人たちにそういった「前衛的音楽」は「意味不明」なものとなってしまうわけだ。音楽批評家の小泉文夫氏は、ある共同体にはひとつのメロディーしか存在しない、あとはすべてそのバリエーションであるといったそうである。ここでは、このことを共同体論としてではなく、あるジャンルなり傾向なり、何らかの共通の特徴を有している音楽というものは、固有の事象、あるいは固有の出来事が関わっているものだと捉え直したい。
それが大勢の人々に受け入れられるということは、その音楽が言葉ではなく「センス(sense)」=「感覚/意味」として把握されるためだろうけど、そういったさまざまな音楽の特徴を把握し、分類し、さらに体系化するといった操作を、たぶん、文字言語とは別の記憶の領域によって、人は知らず知らずのうちに行っているのだろうと思う。そのために一方では、そういった音楽の存在というものが記憶のなかで強力な規制力にもなっていくのだし、新しい音楽(まだ記憶にない形象)というのを作ったり理解するということは簡単な作業ではないことになる。だから、音楽を自由に作曲しようとしても、記憶に非常に大きく制限されるわけで、何かのバリエーションになってしまうことが多いのだろう。
新しい音楽というのは、何も、難解なものや複雑なものばかりを指すのではない。かえって単純な、たとえば歌もので、たった4小節でもいい、それが過去のどんな音楽とも同じでなく、しかもバリエーションでさえないフレーズ(まだ記憶にない形象)を作るだけでも、それは大変な作業になるはずだ。単純だから簡単だというわけにもいかないのだ。というのも、まだ記憶にない形象を作りだすためには記憶ばかりには頼れないわけで、何らかの外部性がどうしても必要となってくるからだ。ドビュッシーは西洋の外部であるところのガムランを取り入れたし、シェーンベルクはそれまでの作曲方法の外部である十二音技法を採用したし、バルトークはアカデミズムの外部である民謡に向かい、ジョン・ケージはサイコロを転がすような方法で音楽を作ったり、音楽の外部である静寂に向かった。彼らは、音楽を新しく作り直すための方法を自覚的に模索してきた人たちだった。トータル・セリエルとなるとその音楽は非-意味的な形象(無意味ではなく)を有していると思う。さらに、かつてのブルースやレゲエといった音楽にしても、既存の何かの外部からあらわれてきた音楽であったことには違いない。これまでの「センス(sense)」=「感覚/意味」を変える音楽だった。

[補記] 2009年08月21-24日に書いた文章を、改題したものです。見出しと画像などを付けたほか、本文の訂正は最小限に留めました(いままでHPのほうに載せていた文章です)。
追記:ヘッダー画像を変更しました(2020年05月27日)。
サポートいただけたら大変ありがたいです!いただいたサポートは、音楽を続けていくための活動費に使わさせていただきます。
