
ヴォーカルについての覚え書き
ある観点から見ると、たぶん、音楽には2種類あるんじゃないかと思う。
それは、歌が入っているものと、入っていないものだ。
歌が入っている音楽
これはもう、巷で流れているほとんどの音楽が、そうなんじゃないかと思う。ポピュラー音楽の最も目立つ位置を占めているのが、これら歌入りの音楽だ。こういった音楽では、「曲」というものがほとんど「歌」と同義になっているかのようだ。歌が主体の音楽は、他にも、オペラとか、ヴォーカルの入ったジャズ、ブルース、シャンソン、等々、とても数多い。
歌が入っていない音楽
クラシックには、オペラなど歌のある音楽がある一方、交響曲とかピアノ曲、室内楽など、歌がないもののほうが主流であるような感がある。ジャズでも、モダン・ジャズ以降でヴォーカルのあるものは少ないんじゃないかと思う。ポピュラーでも、ロックやポップスの大半は歌があるものだろうけど、テクノなどには歌がないものが増えてくる。
歌のあるなしは音楽ということを考える上で、何らかの非常に大きな違いを示すものじゃないかと思う。歌の起源は詩の発生と共にあるという説があるし、それは、いったい「歌を歌う」ということは何なのかといった根源的な問題になっていくけれども、ここでは少し平たく考えてみたい。巷で流れている音楽の、一般的に「ヴォーカル」といわれているものについて、それがどのような要素から成り立っているのかを簡単に区分けしてみることで、音楽と歌との関係を整理してみたいと思う。

1. 歌・言葉・声
まず、ヴォーカルとは、大きくつぎの三つの要素に分けられるんじゃないかと思う。
1. 歌
2. 言葉
3. 声
1. 歌:「歌」はヴォーカルが有している音楽的な要素で、単純化するとそれはメロディー・ラインになる。もちろんそこには、弾むような旋律とか、朗々とした歌い方だとかいった、リズムや微妙なノリなども含まれてくる。さらに、ソロ(独唱)とコーラス(合唱)の違い、モノフォニー(単線律)とポリフォニー(複線律)など、音楽的な形態の違いもある。ここでは「歌」を、人が歌う代わりに、他の楽器で代用しても失われずに表れてくる要素であると捉えて、それを「ヴォーカル」が有している「歌」の部分と考えたい。
2. 言葉:何かを歌うという場合、それは通常「言葉」を使って歌うことになる。歌われる言葉の中身は「歌詞」と呼ばれる。歌詞が言葉から成り立っているということは、当たり前のようでいて、じつはなかなか難しい問題をはらんでいる。というのも、「音楽」と「言葉」は、必ずしも、うまく両立しない面があるんじゃないかと考えられるからで、この問題は大きいと思う。たとえばクラシックなどで、歌のない楽曲のことを「純粋音楽」と呼ぶことがある。歌がないということは、すなわち言葉がないということで、音楽にとって「言葉」というものは不純な要素だという考え方があるためなのだろう。「音楽を聴く」ことと「言葉を聞く」ことは別なのは確かなはずだけど、音楽の中に言葉(日本語とか英語などの音声)が入っているというのは、「音楽」というカテゴリーから見れば外部的な、不純な要素が紛れていると捉えることも確かにできるだろう。しかし一方で、音楽の成り立ちを人が歌うことにおく考え方も当然あるわけで、そこでは詩(歌詞)と歌(曲)の両方があってはじめて音楽が形作られると捉えられるだろう。この考え方だと、交響曲などの(歌のない)大規模な音楽もその起源は「歌」に辿りつくということになりそうだ。音楽の起源が歌なのかどうかは簡単に結論付けられない問題なのかもしれない。
3. 声:ヴォーカルのある音楽というのは、人の声が聴こえてくる音楽のことでもある。音楽から声が聴こえてくるかどうかというのは、その音楽を把握する上でかなり大きな印象の違いになってくると思う。声が聴こえるということは、誰かがそこに立って歌っているという、人がいることの存在をあからさまに浮き立たせる。楽器演奏にしても、それは誰かが演奏しているに違いないだろうけど、でも、ヘッドホンなどで音楽を聴く場合、誰かが目の前で演奏している姿は見えないわけで、弦なり鍵盤なりを擦ったり叩いたりして鳴らされる音から人の存在を感じ取るのにはある種の想像力がいる。対して、声というのは、誰かの身体から直接発せられるから、固有の肉体がそこにあることを喚起する。仮に言葉がなくても、「あーー」と叫んだり、唸ったりしただけの声であっても、それは誰かの声であるのだから、それだけで人の存在を強烈にアピールすることだってできる。「そこに誰かがいる」ということを喚起させるのが、声の持つ大きな特色なのだと思う。
以上が、ヴォーカルというものを成り立たせている大きな3つの要素だと思う。
2. ヴォーカリストの存在
通常、ヒット曲では、ひとりのヴォーカリストが舞台のまん中に立って歌うことが多い。主役はヴォーカリストなので、大半の楽曲ではヴォーカルがスピーカーの中心から、一番はっきり聴こえる位置に来るようにミキシングされている。つまり、楽器との関係の中でヴォーカルは中心にある。そして、多くのヒット曲は「ソロ」、つまり「ひとり」のヴォーカリストが主人公である。コーラス・グループやデュエットなどといったものもあるけれど、これらは、クラスやバイト先での仲間同士とか、仲のいい女の子二人組、男同士のなかに女の子がひとりだけいる三人組――などというような日常での人間関係に対応している。特にアイドル系グループは、そういった意図がかなり見えたりするけど。こういったことは、ヴォーカリストのパーソナリティや、パフォーマンス、カリスマ性などといったことにも関わってくることで、一般に音楽の話題というのは、音楽そのものに対する興味よりも、シンガーのキャラクターやアイドル度といったものに対する関心のほうが高いのかもしれない。
3. 曲の紹介
ここでは、先に述べた「歌・言葉・声」の観点から聴いてみて、興味深い曲をいくつか紹介します。
●『環礁』武満徹

武満徹の初期作品(1962年)で、5曲からなっている。編成はソプラノとオーケストラ、2曲目と4曲目にソプラノの独唱が入る。持っているCDでは全5曲のトータル・タイムは16分32秒。複雑なものが凝縮されている感じがする。全体的な曲の印象は、張り詰めた感じ。原初的なもの。まだ生まれて間もないもの。それは、新しいやり方が実践された初期のプリミティブな音楽。
『武満徹の音楽(ピーター・バード著/音楽之友社)』によれば、オーケストラは6つのグループの「層」に分かれ、金管楽器は「点描画」のような雰囲気を出し、木管楽器は「可動(モビール)」のパッセージを繰り返すと書かれている。実際に聴いた感じでは、非常に細かい動きの旋律、マイクロ・ポリフォニー的な要素と、張り詰めた緊張感のある持続音のなか、唐突に強く流動する旋律が混合しあう。
さて、歌は、大岡信の詩を、ソプラノ歌手が単独で歌う。無調的な旋律。2曲目、繁茂する音色が織り成す複数の層が鳴り響いていた音群のなかから、孤高の声が立ち上がってくる感じ。この歌い方が、最初聴いたとき、ちょっと驚いた。シェーンベルクが『月に憑かれたピエロ』で用いた「シュプレヒシュティンメ」という、話すような歌唱法を思わせる。シュプレヒシュティンメとは、音階(つまりメロディー)を用いながらも、その音階を持続せずに巧みに音を上げ下げして、歌いつつ話しているように発声するやり方。そのために、歌うと同時に、声というものが強調されることになる。『環礁』で非常に印象的なのは、歌手が「皮膚となり」と叫ぶ箇所。これは、メロディーの流れに裂け目が入って、あたかもゴチック体で強調された[皮膚となり]という言葉がそこから唐突に表れ出たかのような感触がある。
2曲目最後の言葉は「太陽」「空にはりつけられた」「球根」と羅列される。3曲目では、太陽に照りつけられた眩い地平の上を幾多の帰化植物が繁茂するような旋律が、無数の音を小刻みに震わせながら、曲線状の流れの中で数多の生命が活動しているかのような息吹きを感じさせる。5曲目のエンディングでは、緊張した戦慄が張り詰めるように急激に高まっていき、破砕したあと、緊張の持続とやわらいだ感触がしばらく続く。
●『マーダー・ミステリー』ヴェルヴェット・アンダーグラウンド
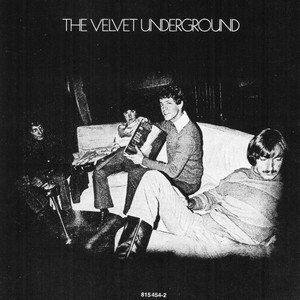
ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのサード・アルバム(1968年)に入っている楽曲で、ヴォーカルに関して実験的なことをしている。トータル・タイムは8分53秒で、ロックとしては長い。この曲には、2つの別々の歌詞がある。歌詞Aはステレオの左側から、歌詞Bは右側から聴こえてくる。内容は非常に難解な現代詩風のもので、分量も相当にある。楽器群はステレオのほぼ中央から鳴らされる。
曲の構成は、ナレーションの部分と、歌の部分が交互に繰り返されていく。ナレーションは、ステレオの右と左で、男性の声(ルー・リード)が同時に別々の詩を読みあげていく。朗読なので、メロディーはない。しかしリズムは拍子に合わさっている。右側の声が4ビート、左側は16ビートで語っているように聴こえる。歌の部分に入ると片側に女性の声が混ざり、男性と女性の二人の掛け合いとなる。朗読と歌の反復が淡々と繰り返されていき、エンディングで曲の展開が急に変わる。ミニマルなピアノ伴奏に乗って、3、4拍目ごとにリズミカルに声が発せられる。2つの声が、やはり別々の言葉を同時に発している。そこに、不協和なピアノがかぶさり、フェード・アウトされる。
ヴェルヴェット・アンダーグラウンドには、この曲の他に、ルー・リード自作の短編小説をそのまま音楽に乗せて読み上げた『ザ・ギフト』などの実験もある。音楽的にも、ジョン・ケイルのエレキ・ヴィオラが延々鳴り続ける『ヨーロピアン・ソン』など実験的なものがあって、興味がつきない。とにかく彼らのラディカリズムは強烈なので、それだけに、曲や、歌詞の内容も相当に過激なものが多い。
●『アヴァンチュール』リゲティ

現代音楽のジェルジ・リゲティ、1962年の作品。3人の歌手と7つの楽器のための曲。輸入盤のCDを持っているだけで、手許に資料がないので感想だけになるけど、これは曲というよりオペラ(劇)の録音盤を模倣しているかのようだ。というのも、歌手たちは歌うのではなく、俳優のように台詞をしゃべっている。ところが、その声には言葉が含まれていない。言葉がなく、声だけが、さまざまなシチュエーションを作り上げているのだ。その声を、すごくアバウトに表記してみると、
あーーーぃえいーー、むぃや、あーっ、きゃっきゃきゃっ、ががが、あぃぇーーーー
あっぱたちょーーーっいち、ぶっーーるるる、ほへほっほ、えーいっち、ほーいっち
へおーー、おーー、しぇーおぃわーーー
なんか、こんな感じでしゃべり合っているように聴こえる。あたかも俳優が演技しているかのような声なのだが、そのセリフには言葉がついていないのだ。しかしそれらの声は、驚いたり、あわてたり、状況が急展開したりして、コミュニケーションによるさまざまな感情の変化や、シチュエーションの展開が伝わってくる。それは劇でありながら、どこかで音楽的な展開をしているように感じられる。とくに、トータル・セリエルでつくられた音楽との相似性があるのではないかとの気がしてくる。というのも、セリー音楽では、単一のリズム(4/4拍子など)が曲全体を規定せず、さらに和音や旋律、音の大きさも予測できないような唐突さが含まれてくるので、曲の濃度は激しい落差のなかで動くようになる。カオスティックな流れはセリー音楽の大きな特徴だと思うけど、『アヴァンチュール』の演劇的要素(声と語り)は、これに似ている。しかし声には言葉が含まれていない。劇の内容は非-意味的なものなのだが、それはセリー音楽に似ているのだ。
●『U.F.Orb』ジ・オーブ
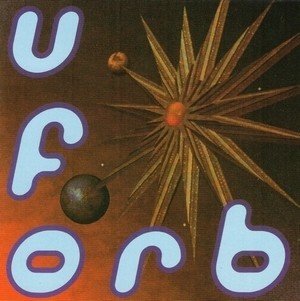
ジ・オーブの『U.F.Orb』は1992年に出た彼らのアルバムで、このアルバムでは、サンプリングされた様々な声を聴くことができる。そもそも、一口に声といっても、ひとりの人間が発する声の中には、ささやき声、つぶやき声、しゃべり声、唸り声、叫び声、笑い声、泣き声、等々といった様々な声がある。さらに声には、男性・女性、大人・子供、語り(モノローグ)と会話(ダイアローグ)、集団で騒いだりしている声、ナレーションや朗読から言葉遊び、ギャグ、擬音、(英語や中国語などの)言語による違い、訛りや方言や地語など、さらに動物の鳴き声に至るまで、無数にあるはずだ。そういった無数の声から幾種類かをサンプリングすることによって、声によるポリフォニーを精緻につくりだすことが可能になっていることを実感させるアルバム。もう少し聴き込んでみないといけないけど。
●『シンフォニア』べリオ

現代音楽のルチアーノ・べリオ、1968-69年の作品。『シンフォニア』は5部からなる楽曲で、ライナーノーツによると、その3楽章目は様々な引用から成り立っている。バッハ、マーラー、シェーンベルク、ヒンデミットその他大勢の音楽家の楽曲の断片が多数引用されることで曲がつくられている。そのためかどうか、曲の感じは機能的(コーダル)というよりも、様相的(モーダル)に流れていくような印象がある。つまり、引用されている旋律は確定できるからその部分は機能的(一種のコード)だといえるけれど、そういった断片がただ単に引用されているだけでなくて、複数が絡み合いつつ変奏もされていくことから、その表れ方は可能態のような変化を伴ってくるのだろうと思える。可能態は様相として表れてくる。
この曲では、複数の引用された歌詞、言葉、歌、声などが、他の楽器と混じり合って聴こえてくるために、全体の輪郭がはっきりしないし、言葉もよく聞き取れない。ヴォーカルと楽器が混在していて、さらに複数の声、たとえば歌と語りなどが混在している。スピーカーで音量を下げて聴くと、確かにもやもやして曲の細部が聴き取りにくい感じがする。
(了)

[補記] 2009年11月13-14日に書いた文章をもとに、修正したものです。10年以上前の、CDメインで聴いていた頃。あと、「ヴォーカル」の表記、「ボーカル」にせず「ヴ」のままにしています。(2020年05月26日)
サポートいただけたら大変ありがたいです!いただいたサポートは、音楽を続けていくための活動費に使わさせていただきます。
