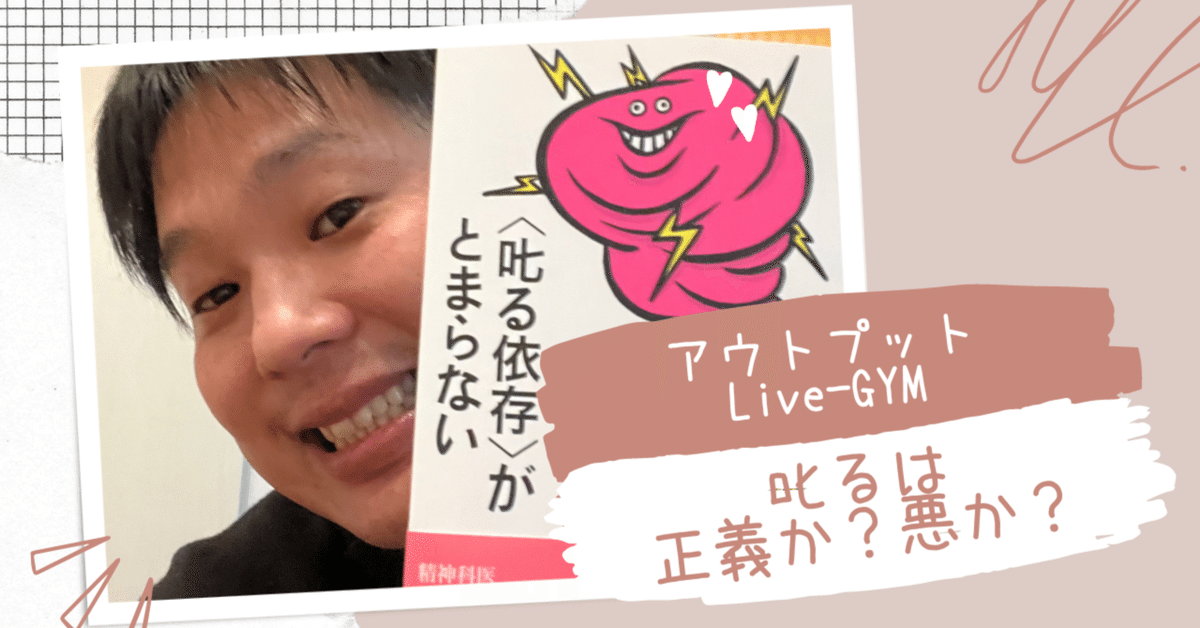
『叱る』は正義か?悪か?(叱る依存が止まらない)
「叱ることのメリットは何ですか?」
こんな質問をされたら僕は何と答えるだろう。
僕なら「どんな人でも相手の行動を変えることができる」と答えると思う。
僕はあまり「叱る」のが好きじゃない。
できれば、叱りたくない。だからよく言われてきた。
「君は甘い。だから、舐められる」
さらに「君は嫌われたくないだけだろ?情けない」と僕を叱ってくる。
確かに僕は嫌われたくない。
だが、そんなに単純ではなく、僕が叱りたくない理由は2つ。
まずひとつ目は、叱るメリットとしてあげた「どんな人でも」という表現に『指導力のない人でも』という意図が隠れていることにある。だから、『叱る』=『指導力がない証拠』と思っているからだ。叱らないにプライドを持っている。
もうひとつは『嫌われる』は効率が悪いと考えているからだ。僕は、嫌いな人の指示はイヤイヤやるし、指示がなければそれ以上のことをしてあげようと思わない。なぜなら僕はそいつが嫌いだからだ。僕が求めているのは『人が生み出す価値』であり『無機質な作業』ではない。あくまで能動的に動いて欲しいからだ。
しかしながら悔しいことに、当の本人は「怒られなくてラッキー」と思っている人が多く、大した仕事もしない人が多い。こんなジレンマと戦っている人は多いのではないでしょうか?
さて、そんなジレンマを抱えながら僕の友人がオススメしてくれた本を読んでみた。
「叱る依存が止まらない」 村中直人(著)
【勧めてくれた友人】
ハンドルネーム:みっきー
役者や声優などの仕事もしていた彼女の声の破壊力はヤバい。1度聞いて欲しいな↓
学びのアウトプットLive-GYM #1.
【叱る依存が止まらない】
この本で学んだこと…それは『叱る』ことの無意味さである。『叱る』という行為は何の意味も持たないということなのだ。
それを説明していくには、まず、『なぜ、叱ってしまうのか?』から考える必要がある。
なぜ、人は叱るのか?それは、
人は『叱る』を過大評価してしまっていることだ。
・「最近は、きちんと叱れない人が増えて問題だ」
・「叱ると怒るの区別がついていない人は、困ったものだ」
・「真剣に叱ることが大切なのに、甘やかしてしつけを放棄する人がいる」
よく聞くワードですね。もはや叱れる自分を神格化しているようにも聞こえる。でも、確かに一理あるとも共感してしまう。僕も実際、過去に叱れない自分にコンプレックスを持ったこともある。「俺もあの人のように怒れたらなぁ」と。
でも、この本で書かれているように、本当に考えなくてはならないことは『世間では叱ることが正しい』を前提に話が進んでいるということだ。もし、叱ることに意味がないのなら世間の常識は覆り、『叱るの過大評価』となる。
『叱る』と『怒る』の違い
『叱る』と『怒る』の違い。僕のイメージとして
『叱る』は相手を思って強く言う。
『怒る』は感情のまま強く言う。
と、なんとなくではあるがそんな認識。
みなさんはどんな認識ですか?
だから、『怒る』はダメで『叱る』は素晴らしいというイメージを持っている。果たしてどうだろうか?それではイメージではなく辞書で引いてみましょう。
叱る:目下の者の言動のよくない点などを指摘して、強くとがめる。
ん?とがめる??
とがめる:過ちや罪・欠点などを取り上げて責める。非難する。
うお~い!「責める」「非難する」。辞書によっては「なじる」。結構、キツくないか?というか『怒る』と何が違うの?と思ってしまう。そう…どちらも同じ『攻撃』であり、「あるべき姿」に変えるため相手に恐怖とストレスを与えるという目的は一緒だということ。
ちなみに「部下が上司を叱る」「子が親を叱る」って聞かないですよね。そう。逆の場合は「キレる」「怒り」「不満をぶつける」という違う表現となる。だから叱るということは権力の行使した攻撃によるコントロールになるわけで、受ける側からしたら『相手の感情が乗ってる、乗ってない』など知ったこっちゃないことになる。だから、叱ることの技術など意味を持たない。
更に厄介なことに、脳科学的に分析したところ、叱るときには『ドーパミン』が発生するらしい。要は「気持ちいい」ということだ。流行りにうとい僕ですら真っ先にあの曲を思い出した。
大人の俺が言っちゃいけない事言うけど説教するってぶっちゃけ快楽
はい。この歌詞、脳科学的にも証明されておりました。
何が言いたいか?ドーパミンの発生ということは依存性があるということ。
更に最悪なことがあるらしい。
それは、叱られても人間は、何の「学び」にもならないらしい。
本来「あるべき姿」になって欲しくて叱っているのに、相手はあなたの攻撃回避方法しか考えなくなる。そう、相手からするとあなたの思い描く像など、既にどうでもよい。いかに怒られないか?が目的となるため「嘘を付く」という手段が最も効率がいい。
いませんか?嘘をついたり隠したりする部下が。
これって完全に冒頭にした会話ですよね?何をしたか?ではなく、「怒られなくてよかったラッキー」になる。そうなんです…歪んでいたのは、いままで叱られ続けてきた環境だということ。
「何を叱るか?」は常に「叱る側」が決めることができ、相手を思い通りにコントロールするために攻撃を行う。こんな環境下で人は主体的に動ける人になれるだろうか?『なれない』と考える方が自然だろう。
だからDVがこの世界で成立する。叱る側はドーパミンで快楽となり依存し、叱られる側は主体性を失い、相手の正解を探しながら耐え続けていると、たまに貰える「甘い言葉」の報酬に依存する。
あなたが求めていた「若者のあるべき姿」は奴隷ですか?
「いまどきのヤツはぁダメだ」とよく言うが、「昔の人間は人間以下だった」言われても仕方がないかもしれない。
これで解決しました。叱ることの意味の無さは。しかし、肝心なところの「叱らずにどうしたらいい?」が解決してませんね。
と言うことで、ここまでが本の要約。(と言いながら勝手な解釈も入っていましたのでお気をつけを!)
さて、ここからは「どうしたらいい?」の太陽流も交えて書いていこうと思います。
『叱る』は正義か?悪か?
このテーマを考えるとき、やはり天秤にかけてしまいますよね。どちらが効率的か?
目的は「相手にミッションを遂行して欲しい」だけで、正直なところ、ちゃんとやってくれるならプロセスはどうでもいい。
でもさ、正直今まで何度も相手を許してやってきたと思ってる。唇を噛み締め我慢して…そこにきて「叱ってはダメ」だと?「ふざけるな!俺の気持ちも知らないくせに」って著者を叱ってやりたい気持ちでいっぱいだ。
「これ以上、俺に我慢しろと?絶対にアイツは1度、痛い目に合わないと治らない!」今こそ正義の鉄槌を!
さて、著者のアンサーはとしては、
「コイツは1度、痛い目に合わないと治らない」「苦しまなければ人は変わらない・成長しない」というのは都市伝説であると。
これを素朴理論というらしい。
実感と知識の差。例えば「地球は丸い」なんて言われても知識はあるけど、どう考えても平面に立ってる気しかしないよね。何もないところから生き物なんて生まれてくるわけないのに「えっ!このハエ!突然発生したぞ!?」って思っちゃうよね。だから、あなたの思い込みと実際は違うのだと。実感と知識には差があるのだと。
そう。この本に書いてあることは確かに事実で「苦痛が人を良い方に変える」なんてことは無い。実際、怒り倒して相手が改心した人を見たことある?うん…確かにねーや。
変わるのは、その場の行動とあなたに対しての行動のみ。その場しのぎの業務、無視、反発、嘘、逃走、復讐など、しっかり残念な方向へと進む。
叱って良いことは無い。ただ、僕たちの1番のジレンマは『相手が大人』だと言うこと。発展途上の子供の教育なら納得ができる。ただし、相手は社会人。いつまで付き合わなあかんねん?!
はい。正解です。
僕は『いつまでも付き合う必要はない』と言い切ってます。社会人教育を専門としている僕は、よく相談されるんです。「こんな問題児がいるのですが、どうしたら改心してくれますか?」って。僕は返します。「無理だよ」と。「その従業員が変わるには長期的な指導とかなりの労力が必要となる。だから、その情熱と労力は他の従業員に注いであげてくれ」とハッキリ伝えますね。
僕が無理だと言っている理由は『人は変わらない』と言いたいのではない。『業務時間が限られ、他にもしなければならない仕事がたくさんあり、とてもじゃないが時間が足りないから無理』ということです。だからこの本はちゃんと切り離して考えて読まなくてはならないと思ってます。
・叱るのは無意味
・成長を促すには叱ってはならない
・変えたい人へのアプローチ方法
この3つは子育てや信頼できる仲間の成長のための教訓となるが、変える必要のない人のための教訓ではない。会社は学校じゃなく仕事をする場所。切り離して考えないと真面目な人ほど振り回される。もしかすると、叱るった方が「相手の転職のきっかけを作ってあげている」と思えば正義なのかもしれない。
そう。ここで僕の言う『変える必要のない人』とは環境が合ってない人を指している。分かりやすく言えば『体格と体力を活かしたいのに事務職』『人と話すのがキライなのに接客業』など、そもそも採用エラーであり、改心より転職だろ?
人が変わるきっかけは苦痛ではなく環境。
たから、変えるべきは環境です。
環境はどのように変えるか?
あなたから半径5メートルから変えていく。
あなたに近い人から。
遠い人を変えるのは次でいい。
ポイントは「あの人が叱られないのはズルい」「やっている私達が馬鹿らしい」という発言に注意すること。これを言う人は環境が合ってない予備軍。一見正しいことを言っているように見せかけた共犯者と思ってくれてもいい。
その人たちに共通して言えることは、この組織が何をする組織なのかを理解していないこと。『みんなと同じことをしたらお金が貰える』組織だと勘違いしている。
さぁ、ここで今一度思い出しましょう。
『叱る』が『悪』だということを。
『叱る』は意味のないことだと。
まずは、あなた自身が『この組織は何をする組織なのか?』を理解しましょう。あなたが考える『あるべき姿』ではなく組織の『あるべき姿』。
少し酷なことを言いますが、相手は「あなたになりたい」とは思ってません。仕事して金が欲しいとしか思ってません。だからこの組織の『仕事』についての評価をしなければ相手は納得しませんし、叱れば相手はさらに考えの押し付けと判断し拒絶します。
そして『前さばき』『後さばき』が大切です。
前さばきとは、事前に予測して先に注意点を伝えること。後さばきとは経験させたあとに振り返り、反省点と注意点を考えさせること。
あなたも相手も共に予測力を高めることが大切。
また、「できない」のか「やらない」のか?これを判断する必要があります。気をつけて欲しいのは「できる?」「分かってる?」と聞くと
「はい」としか返ってこない確率が非常に高いです。
これが「できない」のか「やらない」のか分からない原因です。あなたは「やらない」と判断してしまい、注意→叱る→怒るに発展していく。
この本に載っていた目から鱗がこれ。
今の時代、子供が自転車に乗れるようになるスピードが劇的に早くなったそうです。
なんの変化か分かりますか?
前さばきが劇的に変わったんです。
みなさんは昔、自転車に乗れるまで何を乗ってました?そして、今どきは何に乗ってますか?
補助輪自転車から→キッズバイクへ
自転車に乗るための練習で1番大事なモノは?
漕ぎ方ではない。バランスの取り方である。
補助輪自転車に乗って学べるモノは?
漕ぎ方、スピード感、ブレーキ
キッズバイクで学べるモノ
バランスの取り方
昔はコケるを繰り返して覚えた。
今は安全に「できる」を繰り返し覚えた。
結果、後者が劇的に早く習得できるようになった。
「苦しさ」「昔のやり方」より良い方法があるのかも知れない。まずは疑似体験の中で相手に注意点を考えさせながら修正し、経験させ「できない」「やらない」を判断した後、環境が合っているか?を判断していくことをオススメします。
僕も我が子をたくさん叱ってきました。
部下もたくさん叱ってきました。
もちろんその100倍叱られて育ちました。
『そこには愛がある』論争はありますが、叱ってきたことで、良かったことなどありません。
どこまでいっても、子供や部下は自らの失敗体験から学んできたと思ってます。
自ら選んだことの結果と反省
危険なことをさせる必要はありません。
危険すぎるなら先に止める。
注意点を考えさせ結果をフィードバックしたらいい。
もちろん。私たち大人も同じこと。
新しい手段や方法は、ベンチャー企業の事例がたくさんあります。この世界は学びに溢れている。
叱らず学んでみませんか?
それでは次のアウトプットLive-GYMで。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
