
【成果の出る組織づくり①】〜個人からありたい姿を紡ぐ〜
このnoteは、正解を書くつもりはなく私が経験したことを抽象化させメモをした。
top-downというやり方が難しくなってきた今日、どうしたら一人ひとりを大事にしつつ、同じベクトルを向いて組織を作ることができるのだろうか。今年一年大事にしてきたことを備忘録を含めて記載してみた。
0.私が考える組織づくりの前提
大前提、ダニエルキムの関係の質のフレームを大事にして組織作りを行なってきた。

主に、関係の質を中心にまとめている。
先にアジェンダを概念図でまとめたので添付します。

図の番号の順番に、記していく。
それでは①のメンバー個人のことを知るから。
1.まずメンバー個人のことを知る
まずは所属する、組織のメンバー1人ひとりの特徴をしる。丁寧に。パフォーマンスではなく、心から興味を持つ。人とは面白い。色々な人生があるからだ。否定せずにまずは知ること。おすすめはストレングスファインダーとライフラインチャート。

そのメンバーの人生(過去)について知ることで、色々な気づきがある。別に人生のdetailではなく、起こった事象に対する考え方と嬉しいとき/悲しいときを知ることが狙いです。
この人の思考や考え方というのは、25歳くらいを過ぎるとそんなに変わらない。(良くも悪くも)起こる事象に対する解釈の仕方や、意思決定の思考回路の根幹をなすと思っている。
だからまずは、メンバーの過去からその人について知ることが大事である。
これを疎かにすると、少しづつ心の距離が生まれてする。
手なりの未来ではなく、主体的に「共に」未来を作るために一人一人、①現在→②過去→そして③未来をみつめる。

2.みんなに自己開示する
リーダーがまずは自分の考えや過去のことなどを自己開示することが起点となる。その時に重要なのはドヤ、という過去の成功体験ではなく、主に失敗体験の開示です。

そしてその壁から何を感じ、どう乗り越えてきたのか。その時のポイントは何で、その経験が〇〇を感じだから、今の自分が出来ている。そのようなストーリーが、自分自身のことを知るきっかけとなり、
結果、
心の距離が縮まる。
実際、
私の尊敬する元上司はこのようなやり方で、私の心が初日で解けたのを明確に覚えている。「自己開示」がメンバーの心に共感の接点を作り、相互理解がはじまっていく。自分自身も過去の経験から、今の自分(考え方など)は形作られているのは、万事共通です。
原則、物事には因果関係ある。現在は過去の積み重ね、だし未来は現在からの積み重ね。
これから記載する、ありたい姿も現在から未来にあるゴール(flag)である。
3.時間をかけての1on1の実施
互いの理解を1.2ヶ月かけて、実施していく。そして、懐疑的な関係から、信頼関係へと進化させる。ある程度仕事だけではなく、プライベートについても話せるようになったならば、「組織のありたい姿」について話すことに挑戦する。相互の理解ができるまでは、毎週30分の時間は確保した方がいい。(と感じている)私は、15名のメンバーがいようと毎週雑談を含めて個別の1on1の時間を創出した。優先度をあげてでも、
その人のことを知りたいと思った。
リーダーはそのようにおもえるかどうか。
スタンスの話かもしれないが、素養としては必要な要素な気がする。悩ましいなと思ったのは、今の時代「個人のありたい姿」を聞いてもわからない人が多い。当然だと思う。コロナなんて誰も想像できなかったし、VUCA時代と言われる中、明確なありたい姿を持っている人の方が稀有である。だから相互の理解が進んだら(この人の仕事、私事、志事を網羅的に語れる状態。志事はなければ、興味の方向性を知るということまで)まずは互いが所属している「組織のこと」について探求をする。
少し余談だが、探求と議論は違う。議論はcriticalな意見も含めてissueに対して答えを出す。しかし、探求は否定はしない。どちらかと言うと共通項を紡ぐ作業だ。なので一見非効率な時間もある。しかし、それさえも貴重な意見、factだと捉えて、紡いでいく。
一人一人と組織のありたい姿について意見交換を行い、ビジョンシェアではなく、シェアドビジョンを大事にプロセスを歩む。
シェアドビジョンとは、top-downの意思決定ではなく、現場の一人一人の想いを大事にしながらbottom upのイメージで進めていく考え方。
マネジメントの要諦として肝どころ、その 組織の共通言語を紡ぐことだと思います。
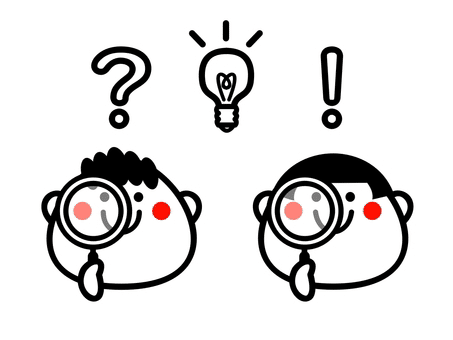
4.みんなで組織の未来を探求をする
ここまで歩むと、今度はみんなで組織のありたい姿を探求するフェーズに入る。個人から組織へ移行するときです。私はこの問いが肝要ではないか?と思う。
我々の強みは何か。
そして、我々は何屋さんなのか?
自分にとって、この船は何屋さんなのか?
この問いの意図しているのは、業界や職種の、当たり前の正解探しではない。意味づけをいかにできるか?である。この意味づけから付加価値が生まれると考えている。
この組織のありたい姿は何か。
を探求するのだ。これが組織の「WHY」となり、目的意識とベクトルが明確化する。明文化するときは、「〇〇な状態」という言葉を使う、状態目標を意識すると良い。
これができると、その状態のために何ができるのか?というGAP=課題が浮き上がってきて、何をすべきなのか?を一人一人が考え始める。
これも余談だが、問題 と 課題 は違う。
問題は、ありたい姿と現状のギャップだ。課題はその問題の中から優先度高く取り組む事柄のことであり、期限もある。設定した課題を乗り越えると、みんなで設定をしたありたい姿に近づく、ということがポイントでありしっかりとした見極めが必要だ。

メンバーのスキル、現状、顧客構成などを考えるという前提が見極めの前提ではないか。
tipsだが、内向きなありたい姿、よりも基本的に変革する対象(たとえばCLやMKTを主語にする)を意識すべきだ。社内軸にフォーカスすると、サークルのようなわいわいがやがや系のありたい姿ができてしまうからだ。関係の質を構築することが目的なのであれば、それも良いがWHYが内向きになってしまうのでエネルギーが外に向かない可能性がある。

5.顧客への現状把握と提供価値は何か
基本的に、組織とはsustainableを意識しないといけないので、売上を作らないといけない。私は売上とは顧客からの期待だと思っている。相互理解をはじめ、ありたい姿を決めた我々は、顧客への提供価値を考える必要がある。
顧客を分解し、セグメント化した後にそのセグメントごとの現状(何が問題なのか?)とその解決策として我々ができること、を議論する。ここは探求ではなく議論(discussion)をする。criticalな意見も含めて、我々は何ができるのか?を考え抜く。それがテーマになるのだ。そのテーマができると、戦略を考える起点となる。
提供価値を考えるときに重要なのはセグメント化するときの定義ではないかと考えている。セグメンテーションが筋が悪いと、提供価値がずれてしまう。売上規模など割と定量観点から切ることがよい。
ここに関しても、全員で議論するのだがある程度の方向性を持った方が良く、組織の中核メンバーで先んじて打ち合わせをしてベクトルを持つ方がいいなと感じた。
そして、前提と総論を敷いた上で各論の議論をする。

6.戦略の構築とプレゼンテーション
個人の理解、自己開示、組織のありたい姿、顧客への提供価値、が明確化してくると「道標であり、どう戦うのか?というシナリオ=戦略」を立てる必要がある。
戦略推進のためのテーマでそれぞれ期限を切り売上(例えば)目標の達成のための枠組み作りをはじめる。みんなが同じ戦い方をするベースとなる戦略と顧客ごとで変える個別戦略。それが筆頭であり、そのためのスキルセットandマインドセットをつけるための人事戦略。特に推進のためにはスキルセットがドライバーとなる可能性が高い?(まだ勉強中)のではないか。
戦略の全体像が見えると、1,から5.を含めて、関わるメンバーにプレゼンテーションをする。プレゼンテーションとは、プレゼントでありみんなへのメッセージ。ここに納得ができると大きく船が動いていくと思う。
A:みんなで紡いできたプロセス。
B:そして大胆なビジョンと細かな戦略。
C:共通言語となる営業推進のためのフレーム。
以上、組織つくりの一つの型としてメモした。
最後に、推進のためには仕組みが必要である。まずやってみる、という人ばかりの組織はチェックとリプランが必要だし、考えてから動く、という人ばかりの組織は、一緒に動く(やって見せ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば人は動かぬ)ということもoptionの一つである。推進と組織つくりは、偏ってはいけない。私の次の課題は、疲弊しない組織×圧倒的な推進力を持つ組織作り。この図のPMの状態をいかに作れるか?である。

成果にこだわり続ける=Pmだと疲弊したり離職リスクがでてくる。一方集団維持によりすぎる=pMとなあなあな組織になる。これを解決するのは、まず仕立て(メンバー理解×思い切った戦略と些細な計画。)
やはり、組織とは関わる人をどれだけ大事にできるかと、ありたい姿を紡げるのか、重要である。組織とはどこまで拡大してもN1の集合体であることは忘れてはいけないな、と今年思いました。
最後に、なぜこのような時間をかけた生成的なプロセスを歩むのか?
この質問をメンバーからもらった。
たしかに、top-downの組織作りの方が早いし楽なのかもしれない。しかし私自身軍隊式なマネジメントを受けたことがあるのと、仕事とスポーツは共通することがあるという前提にたっているが、今の強いスポーツチームは総じて「主体性を引き出す」マネジメントが取り入れられている。そして成果もでている(気がする。論文とかは知らないが。。大学院でもそう習った。)
一人ひとりの強みは何か?にフォーカスし、多少時間がかかっても、1人1人のWHYに迫ることで、自己が所属する組織に対して、自己のwhyの解決策(手段)としての帰属意識が増す。(と思っている)
その総和が、組織力として大きな推進力になるのではないか?
そのような仮説を持ち日々仕事をしている。
私自身が、一人一人を大事にするという考えはこれから先も大事にしていきたい。
組織つくり、面白い。
来年はより推進をして、圧倒的な成果出し、先輩との約束を必ず実現します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
