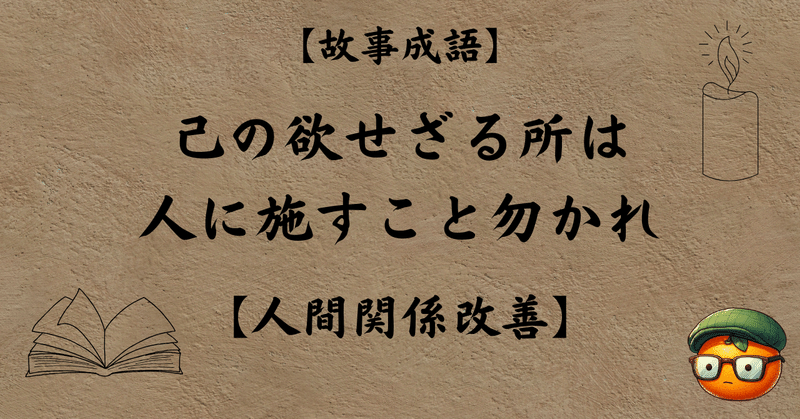
【故事成語】第1回 己の欲せざる所は人に施すこと勿かれ【人間関係改善】
今回取り上げるのは「己の欲せざる所は人に施すこと勿かれ」です。人間関係に関する故事成語で、本稿が人間関係改善のヒントになれば幸いです。
1.意味、出典
【原文※】
己所不欲、勿施於人
【書き下し文】
己の欲せざる所は人に施すこと勿かれ
【意味】
自分がしてほしくないことは、他の人にもしてはいけない
※原文は、故事成語の部分を抜粋したもの。
意味は非常に分かりやすく、多くの人が親や先生などに言われたことがあるかもしれません。小学校の道徳の授業でも教えてそうな内容ですね。
この故事成語は、当たり前のことを言っているのですが、実はそれを実行に移すのは案外難しく、出典の『論語』の別の場面において、子貢という孔子の弟子が、「私は自分がされたくないことは他人にしないようにしたいです」と抱負を語ったのに対して、孔子は「お前にできることではない」と言っていていることからも分かります。
私たちは、特に意識をしないでも人のしてほしくないことはしないようにしていると思います。しかし、実は気付かぬところで人がしてほしくないことをしていることもあるかもしれません。その可能性がある場合、この故事成語は留意する必要があると思います。
2.解釈
(1)論理展開
下図は「己の欲せざるところは人に施すことなかれ」を実践することによって、関係が深まるまでの過程を表したものです。

他人に嫌がられなければ、避けられることもないので自然と接点も生じ、そこに人間関係が深まる余地が生まれると思うのですが、私はこの故事成語には改善の余地があると感じました。そこを改善して実行に移すことで、より人間関係を良好にできると考えています。
(2)改善点
まず、上図の前提条件ですが、自分がしてほしくないことを把握するためには、普段から自分の内面を見つめ、どういう人間であるかを理解しておく必要があります。そのためには、事あるごとに自分と対話し、自分で自分を知ることが必要になります。
また、もう一つの前提条件「自分がしてほしくないこと=他人もしてほしくないこと」ですが、おおよそは当てはまるでしょうが、完全に一致しているとは限りません。特に、自分は平気だけど相手は嫌がることを見逃していると問題になります。
それを防ぐためには、想像力を働かせる必要があります。自分の常識にとらわれず、相手の置かれている状況を考え、その時にしてほしくないことは何かを想像することで、より広い範囲のしてはいけないことをカバーできるようになります。
最後に、「他人のしてほしくないことをしない」というのは消極的な関係性の構築に思えるので、一歩踏み込んで、「他人のしてほしいことをする」ことで、さらに良好な関係が築けると考えています。他人のしてほしいことも、前述の想像力を働かせることが鍵になると思います。
上記3つの改善点を踏まえて、「己の欲せざるところは人に施すことなかれ」の改善版の論理展開を図示すると以下の通りになります。

纏めると、重要な点は、以下の3つです。
自分を理解し、自分がしてほしくないことを理解すること
相手の置かれている状況について想像力を働かせること
「してほしくないことをしない」にとどまらず、「してほしいこと」をしてあげること
3.現代における役立て方
この故事成語、及びその改善版は、現代においても良好な人間関係を構築する上で有効な考え方になると思います。
使える場面としては、人間関係が登場する場面全般になるのですが、以下、幾つか例を挙げます。
営業活動における取引先との関係構築
職場におけるチームとの良好な関係作り
学校での友人関係 etc.
挙げていけばきりがないですが、人間関係が良くなると、様々な恩恵を受けられます。
例えば、上述の例1.で言えば、取引先からの信頼を勝ち取れるので、商売の拡大は勿論のこと、何か失敗をした時でも許してもらえる可能性も高くなるでしょう。それによって、会社の業績にも貢献でき、評価も良くなるなど、良好な人間関係を発端として様々なプラスの派生効果が生まれる可能性があります。
このように、「己の欲せざるところは人に施すことなかれ」という言葉の意味を理解して、その教訓を日々の生活に活かすことで、様々な恩恵を受けることができると考えています。また、本稿が、自分が他人と接するときにどのようにしているかを考えるきっかけとなってもらえれば幸いです。
4.終わりに
「故事成語」とは、中国の故事に由来する熟語です。生まれてはすぐに消えていく近年の刹那的な物事とは対照的に、古代から現在に至るまでの遥かな年月を超えてきたその言葉には、人生や世界についての不変且つ普遍の真理ともいうべき意味が込められているものも少なくありません。
しかし、故事成語はその言葉だけを知っていても、意味が分からないことも多くあります。意味が分かったとしても、そのままの形では教訓としては不十分なこともありますし、また、現代においてどのように活用できるかがわからなければ、あまり意味はありません。
そこで、毎回1つの故事成語を取り上げて、その意味や出典に加えて、私なりの解釈と現代における役立て方をお伝えするのも無意味ではないだろうと思い、投稿してみることにしました。誰でも理解でき、日々生活に活用できるような内容にできればと思っていますので、お役に立てれば幸いです。
最後に、今回の故事成語の出典元『論語』のAmazonリンクを貼っておきます。私は中学の漢文の授業で強制的に買わされて読み始めてから、愛読書となりました。今回の故事成語以外にも様々な教訓を得られるので、ご興味があれば読んでみてください。
人の役に立てる記事を書いていきたいと思います。 宜しければサポート頂けると幸いです。 頂いたサポートは、アウトプットの質向上のためのインプットと、note内の他のクリエイターの方の記事購入やサポートの資金に充てさせて頂きます。
