
チャールズ・ダーウィンが最期に考えたこと
今回はチャールズ・ダーウィンに関する様々な資料を読んで、印象に残ったダーウィンの心の葛藤について、まとめたいと思います。
彼の発見した進化論、これは衝撃的な科学革命であり、この前後で大きく科学界の潮流が変わったのは事実です。
自然淘汰説とは:ダーウィンの進化論において特に重要な部分。3段論法が用いられています。
第一の事実:全ての生物は、生き残れるよりもたくさんの数の子孫を生んでいる。
第二の事実:同じ種でも全ての個体に違い(変異)が見られる。
第三の事実:少なくともそのような違いのうちの一部は子供に遺伝する。
子供の一部しか生き残れない以上、それは変化する生息環境にたまたま適応していた変異個体です。生き残る=その生息環境に適応するということであり、生き残っている子どもはその生息環境においては好ましい変異を遺伝していると考えると、次世代の個体は、平均すると生息環境により良く適応しているはずだとする考え。
この進化論を仮説から理論まで引き上げた理論が生まれて間もない頃の逸話として有名なものがこちらです。
ある貴族か主教の奥方である有名なご婦人が、進化論の投げかける冷酷な真理に気づき、思わず夫にこう叫んだと言います。
「ああ、ミスター・ダーウィンの言っていることが嘘だといいのに。もし本当だとしても、みんなは知らない方がいいわ!」
こんな逸話ができるぐらい当時の人々にとっては革新的であり、信念の根幹を揺るがす衝撃的なものだったと言えます。
当時主流だった「生物は神によって、周到にデザインされている」という考えへの違和感
当時のイギリスにおいて、主流だった考えは、神様は自分の姿に似せて、人間を作り、最初の5日間を除いて、全ての動物の支配権を人間に委ねたというものです。
生物を周到にデザインしたのは神であり、人間はその中心にいました。同時にそれが多くの人にとって「事実」に基づく心の拠り所でした。
そして、実はダーウィンも大多数の人と同じく英国国教徒でした。
そこに悩み、葛藤が生まれたのは、ビーグル号での世界周航の経験です。この航海中に、地質学者ライエルの著書の内容である、地層がたゆまなくゆっくりと変化する様を知りました。そして、実際に南アメリカの地質学的変化に触れ、同時にガラパゴス諸島の生物が南米由来と思わざるを得ないほど似ていることなど、南半球各地の動植物の特徴から、動植物も地層と同じようにわずかな変化が貯まっていく、そして大陸の変化に応じて適応できる変化をしたものが生き残るという考えを持つようになりました。
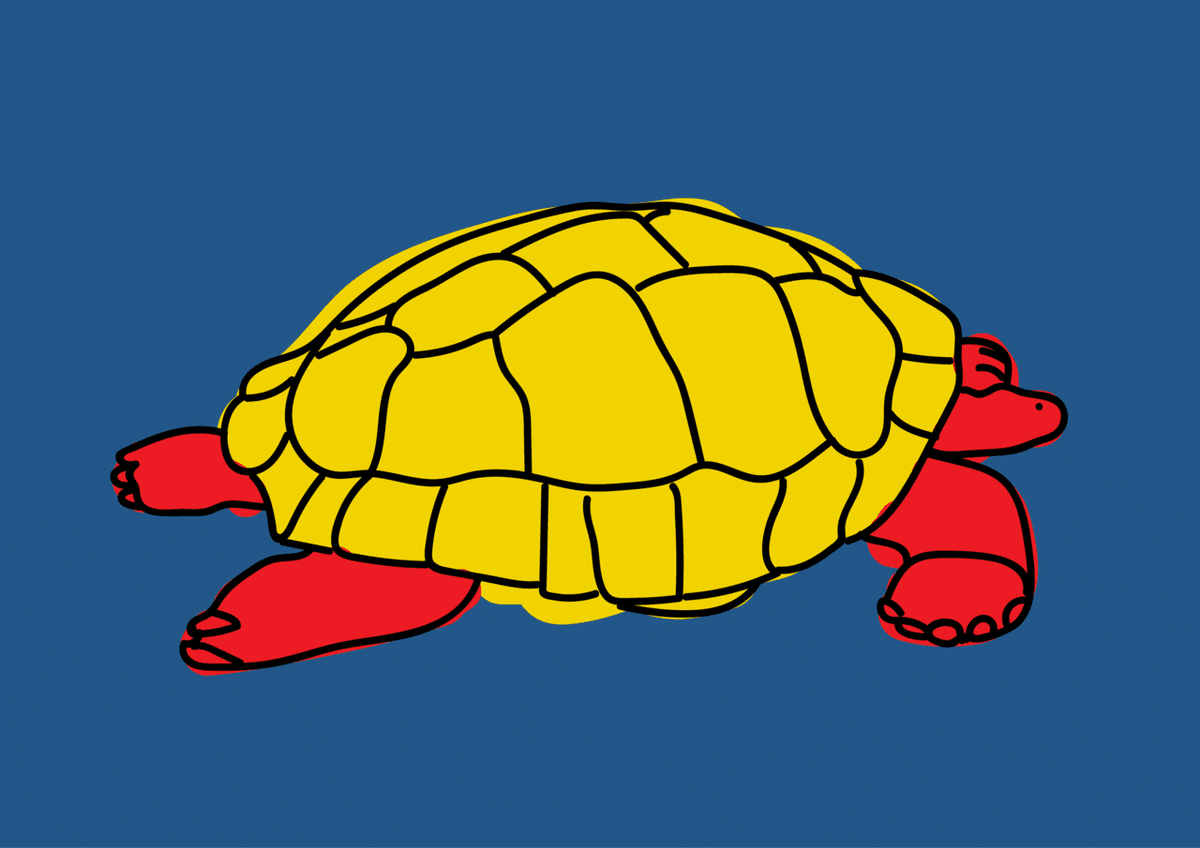
(ちなみにここで進化論のヒントを得た動物の1種はゾウガメで、その際持ち帰ったとされるガラパゴスゾウガメのハリエットは175歳まで生きました。実際は違う可能性が高いそうですが、こんな長生きするのすごいですね)
このような考えを持ち研究を進めていく上でそれが確信になっていくのですが、同時にそれは今まで信じてきたものを否定することであり、そこに多くの悩みや葛藤を抱えていました。
敬虔な英国国教徒であるエマとの結婚と手紙
ビーグル号での航海の後、ダーウィンは結婚をします。その相手が英国国教徒のエマです。生涯を共にするのですが、結婚当初のエマにとっての唯一の不安が、聖書を否定する進化論の萌芽のような考えを持っていることでした。彼女自身は国教徒な訳ですから当然です。そんな中ダーウィンに手紙を送ったと言います。それはヨハネの福音書を読んでみてほしいという内容でした。
「新しい戒律を与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなたたちを愛したように、あなたたちも互いに愛し合うのです」
しかし、ビーグル号での経験を経て彼の宗教観は本能の問題であって、実在する神の云々の話ではないというものなっていました。ですが、それを伝えなかったのはエマに対する愛ゆえでしょう。結婚生活はスタートし、円満な日々を送りますが彼女はその後も夫に手紙を書きました。
私は、あなたが自然界の真理を見つけることに熱中するあまり、別の種類の真理、宗教だけが解き明かせる真理から目を背けていると心配しています。
証明できることだけを信じていたのでは、「同じような証明はできないことや、私たちの理解の及ばないような真理」を受け入れられなくなってしまいます。イエス様があなたや世界中の人たちのためになされたことを、どうか忘れないで
ダーウィンが返事を書くことはありませんでしたが、この手紙は深く心に刻まれたのではないでしょうか。

父ロバートと愛娘アンの死
彼自身が発見した法則と宗教の相容れない壁について悩み続けますが、更に2つの悲しい出来事が彼の宗教観にとって大きな意味を持ちます。
39歳の時に父ロバートが亡くなります。このロバートは医者であり、息子を甲斐甲斐しくサポートし続けました。そんな父のことをダーウィン自身も深く愛していました。
そんな父は宗教に対して懐疑的だったのではないかと考えていたダーウィンは、そのタイミングで信仰なき者は神の罰に苦しまなければならないという考えに触れます。
そのため、父に死が迫っている姿を見て父や友人のような神を信じていない者は苦しむのか、だとしたらなぜそのような残虐な思想を皆が信じるのかという発想に至ります。
また、数ヶ月後に今度は愛娘のアンが病に伏し、亡くなってしまいます。日に日にやつれていく娘を何もできず見守ることは彼にとって何より辛いことでした。治療の甲斐も虚しく亡くなってしまったこともダーウィンにとって耐え難いもので、アンの魂が天国に行ったことも、理不尽な死後も魂が存続していることも信じられなくなっていました。
こうして、ダーウィンは、自然淘汰説を思いついて13年で、キリスト教の信仰を捨てるに近い心情に至ったと言います。ただ、家族に当てて書いた自伝で宗教を痛烈に批判することもあるのですが、彼は、最終的には一貫して不可知論の立場をとります。
自分の理解を超えた範疇のものに対しては言及をしないようになったのです。
不可知論とは:
証明の仕様がないものに対して、正しいとも誤りともしない考え方。
自分が何を信じているかは、自分以外の誰にも関係のないこと
この世に存在し僕たちが認知する事実と、自分が何を信じてどう生きるのかは別であり、それはおそらくこれだけの科学的な大発見をしたダーウィンも多分に漏れず僕たちと同じです。そんな矛盾を孕んだ一人の人間だったのかもしれません。それはもちろんこの法則が大きく議論を呼ぶものであり、多くのプレッシャーを受けたこともあるでしょうが、「大切な人たち」とのストーリーやその人たちの信条が影響していると思います。(晩年は敵対者からの批判に疲れ遅疑逡巡だったという証言もありますが)
自らは、どんなときでも神の存在を否定する無神論ではなく、「不可知論が私の心をもっともよく表す」と述べています。
彼は不可知論の立場をとり、宗教に関する著作は終生発表しませんでした。
疑うことができるときには徹底的に疑い、わからないことに対しては、沈黙を守る、この姿勢を貫きひたすらに事実のみを追い続けたのです。
ただ、ダーウィンは亡くなる直前、彼はエマからもらった手紙を読み返したといいいます。
イエス様の御心を忘れないでほしいと記されたその手紙の余白に「ぼくがこの手紙を何度も読んで涙しながらキスをしたことを、僕の死後気づいてくれますように」と書いたそうです。
種の起源の末尾には「かくのごとき壮大な生命観」という言葉があります。
彼がそのような世の中の根幹を揺るがす法則を語ることで、それまで
自然界の事実と仕組みを理解していくための科学的探求と、「人としてどうあるべきか・どう生きるべきか」「より良く生きるとは」といった倫理的な真理や精神的な意味を探る試みを分けることができるようになりました。
つまり、自然の事実の探求に多くを求めすぎることから僕たちを解放し、事実は事実として認識し、それとは別に、「どう生きていくか」を各々が何を信じて生きていくかという問題として捉えられるようになったのです。
あまり、自らの宗教観について言及しなかったことからも分かるように、
今なお世の中を解き明かすかもしれない「真理」を発見し世に知らしめたダーウィンにとっても、自分が実際に何を信じて何を信じていないのかは、「自分以外の誰にも関係のないこと」だったのです。
学者としての、事実に対する飽くなき探究心は僕たちも見習うべき点が多くあると思います。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
