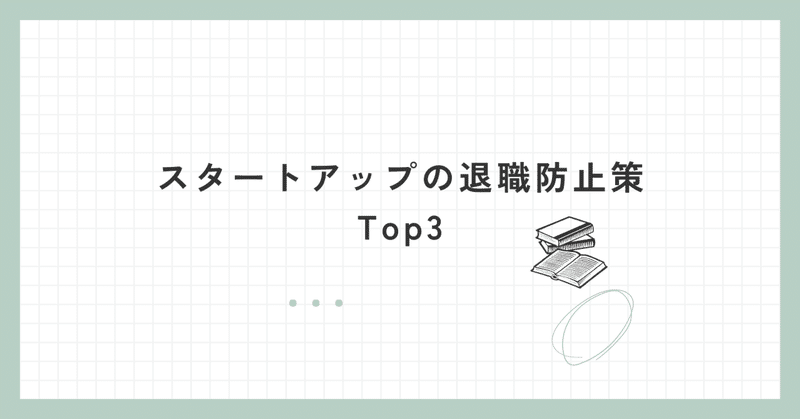
スタートアップの退職防止策 Top3
様々な経営方針があるものの、依然として多くのスタートアップでは、企業成長に欠かせない人員増加。
人員増加の基本は「減らさず増やす」です。
・「増やす」にあたる採用手法
・「減らさず」にあたる引き留める方法、エンゲージメント
に関する記事やノウハウは多くありますが、退職希望者への対処方法ってまとまってないのでは?と思い、今回は退職者を出さないための事前対処方法をまとめました。
ミッションビジョン達成のために少しでもお役に立てれば幸いです。
1. 退職希望者の引き留めは" 感覚 "で行われている
退職希望者の引き留め(以後、慰留と呼びます)の方法について調べるとよくヒットするのは
・否定をせず話を聞く
・妥協点となるキャリアプランを提示する
の2つです。
ですが、本当にこれだけなのでしょうか。
そもそも退職希望を出さない方法があるはずなのですが、よく耳にする対策は年収UP、労働時間の短縮、業務簡略化、福利厚生の充実など「労働環境」「労働条件」に関する施策ばかりです。
採用で魅力になる項目を10項目に分類して、慰留に効果的なアクションを行うノウハウを作れるのではと考えました。
2. 選択と集中:対処項目の特定
慰留を効果的に行うために以下の3つ整理してみました。
1. 把握)多くあげられる退職理由の把握
2. 用意)退職防止方法の用意
3. 実行)用意した方法を実行
データ参照元はハイプ・サイクルでおなじみ、Gartnerさんです。世界中の入社理由、退職理由がまとめてありました。
※海外のデータも含まれるため聞き馴染みの無い言葉があるかもしれません
まずは、退職理由の把握です。
👇入社理由上位の項目

👇退職理由上位の項目

👇入社理由にはなりにくく、退職理由になりやすい項目

(参考まで...)
👇入社理由になりやすく、退職理由になりにくい項目

まとめると以下の傾向がありました。

また、入社理由と退職理由単体で見ると以下の傾向があります。


ここまでで、離職防止のためには
「マネジメント」「キャリア機会」「個人の成長率」の
・入社前後の認識ギャップを極力なくすこと
・改善を行うこと
が重要だと分かりました。
3. 退職防止方法の用意
今回は退職防止に効果的な項目をどう改善するのかをメインにお伝えしていきますので、入社前後の認識ギャップを無くす方法はまたどこかの機会でご紹介します。
3-1. マネジメントの改善
このマネジメントの項目は離職防止に最も効果を発揮します。
退職者の約半数はマネジメントが原因というデータが多くのアンケート結果として出ているのはご存知でしょうか?
採用費用、採用にかける時間などのコストも馬鹿にならないはず。約半数の退職を防げる方法がマネジメントであれば、改善に着手しない手はありません。

マネジメントと一言でいっても様々なマネジメントがあります。
今の組織がマネジメントの中でもどの部分が弱く、どの部分が強いのかを把握し、改善を行う姿勢を取ることだけでも慰留時に使えるカードとして提示することが可能です。
👇マネジメントの種類。貴社にはどんな特徴がありますか?

3-2. キャリア機会の改善
大手企業ではなく、スタートアップだからこそできる対応方法があります。
キャリア機会の解釈を2種類に分類し、その上で対処方法を設定すると選択肢は広がるはずです。
<2種類のキャリア機会>
1. 実業務
= 職務範囲内の業務、延長線上のキャリア
2. 組織業務
= 多くある社内業務(採用、労務、広報etc.)
👇ホラクラシー型組織についての記事
過去在籍していた企業の事例ですと、4つの職種しか存在していませんでした。
エージェント、コンサル、アシスタント、経営者です。
ですが、プチホラクラシー型組織では
・事業レベル向上
・ブランディング
・マーケティング
・自社採用
・労務
・育成
など業務外の対社内向け業務を全メンバーが何かしら兼務し、組織運営を行っています。
実際に
・コンサル+自社採用(田儀はこのパターン)
・コンサル+ブランディング
・コンサル+事業レベル向上
と同じ業務を担当していてもスキル/キャリアが異なったメンバーで組織を構成することができています。
実業務 × 組織業務とすることで多くの選択肢を作ることが可能です。
大手企業には無い、スタートアップだからこその強みを是非生かしていただければと思います。
3-3. 個人の成長率
・成長率を見える化すること
・相対的に比較する対象を作ること
の2点を押さえれば個人の成長率項目はクリアできるはずです。
ここで考慮いただきたいのは「幅」と「深さ」です。
💡「幅」と「深さ」とは?
・幅 = 業務範囲、スキルの種類
・深さ = 業務レベル、思考の深さ
幅は数字を出しやすいので、入社から半年、1年、2年、3年などで他と差分を出していけば問題ございません。
深さはどのように表現するかというと
・量、数
・期間
・実績
で出せる状態を作っておけばOKです。
一方、コミュニケーションや思考力など定義しづらい項目は、一定周期でフィードバックを得られる環境を作る/提供する対策をとっていただければと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか?
採用領域、組織領域のご支援を行っております。
ご興味をお持ちの方はお気軽にご連絡をいただければ幸いです。採用状況を鑑み、無料でカウンセリング・商談も実施しておりますので、よろしくお願い致します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
