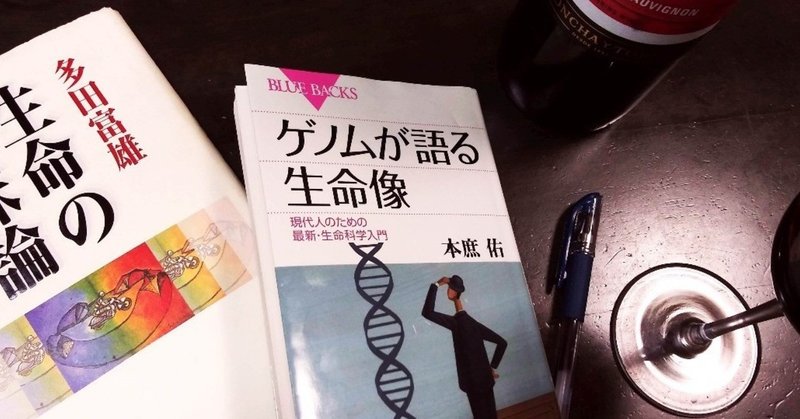
多様な世界の中の例外としての私:本庶佑「ゲノムが語る生命像」
自己と非自己の区別というのは意外に厄介なものだ。その境界は曖昧で、はっきりさせようとすればするほど、いつの間にか境界が消失してしまう。しかし、いろいろな面倒な話はさておいて、生命体としての私と他者を区別するものとして私の免疫系がある、とは言えるだろう。免疫系こそ自己と非自己をくっきりと区別するものではないか。これまで、そのように考えていたので、2018年ノーベル賞を受賞した本庶佑の「ゲノムが語る生命像」を引用しつつ書いておこうと思った。
しかし、読み直しながら改めて考えてみると、ことはそう単純ではないことに気が付いた。自己の定義は免疫系がするのではなく、自己の定義があって免疫系が有効に働く、と言ったほうがよいのではないか。
まずは、簡単に本書を紹介しよう。
本書は1986年に「遺伝子が語る生命像」としてブルーバックスから出版され、2012年にタイトルも「遺伝子」を「ゲノム」とかえて改版されたものだ。7章、52のトピックで構成され、それぞれのトピックは 4 - 5 ページの読み切りで読みやすい。興味のあるところだけ読んでもわかるようになっている。第1章でメンデルからゲノムの全塩基配列決定までの歴史を振り返り、第2章で遺伝子についての基礎が解説される。第3章ではゲノム工学について、第4章で、生命科学の新しい展開、そして第5章から第7章にかけて、生命についてとその価値観に関して、個人と社会、そして生命学や医療はどうあるべきか、が論じられる。
ヒトの遺伝子の数は3万足らずと予想外に少ない事、遺伝子の発現制御と複雑な階層性の微妙な奇跡的ともいえるバランスのなかで私たちが成り立っていること、遺伝子も静的な設計図ではなく、ダイナミックに変化するものであること、遺伝物質としてはすべての生物種において同一であるが、遺伝情報としては種族間あるいは個体間で大きな多様性が見られること、などなど、興味はつきない。

このような複雑でダイナミックなシステムが一つの卵細胞から分割されて出来てくること、そして、そのようなシステムの上で、自分が連続して統一した自分として意識されているというのは本当に不思議だと思う。
また、著者が発見した免疫系を抑えるリンパ球レセプターPD-1に対する抗体に関しては 「33. ガン治療の新たな展望」として4ページを割いているが、ことさら自身の業績や功績を強調せず、そっけない書きっぷりなので、このトピックに注目していないと、すっと流してしまいそうである。
免疫系に関する自己と非自己の識別に関しては、「29.感染症から逃れる仕組み」「30. 獲得免疫系による自己と非自己の識別」「31. ワクチンの効果は免疫記憶の形成による」のあたりの節で扱われる。また、無限にあると思える他者を識別するためには、無限にバラエティに富んだ抗体が必要である。そのような多様性については、「24.多様性は生命の本質である」、「25.動く遺伝子」あたりで扱われている。

さて、自己と非自己の区別をし、非自己を攻撃し、自身の生存への脅威から自己を守るためには、次のことが必要であると考えられる。
1. 無限の可能性がある非自己を認識するためには、非自己を認識する抗原受容体が膨大な多様性を持たなければならない。
2. 自己に対して強く反応、攻撃してはならない。
3. 自己を認識しなければならない。
この 3 つの条件を満たすしくみは次のようにして作られる。
まず、遺伝子の持つ様々な部分が組み合わされることにより、多様な抗原受容体を持つ細胞が胸腺の中で次々と作られていく。遺伝子の種類と数から考えると、その組み合わせは、ほぼ無限といってよい。そして、胸腺から出る前に選別される。すなわち、自己と強く反応するものは死んでしまう。次に、まったくナンセンスなもの、すなわち、自己を認識できないものも死んでしまう。普段の自己を認識することができるから、異常な自己を認識できるという、そういうことだ。
このようにして、自己を攻撃せず、しかし自己を認識でき、非自己を攻撃することのできる細胞のみが選別される。だから、免疫系それ自体は、もともと自己と非自己を定義しない。ランダムに兵隊を作り、自己を攻撃対象とするものと自己を認識できないものを排除する、そのようなフィルタによって選別された兵隊たちによって免疫系が構成されるのだ。すなわち、自己の定義は別にあって免疫系はその定義を参照することで自らの動作を制限しているということだ。

では、私とは、免疫機構によって参照される自己とは何だろうか。本書にはあまりはっきりと書かれていないのだが、多田富雄の「生命の意味論」に、より詳しいメカニズムの説明と考察がなされていたことを思い出し、読み返してみた。それによれば、人間のすべての細胞には、MHC(主要組織適合抗原)であるHLAが自己の標識として提示されているという。そして、免疫機構が参照して胸腺内で自らをフィルタする「自己」こそ、このMHCなのだという。
免疫系は「見る自己」であり、MHCは「見られる自己」と多田富雄は言う。
そのようなわけで、免疫系は私を敵から守ろうという意思はもとより目的も持たない。自ら私を定義しているわけでもない。免疫系はそれそのものが複雑で巧妙に構成されたシステムであり、私を構成する重要な要素ではあるが、私自身とイコールではない。無限に多様な世界の中で私を例外として扱う、いわば独立したシステムとして動いていて、時には私を攻撃し(自己免疫疾患)、時には私の生存を脅かすものの侵入を許し、時には他者を受け入れる(寛容)。
アレルギーや自己免疫疾患などの場合、私としてみれば誤って動作しているとわけだが、免疫系としては正しく動いているとも言える。免疫システムそのものが誤って動作すると考えることのできるAIDSのような病気もあるが、いずれにしても、私にとってうまく動いているときは、私の一部として特に意識されることはないが、うまく動かなくなると、私の外部にあるものとして意識される、「道具」のようなシステムと捉えることもできる。
とはいえ、生命体としての私を敵から守ってくれるシステムである。
「私の敵とは何か?」
「われわれの敵である。」
われわれ、とは免疫系の細胞群であって、必ずしも私ではない。
多田富雄の「生命の意味論」は1997年に出版された、もう古典ともいえる本かもしれないが、改めて名著だと思った。また、いずれ近いうちに改めてとりあげてみたいと思う。
ところで、ブルーバックスは、私が少年だったころによく読んでいたが最近ご無沙汰していた。だが、先進の科学をわかりやすく紹介する素晴らしいシリーズだと思う。今の日本を知的水準を支え、非常に大きな影響を与えてきたのではないか、と改めて思った。今も健在なのは良いことで、今後も末永く続いて、若い人は特に、どんどん読んでほしいと切に願う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
