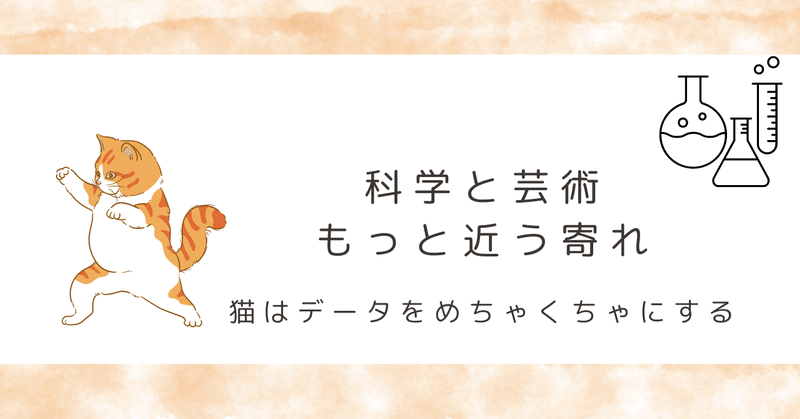
猫は絶対に実験に使うな 〜科学の限界と芸術の創造力
科学者には、運動好きと芸術好きが多い。
これは別に統計に基づくわけでもなんでもないことだけれど、すくなくとも消防士や弁護士、人事担当者、農家、株式仲買人なんかに比べて著しく少ないという印象はない。
彼らは個人的趣味の範囲で楽しんでいるということももちろんあるだろうけれど、運動や芸術については、本業にも活きるようなメリットが多いようなのだ。
何しろ、科学者というものは「プライベートも本業に活かせ」という人種と言えなくもないのだから。
愛読している雑誌を読んでいると、特に芸術の立場や役割について、科学との関連で考えさせられる面白い記述があったので紹介してみたい。
猫は絶対に実験に使うな
柴田元幸さんという、元東大の英文学科教授が編集を行う文芸誌「MONKEY」を愛読している。
2月に発売されたvol.32のテーマは「いきものたち」で、いろんな生きものが出てくる小説が紹介されている。
その中で、ケヴィン・ブロックマイヤーという人が書いたエッセイを柴田さんが訳しておられた。
題名は『祝福をもたらす内なる動物 ーー小説における非 - 人間生物の存在意義』(原題:"An Animal Within to Give Its Blessing: On the value of Nonhuman Creatures in Fiction.")
その中での一節で、彼がベルギー哲学者の著書を紹介している。
たとえば彼女はこう書きます。
「経験豊富な実験者は、猫は絶対実験に使うな、と若き科学者に忠告する。[・・・]食べ物を見つけるために解決すべき問題なり実行すべき課題なりを与えると、猫はたしかに作業をすばやく完遂する。猫の知力をほかの動物たちと比較したグラフを作れば、急激に上昇するカーブが得られることだろう。[・・・]『問題なのは』とヴィレッキ・ハーンはある実験者の言葉を紹介している、『自分がレバーを押すことを研究者や技師が望んでいると勘づいたとたん、猫たちがそれをやめてしまうことです。中には、それをするくらいなら飢え死にも辞さない猫もいます』。この過激に反行動主義的な行動は私の知る限りどこにも公表されていません、とハーンは言い添える。猫を実験に使うな。データがメチャクチャになるからーーこれが公式見解となっているのだ」
猫は比較的知能の高い動物とされているけれど、ネズミや、言ってしまえば細菌だって同じようなふるまいをしていないとは限らない。
それは、単なる因果関係や相関関係に落とし込まずに量子力学的にランダム性を考慮すべきだとか言うことではなく、実験に使われるいきものの側が人間に協力すべきかどうかを考えている可能性があるということだ。
突拍子もない考え方に聞こえるかもしれない。
けれど私の知る限り、一流の研究者ほどそういう考え方をある程度は持っている。
再現性も、因果関係も、可視化も、そしてその解釈も、自分が取り組んでいる科学という学問にはハッキリと限界があると知っている人が多い。
科学論文を読んで、なんとなくわかった気になっている一般人のほうが、科学を過大評価する傾向にある。
あるいは、その成果の一部を切り取って、マーケティングに使おうとする企業が。
ブロックマイヤー氏はこう続ける。
科学が、データが限界に行き当たるその先に、芸術と創造力が引き継ぐ場があるのではないか
なんとも頼もしい発言である。科学はもっと、他のフィールドに託すことを覚えるべきなのかもしれない。
自分の中にいくつもフィールドがある
たとえ自分が科学者であっても、自分という人間にはいろんな側面がある。
それは休日や仕事帰りの過ごし方の話ではなくて、実際にいま科学に取り組んでいる最中にも、いろんなフィールドが混じって考えを巡らせているのだ。
だから、科学者は注意しなくてはいけないのだ。
自分が考えていることが、科学という学問の枠内にあるのか、その外にあるのかを。
そして、意図的に科学的な考え方以外を採用する勇気も持たなくてはいけないかもしれない。
文理融合とか総合知とか言われるけれど、もともと私たちはそういう生きものなのだ。
さまざまな経験をいい感じに取り入れて、目の前の事実をいい感じに処理して、理解する。分野が違っても、原理原則は似ていることも多い。
高校生のとき、どうして私たちは「文系か理系か」を選ぶのだろう。
芸術やスポーツの道に進むのは、ごく一部の人に限られるとしても。
母子手帳の裏には、児童憲章が書いてある。その第5項。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
大人になってからも、どちらも愛でられるように、児童のうちからこんなふうに教育されるのだと思いたい。
決して、子どもだけが科学と芸術の両方を楽しめるわけではないのだと。
一歩外に出てみることの大切さ
たとえば腸内細菌とがんの関係を研究するため、毎日論文を読んで実験する人がいることは、もちろん有意義だ。
でも、その人の頭の中で音楽が流れていたり、研究室メンバーとピクニックに行ったり、帰りの電車で恋愛小説を読むことは、真実とも呼べるなにかに近づくために欠かせない気がする。
そこには、単なる息抜き以上のなにかがある。
寝ても覚めても同じ方向を向いて、同じ視野の幅で生きているのでは見えなかった何かが見えるはず。
先日よしもとばななさんの『王国』を読み返していて、こんな一節に出会った。
川の流れをせきとめたり少し変えただけで、山は致命的に変化した。きっとこれからまたこの山が落ち着いていくまで何十年もかかるだろう。
恋愛とか病気の治癒と同じで、ものごとは正しい時間をかけて、順当な道をたどって変えて行かなくては絶対に収まるところに落ち着くことはない。人だけが、それをはしょったり急いだりする。欲のために。
けっこうスピリチュアルな本ではあるけれど、私にとってこの文章は真理だった。
ほっといても治る病気を薬で早く治そうとしたり、生きものの遺伝子を組み替えて都合の良いものにしようとしたりすること全体に、私が感じていたことを言葉にしてもらえた気がした。
もちろん、そういった研究領域に取り組んでいる人たちを否定したいのではない。彼らは彼らの意志や信念があって、彼らの明晰な頭脳をもって、それに真摯に取り組んでいるのだろうから。
ただ、そういった人たちが分野外の考え方のことを知って、それが間違っているわけではないと知っていることや、自分たちのやっていることの限界を知っていることが、とても大切な気がする。
何もかも、科学的に、数字でわからなくてもいい。
だからこそ、世の中は素晴らしいのだ。
そう思うと、少なくともなんだか肩の力が抜ける気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
