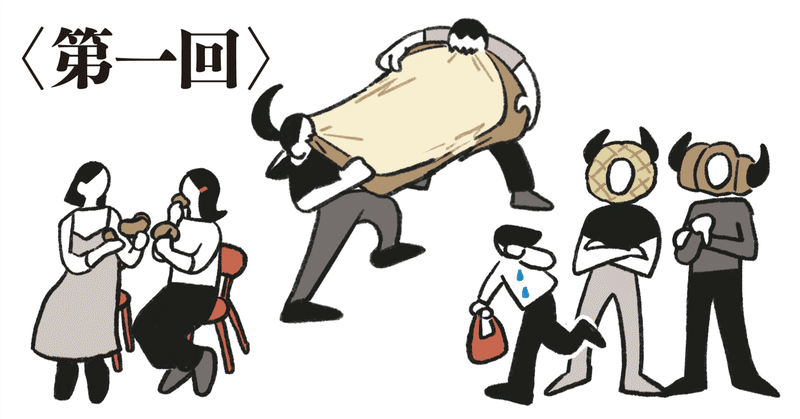
契約を切られた女性ときょうだいの話
壮年の女性社員が契約を切られた。
もう3年前のことなのに、新井には思い出すたびに昨日の出来事のようにも、間近に迫り来る未来のようにも思えた。
あの人はきっと私だったと思う。
3年ほど前。
当時、懇意にしていた先輩と隔週の木曜日はパン屋へ行くというのが習慣になっていた。
たまたまその日、冒頭の女性、A子さんも「一緒に行きたい」というので特段断る理由もないため、3人でパンを買いに行くことになった。
道中、どういう経緯か忘れてしまったが、兄弟姉妹の話になる。新井と先輩は同じ長子で長女だったので「上がいるってどんな感じなのかな〜」とか「先輩がお姉ちゃんなんて幸せだな〜」とか「下はやっぱり世渡り上手〜」というような、下の子の、世間一般に言われるようなあざとさや憎めなさを、長子目線で軽く話題にしていた。
すると突然A子さんが「兄と姉に使いパシリにされたり髪の毛掴まれて引きずり回されたりする下の子もいるのよ」と言った。
空気が張り詰める。
「すみません」つい、いつもの、先輩と自分の内輪のノリになっていたことを謝る。
「A子さんは末っ子なんですか?それは大変でしたね…!」
殺伐とした空気が、先輩の、先輩しか持ち得ない柔和な声と雰囲気でほんの少し緩む。
「そうよ。それはもう大変だったんだから」続くA子さん。
先輩をケア要員にするにはあまりにも難儀だったので、新井はすかさず割って入る。
「たしかに、それは家によりますよねー、わたしも弟と仲良いとは言えないですもん。あはは〜」寄り添いなのか便乗なのか、新井は自分でもよくわからないまま、きょうだいへの不満をこぼす。先輩は妹さんと仲が良かったので、終始困り顔だった。すみません。
「それにうちは転勤族だったし、転校も多くて、舐められないように必死だった」
ああ、と思った。おんなじだと。
地雷を踏んじゃったんだな、と思った。新井にも踏まれた時の感覚はよくわかる。新井自身も転校生で、引っ越し直後からいじめられた過去があった。
転校は一度しか経験していないが、初めにそんな目に遭ったら、次からは舐められないように新井も策を講じたと思う。それが萎縮に転じるのか防御という名の攻撃に転じるのかは、その人の資質にもよるだろうけど。
目的地までの道のりはいつもより長く感じられた。パン屋のラインナップはいつもより売れ行きが良かったのか、目当てのものは残っていなかった。
昼休みを過ぎても、A子さんの一連の発言が新井の頭の中で反芻していた。これは憶測でしかないけれど、A子さんの兄や姉も学校で同じような扱いを受けていたとしたら、その鬱憤が自分達よりも非力な年下のA子さんに向けられることも想像に容易い気がした。そうなった先に、学校でも家庭でも居場所がないとなればA子さんの苦しさはだいたい新井と重なってくる。というか、勝手に重ねていた。つまるところやっぱり居場所がなかった。そういう風にA子さんの怒りを分解した。あくまで憶測でしかないが。
壮年とはじめに表記したA子さんの正確な年齢は不明だが、およそ40代後半と新井は見ていた。そのくらいの年齢の女性が、あのくらい鮮明に怒りを引っ張り出せるのは単純に人としての幼さではなくて、そのくらい傷が深いからだと、新井はA子さんと自分自身を守るために思いたかった。
なぜならA子さんや新井にとって過去は過去ではなかったからだ。
鮮明に思い出せる以上、過去は圧倒的に現在で、怒りや喪失は時間を完璧に止める。その結果、物理的な老いが精神の成熟度に開きを生む。差が開いていくほどわたしたちは苦しかった。
他人から見て幼く見えるのは仕方がないことだと思う。周囲に理解を得られるとも思っていない。どうしようもないからこそ、ふとした拍子に怒りとして噴きこぼれてしまう。相手は新井たちのバックグラウンドなど知る由もないので、そんな些細なことで、と驚く。その繰り返しが対人関係を悪化させていった。人生は常にその繰り返しだった。
個別の事象としては「その程度で?」と言われるようなエピソードが無数にある。問題なのはひとつひとつは大したことがないように思えること。
だから痛みが伝わらない。かといって、そのひとつひとつの痛みが個別に処理できるほど簡単な形をしているかというと、全くそういうわけでもない。
それから数ヶ月が経過したのち、A子さんは契約が満了した。というより、辞めさせられたと言った方が近い。
聞けば、いろいろと問題はあったそうだ。雑談が多すぎるとか、誰のチームにも入りたくないとか、契約内容と業務内容が違うということも訴えていて労基にも行ったらしい。その結果、会社側に問題ありとなり、会社は契約社員の業務内容を見直していた。そんな後出しじゃんけんのような整備で許されるのか、と思って新井はことの経緯を眺めていた。
A子さんが特に問題視されていた感情の起伏はざっくりと更年期にまとめられていた。逆パワハラの気があったとか、業務内容に不満があるなら仕方がないとか。確かに私も怒りを向けられたことがあった。指示内容が不明瞭だったからだ。
一口に更年期と言っても、それを身近に感じるかどうかで冷笑する人と憐れむ人とで、絶妙な空気が入り混じっていた。新井は自分にもいつか起こりうることだと不安を煽られていた。社会はこんな風に人を辞めさせるように仕向けるのだと学んだ。A子さんを追い込んだ存在はいつも透明だった。
A子さんはあるチームに配属されたのちに「症状」がひどくなった。
「辞めさせる方向で動いてるから」当時の上司から、会議の内容が降りてくる。差し挟む口も権利もなかった。新井は心の中で「おまえのせいでもあるだろう」と思った。新井の当時の上司は、A子さんの元上司だった。
「辞めさせる方向で動いてるから」という発言は新井の耳に私怨を含んだように聞こえていたが、他の社員は「それだけじゃないというか、それはそこまでだと思いますよ」と上司をかばった。
健常者からしてみればそうなのだろうなと思った。というか実際はそうなのだろう。
新井のこの感情もまた、上司に対する私怨に他ならなかった。私たちにとって当該の上司は当たりどころが悪すぎた。A子さんと新井はダメになった。
今振り返ってみれば当時の上司のような人間はどこにでもいるタイプで、その下で働く人もたくさんいた。同じ悩みを共有しつつ、それを乗り越えた人も新井は近くで見てきた。でも、新井には越えられなかった。新井は3年という月日を要して、ようやく、自分が勝手に傷ついていただけかもしれないということに思い至った。
新井はある時、別の上司との面談でA子さんのことを聞いた。
「こんなことを聞くのはおこがましいと言うか…あれですけど…A子さんくらいの年齢の女性が、このご時世で再就職ってすごく今、厳しくないですか。そのあたりって、考慮されてたんですか…」
当時はコロナの真っ只中だった。いつ終わるかもわからないパンデミックの最中に、生活の基盤が崩れることへの恐怖は計り知れなかった。
「…それね、本人にも言われたよ。ただどうしようもなかったんだよ…本人もどこのチームにも所属したくないって言うし」
そう言う上司の言葉や表情に険はなかった。本当にどうしようもなかったと思っているようにも見えるし、どうでもいいと言うふうにも見てとれた。
新井もA子さんもいろいろなことに気づくのが遅すぎた。
社会というものがもっと平等だと勝手に思っていた。自分の理不尽もいつか何かのタイミングで、生まれ変わるように報われると信じていた。しかし人生は地続きで、ひとりでに生まれ変わるなんてことはなかった。
生まれ変わるにはやはり、物理的に、相応の手順を踏まないと文字通りの生まれ変わりが望めないことを察した。いろいろなものに勝手に期待し、勝手に失望し、勝手に傷つき、勝手に怒る。
新井は「自己中」と自分を罵る母の言葉を思い出し、泣いた。
新井はもうすぐ会社を辞めるだろう。
一度ふつうの人のように職につけたことが、自分にとってこれ以上ない奇跡なんだと、新井は思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

