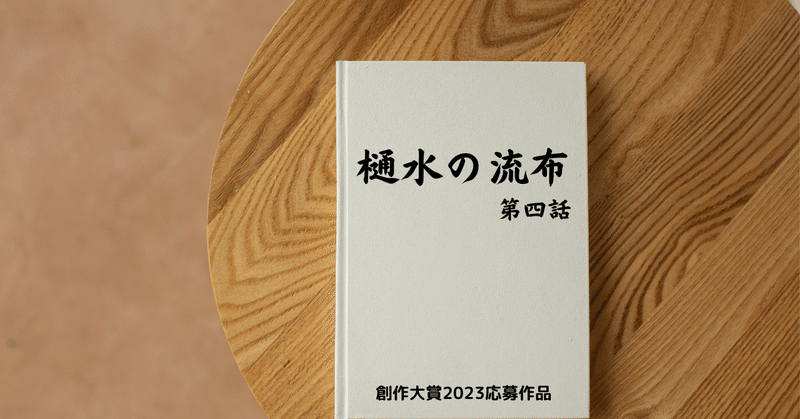
「樋水の流布」 第四話
先生が退室されると、彼は、座り直して、初めて、私と目を合わせた。
「どうかな?流行りの店で、スーツを誂えたんだ。似合うだろう?」
「うん、カッコいいね。スタイルいいから、似合うよ。モデルみたいだね。イケメンで」
「・・・はあ、心の込もっていない言い方だなあ・・・そういう風に、淡々と言うんだ・・・前々から、思っていたんだ。相変わらずなんだ、流布は・・・」
「・・・そんなことないです」
「先生とは、どうなの?」
「先生と弟子ですよ。・・・それ以上も、以下もありません」
「まあ、そんな風だよね。・・・ちょっと、安心した」
え、何?・・・まだ、そんな感じのこと、言うの?
「なんだよ。意外そうな顔するなよ。本当に、変わらないな」
恵一、いや、ここからは、編集者の親見と呼ぶことにする。親見は、大学生の頃と比べて、少し、世慣れた感じで、前髪を整髪料で纏めてあげて、確かに、スーツは、そんな感じだ。多分、東教図書だったら、もう少し、正統派の感じなのかもしれない。香蘭舎は、どちらかというと娯楽中心の出版社で、社員もカジュアルな服装、雰囲気の印象の人が多い感じだ。流行りのファッション誌、各種年代対象の週刊誌、コミック誌、中には、よりスノビッシュな感じの部門もある。その中でも、親見は、彼が希望していたアカデミック企画部門に、運良く配属されたという。
「何?・・・よく見てるね。気になる?なんか、ある?」
「いいえ、お仕事の話、お願いします。親見さん」
「・・・まあ、いいけど。・・・はい、樋水先生」
なんか、全然、変わらない。派手な喧嘩別れしたのが、嘘みたいだが、その昔の関係性が、そのまま続いているわけがないのは、もう、お互いに解るだろう、ということではあるが。
ひとまず、親見は、企画イメージとしてのレイアウトを、いきなり見せてきた。仕事のやり方が、大学の時と同じだ。得意なんだろうな、こういうことが。
「カバーを一新した、竜ヶ崎先生の単行本の中の、10作品分のレビュー集ということで、おまけのブックレット的に考えています。金額の話は、竜ヶ崎先生と当社の上の方で決めています。おまけ、とは言っても、これが、販促用と兼ねることになります。店頭にもぶら下げて、読んでもらえるようにします」
「ああ、見たことありますね。漫画の一話とかの、触りをみたいなの」
「イメージは、そんなもんです。そこをまあ、当時のように、大好きな竜ヶ崎先生礼讃で、おすすめポイントを中心に、ご紹介してもらって、レビューして頂きたいんですが、いかがでしょうか?流布先生」
「決まってるんでしょ?書け、って言われれば、やってみますけど・・・、そちらのニーズ通りのものができるかは、わかりませんが・・・」
「いえ、是非、筋金入りの竜ヶ崎先生ファンで、弟子にまでなった、流布先生ですから、まずは、書いて頂けたらと思います。ただし、作品は、こちらでの指定のものになりますので、それについて、書いて頂くことになります」
仰々しい言い方、わざとしてきた。なんか、意地が悪い感じなんですけど。
「・・・わかりました。文字数はこんな感じで・・・。見開き、単行本のサイズで、かなり、短いんですね」
「まあ、煽りというか、キャッチに近いかもしれませんね。それよりは、流石に長いですが、長尺にならないように、気を付けてください」
「なるほど、コンパクトにですね」
「女性が手に取り易いように、お洒落で、可愛らしい装丁にします。『初めての竜ヶ崎』というタイトルで行こうかなと思います」
「花の写真が良いと思います。作品ごとに、花がよく出てくるので、そのイメージで」
「新しい単行本の表紙も、その意見が出ています。同じ物で呼応要素を持たせましょうか?」
「それ、いい。すごい、いいと思います」
「クスクス・・・出た」
「・・・真面目に、受け答えしてたんだけど。社会人の方に。私は学生だけど」
我慢してたんだよね。お互いに。解ってたけどね。誰も見てないから、昔みたいに話してもいいんだけどね。
「先日、サークルに顔出したけど、流布が来ないって。プロに足を突っ込んだから、もう、来ないのかなって」
「そんな、忙しいんだよ。この家の仕事もあるし、ゼミの課題もあるし」
「いいじゃないか。君は就活の必要がないんだろ?」
「うーん、それは、そうかも・・・」
「いざとなればさ、・・・ねえ?・・・まあ、竜ヶ崎先生が食べさせてくれるからね」
「でも、破門されたら、ダメだから・・・あ、打ち合わせは、絶対、ここでね。私の部屋は男子禁制というか、誰も入っちゃダメなの」
「でも、先生は入るんだろ?」
「ううん、私が来てからは、誰も入室してないから」
「はあ、どうだかね。だって、先生の家、ご自宅だからね。家主じゃん」
「でも、本当に、もう半年以上になるけど、私だけだから、部屋には」
あ、掃除の後に、一度だけ、先生が来たっけ、それは、カウントしなくてもいいよね。
「・・・まあ、いいや。そうか、残念だな、って、一応、言っておくから」
「何、それ?」
「・・・聞かないの?」
「何を?」
「俺の方」
「方、って何?」
「これでも、モテるんだ」
「いいじゃない。良かったね」
ふふふと、含み笑いをした。別に、探ったり、そういう相手がいたって、当たり前だし。
「そんな暇ないな。誘いはあるけど、躱してるし」
あー、いちいち。
「・・・で、親見さん、締め切りは?」
「ひとまず、一作目の『月鬼の祠』のレビューを、このフォーマットに、あ、勿論PC原稿でいいので、これ、フォーム送っておきます。アドレスは、変わってない?」
あ、変わってない。
「変わってないけど・・・」
私は、恵一のは、消しちゃったけど。もう、とっくに、あの時、すぐに。
「ここから、送りますね。あ、これ、会社の持ち物だからね。はい、じゃあ、見ておいてください」
「今度の打ち合わせから、PC持ってきます」
「そうすると、話は早いかもしれませんね。でも、僕は、顔を見て、打ち合わせをしたいので、・・・というか、極力、そのようにするのが、弊社の方針なので。あと、連絡取れるようにしておきたいので、スマホの方も知りたいのですが、僕のは、これです」
名刺を渡してきた。
「あ、そうそう、作家さんも名刺持たれる方、いますよね」
「多分、まだ、門下生の先輩達も、そんなもの、持ってない、と思いますし、多分、竜ヶ崎先生に聞かないと」
「そうですね。竜ヶ崎先生のお名刺も、見たことないから、こちらでは持たない方針なのかな?」
「ならば、私も要らないです」
「なるほど・・・でも、樋水流布は、音も、字面も、女流作家然としてて、いいと思うよ」
「うん、生まれつきのペンネーム、って言われる」
「いいですね。それ、デビュー作で、キャッチにできそうだね。覚えとこう。ああ、その時、是非、担当になりたいと思っているので、このままの流れでね。この仕事が上手くいけば、そのようになるかも」
恵一・・・親見は笑った。懐かしい。
でもね、ないよ、復縁は。少し、チリチリと胃に来てる。探ってるし、アピールしてるし。
「できれば、数日中にじゃあ、第一稿をお願いしますね」
「わかりました。書いたものを・・・あ、えーと、見せる順番は・・・?」「俺が先、先生は後」
「でも・・・」
「これは、仕事だから。聴いてご覧。先生に。まずは、担当の指示通りにやるもんだ、って、きっと、言われるよ」
いいや。そんなの。竜ヶ崎先生の作品レビューなんだから、先生にお見せして、直してもらってから、にしよう。ここは、承諾したことにして、返答した。すると、親見は、とても、嬉しそうにした。一応、お礼を言って、玄関まで送る。
「じゃ、そういうことで、よろしくお願いします。樋水先生」
「こちらこそ」
「あ、次回は、先生のお好きな・・・ハニプラのケーキでも、お持ちしましょうか?」
「あ、最近、食べてない」
「持ってくるよ、今度」
後ろから、渡会が来たのに気づき、親見は、すっと、居住まいを直す。
「あ、香蘭舎さんですよね?どうですか?買い物に出るので、駅まで、乗せますよ」「渡会先生、いいんですか。それは、ありがとうございます。助かります」
庭を通り、門まで、二人を送る。渡会が駐車場から車を出してきたので、私は、門扉を開けた。
「えーと、流布さんは何か、用向きはないですか?」
「今日はいいです。必要なものは、大学の帰りに買うし、大丈夫です」
「わかりました」
「では、失礼します。樋水先生、原稿、お待ちしております」
「へえ・・・よかったですねえ、初仕事ですね、流布さん」
「渡会先生も、月刊ライターズのコラムへのご執筆、いつも、ありがとうございます」
「まあね、書き貯めてあるからね、あの程度のものは。だからね、雑用の時間もあるわけで、・・・じゃあ、いってきます」
「じゃ、渡会さん、いってらっしゃい。あ、香蘭社さん、ありがとうございました」
「はい、じゃあ、ご連絡ください」
私は、ニッコリと手を振って見せた。親見もそれに応える。少し、居住まいが悪い。こんなことしたことなかったな、お互いに。
なんか、親見が、渡会に、何か、私の昔のことを言わないか、心配になった。渡会が帰宅したら、さりげなく、聞いてみよう、と思った。
・・・・・・・・・
初仕事を仕上げる。PCのフォーマットは、紙面に嵌めこめるタイプと、原稿用紙が両方用意されていた。多分、イメージが解るようにしているのだと思う。
親見は、今回のブックレットに関しては、全ての編集の叩き台を任されているのだそうだ。頑張っているんだと思う。偶然が重なったが、最後は、人脈というか、縁故というか、まあ、私との過去の関係を利用して、この一連の流れを自分のものにした感じがした。結構、しぶといよね、恵一先輩。
書いたものを印刷し、竜ヶ崎先生に見せに行った。
「えー、これ、ブックレットになってから見ますよ」
「え?いいんですか?」
「僕のレビューを、こう書いてくれと、添削するのは、おかしな話じゃないですか?」
「あ・・・そうですよね。すみません。お忙しい所、失礼しました」
親見の言った通りだった。この仕事は、結構楽しく、サクサクと進められた。香蘭舎の先生の単行本は、二か月後には、表紙を一新し、綺麗で柔らかい印象で、女性の好む装丁に変更された。
本を一冊買うと、このブックレットが付くが、二冊目以降の購入時から、そのブックレットの最後のページに、購入した本のスタンプラリーに参加でき、そこにスタンプを押す。レビューのある十冊の本を、一冊購入する毎に、そのタイトルにスタンプが押され、三冊、六冊、十冊と制覇すると、それぞれ、ノベルティがもらえるようになっている。作品にちなんだ、女性の好む小物系だ。早い者勝ちで、例えば、その場で三冊購入すれば、スタンプとノベルティがもらえる。小さな練り香水が巾着に入ったものを、私は提案した。それは、先生の小説の中に出てくる香りのもので、私自身があったらほしいと思うものだった。
「そうですね。それなら、五冊は買って頂かないと」
「じゃないと、採算と合わないとか?」
「まあね、後、紙媒体って、今、弱くなってるから。皆、ネットで見てしまう」
「うちの先生は、許可してませんから」
「まあ、そうすると、そのまま行くと、そのうち、知られることもなく、となってしまうかもしれませんね」
「それはダメだと思います。これね、練り香水だから、少しでいいの。つけるの。だから、ほんの小さいケースでもいいのよ。試供品のクリームみたいなの」
「ちょっと、調べてみましょう。やってもらえるかどうか」
購入特典の打ち合わせまで、結局、最後まで、二人で詰めた。三冊の場合は、小さな椿を象ったチャームで、六冊の場合は、その練り香水の小さいもので、何種類か選べるようになっている。十冊の場合は、その十冊分の単行本の専用ケースとなった。綺麗な千代紙の柄で、これまた、微かに匂いの仕掛けがついている。私としては、竜ヶ崎先生の小説に出てくる、女性たちの感じを漂わせたつもりだった。
これは、その実、結構、人気があったそうだ。新作も打って出た先生の作品群は、昨年の売り上げより、三割増しということだった。香蘭社の宣伝、販売戦略のお蔭と、先生は喜んでくださって、私としても、やった甲斐のあった、初仕事となった。
「流布は、持ち上げ上手だ。今度は、君自身の作品をね、本格的にやってみなさい」
褒めてもらえた。俄然、やる気が湧いてきた。親見からも、短編から、書いてみるように勧められている。この成功で、親見は正式に、私の担当編集者になったのだ。
この頃の一門は、先輩たちも、頑張っていた。
渡会が香蘭舎で、小説書評の月刊誌のコラムを書き続けていたが、近代を舞台にした探検家の冒険小説の連載を始めた。賞レースには程遠いが、男性を中心に受けているという。以前、御伽屋文学賞の新人賞をとって以来、鳴かず飛ばずだったが、今回は、その続編として、満を持して、書くことにしたという。
能福は、得意の食をテーマにした、時代小説を書いている。料理一つをテーマにして、物語が展開し、基本は、ほっこりさせる内容になっている。これも、香蘭舎で、料理・グルメを取り扱った雑誌や専門誌の、小さな連載ではあるが、女性に、そこそこ、受けているらしい。ネットでもHPを展開している。「今日のおばんざい~竜舌庵の夕ご飯~」と題して、写真入りで、ここでの夕食を、コメント入りで紹介している。竜舌庵を、料理屋と勘違いする人も多く、開設当時は、どこに行けば、この料理が食べられるのか、という問い合わせが、香蘭舎の方に、ひっきりなしに連絡が来たという。竜ヶ崎先生は、ネットで小説を読ませる以外は、宣伝活動や、趣味ですることには制限をせず、門下生に許しているようだ。
新人賞狙いに大手をかけようとしているのが、武内だった。彼の作品は、女性に受けている。武内の文章は読んだことがある。女性ファッション誌に、服装史をテーマに、昔、コラム連載をしていた。細面の尖った顎、昔の書生風で、少し陰がある。
「昔の僕みたいでしょ」
竜ヶ崎先生が、インタビューで、冗談めかして、そんなことを言っていた気がする。実際に会うと、本当に、そんな感じだった。坦々と、自分のやることを進めている。本人は嫌がったが、雑誌に乗せる為の、モノトーンの宣材写真が受けた。いわゆる影のある若き作家、まあ、イケメンの方になる。これを載せることで、女性ファンが激増したそうだ。
その武内の、香蘭舎の担当は、狭山という30代の女性で、華やかな印象だった。香蘭舎っぽい。そうだ。その実、親見も、香蘭舎っぽくなってきた。どんどん、朱に交わって、赤くなるんだろう。その狭山と言えば、竜ヶ崎先生には、数か月に一度、羊羹持ちで挨拶をする以外は、当の武内とは、外で打ち合わせをする。
「あれ?武内は?」
「打ち合わせに出た」
「また?この間、お姫様来たばかりじゃない?」
台所で、渡会と能福が話している。そこへ、私が割って入る。
「お姫様って?」
「ああ、武内の担当の狭山さん」
「ああ、こないだお見えだった、赤いワンピースの派手な感じの方ですか?」
「ふふふ、派手だよねえ、香蘭舎っぽいよねえ」
「もうちょっと、売れたら、ここを出て行くんじゃないかな?彼は」
「ライトノベル部門の引きもあるしね」
「狭山さんってさ、楢井縫先生の担当でもあるんだって」
「能福も、そっち方面、いいんじゃないか?」
「グルメ推理小説、いいかもな」
「サスペンスドラマ化されるんじゃないか?」
「楢井先生って、推理小説では、最近凄い方ですよね」
「そう、もう大御所だよね」
「うちの先生とも、そこそこ、仲がいいよね。たまに飲んでる」
「前ね、女の子連れて、遊びに来たよね」
「能福」
「あ」
何々?
「あ、もう来ないから、大丈夫だよ、流布さん」
「能福」
「あ」
「なんですか?つまり・・・?」
渡会が、能福を諫めながら、ニヤつく。
「まあ、うちに女の子が来て、何かがあったわけじゃないんだけど、要は、そういう人みたいだからね。縫先生は。うちの先生より十歳も上だけど、女好きで有名で」
「つまりは、狭山さんって、要員なんだよ」
「能福」
「あはは、いいよねえ。そのぐらい、解るよね。流布さんだって」
「はあ、だから、綺麗な人なんだ、ふーん」
「香蘭舎だよなあ。いわゆる」
「でも、流布さんの担当も、いい宛行だよねえ。新人でしょ?イケメンじゃんか。武内とどっこいの。違うのかな?」
「能福・・・もう、いいから、ごめん、流布さん」
「いいですよ。別に、仕事が上手くいけばいいんじゃないですか」
「その通りなんだよな。全部が、そんなんじゃないからね。僕の担当は、同年代のベテラン親爺だし」
「俺もそうだよ。友達みたいでさ、一緒に取材ランチに出てくれる。まあ、気楽かな。まあ、でも、武内はさあ・・・」
「いいんじゃないの?上手く行ってるんだから。一番の売れっ子だからね、門下では。今回、正式に、御伽屋文学賞の新人賞狙え、って、先生がオッケー出したからね」
「まあねえ・・・」
新人賞かあ・・・、それにしても、何となく・・・何かあったのかな?この時、私は、武内の素行というか、その辺りについては、知らなかった。武内といえば、亡くなられた、先生の奥様の仏壇を毎朝、丁寧に、掃除してる。仏壇は、先生の仕事場にある。あまり、喋らない坦々とした感じの人で、でも、話しかければ答えるし、普通の感じだ。ただ、家の作業以外は、すぐ部屋に籠っている。たまに、その狭山という女性編集者が、派手な赤いリルリモを門前につけると、彼は出て行く。その日は、夕食まで戻らない。そんな感じだった。・・・どんな打ち合わせをしているのやら。だから、彼の作風は・・・という、短絡的なことは、言うつもりはないが。
池田は、私の来る半年前に、竜舌庵に戻ってきたという。先生の弟子という意味では、渡会とどっこいの古参らしい。結婚を機に、一度、ここを出た。しかし、それが、離婚して、出戻ってきたという体らしい。全くと言っていい程売れず、作家としては、鳴かず飛ばずだが、人はいい。家事のことは、一番よく知っていて、何でも熟す。この家の物の在処を、一番知っている。渡会が「兄さん」と唯一呼んでいるので、齢も上で、若干、古いのだろうか。実は、先生は、この池田と、あまり、齢が変わらない。普通に「池田さん」と呼んでいる。しかし、当の池田は、先生はあくまでも先生だと、敬っている。食堂での席も、先生の隣でもいいのでは、となったが、不在中に、二番手の渡会が取り仕切るようになっていた為、やはり、ここに来た順ということで、出戻りではあるが、それに則って、自ら、末席近くに甘んじているという。
寛算は、そういえば、最初以来、あまりやってこない。完全に、先生のファン、特別枠のようだ。この赤鬼谷の付近では、安楽寺は大きな寺で、先生も、実は檀家である。「寛算は生臭」と他の者が言うが、良い二代目として、檀家からは慕われているそうだ。弟子という肩書ではあるが、実際は、そんなポジションのようだ。美味しいものを「仏様の御下がり」と言って、酒などと一緒に、たまに持ち込む。そして、それは、夕食に、たまに振る舞われる。
余談だが、酒については、これもまた、創作の援けになるならばの嗜みとしては、認められている。それぞれが、ナイトキャップ程度に飲めるものを部屋に持っているらしい。酒で乱れ、揉めるということも、これまでなかったという。つまりは、個々人の節度が、ルールを最小限にしていると思われる。集団生活としては、理想的なのではないか。正月や、何かの祝いの席が、夕食時等に設けられた場合は、酒盛りということにもなるらしい。
そして、それからというもの、私は、何度か、先生に作品を見せる。
「いいですねえ。でも、これ、やってますよね。僕が。違うテーマで行きましょうか」
とある時は言われ、
「うーん、好きですが・・・、やはり、意外性がないですね。貴女らしくない」
と、また、ダメだしをされ、
「ここ、広げてください」
あ、まただ。そういう所なんだ。
書き直し、って厳しい言い方をされるより、その作品丸ごと却下だったり、特に、男女のそういう場面は、できれば、繊細に表現してほしいのだと言う。これは一貫していて、確かに、門下生になる時と同じことを、指摘され続けている。つまりは、進歩してない、ということか・・・。
~つづく~
更に、創作の幅を広げていく為に、ご支援いただけましたら、嬉しいです😊✨ 頂いたお金は、スキルアップの勉強の為に使わせて頂きます。 よろしくお願い致します😊✨
