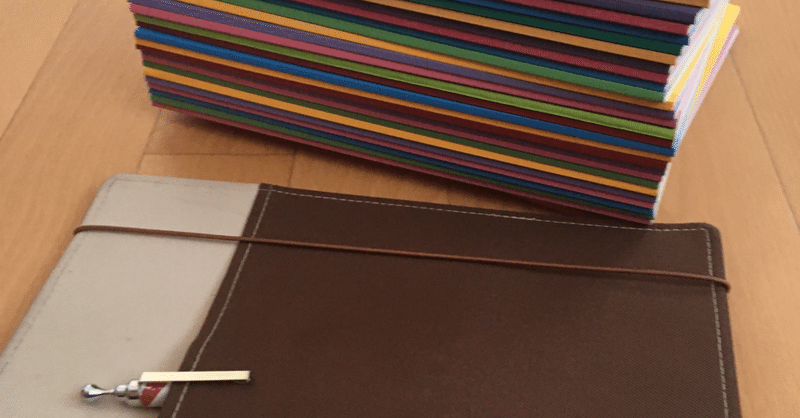
新卒初任の先生に「教材研究の方法」として伝えたこと
国語の授業はなるべく早く伝えてあげたい
初任者の先生が学校に赴任されたら、なるべく早めに師範授業をしてあげたいですよね。国語の授業ならなおさらで、経験のない先生が初めにつまずく授業が「国語の授業」だと思います。
僕は今年度、学校の国語科主任でもあるので、4月の中旬に校内のトップバッターで師範授業を行いました。
行った授業の教材は物語文『いつか、大切なところ』です。オーソドックスな国語の授業を心掛けました。授業の技術としては、「列指名」の技術と「ペアトーク」の技術が主なところです。まだ4月ですから、これからの学習活動の基盤となるような活動を多く仕組みました。
授業後は今日の授業について初任者と話し合いました。
教材研究の方法
教師が「先ず読む」→黙読・音読・場合によっては視写する
まずは1人の人間として教材文を読みましょう。野口芳宏先生の「素材研究」ですね。黙って読む。黙って読むと読みとばしがあるので、今度は音読してみる。研究授業など、力を特別入れたい場合は写し書きするといいでしょう。実際に鉛筆を握って書いてみると、書くという行為を通して作者の筆使いが染み込んでくる感覚を覚えます。発問などのアイデアも生まれやすくなります。
この教材文の面白いところはどこか考える
1人の読者になって教材文を読んだら、この教材のどこに自分は心を打たれたのか、心が動いたところはどこか、面白いと思ったところはどこかを考えます。それは授業構成の礎にもなりますし、この教材の本当の価値を考えることにもつながります。
個人的な感覚ですが、この部分が弱い教師がものすごく多いです。つまり教師本人はとくにこの教材の面白さを感じていないまま、ただ漫然と授業をしてしまう。そんな授業者に教えられた子どもたちが、その教材に真に向き合うはずがありません。
発問を考える
上記の2つを行うと、いくつか発問が自然と思い浮かんでくると思います。そういったものは、あとで忘れてしまわないようにサッとメモをしておきましょう。そのとき大事なのが、発問は教師が明確に答えられるものを授業で使用すべきだということです。
これも国語教育の大家、野口芳宏先生に教えていただいたことです。
国語の授業の発問は「あれもいい」「これもいい」と明確な正当の線引きがないものになりがちです。「どんな気持ち発問」に代表されるような、教師自身も誤答があやふやなものは避けるべきです。誤答があるからこそ、子どもは自身の考えを見直し、成長するからです。
「発問+指示」の言葉を考える
「女の子が驚いたことは何でしょう?○場面から○つ見つけて線を引きましょう。」とか「文中に出てくる『色』は○場面の中にいくつあるでしょう?四角で囲んで調べなさい」など、発問をした後には、必ず指示の言葉を付け足します。指示の言葉がないと、発問に対して優秀な子だけが手を挙げて授業が進む「ハイハイ授業」になってしまいます。明確な指示の言葉を出すことで、授業が全員参加型の授業になります。
いかがだったでしょうか。
初任の先生に伝えたことは、まだこれだけではありません。
これからもいくつかの記事に分けて、書いていく予定です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
