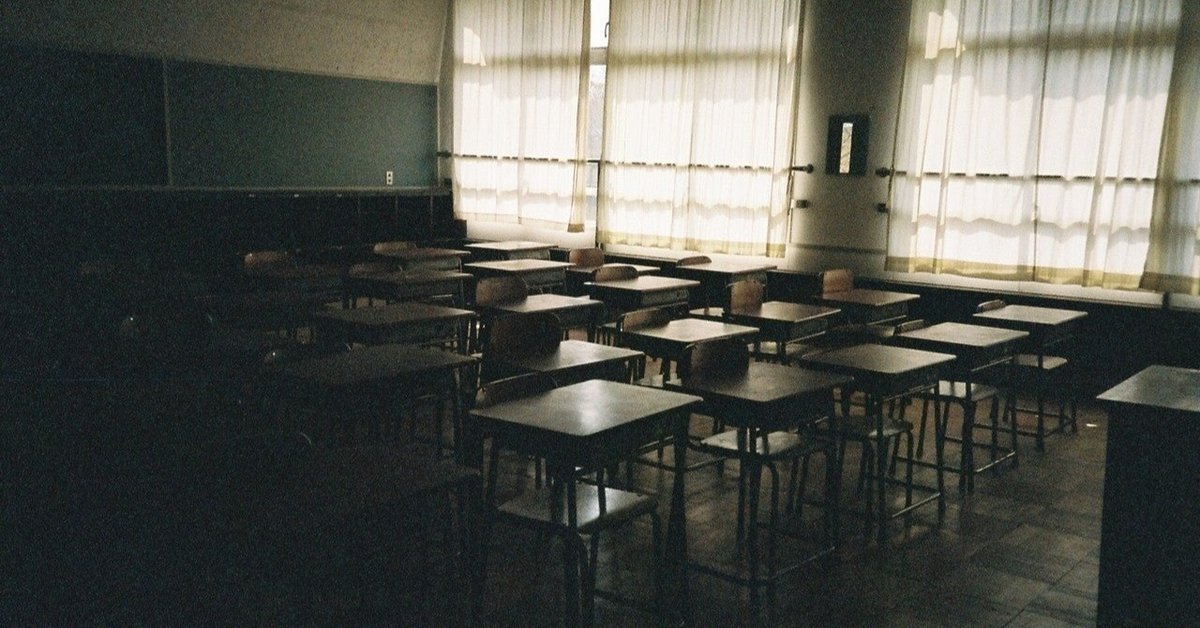
ゴリラの課外授業2
どうも
猿人全開ゴリラ・ゴリラ・ゴリラ🦍
サンシャインゴリラです
先日、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究×日経ビジネススクールのオンライン講座を受講しました。備忘録を兼ねて内容を書いていきます。
日経のビジネススクールはどんな講義をするのか。受けてみようか迷っている人は参考にして欲しい。理解力に差があることは承知しといてくれ。
人口政策推移と現代の分水嶺
人間の言葉を覚えてかれこれ20年は経とうとしているが、ニュースでは日本の少子化についてテレビでたびたび発信しているのを見かけた。
講義中には戦前戦後の人口政策について、「人口政策確立要綱」1941年1月閣議決定【国立社会保障・人口問題研究所WEBサイト】の資料を引用して人工現象の増減について講義。文中に書いてあることは、昭和35年総人口1億人を目標とする。とありました。昭和16年に掲げた目標ですが、昭和35年で9,500万人になり、この目標は6年先の昭和41年で1億人を突破したとのこと。
ここで先生が1970年当時の65歳は人口比7.1%だったが、2019年の80歳以上の人口は人口比8.9%。と、現代と70年当時の高齢者の人口比を比較。そこで先生の考察を引用すると高齢者の定義が変わるって話になった。
この話を下限である15歳にあてはめても同じことが言えるでしょ。
労働生産人口は15歳から65歳というのも、大方が高等学校に進学するのが多数で、15歳で働く人間はレアケースなのに労働者の一員としてカウントすることに対して謎なところがあるし、年金の繰り下げと定年延長をしておきながら65歳も労働者から除外される。生産年齢人口の定義を変えないとアンケートや統計に響く所もあるから、データそのものが信用できなくなってしまう恐れがある。この2020年あたりで生産年齢人口の上限と下限の定義をもう一度考えなおさないと、統計結果の核となる部分が揺らいでしまうのが俺の意見だ。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
