
教育立国推進協議会とは
今回の記事は、教育立国推進協議会についてです。
私は、現在第二分科会の書記として参加しています。
昨年まで現場にいた元小学校の先生です。
今、日本を変えようとする協議会があることを
現場の先生達、教育者、子供達、親御さん達に
お伝えできればと思います。
1.教育立国推進協議会とは
(1)設立と下村博文元文部科学大臣
教育立国推進協議会とは何でしょうか。
8文字の漢字が連なって難しく感じますが、
設立当初の記事を紹介します。
2022年1月19日(水)
憲政記念館において設立総会及び記念シンポジウムが開催されました。
170名(代理含)の国会議員と民間有識者90名、合わせて260名の参加。
元文部科学大臣の下村博文国会議員が総会において会長を拝命。
シンポジウムでは、
アチーブメント(株)の青木仁志氏と
(株)フォーバルの大久保秀夫氏と三人で、
教育で国を立て直す決意を語りました。
超党派の議員連盟に、
教育分野で実践をされている民間有識者の方々が加わり、
大きなうねりなっていくことが期待されている。
元文部科学大臣下村博文国会議員を会長とする、
「教育」で「国を立てる」ことを推進する協議会
ということです。
令和の日本は、様々な課題を抱えています。
その課題を解決するには「教育」しかない。
そのような思いが伺えます。
下村博文国会議員の紹介は、
以下のリンク先から見ることができますが、
教育学部出身、教育事業経験者は、
文部科学大臣としては実は珍しい経歴です。
※経済学部出身者が多いと伺います
何度もお会いしましたが、
教育のことを本気で考えて変えようとしている方と伺います。
(2)設立趣意書
下村博文国会議員が自身のTwitterでも発信した設立趣意書です。
長いですが、6枚の趣意書を提示します。
【教育立国推進協議会 設立趣意書(2/2)】 pic.twitter.com/8BxVdHj2hW
— 下村博文 (@hakubun_s) December 16, 2021


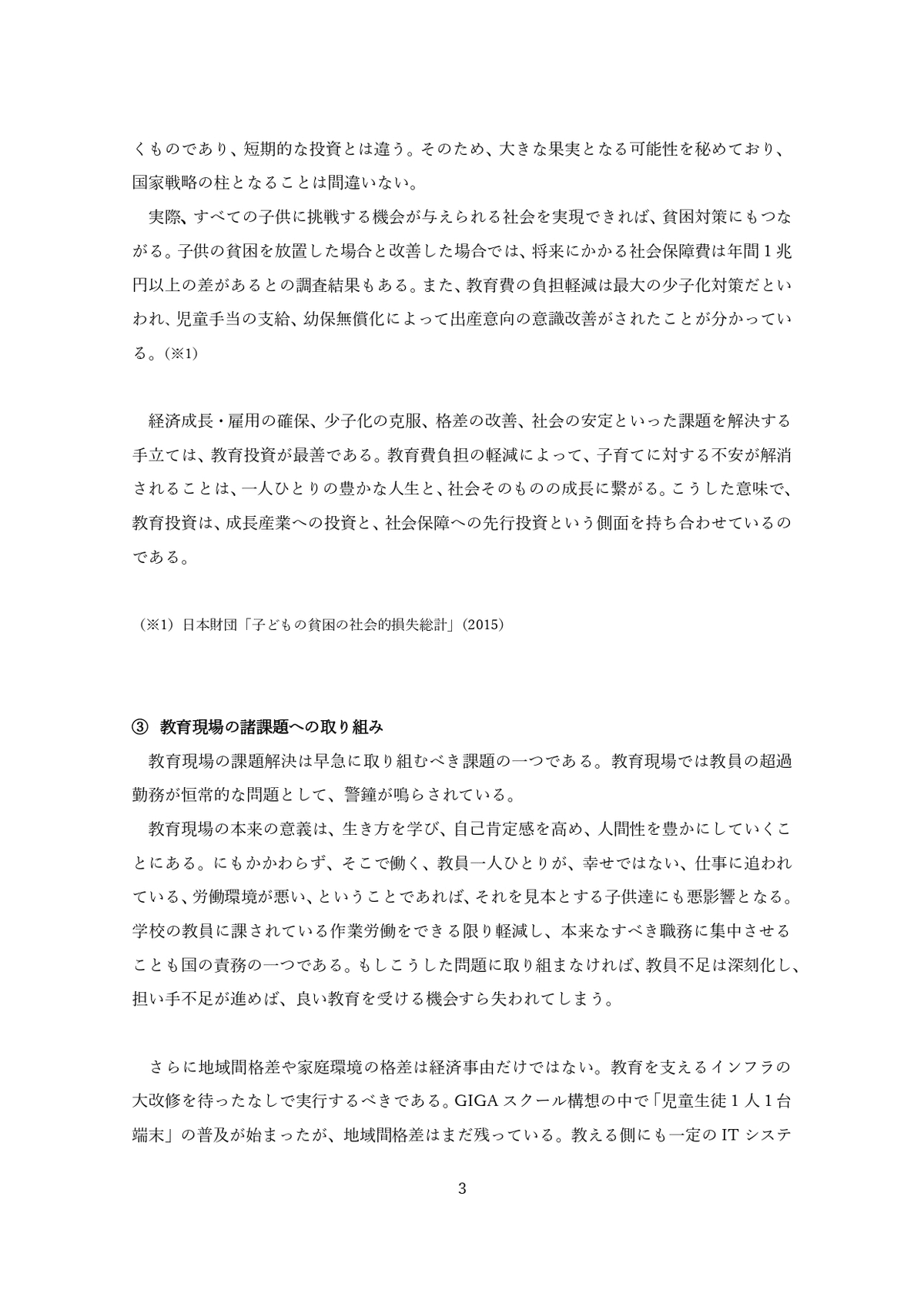



この趣意書は、
6つの項目により教育全体を包括していると伺えます。
教育の目標からはじまり、子供達の未来について、
そして学校現場の疲弊や、
全ての人が豊かに生きることができる教育について言及しています。
この趣意書で特に思うことは、
「教育者である大人」についても触れていることです。
子供達をどのように育てるかという議論はよく出ます。
ですが、大人に目を向ける内容は全体としては少ない。
この趣意書は、大人が働く環境・教育にも触れれていることで、
「学校を出た後の子供」について考える土台となります。
(3)特徴
教育のための会議はたくさんあります。
文部科学省の管轄である中央教育審議会をはじめ、
内閣府のCSTI(総合科学技術イノベーション会議)など。
それらと教育立国推進協議会の違いは何でしょうか。
主な特徴を2点挙げると、
①超党派(党の派閥なく、あらゆる党や省庁が関わる)
②民間の実践者・経営者が数多く参加
が挙げられます。
もう少し詳しく書くと、
①超党派というのは、大切な点で、
党や省庁による垣根があると、制度や実践は上手く進みません。
それは、施作の推進もですが、予算の問題もあります。
「国全体として進んでいく」ためには、超党派が重要です。
②の民間の参加について。
通常「有識者」と言われると「研究者」が多いイメージがあります。
大学教授の名前や大手企業の名前が並んでいるけれど、
「教育現場経験者が1人もいない」会議があります。
すると、現場と乖離した制度や空論が進みます。
教育立国推進協議会は、
教育実践者、教育企業、NPO団体などが参加しています。
企業家目線、現場目線で分科会が進んでいます。
私も元小学校教員です。
現場の声で会議が進んでいくことが最大の特徴と感じます。
もちろん、だからこそ
「各論」や「事業目線」に寄りすぎないようにすることも重要です。
分科会についてを詳しく記述したいと思います。
2.6つの分科会
教育立国推進協議会は、1月からのスタートから、
「総会」と「分科会」で進んできました。
(1)総会
総会は、関係者全員が集まって進む会です。
YouTubeがあります。
教育の第一線で活躍される方々からの講演を受け、
質疑応答をしながら方針を定めていきます。
直近ですと、
工藤勇一先生、今村久美さん、妹尾晶俊さんなどが
講演されました。
私も基本参加しています。
民間実践者の方々、国会議員の方々が参加されています。
(2)分科会
分科会は、20名ほどの民間実践者・経営者の方々で構成されています。
基本的にこの中に国会議員の方はいらっしゃいません。
分科会は6つに分けられています。
大学までの教育の無償化
地域格差、家庭格差、障害格差をなくし、教育を多様化する
インプット教育からアウトプット教育へ
経済優先から精神的豊かさ(Well-being+志)への教育のあり方を変える
教員等の勤務環境を改善する
個別最適化された全世代型の教育の機会を保障する
先程の趣意書とリンクする部分も大きいですね。
私はこのうち、第二分科会に属しています。
分科会それぞれで進め方は違いますが、
少し進め方について説明します。
(3)分科会の進め方
私のいる第二分科会を例にしてみます。
日本各地から参加される方がいるため、
zoomで行われることが多いです。
※時には海外の方もいるかと思います。
事務局の方、分科会幹事の方がいて、
司会や日程の共有をしてくださいます。
日程は1月から4月末まで、1時間半〜2時間を十数回。
分科会テーマをもとに、
課題、解決策、提言に分けて話を進めます。
少し想像してみてください。
初対面で20名の実業家や実践者が集まり、
熱意を持って議論を進める場。
最初は、会がまとまるのにも時間がかかりました。
理想論ではなく、現場に根ざした形。
総論ではなく、各論で。
ただの意見ではなく、データに基づいて。
かなり大変だったことを思い出します。
意見の発表会のような形ではなく、
どうすれば実現可能なレベルに持っていけるか。
数ヶ月にわたり、何時間も議論をしてきました。
本当に色々な方がいます。
私のような学校現場経験者、
全国に展開する塾経営者、
自分で学校を立ち上げて運営している方、
NPO団体を立ち上げて家庭・障害を持つ方を支援する方、
世界で活躍し次世代教育にも力を入れているデザイナー、
多様な方々で進んでいきます。
このような打ち合わせの元、
3人の書記がいて、議事録や先行資料を集約してまとめます。
次週の会議のために国内外のデータを集め、
数百ページを読み、資料としてまとめるなど、
資料作成は時には深夜になることもありました。
5月11日(水)に、
分科会の発表がありました。
各分科会で4枚程度にまとめた資料を発表しました。
提言資料はたった4枚でしたが、
参考にした資料は数百ページ、文献も数十種類。
提言のために作成したスライドは数十になりました。
後日YouTubeでの配信で共有することができると思います。
※現在は限定公開となっています
3.これから
この協議会はまだ始まったばかりです。
4回目の総会のあと、
工藤勇一先生にお話を聞きました。
「この協議会、分科会が実りある提言をするにはどうしたらいいか」
という質問に対し、
本当の意味で何かを変えるには、
全員が最上位目標を正しく共有・認識する必要がある。
という意味のお返事をいただきました。
というのも、協議会は、
個人の意見を述べたり、崇高な理想が先行したりして、
結局現場を含め何も変わらないことが往々にしてあります。
文部科学省が出す多くの政策に反して、
現場の大人や子供の疲弊しているところからも、
そのギャップは感じられるかと思います。
文部科学省を批判したいわけではなく、
懸命に働いている私の知人もいますが、
現実的に現場の先生は人が足りず、不登校は増え、
公教育が成り立たなくなってきています。
本当の意味で変えるためには、
最上位目標を見失わずに、課題を正しく認識し、
解決策を具体的に設定し、継続的にPDCAで進めることです。
それには
「官」だけでは現場と乖離します。
「公」にはバラつきがあります。
「民」の個人的な取り組みには限界があります。
現場の課題を変えるために声を集め、
「民」が事業を計画して実践を進め、
「公」が制度を活用して後押しをし、
「官」が制度を整え国として推進する。
その時はじめて日本の教育が変わると思います。
現在の学校制度における土台とされる明治初期の「学制」。
そこから約150年が経ち、多くの歪みが生まれています。
150年かけて作られた固定観念を乗り越え、
先人が積み上げてきた教育を大切に、
その上で時代に合った新しい教育を再構築していくこと。
最後に、同じく工藤勇一先生に質問させていただいた言葉で終わります。
「教育を変えるにはどうしたらいいですか?」
「1人1人が自走していくこと」
「学校の中のキーマンを見つけて組織を変えていくこと」
「そうすれば少しずつ変わっていく」
一言一句同じではありませんが、
そのような言葉をいただきました。
「結局何も変わらなかった」
そんな未来にだけははならないように。
たった1人の言葉や行動が波及して何かを変えると信じています。
それが連鎖して未来は少しずつ変わるのだと信じています。
始まったばかりの教育立国推進協議会が、
これからもそのような会になり、
日本を変えていくことを願っています。
教育立国推進協議会 第二分科会書記
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
