
非認知能力特集その6 自分自身を受け入れ、自分に優しくする「セルフ・コンパッション」
第6回の今回は、自分自身を受け入れ、自分に優しくする「セルフ・コンパッション」というテーマでお送りします。子どもはもちろん、このストレス過多の時代を生きる大人にとっても極めて重要な特性のようなのでぜひご一読いただければ嬉しいです!それでは始めましょう!
コンパッションとは?
困っている人を無条件で助けたいと思う気持ちのこと。その人の考えや行動を肯定し、立場や境遇を理解したうえで、あたたかい声をかけてやること。何の見返りも求めず、ただただ助けたいという気持ちのことを指す。
セルフコンパッションを構成する3要素
1 マインドフルネス
自分の感情(ネガティブなものも含む)をありのままに受け入れる
2 共通の人間性の認識
傷ついている存在に対して、「あなただけじゃなく、他の人も同じような経験をしているよ。」といった内容を認識することで、自己否定から外へと意識を向けさせる。様々な苦難は人類に共通しているものだ、自分だけじゃないという認識をもたせること。
3 自分への優しさ
自分を励まし、優しく包み込むような声かけをする。今現在の、傷ついた自分を受け入れながらも、今回の失敗を教訓として、また次への一歩を踏み出せるような言葉をかける。

セルフコンパッション尺度
セルフコンパッションを提唱したのは、ネフというアメリカの心理学者。彼は、アメリカの仏教寺院での瞑想体験から自分にコンパッションを向けることが自尊感情からの解放につながり、メンタルヘルスの改善をもたらすと考えた。
そして、26項目からなるセルフコンパッション尺度を作成し、抑うつや不安、主観的幸福感といったメンタルヘルスの指標や、自尊感情、自己愛、自己受容といった自己に関する指標との関連性を検討。
以下、簡単な入力で自身のスコアを測れるサイト(無料・個人情報入力不要)です。
サイト内の結果をみてわかるように、セルフコンパッションには困難に対するネガティブな反応もチェックリストに入ります。
①自己批判
自分のダメなところに注目し、自分自身に批判的な言葉をかける。
②過剰同一化
否定的な感情に支配され、頭の中が混乱してしまう。
③孤独感
自分だけが困難に直面して苦しみ、孤立していると感じる。
また、セルフコンパッションが、不安や抑うつ、自己批判傾向、完璧主義とは負の相関関係に、自尊感情や人生満足感とは正の相関関係にあることも示されています。
自尊感情や自己愛とセルフコンパッションとの違い
自尊感情は失敗の経験から低下してしまうことから、自分や他者の評価に依存したもの。
自己愛とは、根拠のない自信をもち、自分を誇大評価し特権意識をもつ特性のこと。自分に優しくするという言葉から、自分が好きな人という印象をもち自己愛とセルフコンパッションとの混同がみられるが全く異なるもの。
セルフコンパッションとは、失敗をしてボロボロの状態になったとしても、そんな自分の良いところにも悪いところにも、ともに目を向け、優しい気持ちを向ける心のもちようのことで、評価や結果に依存せずに自分のやりたいことをやろうとする気持ちの維持につながっていくもの。
自尊感情と正の相関を示すのは、セルフコンパッションが高い人はそれだけ自己の傷を修復できるため自尊感情の必要以上の低下を防ぐことができている可能性があるということ。

セルフコンパッションは甘やかしなのか?
できるだけたくさん食べたいもの。例えばケーキ。1個だけじゃなくて、2個でも3個でも食べたいだけ食べちゃおう!
これは、完全に「甘やかし」です。結果は体重計や健康診断で一撃で判明しますね。
一方、セルフコンパッションでは、自分のことを親しい友人のように捉えます。そして、将来も含めた自分自身のことを大切にした接し方をします。よって上記の例で、食べたい自分にはこんな言葉をかけます。
「おいしかったね。もっともっと食べたいよね。でも身体にはよくないから、また今度食べることにしようよ。君と長く、色々なものを食べて、笑顔になって楽しみたいんだ。」
また、傷ついた悲しい気持ちに寄り添う「憐憫(れんびん)の情」とも異なります。悲しむ気持ちに共感するばかりではなく、自分の良いところや今現在の肯定的な感情にも気づいた上で、否定的な感情も受け入れていくというポジティブな側面があるためです。
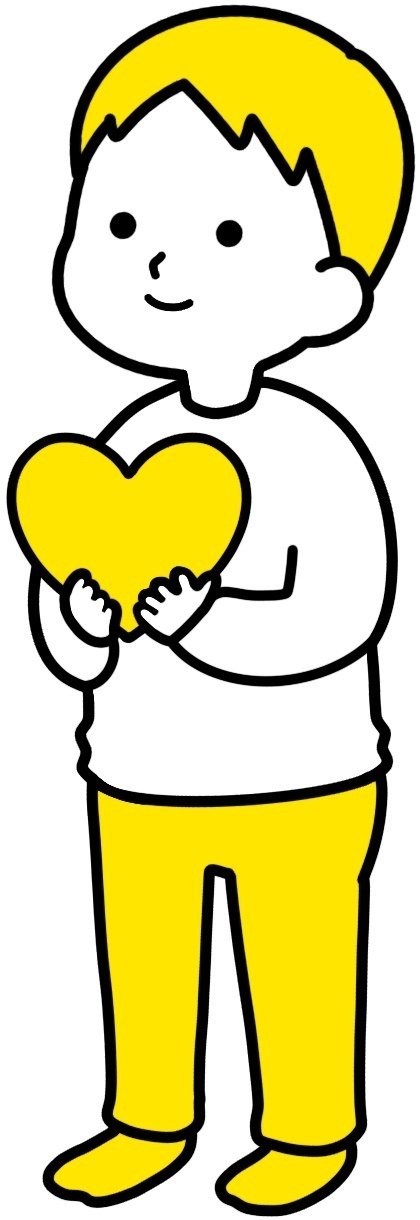
セルフコンパッションが高いことは、学業成績の上昇にもつながる!
2005年の、先ほど登場したネフの研究によれば、セルフコンパッションが高い人は、学業で失敗しても自己否定を熱心には行わないため、失敗を恐れる程度が低くなることや、学業を修められるというコンピテンスが高まることが判明している。その結果、動機づけは高まり、成績の向上を見込めるとのこと。また、セルフコンパッションは内発的動機づけを高める要因になることも明らかになった。他者に言われて動くのではなく、自ら進んで学習したり物事にチャレンジしようとする姿勢をもてることで好ましい結果につながりやすくなるのではないか、ということ。
今の時代に必要なメンタルヘルスにも!
教員の休職者の数の上昇が続いているとの報道が、ここのところ毎年のように流れてきます。今年もそんな報道がありました。
このような環境下において、子どもたちのみならず、先生方にもセルフコンパッションは重要な役割を担う特性だと思います。
自尊感情との関係性はすでに記しました。自尊感情が低い場合(外部から自分を認めてもらえない状況)であっても、セルフコンパッションが高ければ、メンタルヘルスの低下はみられない、という研究結果が出ています。(2015年Marshall et al.)
自尊感情が低ければそれだけ抑うつや不安が高まりやすくなるところを、セルフコンパッションが調整し、抑えにまわるという効果が認められたようです。
セルフコンパッションを高めることは、もはや誰にでも必要なこととなってきているように感じます。

セルフコンパッションを伸ばすためには?
まず前提として、トレーニングによって向上させることは可能です。
以下に4つの方法をまとめます。
1 呼吸のマインドフルネス瞑想
呼吸によって生じてくる身体感覚に気付き、そのまま受け入れる。雑念が浮かんできたら、身体感覚に気付きを戻す。
2 慈悲の瞑想
自分自身や親しい人の幸せや健康を願うフレーズを繰り返す。慈しみの気持ちを、嫌いな人から生きとし生けるものにまで広げていく。
3 セルフ・コンパッション・ブレイク
今現在、困っていることをイメージして、マインドフルに感情に気付き、誰しも経験する苦難であることを認識し、自分に優しい言葉をかける。
4 セルフ・コンパッション・レター
困っている自分自身に向けて、その感情を理解し、誰しも経験することを伝え、優しい言葉をかける手紙を書く。
自分のことを大切に、自身の心のありようを受け入れた上であたたかい言葉を自分自身に送ることで、セルフコンパッションを高めていきましょう!こんなワークは今の時代、最も必要とされることかもしれません。私自身も、あまり高い方ではないことが判明したので、今日から取り組んでみたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今回は第6回として【自分自身を受け入れ、自分に優しくする「セルフ・コンパッション」】についての学びをまとめてみました。
Supportiaでの学びは、こうした非認知能力に関する最新の知見をもとに、教育の責任者と環境設計責任者とが議論を重ねながら学びの環境を整えています。体験へのご参加も随時受け付けておりますので、お待ちしています。下記フォームからご参加いただくことができます。
https://docs.google.com/forms/d/1_qHGcyQbvZ0dWVjZn7xSClh9egprun34p5J8mTHOCPk/edit
また、HPもマインクラフト教室を中心にリニューアルしましたのでぜひ参考となれば幸いです。
