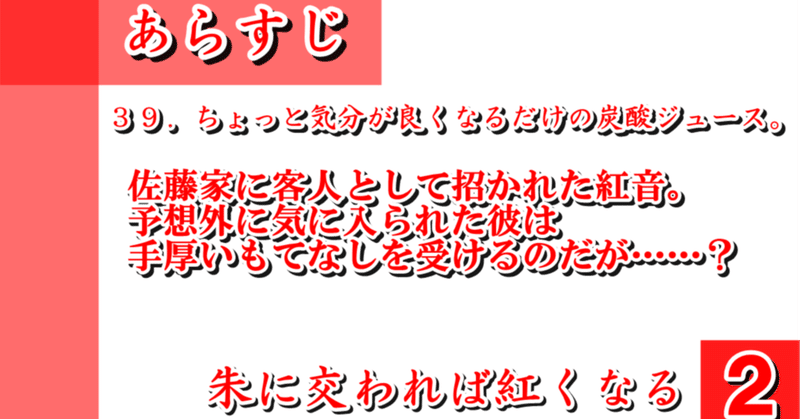
39.ちょっと気分が良くなるだけの炭酸ジュース。/朱に交われば紅くなる2
本編
「ごめんなさいね~狭い上に散らかってて~ほら、陽菜(ひな)ったらあんな感じだから、彼氏なんか連れてきたことなくって~」
「だから彼氏じゃないって言ってるでしょ!いいから手伝ってよ、夕飯の準備」
「え~だって~……せっかく陽菜がこんないい男連れ込んだのよ?この機会を逃すわけにはいかないじゃない~?」
「つっ……!違うわよ!そいつが行く当てが無いっていうから仕方なく」
「と、いいつつもどこか嬉しそうな陽菜なのであった」
「変なナレーションをつけるなー!!」
「はは……」
なんだろう、これ。
なんだと思います?(挨拶)
ちなみに分かる範囲で説明をしておけば、今紅音(くおん)のことを「彼氏」と呼んでいるのは陽菜の母親で、キッチンの方から、リビングにいる紅音と母親に怒鳴っているのが陽菜である。
その服装は先ほどから全く変わらない。部屋の明かりで露になった、つぎはぎのあるジャージに、赤い縁の眼鏡。
金髪と声のおかげで紅音はかろうじて佐藤陽菜として認識が出来るが、これで髪を黒く染めようものなら完全に別人である。なんならウィッグなんかでもいい。元の印象が強烈なだけに、地味な見た目にするだけで印象が全然変わってしまうだろう。
「それにしてもどうしたの~?行く当てがない、なんて~」
「それは……」
困った。
行く当てが無い。
確かにその表現はある意味では的を射ている。事実、紅音は先ほどまで駅前で考え込んでしまっていたわけだし、家には戻れない以上、どこか行く当てを探さねばならなかったのは確かである。
しかし、もし仮にそうだったとしても、別に全く行くところがないわけではない。
それこそ駅前にはネットカフェだってあるし、朝霞(あさか)や、葵(あおい)の家を頼ってもいい。
葵の家は西園寺家のすぐ隣なので、あまりいい選択肢ではないかもしれないが、それもで家にそのまま戻るよりは間違いなくましである。
従って、全くどこにも行く当てがなく、途方に暮れていた、というわけではないのもまた、確かなのだ。
「ちょっと色々ありまして。まあ、幼馴染のところにでも行こうかなとも思ったんですけどね」
嘘だ。
葵の家なんて選択肢は思い浮かばなかったはずである。
そもそも“あの家”に近づくこと自体、考えなかったはずなのだ。
ただ、そんなことを知る由もない陽菜の母は、
「幼馴染がいるの~?男?女?」
「えっと……女ですけど」
それを聞いた彼女は途端に慌てるようにして、
「大変よ陽菜!幼馴染の女の子がいるんですって!これは強敵よ!」
そこまで言ってから、今度は紅音に、
「西園寺(さいおんじ)くん~?」
「は、はい」
「私、陽菜の母で、佐藤文(ふみ)って言います~。覚えにくいときは「ママ」か「お母さん」って呼んでくださいね~」
覚えにくいとき、の意味が分からない。
そもそも「ママ」と「文」は音の数が一緒だし、「お母さん」に至ってはその方が呼びにくいまである。
仮に「文さん」という呼び方と比べるにしても、なお一文字分のディスアドバンテージがある。どうして覚えにくいからそっちで呼ぶと思ったのか。それは文が言わせたいだけではないのか。
ドンッ!
「手伝って」
叩きつけるようにサラダの乗った器をテーブルに置く陽菜。
その眼光はまっすぐに文を睨みつけていた。
ただ、文はというと、
「はぁい」
特段ひるんだ様子もなく、立ち上がり、
「それじゃ、ゆっくりしててね~」
と、紅音に、手を振って、陽菜と共にキッチンへと消えていった。
なんなんだ、あれは。
◇
「そうなのよ~この子ったら、ほら。見栄っ張りだから~」
「分かりますよ。ほら、ハリネズミってあるじゃないですか。あれみたいな感じですかね」
「紅音くん、例えが上手~」
「そうですかね?それなら良かったです。あ、お酒、つぎましょうか?」
「あら、いいの~?それじゃあお願いしようかしら~」
「ええ、お安い御用です。よっ……と」
「ありがと~」
「……………………」
「どうした、佐藤、食べないのか?」
「陽菜、お腹すいてないの~?」
「…………なんでそんな仲良くなってるのよ」
なんで、と聞かれても困る。
あれから少し後、陽菜たちの作った晩御飯が完成し、食卓へと運ばれ、無事に夕食という運びになった(なぜか紅音は客人扱いで、終始もてなされていた)。
そして、実際に食事をする段になると、文から紅音への質問責めが待っていた。
「陽菜とはどういう関係なの?」
「出会いは?馴れ初めは?」
「正直に答えてくれていいわよ、もうヤッたの?」
「あの子のどこが気に入ったの?あんなに断崖絶壁なのに」
とまあ、こんな具合に、質問がぶつけられていったのだ。紅音もはじめのうちは困惑したし、やりとりを見ていた陽菜からの妨害も入ったりしたのだが、
「なんか、気が合っちゃって」
なんか気が合った。
そうとしか言いようが無かった。
一応一児の母親であり、いろはとそこまで年齢が変わるわけでもないはずなのだが、こうも印象が違うのだろうかと驚いてしまう。
話している感覚は親よりはむしろ友人、いろはよりは葵に近い感じがする。良い意味で親しみやすさがあった。
そんな回答が不満だったのか、陽菜は手元にあった缶飲料に手を付けて、グラスに注いだ上で、一気飲み、
「え、おい、それって」
「……なに?」
「…………なんでもないです」
さもありなん。
そもそもこの部屋にある飲み物は、冷蔵庫に常備されている麦茶を除くと、ほぼ全てがアルコールの入ったものであり、未成年が飲んではいけないものであり、つまるところ、陽菜の行為は、良い子には絶対真似をしてほしくないものなのである。陽菜に関しては既に手遅れだが。
基本的にアルコールへの耐性は血筋であり、親が強ければ子も強いことが多い。そのため、既にそれ相応の量を飲んでいるはずの文と血が繋がっている陽菜も、それなりに強いのではないかと思っていたのだが、
「大体ねえ、あんたは私が見つけなきゃ外でそのまま夜を明かすことになったんだからね~……感謝しなさいよ~」
プシュッ!
ぐびぐびっ。
駄目だこりゃ。
こうなってしまったらこちらの話など聞かないのではないか。
紅音は文に、助けを求めるように、
「いいんですか。あれ?多分アルコール入ってるやつですよ?」
「そうよ~陽菜ちゃんは偉いの~こんないい男を連れ込んできたんだから。よっ、玉の輿!」
「ははは…………」
駄目だこりゃ、パート2。
どうやらこっちもすっかり出来上がってしまったらしい。
2人の酔っ払い(話を聞かない)対1人のシラフ(紅音)。
対戦結果など目に見えている。しかも無理やりお暇するわけにもいかないときた。今から駅前のネットカフェに行って、もし万が一入れなかったりしようものなら、いよいよ行く当てがない。流石に外で一夜を過ごすのはごめんである。四月とはいえ、夜はまだまだ冷える。
そんなわけで、
「そんないい男でもないですよ。ほめ過ぎです、ほめ過ぎ」
適当に相手をすることにした。この出来上がり具合だ。そのうち酔いつぶれて寝るだろう。
まずは文が、
「そんなことないわよ~いい男じゃない。きっと股間にも良いものを持ってるんでしょ?このっ、このっ」
そんなことを言いながら紅音の股間をつんつんしようとする。それを見た陽菜が、
「こらぁ~何してんの~。それは私のなんだからとっちゃだめ~」
「私の!?」
衝撃発言が飛び出すも本人は至って真面目に、
「そうよ~私が見つけたんだから、お母さんには上げないもん」
と、いいつつずりずりと紅音の元にすり寄ってくる陽菜。やがてその距離は縮まり、腕に抱きついてくる。
「あの、佐藤さん?」
「陽菜」
「……佐藤さん?」
「陽菜」
「陽菜……さん?」
「なあに?」
「これはなんですか?」
そう言いつつ右腕を軽く上下させる。すると陽菜は自慢げに、
「ふふん。当ててんのよ」
正気か?
別に胸の大小で人を判断したりはしないつもりだし、そこにフェチシズムを持っているつもりはないが、よくその断崖絶壁みたいな胸で「当ててんのよ」とかやろうと思ったな。素面に戻ったときに記憶が残ってたら悶絶もんだぞ、これ。
そんなやり取りを見て何を思ったのか文が、
「あ、私もやる~」
むにゅっ。
紅音の左腕に何やらとてつもなく柔らかいものが当たる。間違いないこれは、
「当ててんのよ~」
そんな気軽な口調で言っていいものではない。
これはあれだ、一種の暴力だ。
血が繋がっているとは思い難いレベルの戦力差を持ったそれは、男を篭絡するのには間違いなく有用であり、きっとそれを使って数多の男の視線を釘づけにしてきたはずだし、なんなら貧乳派でも、この一撃で己の性癖と、それまでの人生で巨乳のことを「はっ、あんなものは脂肪の塊だろ」と馬鹿にしてきたことを後悔し、懺悔してしまうくらいの威力がありつまるところ、
「あ~駄目だって。これは私の~」
ぐいっ。
惜しい。
残念ながらこちら側からは一切の弾力が感じられない。いっそのこと清々しいくらいのそれは、きっと一部の金髪ツンデレ貧乳好きからは絶大な支持を受けること間違いなしの、
「いいじゃない~お母さんにも貸してよ~」
むにゅっ。
いかん。
こっちはいかん。
なにがいかんのかって、その弾力が一体何によるものなのかは最早見るまでもないことである点であり、それはつまり、頭が現在の状態をきちんと理解しているということでもあり、その思考と興奮はいくら頭の中で素数を数えて気持ちを落ち着かせようとも、動かざる証拠として顕在化してしまうことである。端的に言えば、体は実に正直だって話。
流石にこのままではまずい。今はまだちょっとした戯れで済んでいるし、記憶が残っていた場合は陽菜が丸一日悶絶するくらいで済むかもしれない。しかし、ここから先に足を踏み入れてしまえば、後戻りが出来ない。いくら手招きされようと、そこが桃源郷に見えようとも、踏み越えてはいけない一線がある。ポイント・オブ・ノーリターンなんて言葉もある。こんな時に使うものではないけれど。
そんなわけで、
「ちょっと、流石にこれは不味いですって!」
と跳ねのけようとしたその時、
「…………ぐぅ」
「ぐう?」
紅音が視線を向けるとそこには、
「…………寝てる」
実に幸せそうな顔で寝ている陽菜がいた。そして、
「もう、そんな大きくして……」
反対側にはやはり幸せそうな顔をして、とんでもない寝言を言う文がいた。
「もう……そんな大きいのが入るように開発はしてないわよ~……」
何が?
そんな疑問はとてもではないがぶつけることが出来なかった。例えシラフだろうと、どんな答えが返ってくるか分かったもんじゃない。
関連記事
・作品のマガジン
作品のマガジンです。目次や、あらすじなどはこちらからどうぞ。
・カクヨム版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
