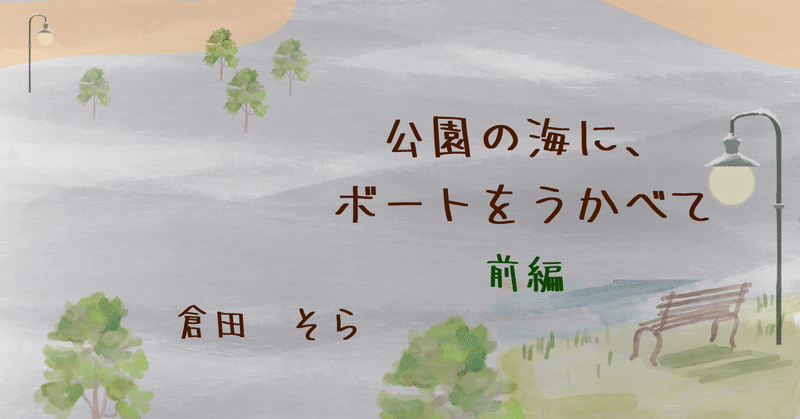
【短編小説】公園の海に、ボートをうかべて 前編
すぐ向こうに見える住宅や道路は、いつもと何の変わりも無かった。公園の中だけが箱庭のように、小さな海になっていた。
大きさは池のようでもあったが、しかし海だった。その証拠に潮の香りがしたし、打ち寄せる波は、海そのものだった。(本文より)
夜の住宅街はとても静かだ。
真冬のしんと空気の冷える日、星がいつもより美しくはっきりと見える夜は、特に静かに感じる。そんな夜にはいつもの見慣れた住宅街でも、見知らぬ異国にいるような不思議な感覚に捉われる。
恭介は、二十三時まで開いている本屋にいた。
自宅近くのバス停前にあり、一階は本屋、二階はレンタルDVD屋になっていて、店舗は割と大きかった。
恭介は一階で、特に興味もない雑誌や文庫本を立ち読みしたりして、のろのろと時間を潰していた。
店内のスピーカーから「蛍の光」が流れ始める。ふと気付くと恭介は最後の一人になってしまった。レジを閉めるジジジジ…という甲高い音が辺りに響いている。
店員の迷惑そうな視線を感じ、さすがにもう粘ることが出来ないので、恭介はとりあえず欲しくも無い週刊誌を一冊買った。
「ありがとうございましたー」
若い男性アルバイトが、乾いた声で言った。
恭介は週刊誌を脇に抱えると、自動ドアを出た。
「うわ…」
室内の暖かさに慣れてしまった体に、冷え切った空気が鋭く突き刺さる。
その日、予定されていた会社の忘年会が急に延期になった。恭介は残業をせず参加する予定だったので、思いがけず早く家に帰れることになった。
恭介は都内の印刷会社に勤めていた。
普段はかなりの激務で、遅くまでの残業は当たり前、休日も出勤することが多い。いわゆるブラック企業だった。
学生時代からの友人たちは結婚したら太ってしまう者がほとんどだったが、忙しすぎる恭介は結婚してからも太る暇も無く、ひょろりと痩せていた。
三歳になる娘と八ヶ月の息子がいる。子供のためにと二年前に一戸建てを思い切って購入した。
三十年のローンが残る小さなマイホーム。
三十三歳の恭介の給料では、駅からかなり離れたところが精一杯だった。
休日はもちろん家族サービスで、あちこち出掛けなければならない。それはそれで楽しくない訳ではないのだが、たまには何十時間も、いや何日も眠り続けてみたいと思う。
「今日は早く帰れる。いつもは眠ってしまっている子供達にも会えるし、家事を手伝えば妻もきっと喜ぶだろう。たまっている録画も観れるし、ゆっくり風呂にでも入ろう。
それから久しぶりに早寝して、明日の朝はすっきり目覚めよう。」
そんなふうに「コトバ」で思った。
そのコトバたちは恭介の意識の遥か上のほうでつらつらと、電光掲示板のように流れていっただけだった。
駅からバスで十五分。最寄のバス停までは真っ直ぐ帰って来た。
しかし身体は物凄く疲労しているのに、恭介はその日、どうしても家に足が向かなかった。最近、朝目覚めても全然疲れが取れないでいた。体が鉛のように重い。
睡眠時間が短いこともあるが、眠ることで返って疲れているかのようだった。
バスの時間ぎりぎりに死人のような白い顔で起き出し、コーヒーだけ飲んで重い足取りで家を出る。妻は「大丈夫?」と声をかけるが、子供達の世話が大変でその片手間に、といった感じだった。
妻のストレスだって溜まるし、育児を手伝いたい気持ちはあるが、恭介にはどうにも、その余裕がなかった。
妻や子供達だって大切だし、夫、父親として家族は守りたいと思う。
でも。
時々思う。何もかもが、ああ面倒くさい。
本当に、面倒くさい。
だって三十年。あと三十年は絶対に働かなくちゃならないんだ、俺は。
灰色の冷たいアスファルトの一本道を砂袋でも背負いながら、どこまでもどこまでも歩いて行かなければならないんだ。
どこにも逃げ場が無い。
ガラガラガラガラ…キィ…ガシャン
しばらく自動ドアの前で立ち止まっていた恭介の後ろで、本屋の店員がシャッターを下ろし、辺りは急に薄暗くなった。
恭介は週刊誌をカバンに仕舞うと、コートのポケットからスマホを取り出した。
画面を立ち上げると、ラインの通知が来ていた。
最近は妻や仕事の関係者以外からは、ラインもほとんど来ない。
学生時代の友人のSNSをのぞくことはあるが、連絡はあまり取っていなかった。自分から何かしている訳ではないくせに、それでも通知マークを見ると恭介は何となく期待してしまう。
今日は忘年会だと思っている妻からは、ラインは入っていなかった。代わりに入っていたのは、何かのキャンペーンで登録したビール会社の宣伝メッセージだった。
「んだよ…」
恭介は理不尽にがっかりして、電源を切ってしまった。
スマホの明るい画面を暗い場所で眺めていると、目潰しを食らったように辺りがあまりよく見えなくなる。恭介は少しの間目を細めていたが、顔を上げて家へと続く登り坂をちらっと見た。
少し迷ったが、恭介はスマホをカバンに放り込むと、結局そのまま斜め向かいにあるコンビニに入った。
「いらっしゃいませ」
店員が、あまりやる気の無さそうな声で言った。
店内は数名の客がいた。二十四時間のコンビニは、真夜中でも昼間でも明るさはさほど変わらないのに、何かが決定的に違う気がする。
光々と明かりがつき、そこだけの特殊な時間が流れる。
入り口横の雑誌の棚に近寄り、もう嫌というほどした立ち読みをしようと思ったが、ほとんどの雑誌が開けないようになっていた。
仕方なく端から順番に表紙を眺めていたが、恭介の意識はそこには無かった。
書籍棚の向こうのウインドウに、恭介の顔が映っている。
二十代の頃に比べて骨張ったような気がする。目は使い過ぎてクマができ、落ち窪んでいた。疲れ切った顔は自分ではなく他人を見ているようだった。街でこんな人を見つけたら気の毒に思うだろうな、と、恭介は他人事のように思った。
恭介が再び、書籍棚に目を移そうとすると、突然赤い光がガラスに映った。
それはバスの最終便を示す光だった。
恭介の家の地域では、終バスは行き先の表示が嫌な感じの赤色になる。バスは会社帰りのサラリーマンやOLを数人吐き出すと、大きなエンジン音を響かせて走り去った。
人々はすぐにそれぞれの家の方向に散り、足早に歩いて行った。
それを見て恭介は深いため息をつくと、レジ前にあるミントのタブレットを一つとり、代金を支払った。
外は更に冷えてきていて、恭介はコートの襟を寄せた。
「さむ…」
思わず声に出してしまう。朝はマフラーを巻いて出たのだが、会社に忘れてきてしまったのだった。
コンビニや本屋があるバス通りから右に曲がると、住宅街へ続く道になる。この辺は山を切り崩して作られた新興住宅地なので、家までずっと登り坂だった。
電車に一時間、あまり本数のないバスに十五分。やっと地元のバス停までたどり着いても、登り坂を十分程歩く。電車が遅延することも少なくない。バスが目の前で行ってしまうこともよくある。
そんな時や疲れて帰って来た日は、何でこんなに不便な場所に家を買ってしまったのかと、恭介は本当にうんざりした気持ちになった。
道には恭介一人だった。
登っていくとすぐに、辺りは静けさに包まれる。バス通りを通る車の音も遠ざかり、そんな中たった一人歩いていると、全世界に一人ぼっちのような気分になる。
吐く息が白く立ち昇り、息をすると鼻の奥が痛かった。あんまり寒いので、さすがに恭介の歩も速くなった。
少し登っていくと三差路がある。その三差路の右側の角は公園になっていた。中央にミニサッカーくらいは出来そうな広さのグラウンドがあり、それを丸く囲むように、コンクリートタイルで歩道のようなものが作ってあった。
右に曲がった方に恭介の家があるので、その公園を突っ切って行くと、少しだが近道になる。
公園の裏側は低い山になっている。恭介はいつものように道を逸れ、山の斜面に作られた細い階段を登った。その階段を登りきると公園が見え、そこが入り口の一つになっていた。
コンクリートの階段には落ち葉や小枝が山のように溜まっていて、恭介が歩くと小枝のパキパキ折れる音が聞こえた。雑草が段の細い隙間に、無理やり体をねじ込むように逞しく生えていた。
背中を丸め、自分のつま先と雑草を見つめながら歩く。
そのときだった。
ザザ…ザ…
「なんだ…?」
ラジオの雑音のような音。階段を登るごとに大きくなってくる。
恭介は立ち止まり、耳を澄ました。
ザザザ…ザザ…
誰かが公園の中でラジオでも聞いているのか?
いやしかし、ラジオとは違う。
ザザザザザ…ザザ…
そして、匂い。
音といい匂いといい、まさにこれは…でもまさか…そんなバカな…。
ザザザザザ…ザザ…ザザザ…
そして。
「……!!!」
階段を登りきった恭介は、目を見開いた。
足元には、白く砕ける「波」が打ち寄せていた。
(中編に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
