高山宏「殺す・集める・読む 推理小説特殊講義」
トリックの新奇さや謎解きの完成度、動機のリアリティといった、通常の推理小説を語るイディオムとは別の角度、すなわち「なぜ推理小説というジャンルは19世紀末に確立したのか」を文化史、近代史の視点から読み解こうとした野心的な推理小説論です。
まず語られるのはシャーロック・ホームズ。「ヴィクトリア朝世紀末の感性と切り離してはドイルの推理小説は絶対に成り立たなかった」というところから論が始まります。
そこで高山さんが提示したのは「ホームズのいないホームズ作品というものを考えてみると、残るのは確かに世紀末的としか言いようのないビザルリー(異常)とグロテスク(醜怪)の趣味だけである。」というテーゼです。少々驚かされますが、高山さんは次々と死体描写の場面を引用しこれを裏付けていきます。興味がある方はぜひ手元のホームズ作品を繙いてみてください。
「犯罪の論理が要求するところ異常に殺し方に凝る描写のフェティシズムをわれわれは見ているのだ。人間をたえず鳥獣や昆虫にたとえるドイル一流の悪趣味なメタファーがここでも縦横に活かされている」という指摘に私はなるほど、と膝をうちましたが、皆さんはどうでしょうか。
高山さんはさらに論を進め、死の美学を直接的に盛り込むことができる推理小説というジャンルは世紀末美学の表現にうってつけの世界だったと述べています。そこから当時のヴィクトリア朝時代が、コレラ、チフス、天然痘、猩紅熱といった悪疫流行が繰り返された、ネクロポリス(共同墓地)的世界であり、死の意識が蔓延し、室内へ逃避するヴィクトリア朝のどんづまり状態の時期に出現したホームズ作品は〈被害者の殺害という形でとりこんだ死を、因果律と目的論の「鎖」(ホームズ愛用の言葉だ)で説明しさることによって馴致する悪魔祓い装置として働き、かつ自らは死をタブーとする室内文化の中に、いわば必ず結末があり解決がつくという条件の下に死を一時の阿呆王として許容するという、死の祝祭装置として機能した。〉と続けているのですが、ここで説明されているヴィクトリア朝の社会が、現在の私たちが置かれている状況に近似していることに驚かざるを得ません。
「古典」だったはずのホームズ作品が、時を超えてかつてないリアリティをもって迫ってくる世界に私たちはいるのです。
論はまだ続き、「俯瞰」の視線の問題や、犯罪を収集する「標本」としての問題、世界を「読む」ことの問題が綿密に語られていくのですが、ここでは割愛したいと思います。
この本ではホームズ以外にも、クリスティやチェスタトンから江戸川乱歩や小栗虫太郎に至る作品が広くて深い視点で語られています。
推理小説のファンだけではなく、広く近代の文化史に関心がある方にも手に取って欲しい、スリリングな一冊です。
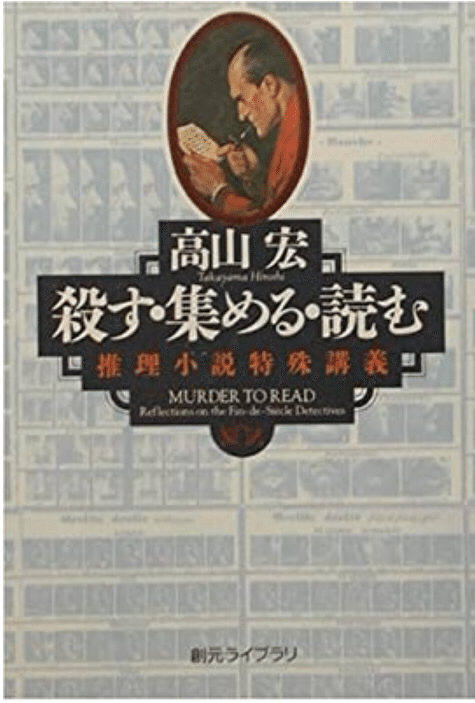
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
