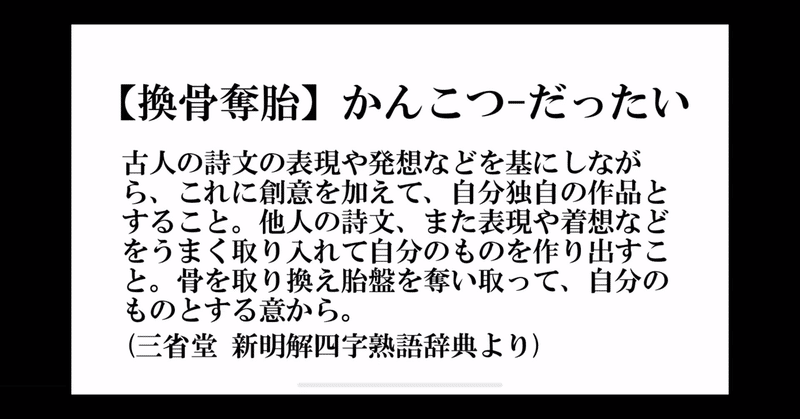
古から伝わる創作術「換骨奪胎」
今回はこちらの動画のテキスト版になります。
こんにちは、染島です。16年間、様々な作家に影響を受けながら小説を書き続けてきました。
今日のテーマは、「換骨奪胎(かんこつだったい)」です。長く創作に関わる人以外だと聞きなれない言葉かもしれませんが、これはタイトル通り古くから伝わる創作術です。現代でもストーリーラインを考える際に有効な手段となります。ぜひ覚えておいてください。
というわけで、今回はまず「換骨奪胎とは何か?」という話から、次に小説の構想を練る上での扱い方を解説していきます。
①換骨奪胎とは
まず、この「換骨奪胎」という言葉について、辞書で引くとこのように書かれています。
【換骨奪胎】
古人の詩文の表現や発想などを基にしながら、これに創意を加えて、自分独自の作品とすること。他人の詩文、また表現や着想などをうまく取り入れて自分のものを作り出すこと。骨を取り換え胎盤を奪い取って、自分のものとする意から。(三省堂 新明解四字熟語辞典より)
この説明文からも何となくわかるかと思いますが、換骨奪胎という四字熟語は古くは中国の漢詩の世界から生まれた言葉です。元々は12世紀の黄庭堅(コウテイケン)という詩人が唱えた作詩の技法になりますが、これは小説でも応用することが可能です。
小説風に考えるなら、「物語の骨格となるストーリーラインは既存の作品を参考に、肉付けの部分を変えてオリジナリティを出す方法」と言い換えると、よりしっくりくるかもしれません。
では、実際に例を出せばわかりやすいと思うので、桃太郎を例にして換骨奪胎してみます。
まず、桃太郎の大まかなストーリーラインは、
「昔、桃太郎は仲間のイヌ、キジ、サルを引き連れて鬼ヶ島へ鬼を退治しに行った」
という流れになります。
では、この物語の骨格部分を抜き出すと、
「昔、主人公が仲間を引き連れて悪の本拠地へ敵を退治しに行った」
こんな形になります。
さらに、この骨格を元に新たな肉付けを加えていくと、
「新暦1405年、勇者は仲間の戦士、魔法使い、僧侶を引き連れて魔王の城へ魔王を退治しに行った」
このように、換骨奪胎によって桃太郎は王道異世界ファンタジーに様変わりしました。
換骨奪胎の流れはこれで掴めたかと思いますが、実際にやってみようとすると最初からノーヒントでは意外と難しいです。なので、換骨奪胎のコツについてさらに細かく掘り下げていきます。
②換骨奪胎のコツ
ここから、換骨奪胎の具体的な方法について解説していきます。
1.元となる作品をざっくり要約
換骨奪胎をするにあたり、まずは元になる作品をざっくりと要約してみましょう。先ほど例で出した桃太郎のように、1行でまとまるのが理想です。
いきなり1行で物語をまとめるのは難しいかもしれませんが、これにもコツがあります。それは、「4W1H」を元にまとめるというやり方です。
ではこの4W1Hが何を指すかと言いますと、
いつ(when)
どこで(where)
誰が(who)
何を(what)
どうした(how)
という5つの疑問形を指します。この5つの答えとなるような形で要約すると、わかりやすくまとめることができます。
2.要約した文の4W1Hから具体的な名詞を抜き取る
次に、この要約した文の4W1Hから具体的な名詞を抜き取っていきます。
桃太郎の例で言うと、「桃太郎」を「主人公」に変えて、「鬼ヶ島」を「悪の本拠地」とするような具合です。こうして出来上がった抽象度の高い文が物語の「骨格」にあたります。逆に言えば、ここで抜き取られた具体的な名詞というのが物語の「肉」の部分にあたるわけです。
3.4W1Hに別の名詞を入れていく
続きまして、この「肉」の部分に注目していきます。骨格部分はそのままに、新たな肉付けとして4W1Hに全く別の名詞を入れて変えていきます。
引き続き①の桃太郎の例を使って解説します。例えば「いつ」の部分は昔になりますが、ここを変えて架空の暦「新暦1405年」にします。「どこで」の部分を日本から中世ヨーロッパ風異世界へ、またボスの待つ舞台を鬼ヶ島から魔王の城に置き換えます。そして「誰が」の部分で桃太郎とイヌ、キジ、サルは勇者と戦士、魔法使い、僧侶となり、「何を」の部分で桃太郎の鬼の部分を魔王に変えていきます。「どうした」の部分にあたる「退治しに行った」は変えずにそのままとします。
こうして、「昔、桃太郎は仲間のイヌ、キジ、サルを引き連れて鬼ヶ島へ鬼を退治しに行った」という物語の話は「新暦1405年、勇者は仲間の戦士、魔法使い、僧侶を引き連れて魔王の城へ魔王を退治しに行った」という骨格は同じでも全く異なる物語ができました。
4.3でできた文を元にストーリーを広げていく
ここまでできたら、後は3のパートで完成した文をもとにストーリーをさらに細かいところまで広げていきます。
この部分についてはプロットの領域になってくるので、過去のプロットの作り方について解説した動画やnoteを参考にしてみてください。
まとめ
今回は換骨奪胎というストーリーラインの作り方を紹介しました。これは古くから使われ、現在でも有効な技法として伝わっているやり方です。
それでも、このような方法を実践しようとすると「それってパクりなのでは?」と考えてためらってしまう人がいたり、特に創作に触れたことのない人からは直接同じような指摘がくることもまれにあります。
しかし、そういう考え方や意見は気にしなくてOKです。
そもそも、今の時代は誰でも気軽に小説や漫画を書いてweb上で公開できる時代です。毎日膨大な作品が生まれている中で、もはや完全なオリジナルは存在しません。また、自分も含め現代の作り手は全て何かしらの作品に影響を受けているため、作り出すことも当然不可能です。
だから物語を創るなら、それは既存の作品を組み合わせて、その中から生まれた化学反応でオリジナリティを生み出すしかありません。そのための創作術として、この換骨奪胎は非常に役立つツールになります。
換骨奪胎を使いこなして、是非自分だけのオリジナリティを見つけ出してみてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
