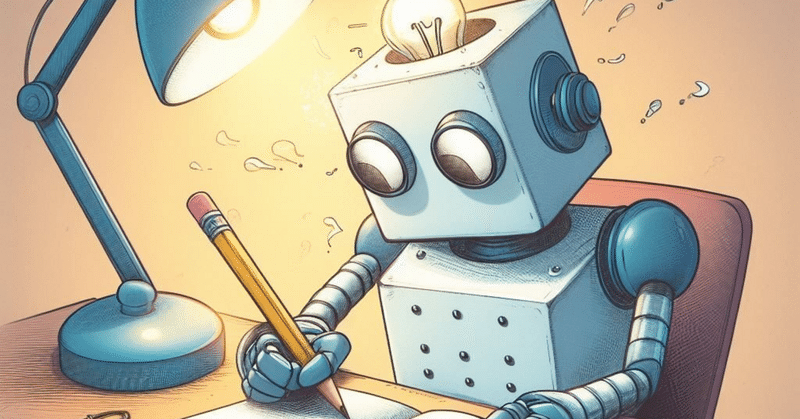
【エッセイ】ラジオを聞いて考えたこと ~人類と生成AIの仁義なき戦いを通じて~
プロフにある通り、これといった趣味がない私の、数少ない趣味らしいものに、「ラジオ聴取」があります。私はラジオを聞いて、仕事でパンパンになった頭をマッサージしてリラックスさせます。お酒を飲みながら、とりとめのない会話(パーソナリティーの方々すみません!)とかに耳を傾けると、カチカチになった頭がほぐれます。
聞く番組は大体決まっています。「絶対聞くもの」と「時間があったら聞くもの」、「お気に入りの聞くものがないときに『つなぎで』聞くもの」というように自分の中では分かれていて、ほとんどはradikoで聞いています。
ラジオとの付き合いは、途中ブランクがありましたが長い方でしょうか。中学生のときに、ニッポン放送の「オールナイトニッポン」を聞き始めて夢中になり、大学受験まで聞いていましたが、大学生になると聞かなくなりました。しかし、きっかけは忘れましたが、社会人になって30代に入ってからまた聞くようになりました。きっと「ながら作業しやすいから」でしょう。テレビや動画だと、それはなかなか難しいです。
先週もTBSラジオの「アフター6ジャンクション2」を聞いていたのですが、5月8日(水)の回は面白かったですね。私はその日電車に乗り帰宅しながら聞いていたのですが、何度か笑いそうになりました。しかし、マスクをしていて助かりました。にやけた顔でいたら、周りの乗客から不審者に見られかねません(あぶねー!)。
この回は、前半のビヨンド・ザ・カルチャーのコーナー枠で、「つまらなイイ話 ザ・ファイナル!マシンvs人類の最終戦争、つまらなイイWars勃発」というのをやっていました。これは「つまらなイイ話」というミニコーナーの最終回で、拡大版でやっていたのですが、私はこのコーナー、何気に好きでした。
一聴すると「つまらない」けどこれは実は「イイ話」なのではないか、という趣旨のメールを募って紹介するという趣旨のコーナーなのですが、これが絶妙なラインでどれも「つまらない」(笑)。でも、何て言うんでしょうか、こう普段面白いことをメールで送るハガキ職人さんが「あえて」腕によりをかけて「つまらなくしている」ので、逆にシュールな内容になり一周回って面白いと、少なくとも私は思いました。でも、パーソナリティーの宇多丸さんが毎回と言っていいほど突っ込んでいたように、そのほとんどはつまらないだけで「イイ話」ではないという、そんな不思議なコーナーでもあります(笑)。
で、今回はコーナーの最終回ということで、普段と趣旨や趣向を変えて(なぜ変えたかはradikoやYouTubeで放送を聞いてください)、リスナーさんが生成AIで作ったメールか、もしくは自ら(人間が)書いたメールか、どちらかを送ってくるので、それがAIが作ったものか、人間が書いたものかをパーソナリティーの宇多丸さんとパートナーの宇内梨沙さんが当てるというものでした。
これがね、なかなかわからないんですよ。リスナーもばれてはいけないから、あのAIの「文法的には間違っていないし、論理的に矛盾はないけれど、回りくどく不自然で落ちもない、つまらない文章」をあえて真似て、AIに擬態して書くので、見破る(聴き破る?)ことが、当初お二人もできませんでした。(しかし、段々慣れてきて、後半お二人が見破り始めるのは、逆に「AIを越える人間の可能性」が感じられて笑えます驚きます。)
とても楽しい放送だったわけですが、ただ聞いていて少し考えることもありました。序盤に宇多丸さんが、あるメールに対して「これは、飛躍や破綻がないからAI(が作ったの)だろう。」というようなことをおっしゃっていました。このときに、これは、これから始まる(始まっている)AIと共存する社会の中で生きるヒントになりそうだと思いました。
私は常々、自分の仕事(中高生に小論文などの書き方を教える仕事)はそう遠くない未来でなくなっている、と考えていました。人間の手計算が計算機やコンピュータにとって代わられたように、やがて論理的な文章を作ることはAIにとって代わられるはずだと。論理的な文章は、文法などの諸規則や論理法則の集積によって構築されるものです。そうしたものの作成は、まさにAIの得意とするところであり、人間のようなミスをすることなく文章を構築できるはずです。
未だに、世間では「ビジネス文書」や「セールス文書」の作成術の本が出ていて、出すとそれなりに売れるようですが、それもいずれなくなると思います。文章を書くのが苦手な人が、そうした本を読んで論理的な文章を構築する術を汗水流して(まさに)身に付ける必要はいずれなくなります。そして、それを教える私たちのような仕事も、いずれなくなるでしょう。その代わりに、「これからの人たち」は、そのAIをどう目的に合うように運用するかといったプロンプト(指示出し)の書き方を学ぶ必要が出てくるでしょう。
大分前から、数学教育の場では、「複雑な計算は計算機に任せて、計算力を磨かせるよりも、生徒には数学的思考を身に付けさせるべきだ」と言われていると聞きます。国語教育の場でも、早晩「論理的な文章の作成はAIに任せよう」というようになると、私は考えています。
この放送で、普段から多くのメールを読む宇多丸さんは、「(人間の書いた文章ならば)論理の破綻や飛躍があるはずだ(なのにこの文章にはそれがない)」というようなことをおっしゃっていました。それは、本来破綻や飛躍がないように文章は作成するべきだが、そのエラーにこそ「人間らしさ」や「人間的価値」があって、どんなにAIを真似ても隠し切れずにそれは発露する、ということをおっしゃっているのだと、私は聞いて思いました。私はこのような生成AIの登場した社会と未来に対して、漠然と悲観していましたが、これを聞いて何に対して悲観していたのか、と改めて自分の考えを見直そうと思いました。私が悲観した原因は、失われていく技術に対する、単なるセンチメンタルな郷愁に過ぎなかったと気づかされたからです。
AIの登場によって、私たちは文章を書かなくなるわけでもその書く意味を失うわけでもないのだと、放送を聞いていて思いました。また、AIによって文学や国語学などの人文学的なものが意義を失うわけでもないと考えました。破綻や飛躍を恐れずに書きたいことを書く、「だって人間だもの」。それは今のところAIにはできない、人間にしかできないことであり、そこに、次世代の文学やエンターテインメントなどの新たな可能性が隠されていると、私は思いました。
だから、明日からも、みなさん、note頑張って書きましょう。
…さて、酒飲みながら、今晩もラジオを聞こうか…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
