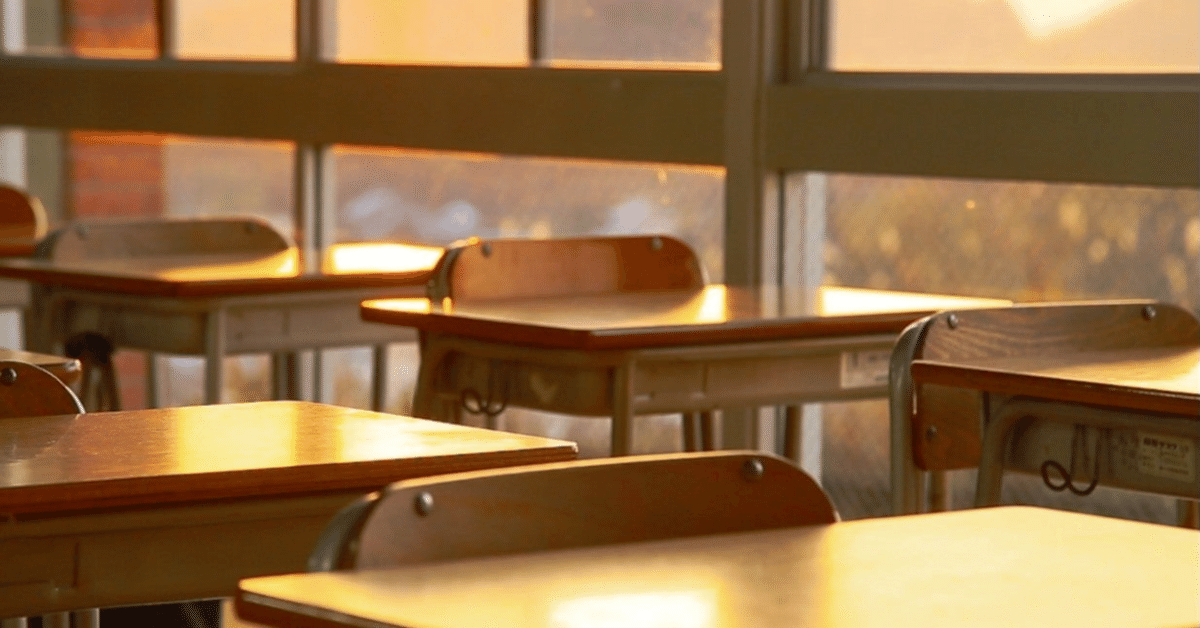
なぜ、自己調整学習理論なのか?
学び方を学び、生涯を通じて学ぶためのスキルと力を身につける。
これは、いっそう不確実性が高まり、より曖昧さが増すであろう社会に生きていくことになる私たちには不可欠な要素です。
ただ、そうはいっても、どのようにしてそのスキルや力を身につければよいのでしょう。
私たちは、おそらくそれを、実際の学習を通して「体験的に」学び取っているのではないかと思います。
ここで言う「学び方」「学ぶためのスキルと力」というのは、「どの問題集を使うと力がつくか」であったり、「どこのポイントを押さえれば試験で点数を取りやすくなるか」などといった、テストの得点につながるテクニックという狭義のものを指しているものではありません。
学ぶということはどういうことなのか、自分自身の学習をどのようにコントロールしていくと成果につながりやすいのか、といった、いうなれば「学びに向かう基礎体力」〈学び続けようという体力〉であり、「学びを調整するスキルや力」〈学びを自己調整する手法〉といった、広義の資質・能力を指しています。
この広義の力は、おそらく多くの人が大なり小なり獲得している力でしょう。そして、それは冒頭触れたとおり成長していく過程で、また学びを通して「知らず知らずのうちに」無意識的に身につけているのかもしれません。
私たちは、ここに意識的に焦点を当て、「意図的」に身につけていくことを目指していくべきなのではないか、と考えています。
多くの方が感じていらっしゃるのではないでしょうか?
学力が高い子たちは、学び方が上手であると。
もちろん、生来備わっている能力の差が学力の高低に影響しているという考え方も成り立ち得るものであり、否定はできません。
一方、仮に生まれ持っての能力を変えることが難しかったとしても、「学び方」はスキルにあたる部分が多く含まれており、トレーニング次第で十分に、後天的にでも獲得できるものなのではないでしょうか。
今後の教育が果たすべき役割のキーは、ここにこそあると考えています。
ただ、ここでもう一度触れておきたいキーワードがあります。それは、「意図的に」ということです。
よくよく考えてみると、人は生まれてからの日々が学びの連続で、一日一日成長しています。
乳幼児は、誰から教わることなく、自分自身で学び、できなかったことがどんどんできるようになっていきます。
それが、小学生になり、中学生になり、高校生になるにつれて、学校での学習において上手に学べなくなっていく人が出てくるのはなぜか?
それは、教科等を通した学習という未知の学びの領域における学び方という「枠組み」を持ち得ていないから、なのではないでしょうか?
「枠組み」を獲得させるために、
定期考査に向けて学習計画を立て、終了後にはふり返りをさせています。 学校行事が終わるごとにふり返りの時間を設けて、良かったことや改善す
べきことを整理するようにしています。
こういったお話を先生方から伺う機会は非常に多いです。
どれも、意味のある取り組みだと思います。
一方で、
その取り組みにどのような意味があるのか?
そうすることによって、どのような力が身につくのか?
その取り組みのポイントや取り組む際に気を付けるべきことはどういうことなのか?
ということにおいて、明確な概念に基づいた「意図」を持って児童・生徒を指導することができていますでしょうか?
あるいは、
学ぶということはどういうことなのか
効果的に学ぶために身につけるべきスキルとはどのようなものなのか
ということを児童・生徒に明示的に示すことができていますでしょうか?
そこに踏み込み、「意図的」に児童・生徒に学び方という「枠組み」を獲得させていくことこそ、これからの教育には必要なこと、そのようにこれからの教育を定義することができるかもしれません。
ここでの学び方という「枠組み」として、非常に参考になるのが、自己調整学習理論という認知心理学に基づく学習理論です。
自己調整学習理論とは、1990年代にアメリカでジマーマンらによって研究が進められた理論で、近年日本でもその有効性が注目されています。
自己調整学習理論では、動機づけ・学習方略・メタ認知に働きかけていくことによって予見(目標と計画を立て)・遂行コントロール(実際に取り組み、その取り組みを調整し)・省察(取り組みをふり返りつぎの計画に活かす)というサイクルを回していく学習者の育成を目指しています。
日本でも、先行研究はだいぶ蓄積されてきており、この理論に基づく実践と、その成果と課題も数多く示されています。
「試行錯誤」は、ベースとなる「枠組み」があると進めやすくなります。その「枠組み」や先行研究から得られている知見を基にして、現状を判断したり改善策を考えたりしやすくなるからです。
主体的学びを科学する研究会では、共同研究校として参画いただいている先生方に、この自己調整学習理論を学んでいただき、それを参考にして実践計画を立て、データを取って検証し、また改善するというサイクル(これこそ自己調整学習のサイクルそのものです!!)を回しながら実践に取り組んでいただいています。
自己調整学習理論の概要に触れたのち、実際の先生方の取り組みを紹介していきたいと思います!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
