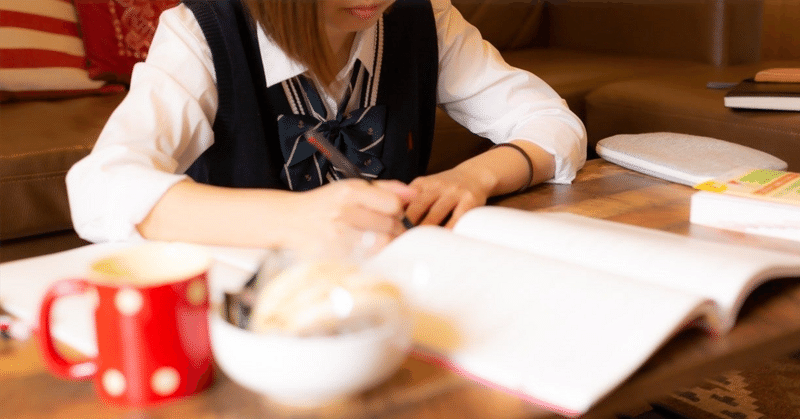
コーチの社会分析 Note【生きる力?・間違いだらけのキャリア教育を解説するシリーズ②】
これからの世界的変化。ICT やAIの普及に伴う従来の仕事の消滅や変質は、等しく万人に及ぶのは誰しも聞いたことがあるでしょう。ましてや人口減少が進むこの日本では、これらの科学技術を積極的に取り入れ、生産性を上昇させ、効率化に取り組むことはむしろ不可欠でした。
キャリア教育にはこうした背景があることは言うまでもありません。
しかし、実際にその進展は世界的に見ても致命傷になりかねないほど遅れており「Society5.0」「第 4 次産業革命」(経済産業省2017)という政府のスローガン。新設されたデジタル庁もその効力に疑問符が付くような実際なわけです。
上記前回の後半からちょっと抜粋しておきました。
つまり、こうした背景の中で
「これからの時代を生きていく子供たちに必要とされる学びは何か?」
ということが可視化、言語化され、具体化される。ここにきちんと落とし込まれていない。説明できる人が極小数なので、今のキャリア教育ではそれぞれが、それぞれの理解で、エビデンスのない好き勝手な自己流を主張しているような状況が発生してしまっています。

先日、僕のSNSに出てきた広告画像ですが、国家資格キャリアコンサルタントに合格した方々が「何が身に着くか?」「どう活かせる?」が分かっていないことを宣伝しています。自分自身のキャリア形成も出来ない。ツールとしてすら使えないレベル。そんな人にキャリア相談をしたとしても、結果は明白です。だから「国家資格??」と揶揄されちゃうんですよね。つまり、この資格試験を作った人々も、本質を理解し、それにふさわしい人という保証(マーケティングにおける商品、サービスでの約束)が出来ていない。そんなことも人々は感じてしまうわけです。
☆大流行の「生きる力」って本当は何だ??
そして、これらの我が国が配布している資料等のもともと(原本)はOECD(経済協力開発機構)に依るものです。情報リテラシーにおいてはこうした原点にあたることは基本中の基本なのですが、これが出来ていない人が多いわけでもあります。
そのOECD「教育とスキルの未来 2030」においてプロジェクトの目的として「各国が以下2つの問いに対し、答を見つけることを手助けすること」と記されているわけです。その問いが、
①現代の生徒が成長し、世界を切り拓いていくためには、どのような知識、スキル、態度及び価値が必要か?
②学校や授業の仕組みがこれらの知識、スキル、態度及び価値を効果的に育成することができるようにするために、どのようにしたらよいか?
であり、そのキー・コンピテンシー(人がその言葉やツールを行動、成果へとつなげていける土台、能力)が、
① 新たな価値を創造する力
② 対立やジレンマを克服する力
③ 責任ある行動をとる力
とされています。はい。正直、我が国の官僚達は、わざわざ元ネタをわかりにくくしているだけ・・にしか見えないのではないでしょうか。
例えば、最近つとに流行っている「生きる力」は文部科学省の学習指導要領等に載ったことで、その切り抜きワードが独り歩きをしている典型でもあります。巷間では「サバイバル能力!」といった自己都合な解釈も目立ち、初心者キャンプに毛の生えたような低レベルなワークや森を歩くだけの自称リトリートを「生きる力」と称している方々も少なくないようです。上記からは、縄文人のように原始的な暮らしで生き抜く力ではないことは明白ですし、文部科学省自体も、その新学習指導要領において「生きる力」を【知・徳・体のバランスのとれた力のこと】と抽象的ではありますが解説しています。
まあ、いずれにしても、これまでの塾や習い事のように、ツールを習得するという「目標が目的化してしまうこと」。それ自体が、新しい時代の学びにふさわしくありません。
つまり、目的は何か?ということを説明できることが不可欠なのです。
自分たちが関わっている相手に対して行っている行動が「どのようにキー・コンピテンシーを育むことにつながっているのか」を説明できなければ、その行動や研修、ワークといったものは、実は中身がまったく伴っていない。そんなことが、ほとんどという結果になることでしょう。
☆Purpose(パーパス・目的)
と、ここまで書いてきて、やはりアンラーンより先にパーパス(Purpose)の話をした方がいいかなと思いなおしました。
詳しくは次回にとしますが、私たちは本当の意味での「目的」と向き合わずに生きてきたことが多いのではないでしょうか?
高校受験や大学受験に合格することは「目的」にはなりません。そこに入学して「私は何をするのか?」の中に本来の目的があります。会社選びもそうです。会社に入ることは目的にはなりません。お金を稼ぐこともまた目的になりません。地位を得ることも同様に目的にはならないのです。
会社に入ったらどうしたいか。
お金が手に入ったら何をやりたいのか。
地位を得たらどのように貢献したいのか。
こうしたその先の未来に「目的」は潜んでいます。
この「目的」を言語化、可視化しないこと。わかっているつもりでわかっていないことを、そのまま進めていくこと。これが、私たちの国の病の一つであるかもしれません。
というわけで、次回に続きます!
ありがとうございます。頂きましたサポートは、この地域の10代、20代への未来投資をしていく一助として使わせて頂きます。良かったら、この街にもいつか遊びに来てください。
