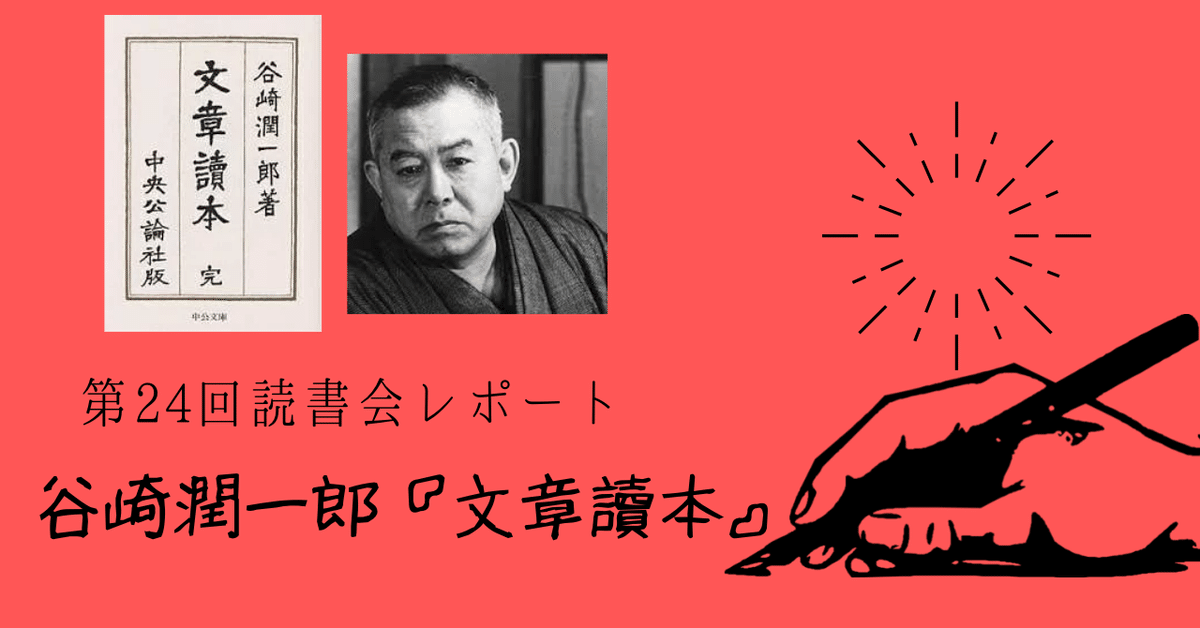
第24回読書会レポート:谷崎潤一郎『文章讀本』(感想・レビュー)
毎年1月は文章について考えよう、をテーマに課題本を決めています。
今回は本棚の肥やしになっていた谷崎潤一郎の『文章讀本』にしました。
読書会で取り上げない限り一生読まないであろう本のひとつ(笑)。
特に谷崎に対してはエロたぬきおやじ(失礼!)のイメージが払拭できず、美しい日本語を操る希少な作家と言われても白い目で見ていました。
でも今回読了してみてまず感じたのは、谷崎の日本語への愛の深さでした。
この本は文章に携わるすべての方に読んでもらいたいなと思ったのでした。
参加者の皆さんのご感想
今回も9名の方にお越しいただき、大いに盛り上がりました!
お久しぶりの方や初めましての方など、これからも常連さん以外も気軽にジャンジャンご参加いただきたいものです^^
(もちろん常連さんも大切です♪)


・読み応えがある
・日本語が流暢
・国語の教科書っぽい
・90年以上前に書かれた文章とは思えない
などなどさまざまな感想が寄せられました~
国文学科を専攻しない限り触れない世界?
まずはじめに気付かされたのは、谷崎が本書で伝えたかった内容は、国文学科を専攻しない限りなかなか触れることのない世界だということです。
作家達は、漢字の閉じ開きやカタカナ表記、送り仮名の問題や句読点の位置など、物語世界を”どうやって表現するか”を考え抜いて文字を紡いでいくため、無駄なシーンや冗長表現といった概念は存在しないのが大前提です。
たまに「この部分は無駄だ」といった感想を聞くことがありますが、それはナンセンスなのです。
どうしてそんなことを言うのか疑問に思っていたのですが、そもそも文学を修めない限り”大前提”を知らないのは致し方ないことでしょう。
谷崎は言葉の限界を知っている人だった
大変興味深い意見として、「谷崎は言葉の限界を知っている人だった」というものが出ました。
対象的に三島由紀夫は、言葉の可能性を信じて活動した作家でした。
谷崎の晩年は自由を謳歌し、三島は自刃する結末は、こうしたスタンスを如実に表しているように感じます。
言葉は万能でないことを悟り、なんならその響きを愉しめばいいのだとする姿勢は好感が持てます。
声に出して読んでみたときに音楽的なリズムのある文章は、一種の快楽を沸き立たせるのは事実でしょう。
谷崎が官能的な文章に取り組んできた理由が若干理解できたような気がします……。
日本語は語彙が少ない!
谷崎は「日本語は語彙が少ない」と言い切っています。
確かに、日本語では「まわる」の一つしかない表現でも、漢字では「回る・廻る・周る・巡る」とさまざまに使い分けなければなりません。
日本人の寡黙を良しとする文化が、言い過ぎないことを品格の表れとして美徳とされ、それはつまり国民性を反映しているということです。
日本語の性質を変えるには、日本人の性質自体を変えない限り達成されないのは言うまでもないこととしています。
ただのエロオヤジではない!日本語を誰よりも大切にしていた谷崎
谷崎がこんなにも日本語に対する愛が深い人だとは知りませんでした。
極めて常識的な安定感のある日本語を礎に、変態的な作品を生み出し続けたそのバランス感覚が、未だにファンが途絶えない理由なのかもしれないという意見も出ましたが、納得です。
そのうち谷崎文学を読書会で取り上げてみようかと、たぬきおやじに対する見方が変わりました。
意外に課題本として官能小説のリクエストが多いという事実もあります(°_°)
(2022年1月23日日曜日開催)
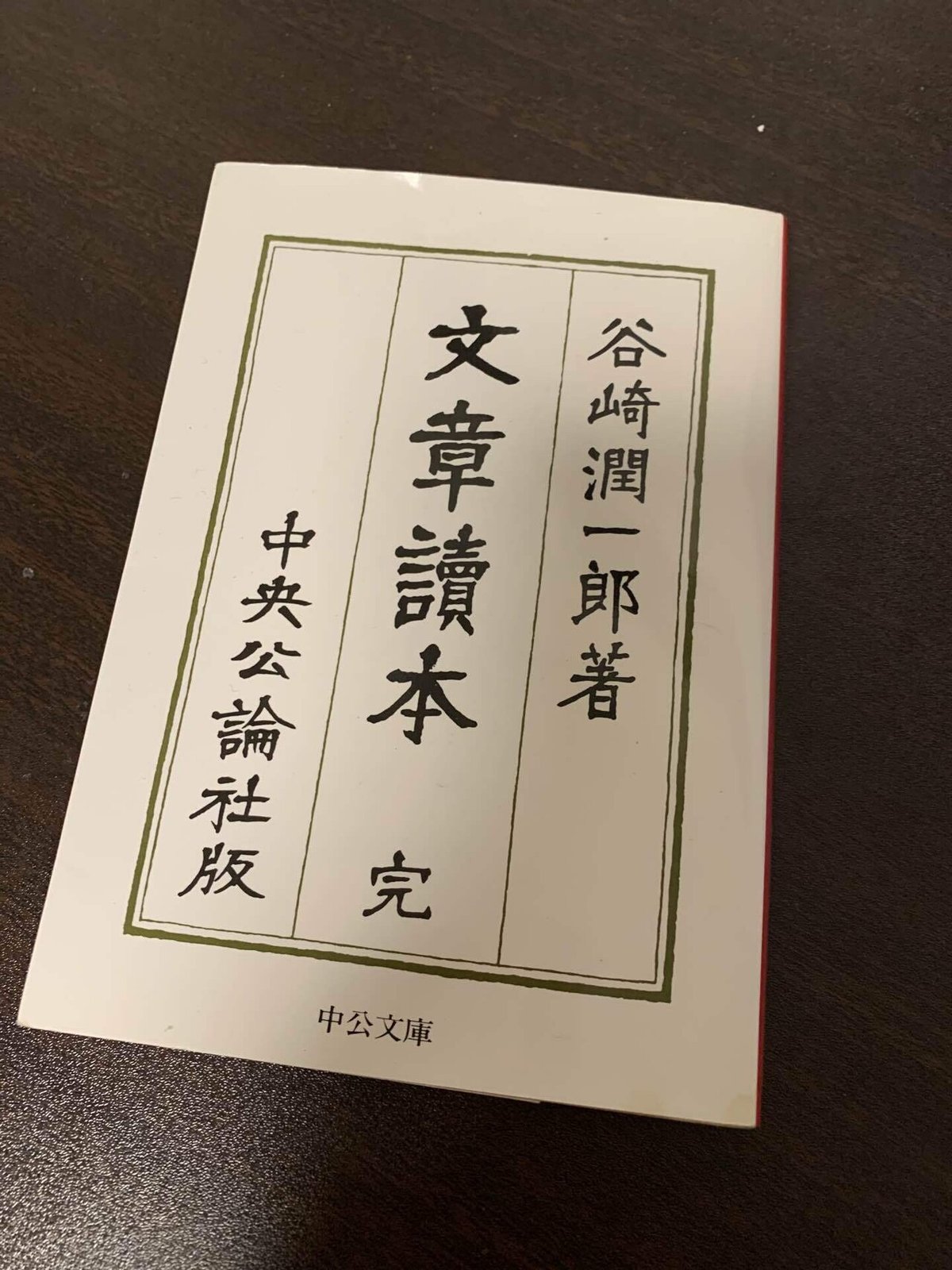
**********
【参加者募集中!】
「週末の夜の読書会」は毎月一回開催しています。
文学を片手にワイガヤで一緒におしゃべりしませんか?
参加資格は課題本の読了のみ!
文学の素養は一切必要ありません^^
ご参加希望の方は、以下の専用フォームより最新の開催内容をご確認の上お申し込みください。
【随時更新中:申し込みフォームはこちら↓】
【問い合わせ連絡先↓】
shuumatuno46@gmail.com
【読書会会場↓】
【第24回課題本】
文学は人生を変える!色々な気付きを与えてくれる貴重な玉手箱☆自分の一部に取り入れれば、肉となり骨となり支えてくれるものです。そんな文学という世界をもっと気軽に親しんでもらおうと、読書会を開催しています。ご賛同いただけるようでしたら、ぜひサポートをお願いします!
