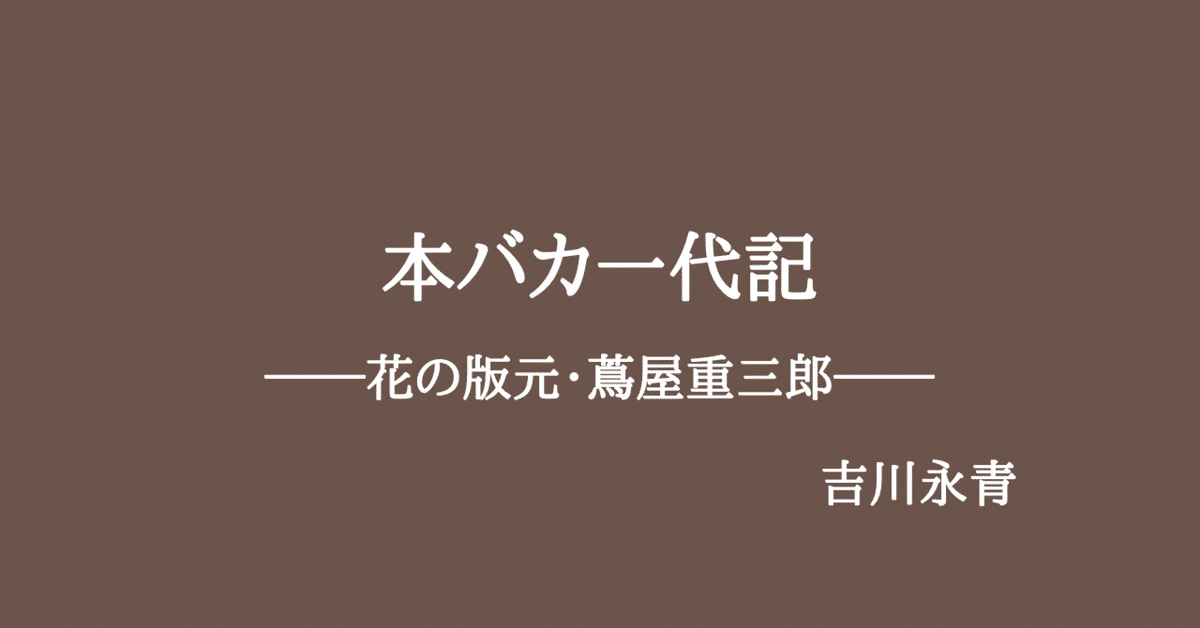
本バカ一代記 ――花の版元・蔦屋重三郎―― 第十話(下)
*
写楽の絵は本物だと、北尾も認めてくれた。しかし、その本物の才、持ち味こそが足枷になっている。
客を写楽の絵に慣らすには、どうしたら良いのだろう。そうすれば売れる、良さを分かってもらえるのかと言えば定かでないが、それでも慣れてもらわねば話にならない。
数日の間、重三郎は考えに考えた。そして今、写楽の家を訪ねている。江戸八丁堀、地蔵橋の袂であった。
「描き方を変えろって?」
「そう。次は大首絵じゃなくて、役者さんの総身を描いてください。できるでしょう?」
「そりゃあ、できますけど……」
いきなり描き方を変えろと言われては、戸惑って当然である。何しろもう六月初旬、七月興行の下描きを始める直前なのだ。
「でも、どうして?」
問われて、重三郎は軽く唸った。
「写楽さんの絵、あたしは大好きなんですけどね。でも、何て言ったらいいのか……新し過ぎるんですよ」
新しいということなら、歌麿の美人画も同じだった。なのに歌麿の絵は当たり、写楽は鳴かず飛ばずである。
何ゆえか。それは歌麿が美人画で、写楽は役者絵だからだ。
江戸で美人と目される女は、まずまず顔の作りが似通っている。歌麿はそういう女たちの顔を描き分け、個々に違う美しさを表そうとした。人々の「美人とはこういうもの」が大本にある以上、誰の目にも「これは美人だ」と見てもらえる。
対して役者絵は、美人画と違って「役者とはこういうもの」がない。二枚目は色男、三枚目は滑稽、悪役は憎々しく、女形は優しげな顔で、それぞれ大きく違う。ゆえに、まず各々の贔屓筋が納得しなければ「駄目な絵だ」と見られてしまう。
とは言え、そこは口に出せない。
「新し過ぎて、お客が付いて来られないみたいで。なら、他の絵描きさんと同じに総身を描いてみたら……って思ったんですよ」
この言葉は一面で真実であり、一方では嘘であった。写楽の新しさは、その多くが顔の描き方に出てしまう。これが嫌われているから、総身の絵で顔を小さくしようと考えたのだ。写楽の一番の特長を目立たなくして、少しでも客を慣らすために。
「分かりました。蔦屋さんがそう仰るなら」
承諾を得て、下描きに掛かってもらった。
そして一ヵ月、七月興行を迎える。耕書堂は再び、写楽の絵を派手に売り出した。
しかし、これも売れなかった。
なぜなら、総身を描けば他の絵師と似てしまうからだ。五月の絵では、多くの客が写楽の良さを解し得なかった。そういう人々は、似通った絵なら「誰が描いたか」で見てしまう。つまりは他に埋もれてしまったのだ。少しでも慣れてもらおうと写楽の色を薄めたことが、かえって仇になってしまった。
八月を迎え、重三郎はまた注文を付けた。
「やっぱり大首絵でいきましょう。ただ、顔の描き方ね。あれ、少ぉし抑えめで。ね?」
「まあ……できますけど。でも」
写楽は口籠った。何を言いたいのかは、顔を見れば分かる。思いどおりに描けないのが窮屈に感じられるのだろう。
しかし、と重三郎は頭を下げた。
「お願いしますよ。お客が写楽さんの絵に慣れさえすれば」
そうすれば、良さを分かってもらえる。否、分かってもらわねばならないのだと、声に熱を込めた。
「あたしは、あなたを江戸一番の売れっ子にしたいんです。だって、そうなれるだけの力があるんだから」
「でも、非番の一年だけって約束ですよ」
「まだ半年も残ってるじゃないですか。最後の最後に大勝負を仕掛けて、そこで勝ちゃいいんです」
写楽は「やれやれ」と眉を寄せた。
「分かりました。それにしても蔦屋さん、相変わらず押しが強いですね。耕書堂で描いてくれって、頼んできた時と一緒だ」
「そりゃ、今もあの時と同じ気持ちだからです。ともあれ頼みましたよ」
さらに三ヵ月、歌舞伎の十一月興行が始まる。耕書堂も、三度目の正直とばかりに写楽の絵を売り出した。
しかし。
その絵からは、玄人筋を唸らせた凄みがすっかり抜け落ちていた。おとなしく描いてくれと頼んだ以上、致し方ないのかも知れない。とは言え、これでは人を惹き付ける力に欠ける。
結果、やはり売れなかった。
そのまま一ヵ月、十二月の声を聞いた。写楽と約束した一年も、あと少しで終わろうとしている。
年が明けたら、歌舞伎の正月興行で大勝負を仕掛けるつもりだった。だが今となっては、それも虚しい夢と化していた。
世の人々を写楽の絵に慣らすことは、ついにできなかった。そればかりか、最近では写楽自身も精彩を欠いている。
それでも、誠だけは尽くさねばならない。一年間、耕書堂は写楽の絵しか売らないと言って拝み倒したのだから。
「どうも。最後の絵、頂戴しに来ましたよ」
八丁堀を訪ね、六畳間で差し向かい。案の定、手渡されたのは抜け殻の如き絵であった。
「すみません。こんなのしか描けなくて」
申し訳なさそうに言いながら、しかし写楽の面持ちには、どこか清々としたものが見え隠れしていた。
「ねえ写楽さん。どうして……力が抜けちまったんです? あたしが、あれこれ口を出したからですか?」
「まあ……そのとおりと言えば、そのとおりです。でも、違うと言えば違いまして」
「んん? そりゃ、どういう?」
きょとん、とした顔になる。何とも言えない苦笑が返された。
「実はね。蔦屋さんと知り合った頃、ちょっと面倒ごとを抱えてたんですよ。本当は……人様に話すようなことじゃないんですがね。ただ、迷惑をかけた身ですから」
そして写楽は眉を寄せ、驚くべきことを口にした。
「俺のせいで、人がひとり死にました。自害です」
苦渋、苦悶の面持ちである。重三郎の背に、ぞくりと寒気が走った。
「写楽さん、いいから! それ以上は」
山東京伝を思い出した。手鎖の日々を語って正気を失いかけた、あの姿を。写楽は京伝よりずっと芯が強そうだが、だからと言って、こんな傷に触れる訳にはいかない。
「ね? もう話しなさんな」
「いえ。けじめ、付けさせてください」
凛とした言葉、続いて溜息をひとつ。写楽の心が、どう動いていたのかが語られた。
「自分のせいで死なせた……って思うとね」
辛い。苦しい。逃げ出したい。そんな気持ちに押し潰されそうになった。夜中にふと目を覚まし、朝まで泣いていた日もあった。
しかし。好きな歌舞伎を絵にしている間だけは、少しばかり気が紛れた。
「悩んで、悩んで。居たたまれなくなった気持ちをね。絵に叩き付けてたんですよ」
ぶるりと身が震える。重三郎は得心した。そういうことだったのか、と。
深いとこから、うわあ、ぎゃあ、と飛び出して来ている――写楽の最初の絵を、北尾重政はそう評していた。まさに、そのとおりだった。
何となく分かる。恋川春町の切腹、朋誠堂喜三二の断筆、さらには山東京伝の筆禍。それらが重三郎の胸に残した傷と重なるところがある。
「……痛いですよね、そういうの。いつまでも痛い」
「ええ。でも、どうにか折り合いを付けられるくらいには。時も薬になってくれたんでしょう」
月日が過ぎるほどに、徐々に心が軽くなっていった。すると、次第に絵から力が抜けてしまった。十一月興行の頃には、もう元の絵は描けないようになっていたらしい。
「なるほど。加えて、あたしが色々と注文を付けたもんだから……」
「それも、まあ……。申し訳ない話ですが、何をどう描けばいいのか分からなくなりまして」
しくじった。重三郎の中には、その悔恨だけがあった。
耕書堂で描いてくれと頼んだ時、写楽は言っていた。自分は能役者であって絵師ではない、この絵は自分のために描いているのだと。その言葉を軽く考え過ぎていた。
「そうか……。あたしか」
肩が、がくりと落ちた。背が丸まった。
「絵が売れなかったのは、写楽さんのせいじゃない。あたしのせいです」
巧みに言葉を綴る人が、珠玉の物語を紡ぎ出すことがある。絵の巧い人が、一世一代の作を叩き出すことがある。だが、それが一度で終わるようでは戯作者ではない。絵師ではない。十点を満点として、七点か八点。そういう作品を長きに亘って、しかも常に生み出し続けるのが戯作者であり、絵師なのだ。
写楽の絵は、回を重ねるごとに萎んでいった。
では、本当の意味での絵師ではなかったのか。
違う。確かに、初めは絵師ではなかった。だが、いずれは絵師になれたはずだ。
「あたしは、あなたの絵に惚れ込んだ。だったら、腰を据えて掛からなきゃいけなかった」
「え?」
「写楽さんは心が強い。今日だって、自分から辛いことを話そうとしたくらいだ」
写楽の絵の源は、押し潰された心だった。だが、それだけではない。吹き飛ばされそうな向かい風に見舞われ、なお必死で抗おうとする心も、また、大きな力だったと言える。
「あなたは強い人なんですよ。人の命に関わるような痛みに、自分で折り合いを付けられるくらいに」
そういう人なら自身の心を飼い慣らせただろう。胸の重荷、心の痛みが薄れた後でも、あの鮮烈で力強い絵を描き続けられたはずだ。
「あたしは……もっと長くかけて、あなたを本当の絵描きに仕立て上げなきゃいけなかった。能の舞台が一年置きに非番になるんなら、一年置きに描いてくれるように頼みゃ良かったんだ。少しずつ前に進んでもらえば、きっと」
そう言って、歌麿を思い出した。長く自らの許に置き、あれこれの挿絵を任せて腕を磨かせたからこそ、歌麿は第一人者への道筋を辿り得た。
写楽に対しては、同じことができなかった。
歌麿と敢えて袂を分かった。何としても歌麿に代わる絵師が欲しかった。そんな時に、この人を見付けた。しかし約束は一年のみ。そこに焦って勝負を急いだ。
そして、負けた。
「写楽さん。いえ……斎藤さん」
辿るべき道筋を示すのが、版元の役目だったはずだ。なのに、目先のことに囚われて、ただ注文を付けるのみだった。その果てに――。
「あなたの中から、もう写楽は消えちまった。ですよね?」
「はい。俺は能役者、斎藤十郎兵衛です」
清々しく言われて、納得の笑みが浮かんだ。寂しい笑みであった。
「分かりました。約束どおり一年で終わりです。もう、お会いすることもないでしょう。あたしの我儘に付き合ってもらって、ありがとうございました」
最後の絵の代金は、追って見世の者に届けさせる。重三郎はそう言って深々と頭を下げ、斎藤家の小ぢんまりした屋敷を去った。
見世に帰る道中では、虚しい心を持て余した。だからだろうか、今日は特に足の動きが鈍い。
重い足を励まし、励まし、八丁堀から西へ進む。東海道に出て北へ行けば、左手の向こうに北町奉行所が見えた。
歩みを止め、その佇まいを眺めた。
「やっぱり……焼きが回ってたんだな。年が明けたら、あたしも四十六か」
筆禍の一件で裁きを受けた時に、同じことを考えた。あの時はお甲に励まされて奮起したが、今回は心の中に湧き上がるものがない。
「勝負しなけりゃ楽しくねえ、か」
その思いで商売を始め、何も持たぬ身の強みで世に挑んできた。巧くいけばそれを足掛かりに一歩を進み、躓いたことは次の糧として一歩を進んだ。そうやって多くを積み上げ、耕書堂もここまで大きくなった。
「でも……、この先は、もう勝負云々じゃないだろうね」
裁きの日に北町奉行は言った。幕府は民の親であり、国家という皆の家を保たねばならないのだと。それと同じである。自分は、既に何も持たぬ身ではない。奉公人たちの親であるべき身、耕書堂という皆の家を保つべき立場なのだ。
「何より、こうも勘が鈍っちまった」
ならば、今まで積み上げたものを活かして手堅く進もう。それがこれからの蔦屋重三郎だ。
思い定め、また歩き出す。
と、その途端――。
「うわ、とっ!」
足がもつれ、真っすぐ前に体が倒れた。慌てて手を出すも、自らの体を支えられない。
顔から、道に突っ込んで転んだ。額の右側を擦り剝いて血が滲む。一方で、頭の中からは血の気が引いた。
「……どうしたんだよ。おい」
足が痺れている。そして動かない。
動かしにくい、どころではないのだ。全く、動かない。
自分の体は、いったい――。
*
医者は重三郎の病を脚気と見立てた。江戸ではこの病に罹る人が多く、俗に「江戸患い」とも呼ばれる。米の飯を多く食い、青物が足りないことで発する病であった。
薬を飲み続け、青物を多く摂れば良くなるかも知れない。医者の言葉に従って、日々の飯が変わった。
しかし病は、じわじわと重三郎を蝕んでいった。
手足の動きが良い日があるかと思うと、全く動かない日も多い。そんな日々を重ね、寛政九年(一七九七)五月を迎えた頃には、病床に伏せるばかりの身となっていた。
「按配はどうだ、重三郎」
「重さん、久しぶりだな」
北尾重政が病床を見舞ってくれた。平沢常富――かつての朋誠堂喜三二と一緒である。五月五日、端午の節句の日であった。
「こりゃ、どうも。今日は少しばかり気分がいいですよ」
弱々しい声で頬を緩め、何とか身を起こそうとする。しかし、やはり手足が痺れて動かない。
「無理すんなよ」
もぞり、もぞりとしか動けぬ身を労わって、北尾が寂しげに笑みを浮かべた。
「そう、寝たままで構わんよ。楽に、な?」
平沢も沈痛な面持ちである。重三郎は苦笑した。分かるのだな、と。
脚気は軽いうちなら平癒することも多い病だが、手足が動かなくなると癒えにくい。手足の次は総身が動かなくなり、ついには心の臓も止まってしまう。
その日はごく近いと、自分でも分かる。二人の目にも明らかなのだろう。或いは、お甲が「もう長くない」と報せて、だから二人揃って見舞いに来たのかも知れない。
「嬉しいですよ。昔っから、あたしが一番頼りにしてたお二人の顔が見られて。一昨日はね、利兵衛の親父と次郎も来てくれたんです」
吉原の妓楼・尾張屋を営む養父と、義弟の次郎兵衛。その幾日か前には、何と商売敵の西村屋与八まで見舞いに来たのだから驚いた。
「西村屋さん、柄にもなく神妙な顔しちゃってね。面白かったですよ」
北尾は静かに頷いている。対して平沢は、涙目で首を横に振った。
「頼りにしていたのは、こっちの方だ。重さんと一緒にやれたお陰で、物書きも楽しかった。それに、重さんがいたから世に出られた人も多いじゃないか」
平沢が指折り数えてゆく。戯作者で言えば、恋川春町の弟子・恋川好町。北尾重政にとって絵の弟子だった、山東京伝。絵師では勝川春章の弟子・勝川春朗――後の葛飾北斎――に加え、何と言っても喜多川歌麿である。
「去年には、馬琴さんも読本で一本立ちした。一九さんも一昨年だったよな」
曲亭馬琴――かつて手代・瑣吉として耕書堂に奉公した滝沢興邦である。十返舎一九も同じように、やはり手代扱いで奉公しながら戯作者としての土台を固めた人であった。
「重さんは、物書きや絵描きの父親だった」
平沢が、にこりと涙を落とす。北尾がその肩を軽く叩き、重三郎に向いた。
「写楽は残念だったけどな。でも無駄じゃなかったぜ」
あの異形の才は、客にも役者当人にも受けが悪かった。しかし、やはり絵師たちには写楽の力が分かっていたらしい。昨今の役者絵は、目の描き方、顔の癖を強める描き方など、写楽の画風を取り入れたものが多くなっている。
重三郎は「はあ」と浅く息をついた。
「あたし、色々やってきたんですねえ。どれもこれも懐かしいや」
ついに北尾まで目元を拭う。そして咳払いをひとつ、しわがれた声で「なあ」と問うた。
「歌麿の奴に言わなくていいのか? 手切れの訳、さ」
「それですか。そうですね……あたしが死んだら、お願いします」
歌麿は傲慢な男だが、熱い心の持ち主でもある。手切れの理由を知れば、きっと「重三郎が生きているうちに耕書堂で描く」と言い出すはずだ。
「おめえさんが浄土に行った後だって同じだろうよ。恩返しだって言って、耕書堂に戻って来るに決まってらあな」
「あたしの許で描いたら、歌麿さんが目ぇ付けられますから。あたしがいなくなりゃ、少しは変わるで――」
言葉の途中で、胸に痛みが走る。心の臓がおかしな拍子で脈を打ち、次第に息が苦しくなってきた。
「いけねえ。女将さん、お甲さん!」
北尾が慌てて声を上げる。お甲が泡を食って飛んで来た。
「おまえさん!」
が、その頃には重三郎はだいぶ落ち着いていて、息も楽になっていた。
「まだ大丈夫。でも、ちょいと疲れたね」
ならば長居はするべからずと、北尾と平沢は帰ることになった。
去り際、二人がそれぞれ左右の手を握ってくれた。痺れている重三郎の手
に少しでも伝われと、強く、強く。
二人が帰ると、重三郎はしばらく眠った。
目が覚めると、もう翌日、五月六日の朝だった。お甲は左脇の畳に身を横たえている。だが眠ってはおらず、重三郎が目を開けると、安堵したように「おはよう」と笑みを見せた。
「まだ、大丈夫かい」
「今んとこね。ただ、そろそろ見世の後をどうするか、番頭さんに伝えておきたい」
それではと、お甲は番頭の勇助を呼んだ。
重三郎は、静かに告げた。
「番頭さん。あたしとお甲には子がいない。あなたが耕書堂を継いでくださいな。良かったら蔦重の名前も。ずっとこの見世の番頭だったんだし、誰も文句は言わないだろうから」
勇助は驚いていた。しかし重三郎が「ね?」と目元を緩めると、涙をぼろぼろ零しながら「はい」と頷いた。
「見世の金を五百両、お甲に渡してやって。それで地本の株を買ったことにしてください。あなたの後の番頭は、手代の鉄三郎さんがいいでしょう。他は任せます」
ひととおりを告げ、勇助を下がらせる。
それから少しすると、重三郎はお甲に向いて悪戯な笑みを浮かべた。
「ねえ、お甲。最後に、ひとつ勝負したいんだがね」
「何言ってんだい。この期に及んで」
お甲は驚いたような、困ったような顔である。そこに向け、かさかさと乾いた声で「はは」と笑った。
「軽い賭けだよ。写楽さんの絵で負けて、それで終わるのは癪だからね」
「はいはい。で、どんな賭け?」
「あたしが、いつ死ぬかさ。そうだね……今日の昼だろうな」
正午の鐘が鳴ると共に、自分の命は尽きる。そう言う重三郎に、お甲は何とも言えず悲しげな眼差しであった。
「さっき鐘が五つ鳴ったよ。おまえさんが目を覚ます、ちょっと前」
朝五つ(八時)の鐘である。正午までは、あと二時(一時は約二時間)もない。
「そうか。ちょいと……短いけど、でも午の刻までに覚悟を固めとくんだよ」
そのまま、ぼんやり身を横たえ続ける。やがて、正午の鐘の音が届いた。
が、重三郎はまだこの世にあった。
「最後の勝負も負けちまったね。おまえさんが生きてんの、あたしは嬉しいけど」
お甲の穏やかな声に、重三郎は「いやあ?」と目を細めた。
「そんなこたあない。勝ったよ」
「外れたのに?」
「そう。だって、まだ生きてんだから」
自分の命と勝負して、勝った。この言い分に、お甲がくすくす笑う。重三郎は嘆ずるよう「ああ」と唸り、遠くを見る目になった。
「自分の一生を賭けて、あたしは好きな道で生きてきたんだな。ずっと、あれこれ挑んできた。本当に……楽しかったよ」
「そうかい。いい人生……だったね」
互いに涙の笑みを交わす。そして重三郎は、目を瞑った。
もう、時は幾らも残されておるまい。
お甲の静かな息だけが、傍らに聞こえている。重三郎、四十七歳であった。
重三郎が常世に渡ってからも、耕書堂は多くを世に送り出し、大当たりを取り続けた。中でも、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』や十返舎一九の『東海道中膝栗毛』などは、特に優れた快作であった。
そして、戯作者と絵師たちは――。
朋誠堂喜三二こと平沢常富は、重三郎の死後も十六年を生き、七十九歳で逝去した。北尾重政は喜三二のさらに七年後まで永らえ、八十二歳の生涯を閉じている。
喜多川歌麿は、再び耕書堂で描くようになった。幕府はこれに対して締め付けを強めるも、歌麿はかえって反発し、美人画を描き続けている。
しかし文化元年(一八〇四)のこと、ついに罰を受けた。豊臣秀吉の「醍醐の花見」に材を取った『太閤五妻洛東遊観之図』を咎められ、手鎖五十日の罰を受けている。織豊時代に材を取ることは、出版取締令以前から禁じられていた。
東洲斎写楽の絵は、残念ながら人々に解されぬまま、長く時を重ねた。しかし徳川幕府が終わって明治の世になり、さらに大正時代に至ってようやく見直される。明治四十三年(一九一〇)にユリウス・クルト――ドイツの美術研究家が絶賛したことが、その契機となった。本当に良いものを世に送り出し、人々の心を楽しい方へ押し流す。重三郎の願いは、思わぬところから形になった。
もっとも耕書堂は、それを待たずに見世を畳んでいた。明治維新の少し前、文久元年(一八六一)のことである。激しく動く世情は、憂き世を忘れるための娯楽には強過ぎる逆風だったのかも知れない。四代目・蔦屋重三郎の時であった。
〈了〉
【第一話】 【第二話】 【第三話】 【第四話】 【第五話】
【第六話】 【第七話】 【第八話】 【第九話】
【プロフィール】
吉川 永青(よしかわ・ながはる)
1968年、東京都生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2010年『戯史三國志 我が糸は誰を操る』で第5回小説現代長編新人賞奨励賞、16年『闘鬼 斎藤一』で第4回野村胡堂文学賞、22年『高く翔べ 快商・紀伊國屋文左衛門』で第11回日本歴史時代作家協会賞(作品賞)を受賞。著書に『誉れの赤』『治部の礎』『裏関ヶ原』『ぜにざむらい』『乱世を看取った男 山名豊国』『家康が最も恐れた男たち』など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
