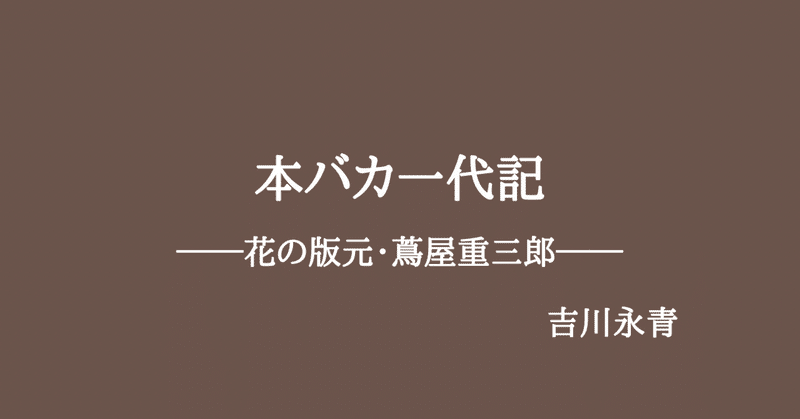
本バカ一代記 ――花の版元・蔦屋重三郎―― 第四話(上)
丸屋に地本問屋株の買い取りを持ち掛け、色好い返事をもらうことはできた。とは言いつつ条件付きである。
本当に価値あるものだけを売り出そうと思って商売をしてきたが、巧くいかなかった。同じ思いで商売をするのなら、巧くできるという証を見せて欲しい。丸屋小兵衛はそう求めた。
それに対して言い放った。世の中と勝負をして、きっと勝って見せると。
株を持たない自分にできることは少ない。しかし手管が限られているからこそ、何をすれば良いのかは見えていた。このやり方なら、きっと丸屋小兵衛を納得させられる。その目算に、胸の内は滾るほど熱い。
とは言え、ひとつだけ難題がある。これを如何にして越えたものか――。
「――さん。ねえ重さんたら!」
びくり、と身が震えた。腰掛けた上がり框の脇で、女郎の浮雲が眉をひそめている。本の貸し歩きで三文字屋を訪れている最中だった。
「これ、この本。借りるって言ってんのに」
「あ、すみません。っと、今日は三冊も? いつも、ありがとうございます」
「で、何ぼんやりしてたのさ」
「まあその、ちょっと考えごとをね」
貸し賃を受け取りながら答えると、浮雲は「ふうん」と軽く首を傾げた。
「考えごとねえ。あんたほど商売熱心な人が、私っちみたいな上客を放ったらかしにするほどの話って?」
重三郎は軽く苦笑を浮かべた。
「 姐さんに話したって、埒が明かないと思うんだけどね」
「そんなの、言ってみなきゃ分かんないだろ。こっちは九年も女郎やってて、世の中の裏側まで知ってる身だよ。それに、人に言うだけでも気が楽になるって、そういうのもあるじゃない」
気風の良い、さばさばした笑みを向けられた。かつての火事の折には客の頭を踏み付けにして逃げたような女だが、こういう情に篤いところがある。そこは、いつも好ましく思っていた。
「じゃあ話しますかね。株のこと、前に聞かせたでしょ? それで、丸屋の旦那から難題を頂戴してんですよ。自前で本を出して、きちんと商売ができるって証を立てなきゃいけない」
浮雲が「へえ?」と目を丸くした。
「とは言ってもさ、重さんが出せる本って言ったら、細見と……里の見世の宣伝本くらいじゃないさ。あ、それと蒟蒻本もあるか」
蒟蒻本――吉原や岡場所などに材を取った「洒落本」である。浮雲の言うとおり、それなら重三郎が作っても咎められない。洒落本は世間に「いかがわしい本」と見做されていて、地本問屋が取り扱おうとしないからだ。
「でも蒟蒻本じゃあねえ。あっちこっちで読まれちゃいるけど、大概が貸本だからね」
そう言って、浮雲は軽く眉を寄せている。自ら貸本の「上客」と言うだけあって、洒落本というものの事情も良く知っていた。
地本問屋が扱わない以上、洒落本は広く世に売り出されない。いかがわしいと思われている本ゆえ、好事家が少し刷るのみに留まる。数を刷らないために値も高く、半ば貸本のために作られているような按配なのだ。
しかし重三郎は、逆に「お」と目を見開いた。
「さすが姐さん、いいとこ衝いてくるね」
「え? あんた、まさか丸屋の旦那を蒟蒻本で納得させる気?」
「そう。その『まさか』ですよ」
浮雲が言うように、洒落本は貸本でそれなりに読まれている。広く売り出されはしないが、客が付かない本ではないのだ。
「どうして皆、蒟蒻本を読むんだと思います? 面白いからですよ」
吉原や岡場所、色町の客はまさに十人十色と言えよう。ありとあらゆる客を見渡せば、それこそ想像も付かないような話が山になっている。これに材を取っているのだから、面白くないはずがない。
「なるほどね。でも蒟蒻本って『いかがわしい』って言われてんじゃない。私っちら女郎にとっちゃ、腹の立つことだけど」
腑に落ちない、という眼差しが返される。重三郎は「ええ」と頷きつつ、すぐに「でもね」と続けた。
「もしも、ですよ。売れっ子の物書きが蒟蒻本を書いたら、その『いかがわしい』ってやつ、変えてやれるんじゃねえかな……って思うんだ」
「んん? そういうもん?」
なお腑に落ちないらしい。軽く「はは」と笑って返した。
「じゃあさ、姐さん。確か、前に黄表紙の『金々先生』借りて読んだでしょ?」
「うん。面白かったね、あれ。さすがは恋川春町だよ」
「そこ、そこなんだ」
言いつつ、右手の人差し指を立てて幾度か前後に振った。
「たとえば『金々先生』を書いたの、春町先生じゃなくて、この蔦重だったと思ってみてよ。あたしが書いた本だったら、わざわざ借りて読みました?」
浮雲は「あ」と大きく口を開け、それを右手で覆った。
「……そういうことか」
「そういうことです」
誰が書いたものだろうと、面白いものは面白い。これは動かしようのない事実だ。一方で世の人は、面白いか否かの前に「誰が書いたか」で判じてしまうところがある。これも動かしようのない事実なのだ。
「名前のある人が蒟蒻本を書いたらさ、皆『こりゃどうしたことだ』って興味を持ってくれるでしょ? で、読んだら、実は面白いって分かってもらえる」
そうすれば、今まで「いかがわしい本」だったものを、黄表紙と同じ「面白い本」のひとつに変えてやれるはずだ。丸屋小兵衛も納得してくれるだろう。
重三郎の肚を聞いて、浮雲は「なるほどねえ」と目を輝かせた。
「世の中の考え方から変えちまおうって訳か。すごいよ、まさに大仕事じゃない」
「でしょう? それも、勝てる勝負なんだ」
「あれ? でもさ」
そこまで考えていながら、いったい何を悩んでいるのか。浮雲はそう言って眉を寄せた。
「あんた物書きの先生は色々と知ってんだろ? だったら、あとは楽なもんじゃないさ」
「いやいや。その逆で、こっからが難しいんですよ」
世の中の見る目を変え、考え方を覆してやろうというのである。それこそ、誰でも知っている大物の戯作者に頼まねば話にならない。しかしながら、未だ世に「いかがわしい」と思われている本を書いてくれと言えば、相手はどう思うだろうか。
「下手したら縁を切られるかも知れねえ。でしょ?」
「あら。自信ないのかい?」
「まさか。自信は十二分にありますよ。でもね」
重三郎にとって戯作者の知り合いは、全て浮世絵師・北尾重政に紹介された人々である。その中の大物に縁を切られたら、北尾の面目も丸潰れであろう。北尾まで怒らせては、これまで積み上げてきたものがご破算になりかねない。
「そんなことになんねえように、話の進め方を考えてんです。さっきも言ったとおり、勝てる勝負だからこそね。けど考えりゃ考えるほど、もっと巧いやり方があるって思えてくる」
重三郎は、がりがりと頭を掻いた。すると浮雲が「なるほどね」と首を傾げる。気のせいか、そこはかとなく不満げな眼差しに思えた。
「でも……。そうか。だったら、ちょっと息抜きでもどうだい? いったん頭ん中を空っぽにしたら、コロッと巧い手が見付かることもあるじゃないさ」
「息抜きって。いや……息抜きか」
そんな暇があるものか、とは思った。だが、確かにこのところ根を詰めすぎている。
「姐さんの言うとおりだ。こういう時ゃ、ちょっと何もかも忘れてみた方がいいかも知れない」
すると浮雲は、今度は少し嬉しそうに「それじゃあ」と笑みを見せた。
「今日の商売、もう止めにしちゃいなよ。で、今から私っちに入ってくんない? 揚げ代はこっちで持つから」
「ええ? 何なの、それ」
「ぶっちゃけた話、実は少し休みたいんだよね」
昨晩は四人の客を相手にして、ほとんど眠っていない。今は昼見世の時分だが、ここで客が付いては堪ったものではないのだと言って、溜息交じりである。
「私っち、あと一年くらいで年季が明けるんだけどさ。それで、今まで付いてた客がバンバン来やがるんだよ。儲かるのはいいけど、とにかく大変でねえ」
「何だ。要するに、姐さんの昼寝に付き合えってことか」
呆れて肩の力を抜くと、浮雲は「うふ」と妖しい笑みを見せた。
「することは、していいよ。重さんの息抜きでもあるんだから。見世で女を抱くのだって、初めてじゃないだろ?」
「そりゃ、まあね」
吉原に生まれ育った以上、齢二十七を数えて女の味を知らぬ訳はない。さすがに養父・利兵衛の営む尾張屋では遊ばないが、遊里の東西にある河岸見世――小見世の女を買ったことは幾度もあった。
「分かった、付き合うよ」
「ふふ、ありがと。それじゃ……ね?」
浮雲の上目遣いが濃厚な色香を漂わせる。少し、どきりとした。
〈次回に続く〉
【プロフィール】
吉川 永青(よしかわ・ながはる)
1968年、東京都生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2010年『戯史三國志 我が糸は誰を操る』で第5回小説現代長編新人賞奨励賞、16年『闘鬼 斎藤一』で第4回野村胡堂文学賞、22年『高く翔べ 快商・紀伊國屋文左衛門』で第11回日本歴史時代作家協会賞(作品賞)を受賞。著書に『誉れの赤』『治部の礎』『裏関ヶ原』『ぜにざむらい』『乱世を看取った男 山名豊国』『家康が最も恐れた男たち』など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
