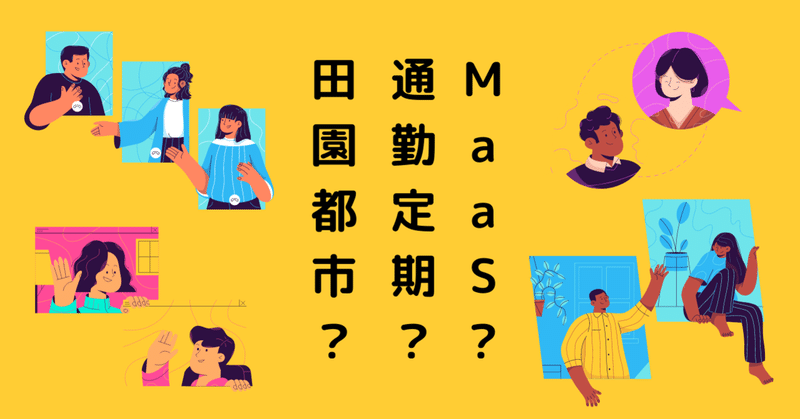
東急の通勤支援サービス「DENTO」を立ち上げたけど、これはMaaSじゃないねって話。
2021年1月13日、東急株式会社からWEBサービス「DENTO(デント)」がリリースされました。私はそのサービス企画・開発のPMを担当させていただきました。本日は、DENTO開発の狙いと背景をかんたんに解説します。
DENTOとは。「通勤に自由を」

まずは簡単にDENTOの解説から。DENTOとは、「多摩田園都市エリア」に特化した通勤支援サービスです。「多摩田園都市エリア」とは、田園都市線沿線、中でもたまプラーザから中央林間に位置する地域を指します。
多摩田園都市エリアの人口は約60万人。高齢化と通勤混雑が根強い課題でした。電車による渋谷までの通勤手段は田園都市線のみ。コロナ前は乗車率平均180%を超え、「痛勤」と住民から揶揄されました。
そんな通勤課題を抱える多摩田園都市エリアに新しい就労スタイルを確立できれば、他線への展開への大きな示唆を得ることもできます。そのような経緯から、まずは多摩田園都市エリアでの実証実験エリアとして選定しました。
DENTOでは、電車での通勤だけでなく、高速バス(Satellite Biz Liner)や相乗りハイヤーなどを組み合わせて、これまでの電車通勤に加えて多様な通勤手段を提供しています。
また、ワーキングスペースやアクティブクーポン(東急線沿線のお店で使えるクーポン)など、移動に紐づく生活支援サービスも同時に提供。100円チケット(電車・バスが100円で乗り放題となるサービス)と組み合わせて通勤経路以外の沿線移動も支援します。
そしてこれらのサービスは、東急線沿線の通勤定期券の有無で利用権利を区分しています。
●通勤定期券をお持ちの方のみ利用可能
・相乗りハイヤー
・100円チケット
・アクティブクーポン
・ごほうびセットチケット
●誰でも使える
・ワーキングスペース
・座席指定乗車券「Qシート」事前予約機能
・Satellite Biz Liner(通勤高速バス)
NHKで取材された様子
DENTO開発の契機。「コロナと通勤定期券のズレ」
1959年からはじまった多摩田園都市の生活スタイルは、かつての高度経済成長・バブル期を背景とした旧来型の生活様式。コロナの到来によりその生活スタイルは「通勤定期券の売り上げ落ち込み」として限界が見えはじめます。
通勤=電車を利用する、と言う時代が終わりを迎えたのです。TV会議システムの浸透、コワーキングスペース の増加、外出自粛などを背景に、通勤定期券はその存在価値を再確認されるようになりました。
しかしこれは、通勤定期券・電車の価値が低下した、という話ではないと思っています。都心への大量輸送手段のニーズは今後も一定数はあると考えられ、電車はその経済合理性を持つ有効な手段の一つであると考えます。※多摩田園都市という、少子高齢化においても人口増加が見込まれている特殊な環境という前提で申し上げています。
しかし、社会のニーズからズレ始めているのもまた事実です。
公共交通は使ってもらって当たり前と言う時代から、選ばれるために価値提供しなくてはならない時代なったことを自覚しなくてはなりません。東急電鉄収益の約4割を担う定期券収入の落ち込み。移動を前提とした、移動に頼り切ったビジネスモデルの危うさに気づくいい機会となったと考えています。
通勤定期買う?買わない?「二者択一ではない【東急線生活定期券】を目指して」

ここまで読むと、DENTOは通勤定期券販売落ち込みのテコ入れ策と捉えた方も多いのではと思います。もちろん、その側面は大きいです。しかし、我々の真の狙いは、通勤定期券の有無ではなく、通勤定期券も「生活の一部」として捉える「東急線生活定期券」という考え方です。
通勤定期券を購入するかどうか。現在の就労環境下では、我々はコントロールができません。正直言って、予測も難しいです。しかし、衣食住・就労することはこれからも続いていくことは確かでしょう。
東急線沿線に住み続けてもらうこと。
これがDENTOの目的です。
サービス開発のポイントは4つ。
●スマホをベースとしたデジタルツールを活用し、いつでも、どこからでも、東急グループが持つサービスにアクセス・決済・利用可能な状態を作ること。
●東急グループだけでなく、東急線沿線のあらゆるサービスにアクセス・決済・利用可能な状態を作ること。
●通勤定期券を所有していようがいまいが、「働きやすい街」と思ってもらえるサービスを提供する。
●その中でも、東急サービス(賃貸、住宅、定期券)を利用している人にはインセンティブを大きく働かせること。
この4点を軸に、DENTOは今後も沿線住民と対話をすすめ、サービスを模索していきます。
最後に。「これMaaSじゃないね」
以上、簡単ではありましたが、DENTO開発背景の一部をお話させていただきました。
あれ、MaaS(Mobility as a Service)の話は?検索・予約・決済機能の話は????
そうです。もうお気付きかと思いますが、DENTOはそもそもMaaSを提供しようとは思っていません。
MaaSの基本概念は、交通モードのシームレス化(様々な交通手段を一つのデバイスで予約・決済・利用が可能な状態)していくこと。
MaaSの母国フィンランドでは、環境問題を解決する手段としてMaaSが登場しましたが、MaaSの提供価値や課題設定は、地域によって変わっていきます。
多摩田園都市線における地域課題は、交通モードのシームレス化だけではないのです。様々な就労・生活スタイルに合わせた「生活モードのシームレス化」が求められていると考えています。
既存のMaaSの概念にとらわれることなく、冷静にローカライズさせる必要があります。MaaSのエッセンスを取り入れながら「まちづくり」をしているという自覚を忘れずに臨んでいきたと思います。
どんなに社会環境が変わろうとも、ニーズが変化しようとも、社会が求めるニーズに柔軟ににサービスを提供できる状態を作ること。
これが、東急電鉄ではなく、まちづくり会社である「東急株式会社」が取り組むべきサービスであると考えています。
DENTOは、今後もスピーディに多様なサービスを提供しながらトライアンドエラーを続けていきます。
是非、利用者の皆様の忌憚のないご意見をお待ちしています。
みなさまの声がサービスに還元され、そして街づくりに還元される好循環が生まれるよう、我々は努力を重ね続けます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
