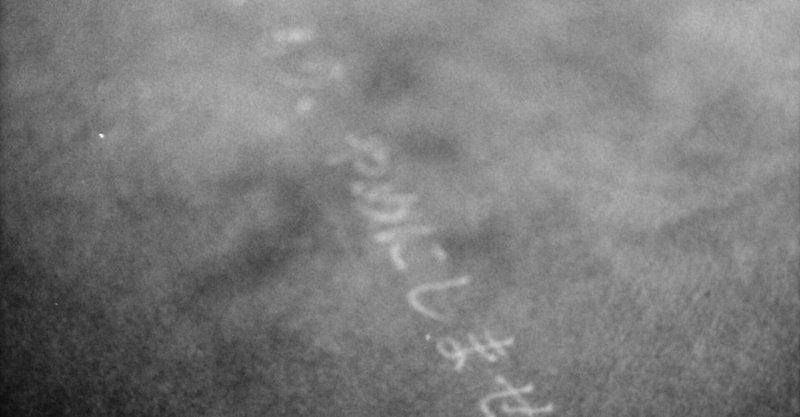
プラグマティズムは「言葉に騙されない」ための思想
世の中は怪しい言葉に満ちている。
例えば、次のように言う人がいる。
役に立たない研究はいらない。
このような言葉を聞けば、多くの人が「もっともだ」と思うだろう。
しかし、本当に納得してしまっていいのか。「言葉に騙され」ているのではないか。言葉を疑う必要がある。
どう疑うのか。次のように要求するのである。
「役に立たない研究」の事例を一つ挙げよ。
具体的な事例を挙げるように求めるのである。事例が無ければ、その言葉が何を言っているか分からない。だから、正しいかどうか分からない。
こう考えるのがプラグマティズムである。プラグマティズムは言葉を疑う思想なのである。〈言葉だけで済まさず、裏づけになる事実を求める思想〉なのである。
事例によって言葉を疑うのである。言葉を検討するのである。
例えば、次のようにである。
〈「役に立たない研究」と誰もが思った研究が最終的にはノーベル賞に繋がった事例〉がある。物理学者のファインマン氏の事例である。(注1)
これは「役に立たない研究」に含まれるか。
これは判断が難しい事例である。最初の段階では「役に立たない研究」と思われていた。しかし、最終的には役に立つ研究であった。
もし、最初の段階で「役に立たない研究」だから「いらない」と決めてしまっていたら、ノーベル賞を取った発見は存在しなかった。
だから、問題は次のことである。本当に「役に立たない研究」を見分けることが出来るのか。最初の段階で「役に立たない研究」とそうでない研究とを区別できるのか。
二つは区別できない。ファイマン氏の研究は誰もが「役に立たない研究」と思っていたのである。本人すら「役に立たない研究」だと思っていたのである。
では、「役に立たない研究」という言葉をどう解釈するか。「役に立たない研究」は事後的な概念なのである。結果から逆算して、「役に立たない研究」と呼んでいるだけなのである。
「役に立たない研究はいらないか」と聞かれれば、答えは「いらない」に決まっている。
「役に立たない研究はいらない」は分析的命題なのである。「役に立たない」が「いらない」を含意しているのである。これは「悪いことはしてはいけない」という命題に似ている。
役に立たない研究はいらない。
悪いことはしてはいけない。
これらの命題は分析的命題である。
「役に立たない研究」は「いらない」に決まっている。「悪いこと」は「してはいけない」に決まっている。
しかし、これは言語的な知識に過ぎない。「役に立たない研究は」という言葉の次には「いらない」と書けるというだけである。
分析的命題は、現実に対して何の情報も加えない。「悪いことはしてはいけない」と聞いて、新しい情報を知ったと思う人はいないだろう。同様に「役に立たない研究はいらない」も無内容である。
だから、現実問題としては、「役に立たない研究はいらない」という言葉は全く「役に立たない」言葉である。研究の最初の段階で「役に立たない研究」とそうでない研究を見分けるための基準にはならないのである。
以上、事例を検討することによって、「役に立たない研究」という概念を明晰化できた。「役に立たない研究はいらない」という言葉の無内容さをはっきりさせることが出来た。言葉の怪しさをはっきりさせることが出来た。
プラグマティズムは言葉を疑う思想である。言葉だけで済まさない思想である。言葉を疑うために事例を重視する思想である。〈言葉だけで済まさず、裏づけになる事実を求める思想〉である。(注2)
プラグマティズムは言葉を疑う思想である。
〈言葉の裏づけになる事実を求める思想〉である。
事実が無ければ、言葉の裏づけが無い。
裏づけ無しの言葉は怪しい。「言葉に騙され」るおそれがある。
だから、言葉の裏づけになる事実を求める。
プラグマティズムは「言葉に騙されない」ための思想なのである。
(注1)
〈「役に立たない研究」と誰もが思った研究が最終的にはノーベル賞に繋がった事例〉については次の文章で詳しく論じた。
(注2)
プラグマティズムについては次の二つの文章で詳しく論じた。
〈思考の結果を問うことによって思考を明晰化しよう〉とする思想がプラグマティズムである。
〈言葉の事例を問うことによって言葉を明晰化しよう〉とする思想がプラグマティズムである。
つまり、プラグマティズムは言葉を疑うために事例を重視する思想である。
そう。
「プラグマティズム」と言えば「ジェームズのリス」なのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
