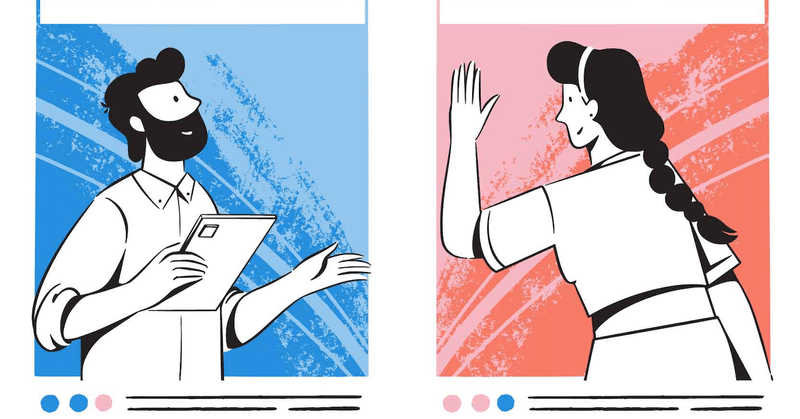
編集者はなんのために存在しているのか?
前回、書き続けることの大変さを書いた。
改めて考えてみると、ぼくは他者が抱いている「書くことのつらさや苦しさ」について、理解が浅かったというか、まったくもって想像力が及んでいなかったんだなと実感した。「マイノリティの気持ちは、マイノリティになったことがある人にしかわからない」というのに近い気がする。自分が書く立場になってようやく、リングに上がり続けることの大変さに気けたわけだ。
書き続けることの難しさにこれだけ鈍感だったのは、10年以上編集の仕事をしてきたことによる過信に加えて、実名を出して矢面に立つ経験をしてこなかったのも関係しているかもしれない。振り返ってみれば、他者の「書き続ける」という行為を、ずいぶん厳しい目で、あるいは軽々と見ていた気がする。
ぼくは主に「ビジネス書」や「実用書」と呼ばれる書籍を手がけていて、著者の大半は、経営者や院長といった組織の長たちだ。
ライターをつける場合も多々あるけれど、もし著者自身で1冊書こうと思ったら、それはそれは大変な苦労が求められる。少なければ5万字程度になることもあるが、それでも日常で書くメールやメッセージの類と比べれば、象と蟻くらい差がある。そして、1カ月か2カ月か、人によっては半年近く、「これでいいのだろうか」という不安や葛藤を感じ続けることになるわけだ。
にもかかわらず、ぼくは「著者は原稿を書き上げるのが当たり前だ」と思っていた節がある。「忙しい」や「時間がない」なんて理由は聞きたくないし、そんな言い訳をつぶやく暇があるなら少しでも書き進めてほしい。典型的な体育会系思考。脳筋ファッキン野郎だ。
ただ、やはりというべきか、現実には予定どおり原稿があがってくることは少なく、そこで、われわれ編集者は対応を求められる。現状の進捗はどうか、懸念点はないか、なにか手伝えることはないか――。執筆へのモチベーションを失わず、少しずつでも前進できるよう鼓舞し、ときにはお尻を叩く。真っ赤に腫れ上がるくらいに。
* * * * * * * * * * *
編集者同士が話をすると、よく「あの本をつくるのがどれだけ大変だったか」という苦労話合戦が起こる。その多くは、著者や外注先に関することだ。
以前、先輩から興味深い話を聞いた。
その先輩はある書籍が入稿間近になった際、なんと著者の自宅に行って直接「監視」して赤字を回収したという。自宅で監視だ。メールや電話ではなく、文字どおり直接お尻を叩きにいったわけである。
「いやあ、一向にゲラを見てくれない著者でさ。そのまま入稿するわけにもいかないから、自宅に行って、張りついて見ることにしたわけ」
「つまり、一緒に読み合わせをしたってことですか?」
「いやいや、俺は1階のリビングにいて、著者は2階の自室でゲラを読むの。で、1章の確認が終わったら連絡が来る。終わりましたって。そしたら2階に行って、ちゃんとゲラに赤字が入っているかを確認する。不明点とか検討事項があったら、その場で協議する。それが終わったら俺は1階のリビングに戻る。著者は2章をチェックする。その繰り返しだよ」
「ノリスケと伊佐坂先生みたい感じですか?」
「うーん、どうなんだろう。伊佐坂さんは締切ルーズなんだっけ?」
「知りませんね。で、著者はちゃんと読んでくれたんですか?」
「さすがに、編集者がリビングにいて、逃げ道はないからね。ときどき『お腹減った』って言われたときには外出を許可してたけど、それ以外は缶詰状態でお願いしてたよ」
「トイレも?」
「なわけないでしょ。トイレは自由だよ」
「著者はなんの文句も言わなかったんですか?」
「入稿直前ってことは伝えてるし、もちろん俺も下からすみませんって感じでお願いしてたからね。それこそノリスケみたいに」
「入稿は問題なくできたんですか?」
「まあね」
7、8年前に交わしたこんな感じの会話を、いまでもよく思い出す。締切を過ぎてもゲラが戻ってこないときは、「いよいよ著者の自宅で監視するときが来たか」とつい思ってしまう。
やはり気になるのは、その先輩が「1階のリビングでなにをしていたか」ということだ。
ごく控えめに言って、その先輩ならソファで昼寝したり、冷凍庫からハーゲンダッツをこっそり取り出して食べたりしていてもおかしくはない。空腹を感じたら、何食わぬ顔でピザーラとか釜寅を注文していたかもしれない。奥さんが帰ってきて、やあやあこんにちはと昼間から一杯ごちそうになって、そのあとは……と想像してみると、これまでの編集者キャリアのなかで、一度も著者宅のリビングでくつろいだ経験がないことに後悔のようなものを感じる。ぜひ著者のみなさんは、締切が遅れたことをきっかけに自宅に招待してほしいものである。いやいや、締切は関係ありませんので招待してください。
ともかく、書くという行為を継続するのはとてもストイックな行為だ。自己規律、計画性、創造性、集中力、忍耐力、好奇心、俯瞰力、ユーモア。数多くの能力を持ち合わせて、それを一時的ではなく、発揮し続けなければならない。そんなことができるのは、いくら鍛え抜かれた経営者でも、ごく一握りなのではないだろうか。
そういう意味で、ぼくたち編集者は、そういった能力を十分に持ち合わせていない人でも、あるいは一時的に力を失ってしまっている場合でも、責めずに寄り添い、ゴールに向かって伴走する、とても大切な役割をもっていると、そう思っている。
だから、リビングでくつろぐことがモチベーションだったとしても、どうか許してあげてほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
