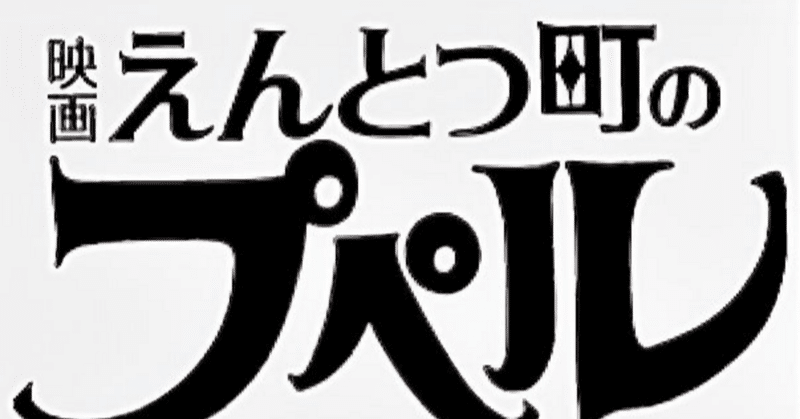
派閥代替としての「大学院」の活用が「大人の学び直し」のハードルを下げるかもしれない
自民党の裏金問題からの派閥解体
昨今問題になっているのが、自民党の派閥による政治資金規正法違反事件です。
これは政治資金パーティーの動員によって派閥から政治家がキックバックを受け取っていたという問題で、すでに政治資金規正法違反での逮捕者が出ています。
岸田総理はこの問題に関して自身が所属する岸田派を解散し、こうした事件が続かせないという姿勢を見せています。これに合わせて今回最も批判を受けている安倍派など他の派閥も解散をする方向になっています。
この記事ではこの事件そのものに関するコメントは差し控えるとして、この派閥解体によって出た派閥機能の代替案に関して考えてみたいと思います。
「派閥」とは何か
そもそも現在話題になっている自民党の「派閥」とは何でしょうか。
詳しい説明はWikipediaを見ていただくとして、簡潔に言えば以下の2つの機能を持つ集団が自民党における派閥です。
人事、資金の集約分配機能
政策勉強会
1の機能に関して、中選挙区時代は選挙区内に複数の自党候補が存在していため、当選するためには大派閥に所属することが必然となっていました。
ところが小選挙区制度となったために、選挙区内の候補は1名を執行部が選出する制度となり、派閥の機能は低下しました。
今回の政治資金問題に関しても、金額が少額である(庶民感覚ではなく事業者レベルの収支として)ことからもそれは明らかです。
一方で未だに健在なのが政策勉強会としての役割です。一般的には○○派という名称が各派閥にはついていますが、正式名称は別に存在しています。
岸田派=宏池会
安倍派=清和政策研究会
麻生派=志公会
茂木派=平成研究会
森山派=近未来政治研究会
二階派=志帥会
といった具合で、政策集団、政策研究を兼ねた組織で、先輩議員から後輩議員へと政治政策の教育が行われるシステムとなっていました。
そして、今回の事件によって派閥の解散が行われることで、政府与党の政策研究のシステムが失われるのではないか、ということが危惧されていました。
「大学院」の活用
そこで出てきたのが以下の報道です。
この報道にある「大学院」とは「自民党中央政治大学院」という自民党が党内に設置した独自の教育機関です。
ここでは地方の自民党支部と連携しながら、現役の政治家や政治を志す人たちに対して様々なアプローチで教育を受ける機会を提供しています。
この「大学院」という名称はあくまでも党が設置する私的な団体であり、学位授与機構が認定した公的な大学院とは異なる機関で、どちらかと言えばオンラインサロン的な要素の強い団体と言えるでしょう。
とはいえ、政治家などの注目を集める人達が学ぶ機会を持つことを公に表明することは社会的にも意義のある動きであるように感じます。
特に派閥という見えにくい場所での教育ではなく、市民が参加できる場所で政治家が一緒に学ぶという機会を設けることには大きな意味があるのではないでしょうか。
「大人の学び直し」とオンラインサロン
複雑化、高度化する現代においては、若い時期に学んだ知識だけでは現実の問題に対応できないというケースが激増しています。
その一方で長引く不景気によって多くの企業は自社での教育を行う体力を失い、教育を受ける機会は激減しています。
放送大学などの再教育を受ける機関は日本においても整備はされていますが、利用までのハードルは高く社会人の多くは活用できていません。
そうした状況において、こうした与党がオンラインサロン的な学習の機会を活用する動きを見せることは、社会に対して学び直しの必要性やその機会の確保を喚起するきっかけになるのではないかと思うのです。
もちろん、注意しなければならないこともあります。オンラインサロン自体は玉石混淆で本当に勉強になるものもあれば、詐欺まがいのものも多数存在します。
(そして私は西野亮廣氏の信者でもプぺルのファンでもありません。)
私自身も数年前まで「みんなのオンライン職員室」というオンラインサロンに参加していました。長く続けていたため、マンネリ化したので現在は退会しましたが、その中で実績のある方の話を直接聞いたりすることもでき、多くの学びを得ることができました。
特にコロナ前に参加していたこともあって、コロナ中のオンライン授業への移行などに関しての知見を多く得られ、業務の改善に大きく寄与しました。
私のいまの状況では時間を取ることが難しいのですが、折を見て別の団体などに参加したいと思っています。
今回のこの報道が「大人の学び直し」に注目が集まる機会になることを願うところです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
