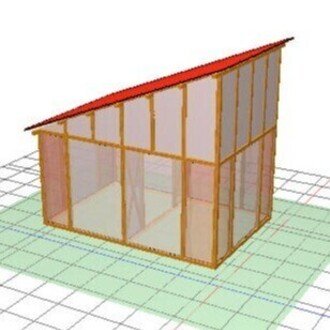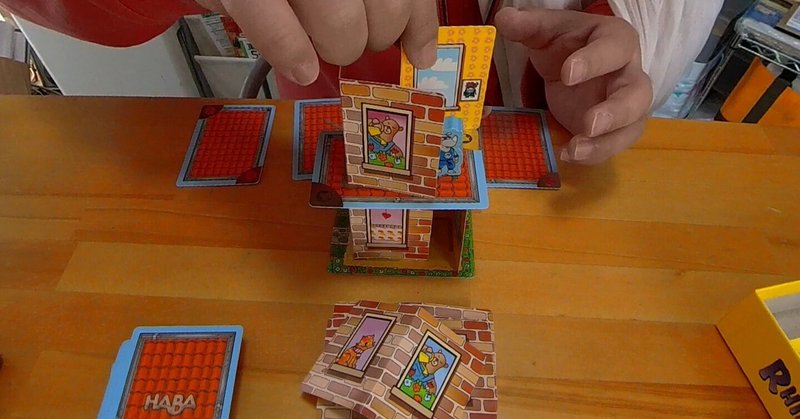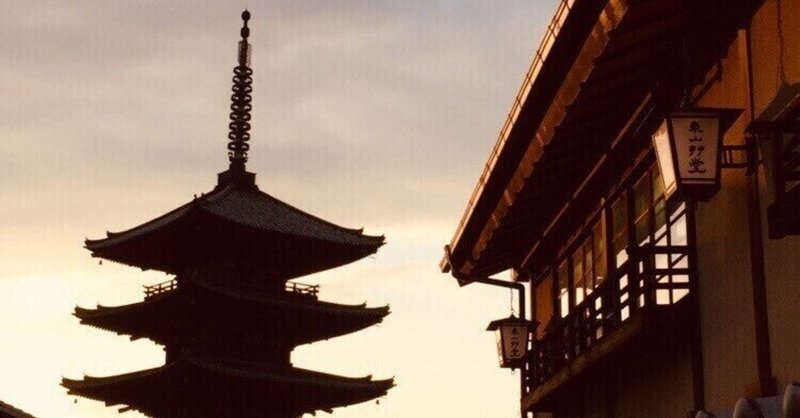#木造
木造構造計算を学ぶ前に読むべき3冊
よく、木造構造計算を学ぶにはどうしたらいいか?と聞かれますが、よくよく聞いてみると、木造自体をよくわかっていない人が多いのに気がつきます。なので、木造構造計算を学ぶ前に読むべき本を3冊紹介します。
安全な構造の伏図の描き方(エクスナレッジ)
伏図が描けない、読めない方が多くいらっしゃいます。正直それで構造力学や計算を学んでも無意味かと。まずは正しい伏図の描き方、読み方をこの本でマスターしまし
それでも通し柱が強いという方へ
木造の構造設計をやっていると、「通し柱は必ずいれてください」とか「通し柱があるから地震に安心ですよね?」と聞かれることが多いです。伝統的構法などの太い通し柱でも無い限り、通し柱の有無は耐震性にあまり影響を与えません。地震に強いと言われているツーバイフォー工法も、通し柱はありません(耐風性をアップするために通したて枠をつかうことはある)。少なくとも普通の個人住宅レベルでは、通し柱を入れたら耐震性が大
もっとみる木造構造設計のお約束 その3
一般の方や意匠設計の方からすると、柱が太いと建物が頑丈になると思っているでしょう。もちろんこれは正しいと言えば正しいです。しかし間違っているといえば間違っています。
というのは、木造構造計算(住宅)では、柱の太さで耐震性が決まることはほとんどないからです。上階の耐力壁が強すぎて、下階がもたず柱を太くする必要があることはあるのですが、建物を強くするために柱を太くする、ということは、実務ではほぼ
木造構造設計のお約束 その1
木造を専門にやっている方なら当たり前のルールも、それ以外からみれば、「何それ??」です。特に法令にもないルールがいっぱいあります。施工上の問題から慣習上の問題、そして通達などのルールなど・・・。
まず筋かいは900㎜以上の幅が必要です。890㎜も不可です。浴室の入口などで900取れそうで取れない部分などありますので注意が必要です。入隅があるサッシの逆側も詰めなければならないことがあり、以外と